実は私、怪談話が大好きでした。
小学時代~中学時代に凝ってました。私にとって、怪談は
男と女の心のあり方を何となく勉強した(?)そんな感じですね。
この時期になると必ず深夜番組で毎年、再放送されていたものでした。
こわいもの見たさっていうんでしょうか、そのころの怪談というと
雪女、お岩さん(四谷怪談)、お菊さん(番長皿屋敷)、耳無し法一など、
時代物が多かったです。このチョー和風本に、まず、
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が出てきたんです。
1890年に特派記者として来日してから、1904年に東京で
なくなったそうです。1890年の8月30日から約1年3か月を
松江の島根県尋常中学校の英語教師として過ごし、
山陰地方の霊的世界に魅了されたようです。
後に妻となる小泉セツと知り合ったこの松江の伝奇を彼女から
聞いたことから始まったようなことを大昔、見た(TV?)気がします。
しかし、松江の寒さに耐えかねて熊本へ移り、神戸クロニクル社、
帝国大学(東大)、早稲田大学に勤務したとあります。
研ぎ澄まされた五感と豊かな感受性で異文化を受け止め、
日本の精神や文化を広く世界へと紹介した人だったんですねえ。
YouTubeで見つけた熊本旧居、これで納得しました。
今は世界で「リング」が知られていますが、
これとて八雲が伝えた精神に繋がるものではないでしょうか。
今は昔ほど、見れなくなりました。深夜仕事へ行く道が怖いです。
↑↑東京散策のリンク
↑↑神戸にもあるんですね。(リンク)
Paul Simon and Art Garfunkel - The Sounds of Silence Lyrics
初めて聞いた洋楽です。
しかも、想い出の曲。
英語を勉強した曲でもありました。
帯ちゃんシリーズ、第三弾!
今回は、帯ちゃんことさっちゃん自身が想い出語りをしています。
さっちゃんのパパはすでに父と呼ばれる時代となりましたので、
題名を少々変更致しました。引き続き、喜怒哀楽をお楽しみ下さい!
題して『 さっちゃんと父 』、どうか宜しく、お見知り置き下さい。。。

≪其の13≫ 忘れられた三年間
中学時代の三年間、私は、父のことをほとんど思い出せない。
なぜだろう?・・・嫌っていたなら思いだせるはずなのだが・・・
不思議なことに、唯一の期間のみ記憶に残っている。
これが、エッセイ記憶とでもいうのかな?
そう、看病記2部 で書いた中学1年生から2年生の間の、
母のグローブの手の入院期間だけが記憶に残っている。
前回書いたことにより、男性不信に陥っていたのだろうか?
いや、それよりも、たぶんあることに一人で一番悩んだ時期
だったと思うのである。それが、どうやって親と付き合っていい
のか、迷うことになっていたのだと思う。

あっ、そうだ。男性不信ではないことは確かやわ。
一応、初恋の男の子がいたんやった!! 卒業式の日、
サイン帳に書いてくれへんと喧嘩別れして帰ったんやった。
「冗談やがな。」 といって、後ろを追ってくるのを、
「ふ~んだ、もう、ええわい!」 な~んて走って帰ったたんやった。
思えば最悪な卒業式の日やったんやなあ。。。
しょーもないこと思いだしてしもたわ~!

そういえば、高校も女子高を選んでいた。当時、公立では最後の
女子高だった。卒業して少しすると共学になってしまった。
今は場所も移動してしまい、母校という感じもなくなってしまったが・・・
後で聞いたことだが、父はこのときの滑り止めで受けた私立高校
に行って欲しかったそうである。私は家庭の状況を見て、
公立でないと・・・という気があったのだが。
このころは、学校でのことが一番楽しかったのかな。
思いだすことと言えば学校がらみのことばかりである。
自分のことは、全てにおいて自分で決めていたような時期。
両親には報告だけしていた。そんな三年間だった。
父には悪いことしたかなと今になって思う。
家紋の歴史は、詳しく書かれているものがいくつかあります
ので、ここでは省かせて頂きます。
下のコラムも家紋にまつわる面白い情報が載ってました。
↓↓↓
家紋の歴史
★-9:「様々な役割を担い千年を経る」--戦陣で磨かれた家紋
↑↑↑
いつも御世話になっているところです。詳しく載ってます。

【家紋の改造】
現在では、主に、家紋=苗字を表すものとして使用されています。
しかし、兄弟がいる家では、本家から分家していくのは当然でしょう。
その時に、全く同じ家紋では、区別ができないわけです。
そこで、家紋の改造が必要になってくるわけです。
1.≪付加≫
本家の原型を残して、丸・角をつける方法
と、紋自体に剣・蔦などを付け加える方法。
【輪の種類】
太輪、丸輪、中輪(なかわ)、細輪、糸輪、二重輪、三重輪、
石持ち(こくもち)などの他に、他の紋で表した州浜輪、
菊輪、藤輪、竹輪、鐶輪、雪輪など。
【角の種類】
平角、垂れ角、隅切り角、撫で角、隅入り角、
雁木角、六角、八角、寄せ角、
組み合い角、角持ちなど
2. ≪改造≫
原型の面影を残して形を他のものに似せるとか、
手を加えて変形(改造)させたりする方法。
【例】 裏表・単複葉・花の線を鋭角的に描く・観点の変化・
上下・角度の変化・折り(折れ)・捻じ画風の模倣・
結び・別の紋の形に真似るなど。
3.≪合成≫
対い・抱き・並び・違い・重ね・盛り・寄せ・離れ・
頭合わせ・尻合わせ・追い・待合い・繋ぎ・
子持ち・他の紋との組み合わせなど。
4.≪分割≫
独立した紋を分割して1つの紋を作り、
円形や角形の中に配置する方法。
「割り」と呼ばれる。(二つ割り、三つ割り・・・八つ割りまで)
5.≪省略≫
合成紋のうち片方を省略する。
 「日本家紋総鑑」日本家紋研究会会長:千鹿野茂様著書
「日本家紋総鑑」日本家紋研究会会長:千鹿野茂様著書  参照
参照
久々にTVドラマを観ました。途中からでしたが、
ちょっと手話のことが気になって観てしまいました。
水曜スペシャル~風の歌が聴きたい~
音のない世界に生きる聴覚障害夫婦の16年。
これは16年もこの家族を追って作られたものだろうということ
にもびっくりしました。健常者にも起こり得る家族不破をどう
乗り越えるか、家族というものについて考えさせられた話でした。
私の周りにはろう者の方はいませんでした。が手話を習って
いる人は周りに少し居るので興味を持っていました。
聞こえない親の聞こえる子供の手話は「心を伝える声」。
ろう者の方が良かった、聞こえない世界は楽しいという子供。
これを聞いた時、物凄い親の愛に包まれていたのだろうという
ことが伝わってきました。途中、見えない壁に惑わされて
しまったけど、二つの世界と思っていたのが、はじめから
家族という一つの世界だったということに、早く気付けて
この家族は幸せだな、と思いました。
『今、27万6千人の聴覚者がいるそうです。
聞こえる人と聞こえない人の壁などないのです。
同情や哀れみとは少し違うと思います。』
『僕の誇りは(聞こえない)両親です。』 怜音
親にとってこれほどの言葉はないでしょうね。
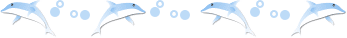
中世の武士は、鳩は軍神とされ、八幡大菩薩の神使として崇めた。
鳩は平和のシンボルとされ、その帰巣本能から書を伝える鳥
としても用いられたが、日本では、平和のシンボルという
よりも、戦のシンボルとして遇されていたことが興味深い。




鳩 小島対い鳩 孔雀鳩



対い鳩 鳩に寓生 鳥居に対い鳩
八幡宮の神官であった宮崎氏が鳥居に鳩紋を用いたのは、
「鳩は軍神とされ、八幡大菩薩の神使」 という故事による。
また、『吾妻鏡』には、
千葉介常胤が軍旗の上方に伊勢大神宮と八幡大菩薩を、
下方に対いあった二羽の鳩を縫って奥州征伐に赴いたとあり、
“源平盛衰記”“太平記”でも神使として扱っています。
鳩紋の中では 寓生と添えたものが多い。
『鳩に寓生』は熊谷氏の代表家紋。
寓生は、欅(ケヤキ)、榎などの喬木に寄生する常緑植物で、
寄生木、飛蔦ともいわれ、平安時代から織文として愛好された。
<!-- 崖の上のポニョ -->
マーちゃんが振り付け有りで歌ってた曲。
「ぽにょがやってるのん?」
と聞けば、歌ってる子がやってただって。(大橋のぞみ)
「1度きいたら頭から離れな~い!」と言っていた。
宮崎駿監督の4年ぶりの新作アニメーション映画「崖(がけ)の上のポニョ」
昨日から公開らしいです。
今日はマーちゃんは飲み会。
珍しく心斎橋だって。
「絶対いつも行けないショットバーへ行くぞー」
って張り切っていた割には、2度、忘れ物取りに戻ってきてたなあ。
ゆうちゃんは、例の姫路の一人住まいの後輩が大阪へ
帰ってるとのこと。車だから遊びに行くらしい。
明日は久々の友人(女の子も交じってたぞー)と4人で飲み会。
その前におでぃと! っていってたような~~。
今日はホッとしたのか、めっちゃ寝過ごしてしまいました。
起きたん、夕方!
洗濯のし直しと更なるてんこ盛りの洗濯。
大変でした。お天気でよかった~!
お兄ちゃん(マーくん)に送ったメールは届いてなく、
「エラーかかっとるやん!何処送ってんのん?」
といいつつ、ちゃんとアドレス訂正してくれてました。
いつもより早い帰宅でした。おーお、珍しい!!
今日は全員、バラバラな1日でした。




























