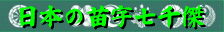【 午・馬の文字の語源 】
「午」は音読みで“ゴ”。
意味・・・杵で穀物を搗く音(許〈こ〉)と関係がある。
『説文解字』に「午は牾(さから)うなり。
5月には陰気陽に牾(ご)逆して地を冒して出づるなり。」
とあるように、「午」の上の形は地表をあらわし、
下の「十」の横一は陽気、
縦1は陰気が下から突き上げて地表に出ようとする象形文字
で、午は杵なり「そむく」「さからう」の意味になる。
交互になる、の意味から陰陽の交差する「うま」の意味
があるとも言われ、十二進法では前半が終わり後半が始まる
位置にあって、前後の交差する数のことを午(ご)という。
午(ご)は陰が陽に逆らって頭をもたげ、
盛りから衰え始める時点を示す。
「午」・・・十二支の第7番目
〔方角〕 南
〔時刻〕 昼の12時(または午前11時~午後1時の間)
「馬」・・・上半分は馬の“頭とたてがみ”を、下の
4つの点は“四本の足”を表す象形文字。
“うま”と発音するのは、朝鮮語の“マル”と同源ではないかと
言われている。また、「馬」の字音による語という説もある。

馬偏に属する文字は520文字もあるが、
一般に使用されているのはそのうちの40字程度にすぎない。
 『十二支のE~話』『(続)十二支のE~話』
『十二支のE~話』『(続)十二支のE~話』 
 戸出 武著 参照
戸出 武著 参照 
【 巳・蛇の文字の語源 】
「巳」・・ヘビの象形文字。“ミ”はへミ、つまりヘビの略。
上の「口」は蛇の頭ととぐろを巻いたさまを、
下の「乚」は胴と尾
といった具合に、文字自体が蛇を表している。
説文学でいうと、今まで冬眠していたヘビが
春になって新しい地上活動をすることを意味している。
「巳」・・・十二支の第6番目
〔方角〕 南南東
〔時刻〕 午前10時(または午前9時~午前11時の間)

巳は音読みは“シ”。
草木の繁茂の勢いが極まって静止の状態を表す
もので、万物がすでに盛りを過ぎて、
これからは実を結ぶ時期にあることを意味している。
また、
巳は頭とからだができかけた胎児ににているところから、
植物の芽が子房の中に芽ぐみ始めることとする説もある。
「蛇」・・・左は虫偏で、これも虫の象形文字。
右半分もヘビそのものの象形。

巳と記された我が国の最古例は、
正倉院文書の大宝二年(702)以降の戸籍簿に見られる。
 『十二支のE~話』『(続)十二支のE~話』
『十二支のE~話』『(続)十二支のE~話』 
 戸出 武著 参照
戸出 武著 参照 
そうそう、また忘れるところでした。
PCのお気に入りに入れていた中から、今回の選挙および
国民審査についての記事を何気なく見つけました。

http://www.clinic-nishikawa.com/post_123.html
「国民と司法との距離を縮め、司法を身近なものにするためという理由で裁判員制度が導入されましたが、突然、人を絞首台に送る役目の片棒だけ担がされるのは迷惑千万です。それよりも裁判官の選択にもっと国民が関与できるようにするべきではないでしょうか。
ところがよく考えると、とても消極的ではありますが、唯一国民が司法に直接関与できる仕組みはあったのです。それが総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査です。」(引用)

PCを全く触らなかった時代、新聞もとれなかった時代、
私は、○×方式のこの審査って何?って良く思ったものでした。
最高裁判官の名前ってすぐには出てこないからです。
しかも選挙候補者の名前は貼り出してあるものの最高裁判官の
名前、扱った記事などどこにも見当たらないからです。普通、
自分に関係がない記事など到底覚えているものではないでしょう。
任命後初の衆議院議員選挙の時に審査を受け、その後は審査を
受けてから十年を経過した後に行われる総選挙時に再審査を受け
るとあるようですが、事件としてはニュースで過去に聞いたことが
あっても、果たして最高裁での判決など、一般市民が覚えている
人がいるのでしょうか?
ましてやその時の最高裁判官の名前って言われてもねぇ。。。
結果、これまでに過半数の不信任を受けて罷免された裁判官は
いないといいます。
今回、私は運良く忘れずに少々の事件に目を通せそうで、少しは
ちゃんとした国民審査ができそうです。
しかし、ネットでのPDFをすべて見るにはかなり時間がかかるし、
ネットを見ない人の方が多いでしょう。
こんな審査はやっぱり変です。
もっと、目立つように広報を貼っておくべきだと思います。
こんなことも改善しないで、裁判員制度が導入され、
人を絞首台に送る役目の片棒だけ担がされるのは迷惑千万、
と思う人がいても当然ではないでしょうか。
もう一度寝るか?・・・いや6時間以上はもう眠れない。
起きたらすぐ、うがい。コップ一杯の若水!
これが健康維持によいのだ!
休みというのにこんなにも早く起きてしまった。
さて、何をしようか?
まずは少しブログ巡り!
けど、少ししか見れない。
けど、最近アクセス数が増えてきた。
記事アップしていないときでも見にきてくれる人がいるようだ。
二日更新を休むと前は必ずアクセス数は落ちてきていたものだが、
異常に上がっている時がある。不思議な現象が見受けられる。
しかし、有難いことと思う。
秘密主義の私にとって、アクセス数は意味がないこと、関係ない
と表示してこなかったが、あるとき、人のブログ訪問したときに
気になることに気がついた。
前に見た時よりぐんと減っていたブログに出会う。
そんなとき、訪問者(私)が相手のことが凄く気になっているのだ。
毎日見ているわけではないので、ずーっと更新がなければ減って
いくのは当たり前なんだけど、そんなとき更新しても
全く変わらなかったりしている。気がつかれないのだろうね。
実生活が忙しいのだろうな。。。
元気でいるといいな。。。なんて思う。
そっか、表示してみるかな。別に隠すほどでもないか!
カウンターでも
「へぇ~、私が○○番目なんだー!」
って思ったことがある。こういうのって、
ある意味、訪問者にとって意味があるのかも・・・
そんな風に思えてきた。。。
朝、PCを見続けると一日中目がぼやける。
最近は30分~1時間以内に留め置く。
ああ…完璧に明るくなった。
今日は定休日!
というのに、夜明け前の3時半から起きて、
しかも、一日の始まりというのに
何で日記なぞ書いとんねん!?
などなど、思いはあちこち飛んで行く。
あははー!
これが気まぐれobichanのいいところー!
なあ~んて、誰かに言われそうだなあ。。。。。
さて、朝ご飯にしよっっと!!!
~マゴちゃんからの贈り物~
ピオーネ
今年のは凄く甘くて種なしで食べやすく、
とっても美味しかったです。
広島に移住したマゴちゃんからの贈りもの。
これは、奥さんの実家(岡山の農家)のものです。
初夏と冬は白菜と沢庵の漬物。
夏は今年はビールでした。
あ、100%ジュースも送って頂いたような…
えっと。。。お米も頂いたような…
11月はソーメン南瓜。
プラス、その時々の気が向いた物を送ってくれます。
今では、運送屋さんに
「まいどありがとうございます!」
って言われます。
マゴちゃんはマーちゃんと同い年なんですが、
まるで実家のようなお付き合いして頂いてます。
本当にお世話になっております。
いつもありがとうございます。
(株式会社 日立メディコ)http://www.hitachi-medical.co.jp/
とかいう乳がん検査があるとのこと。
エコー検査と同じで痛みはなく患者にとって負担が少ない。
5~10分ぐらいで終わる。
エコー検査と違うところは、カラーになってるところ。
硬いものを青で表示し、柔らかいものを赤い色で表示。
これにより、今までのものより、見逃しが少なくなったらしい。
乳癌はぼこぼこした感じの形だという。しかし、形だけだと
良性に見えるものでも、硬さを見ると硬かったり、明らかに
乳癌と疑わしい形でも硬くなければ大丈夫のようだ。
今まではそれらすべてを注射針で検体をとって調べていたようだ。
そういえば、義姉も一度気になるのでと検査したと聞く。
もうひとつ悪評高いとまで言わしめられている、
マンモグラフィとかいうのも聞いたことがあるが、
はさんで押しつぶすような感じの検査だと聞いていたので、
ギューギュー伸ばされたらしく、かなり痛かったようだ。
(私が聞いたのは胸のない人だったが。。)、
へたな技師による痛みってのもあるらしい。聞くだけで嫌になる。
私も未だやったことがないし、行きたくもならない。
(自分でやる触診はやっているけれど)
これにくらべると、エラストグラフィー は本当に素晴らしい!
まだまだ普及率は100%ではないだろうけど、いち早く取り入れた
病院は確実に乳癌検査率は増えるように思う。
株式会社 日立メディコの松村剛さんたち(あと忘れた。。)が、
癌は固くなるもの!ならば、癌の硬さが分かれば早く癌を見つけ
られるのではないかと研究していたらしい。
本当に今の医学は凄い。
たとえ癌になったとしても、乳房温存手術、
自分の細胞で乳房形成手術なども(前にTVで観た)成功している。
茨城の筑波大学付属病院で新山千春さんが昨日のTVでは、
受けていた。なんだかくすぐったそうだった。
他でも扱ってるとこあるのかなあ~?
【羽生(はにゅう・はぶ)】
ハニュウは「埴生」、ハブは「埴生」「土生」とも書き、二通りに読む。
ハ二ュウ(ハ二ウ)が古く、略されてハブになった。
もともとは埴生(はにう)で、埴(はに)は土のこと。生(ふ)は“ある”
ところぐらいの意。土のあるところとはどんなところか。耕すに良い土
のあるところで石ころや、砂などのない土地。
この土(埴)を元にして、器を作ったり人形を焼いたりする人が
植師(はにし)で、土師(はじ)とも書く。この姓もある。
昔でいう埴輪(はにわ)を焼く人たちの子孫で、殉死を禁止して、
埴輪で間に合わせたという野見宿禰(のみのすくね)の子孫だ。
羽生さんの中にはこの系もある。
しかし、清和源氏で源頼光の子孫だと言っている人も多い。

≪ハ二ュウ≫
①下総国岡田郡羽生村(茨城県常総市羽生町)から起こった土豪羽生氏が室町期に羽生城、横曽根城(常総市横曽根)に蟠踞したが、戦国時代に断絶。
②清和源氏広田流が、 戦国初期に武蔵国埼玉郡羽生(埼玉県羽生市)を領して羽生氏を呼称。忍城の成田氏にほろぼされた。
③中臣氏庶流が、常陸国南郡羽生(茨城県行方市羽生)を領して、羽生氏を呼称。鎌倉初期から江戸末期まで鹿島神社の大祢宜。
④土佐にも羽生氏があった。
≪ハブ≫
①桓武平氏上総常澄の子常益が、下総国埴生郡羽生荘(成田市の西北部)を領して埴生氏を呼称。
②越智系河野流遠藤親家の子親遠が伊予国温泉郡埴生郷(松山市埴生)を領して、埴生氏を呼称。
③桓武平氏北条時治が、南北朝期に和泉国土生郷(大阪府岸和田市土生町)を領して、土生氏を呼称して、南朝に加担、弘治年間(1555‐7)に末裔が安芸に移住。
【(波)現代の珍姓珍釈編】へ戻る。
 『姓氏・家系・家紋の調べ方』丹羽基二著
『姓氏・家系・家紋の調べ方』丹羽基二著 
 『日本家系・系図大辞典』奥富敬之著
『日本家系・系図大辞典』奥富敬之著 
ゆうちゃんの有給休暇、3日目・・・最後の日です。
これで、今年の有休を使いきったとのこと。
年間の有休を残らず11月までに使いきること!
会社からのおたっし…だそうな。
しかし、
なぜに今…全て使いきるかな~?
用もないのに…?
先週、5日間(12~16日)休みちゃうかった?
「だって、公休があるもんっ♪」
そう、2週間に1度、
年間予定表に組み込まれてる公休分で十分だという。
しかも、土日祝日大型連休全て休みなのである。
(そういや間の祭日は出勤だったナ)
大企業では、きちんと有休を消化させるようになってきた。
不況と言われてる時期に人を入れ、
正社員にきちんと休みを取らせるようになった。
しかし、その反面、
お兄ちゃんの方(中小企業)は・・・というと、
いまだにフリーター(契約社員?)だが、
正社員並みに出勤せざるをえないようである。
今年は特に新型インフルエンザのせいで
高校生を縮小せざるを得ない状況下で、
大学生はそれなりに休みがちになる時もあるようだ。
社員か店長になれば、こんな煩わしい人材のやりくりさえ
考えねばならない。責任上、
時間どおりにいけばいいものでもなくなるだろう!
となると・・・時間給率も割安になる。
「ぜんぜん休んでへんのとちがうん~?」
「だって、人がおらんねんもんっ!!」
なんだか。。。おかしいぞー??
この日本は!!
正社員を断るお兄ちゃんの気持ちもわかるなあ。。。

なあなあ。。。行こっ♪行こう~♪
連れってって~~ナ~~♪
今日はゆうちゃんにおねだり~~~♪



私たちが座ったと同時に立った親子連れが、
「50皿だって!」
とゆうちゃん。
「お母さんと、普通の体型の小学3年生ぐらいだったでー!」



「当たったでー!」
「へっ?」
5皿ごとにゲームが画面から流れます。
15皿目の3回目から
何やらゆうちゃんがしてるのに気付きました。(おそっ!)
こんなん、出ましたけどぉ!
バッジ。だそうです。
2回当たりました。
てなわけで・・・お腹がいっぱいだー!
ストラップがいいなっ♪



「あと3皿で30皿やでー!僕、炙りうなぎとポテト!」
「じゃあ、いくら~、一貫だしー♪」
お見事!
はずれだよ~ん♪



ネタが大きくて分厚い上等なお寿司は実は苦手!
なんたって生魚がちょっとね~。。。
ゆうちゃんが好きだった幼少のころのネタは・・・
おいなりさん、なっとー巻きのみ。
小学生の頃は・・・プラス、海老、サーモン、うなぎ。
そして、とうとう、気がついたようです。
食べてみないと美味しさが分からないということに。。。
ああ。。。
随分と大人になったもんだ!
漢二字(その多くが道義的な意味を持った)の名が盛んになったのは、
平安期に入って、三代目の50人の皇子女がいた嵯峨天皇のとき
からである。
【 嵯峨天皇による人名習俗の新改変 】
① 身分の高い生家出の后妃が産んだ場合〔皇族へ〕
皇子・・・漢二字(正負・秀良)
皇女・・・漢一字に子(正子・秀子)
② 身分の低い生家出の女性が産んだ場合〔源姓を賜り臣籍へ〕
皇子・・・漢一字(信〈まこと〉・弘〈ひろむ〉)
皇女・・・漢一字に姫(貞姫・潔姫)
唐風賛美の強かった嵯峨天皇による人名習俗の新たな改変は、
すべて唐風の模倣であった。それ以前にあっては、皇子女の名は、
おおむね乳母の生家の家の名が付けられていた。
桓武の山部、平城の安殿(あて)、嵯峨の神野、淳和の大伴など。
漢字二字を重ねて人の名とする習俗、またその上の一字を共通
にする行列字の習俗も古くからのものであり、現在に伝えられている。
②の場合、信(まこと)・弘(ひろむ)・常(ときわ)・寛(ひろし)・
明(あきら)・定(さだむ)らに一字名と源姓を賜うて臣籍に降ろした
のは、北魏の世祖が、同族の河西王の子、賀の人物の非凡を
認めて西平候に封じ、龍驤将軍に任じ、
「卿と朕とは源を同じうす。事に因って姓を分かつ。
今より源を氏となすべし」(『魏書』源賀伝)
と、源姓を与えた故事にならったものである。
嵯峨帝によって、創始された皇族子女の二字名・一字名の習俗
は、皇弟淳和帝が踏襲して定着し、今日に至っている。
漢二字のこの人名習俗は、後続のみならず、貴族からさらに武士
階級に及び、実名のことを「二字」とまで呼ぶまでに至った。
下層の庶民は、長く二字名を用いることをはばかったが、、
明治維新による四民平等の社会の到来とともに誰もが二字名、
一字名を望むがままに付けている。
 『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考
『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考
いつもありがとうございます。
名前の習俗
日本における名前の習俗も、歴史と共に変遷した。
『古事記』の伝える伝承によれば、天皇家のこの国土における
始祖は、高天原(たかまがはら)から九州は日向国高千穂に降臨
したいわゆる天孫(日の神天照大御神の孫)にして、正勝吾勝
勝速日天忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)の御子、
天津日高日子蕃能爾爾芸命(あまつひたかひこほのににぎのみこと)という。
神話の時代から歴史の時代に入ると短くなったものの、身辺卑近
の事物をかたっぱしから人の名としたのである。
例えば、中臣必登(ひと〈人のこと〉)・石川虫名(狢〈むじな〉)・
土師八手(はにしのやつで)・門部金(かどべのこがね)・
藤原愛発(あらち〈爆風のこと〉)・伊余部馬飼(いよべのうまかい)・
大中臣魚取(おおなかとみのなとり)・錦織壺(にしごりのつぼ)・
県犬養手襁(あがたいぬがいのたすき)・榎井靺鞨(えのいまつかつ)・
丹治大目(たじひのおおめ)・巨勢奈氏(なで〈撫でる〉)麻呂・
宮道阿弥陀(みやじのあみだ)・船小揖(ふねのこじか)など。
 『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考
『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考