【長浜浩明】[桜H26/4/15]
私たちの時代は、倭人といえば日本人と教えてもらったけど・・
最近はちょっと違うと聞きました。
これは、また違う角度からかしら?
驚いたのでアップしておきます。

それにしても、
今の韓国人は漢字が読めないとは何かで読んだけど、
(少々は使用されているのだけどね)
韓国にもこんな、漢字で書かれた歴史書があったなんて・・
しかも隠されていたなんて・・絶句!
三国志紀?(記?)、三国志ではないらしい。
本当かなあ・・
【 10以上の数詞 】
★『古事記』(712年)の中に出て来る数字・・・5つ
十一 トヲ・マリ・ヒト
十二 トヲ・マリ・フタ
十四 トヲ・マリ・ヨ
十六 トヲ・マリ・ム
十七 トヲ・マリ・ナナ
「マリ」=「アマリ」の「ア」が脱落。
トヲ 数えて アマリがいくつあるという表現。
・8世紀の碑文に47を「40余り7つ」とチュルク語でかかれたものがある。(柴田武)
・英語で11、12(eleven,twelve)の語源が「10数えて1つ(2つ)余った」という。
★『古事記』にみえる20の位
廿一 ハタチ・マリ・ヒト
廿六 ハタチ・マリ・ム
「ハタチ」の「チ」=「ヒトツ」「フタツ」の「ツ」が転じたもの。
「箇」を意味する。
「ハタ」=二十
・「ハタ」は動詞「ハテ」(果)と同根。(大野晋ら)
これ以上数えられない、両手、両足の指すべてを使いきった数の意。
・「ハタは」二十(フタソ)の略転。(大槻文彦)
☆ 十は複合語の場合に「ソ」という。「ト」の転音。十露盤(そろばん)など。
★30以降の例
三十 ミソ 三十八 ミソヂ・マリ・ヤ
四十 ヨソ 四十九 ヨソヂ・マリ・ココノ
五十 イ 五十六 イソヂ・マリ・ム
六十 ムソ 六十三 ムソヂ・マリ・ミ
七十 ナナソ 七十七 ナナソヂ・マリ・ナナ
八十 ヤソ 八十三 ヤソヂ・マリ・ミ
九十 ココノソ 九十五 ココノソヂ・マリ・イツ
※「ヂ」=「ハタチ」「チ」と同じ「ツ」(箇)の転じたもの。
数詞に添える接尾語、助数詞。
※「五十」=イ
5(イ)と 50(イ) は同語。(大野晋ら)
ポリネシア語などに一つの単語で4と40を表すのがあるのと同類。
※50で10を表現しないのは、20「ハタ」で10を表現しないのと同じといえる。
例)伊勢神宮に五十鈴川(イすずがわ) (川本宗雄)
★3桁の数字
・百(モモ)・・・由来は諸々(モロモロ)とも物物ともいわれる。(大槻文彦)
一百三十七 モモ・アマリ・ミソヂ・マリ・ナナ
一百五十三 モモ・アマリ・イソヂ・マリ・ミ
※762年頃の仏足石歌(奈良薬師寺の石碑文で万葉仮名)に、
「32」を弥蘇知阿麻利布多都(ミソチ・アマリ・フタツ)という例がある。
※百は単位として使う時・・・「ホ」という。上代は「ポ」といい、
「オポ」(多、大)からきている。(白鳥庫吉)
例) 八百屋(ヤホや)、八百萬神(ヤホ・ヨロヅのかみ)
三百(ミホ)、六百(ムホ)
※『古事記』での読みに五百八十を「イ・ホ・チマリ・ヤソ」というのがある。
「チマリ」=「留り」の上代東(アヅマ)方言。 (大槻文彦)
★その他実例
千五百 チ・イ・ホ (『古事記』)
万五千 ヨロヅ・アマリ・イツ・チ (『日本書紀』720年)
★借り物の漢数詞(1~10)
壹、貮、参、肆、伍、陸、柒(漆)、捌、玖、拾
・音は呉音に由来する。
※呉音・・・中国の南朝時代(4~6世紀)、揚子江下流域(江南:かつての呉の地)
のシナ音で、朝鮮半島の百済を経て仏教(538伝来)とともに伝わった。
↓
その後、漢音が長安、洛陽から遣唐使らによってもたらされた。
この借り物の漢数字のお陰で日本人の数体系への進化が進んだと思われる。
 『数の民族誌 世界の数・日本の数』内林政夫:著(八坂書房)参照
『数の民族誌 世界の数・日本の数』内林政夫:著(八坂書房)参照

二十はハタチって読むのって、ちゃんと古事記に載っていたからなんですね。
その由来ははっきりした記録としては残っていないので、
だいたいは後世の人たちの想像でしかないです。
でも、両手両足の全て数えきれなくなった「果て」
という単純なのが一番当たってるような気がします。
「ありゃりゃ、指を使い果たした~、んじゃあ、
コレをとりあえずハタチ(20)としておくか~。」
なあ~んてね、そんな感じだったんじゃあないかなあ・・
いにしえのものって結構好きですが、
一百三十七 モモ・アマリ・ミソヂ・マリ・ナナ
一百五十三 モモ・アマリ・イソヂ・マリ・ミ
この読み方だけは堪忍~~!!
ホント、借り物の漢数字様様ですね~!(笑)
「ヒトツ」の「ツ」
・「ツ」は箇の意味
・9までの数字にみなついている接尾語(助数詞)
☆ 「ヒト」
【ハ行の音】
奈良時代以前(700年より前)・・・ p音
↓
室町時時代(1600年)まで・・・ 両唇を近づけて音を出すФ(F)音
↓
その後現代まで・・・ h音
☆「日本語では、1~10までは辛うじて大和(やまと)言葉の数詞が
用いられているが、10を越せばすべては漢語からの借用である。」(泉井久之助)
また、そのことが現代の桁の大きい数への容易な取り扱いに大きく貢献している。という。
【数の数え方】
☆ 未開の言語に、「1,2あとは多数」というのがある。
●白鳥庫吉説 (明治時代~1936年にまとめた日本の数詞論)
1、2「 ヒ ト・フ タ / ピ ト・プ タ 」 3、6「 ミ ・ム 」 4、8「 ヨ ・ヤ 」
≪なんとなく口調が良いわけ≫
ピ・プ (i→u)、ミ ・ム (i→u)、ヨ ・ヤ(o→a)
・それぞれ母音の入れ代わり、つまり母音交替が起こっている。
・おのおのが倍数関係・・・日本の数詞の特徴
他には台湾語の一部(村山七郎)、北米のエスキモーの言語、
アメリカ・インデェアンのある部族の言語(白鳥庫吉:市河三喜)
★「我々の祖先は片手で閉じた状態から、親指、人差指、中指、を順に起こして数え、
5で完全に手を開いた5進法であったことがわかる。」(白鳥庫吉)
※じゃんけんのハサミに親指と人差し指を出す老人がいたのは、
この1、2を数えた名残りだろうという。
↓
★「韓語、満州語、アイヌ語・・・5=閉じる、10=開くと同じ方式がみられる」(白鳥庫吉・大野晋)
今日の開いた手から始める方式と逆。
朝鮮半島からの影響で古代方式より現行方式へと変わったのだろう。
1)「ピト」・・・ まず片手の親指を起こす(「プト(太、大)」の転音)
2)「プタ」・・・つぎに人差し指を出す。
大きい別の1という意味を込めた「ピト」の複数形。
3)「ミ」・・・つぎは中指を起こす。
数量の増加、衆多を意味する。
4)「ヨ」・・・つぎは薬指を起こす。
いやがうえにも増加を意味する。
5)「イツ」・・・5本の指を全部使ってしまった極みという意味。
6)「ム」・・・「ミ」までの3本指を立て、他方も同じように立てて「ム」とした。
対立、並列の倍数関係が成立。
7)「ナナ」・・・並べようのない数(並無)
手の指を並べて計算できない数の意味。
8)「ヤ」・・・4本指の場合に、一方を「ヨ」、他方を「ヤ」とした。
対立、並列の倍数関係が成立。
9)「ココ・ココノ」・・・屈めようのない数(屈無〈かがめなし〉)
指をかがめ折っては計算できない数。
10)「ト、トヲ」・・・撓(タワ・トヲ)で、指を撓(たわ)めつくして数える。
指を曲げて手が閉じた状態を意味する。(大野晋)
5と10にも倍数関係。
5の語幹の「ツ」「ト」では(u→o)の母音交替。
遠(白鳥庫吉)・・・計数の結尾とした語
止(大槻文彦)・・・計数の結尾とした語
止尾、十尾(とを)(金沢庄三郎)・・・計数の結尾とした語
片手の親指、人差指、中指の3本を立てた後、反対の手で
同じく3本の指を立てて、その一方を3「ミ」、他方を6「ム」と呼んだ。
同様に4本の指の場合に一方を4「ヨ」、他方を8「ヤ」とした。
こうして対立、並列の倍数関係が成立することになる。
5と10にも倍数関係。
1~10のうち、2,3,4,5 はいずれも多いという意味をもつ。
それらに対して、6、8、10 がある。 そして、7 と 9 が両手の
指で対を作る事ができないやっかいな数字と古代人は考えた。
★『古事記』の神代期に 7 と 9 の数字が全く出てこないのは、
7と9は厄介な数字、不吉な数字と考えられたためだろう。
★現代の7を好み9を嫌うのは、後に渡米した漢文化の影響。
★10以上に2系列が体系的に存続じなかったのは、借用系が
より簡単で便利だったからである。
【 反 論 】
●村山七郎説
一定の母音関係による倍数関係などは存在しない。
1の語幹は「イト」、
2の語幹は「プタ」で相互関係はない。
4の祖形は「ド」
8の祖形は「ザプ」で、「ヨ」「ヤ」の語頭音の起源は異なる。
●大槻文彦説
1(ヒト、古代ピト)は、「ヒタ」直(単一)、「イタ」最、一などの「ピタ」
にさかのぼり、合一、統一を意味する。
●芝烝説
2(フタ)は「フタゴ」双児のフタでもともと2ではなく、
一対という「双」「対」を意味したもの。
●川本宗雄(南方語源説)
木の実・木の葉を食べて並べたことによる由来では?
★固有名詞以外の必要性
「ヒト、フタ…」→ 数量を表す
「イチ、二…」→ 順序を表す (金田一晴彦;森睦彦)
 『数の民族誌 世界の数・日本の数』内林政夫:著(八坂書房)参照
『数の民族誌 世界の数・日本の数』内林政夫:著(八坂書房)参照
現在、俗にいう花見も元は野山の花の観賞ではないという。
「ハナミ(花見)」・・・花の心をうらげ楽しませて鎮めおちつかせ、
稲の花が散ることを忘れさせ、その稔りの
将来を占おうとしたのが源。
【 農村での「ハナミ」 】
三月三日に行われる土地が多い。
見晴らしのよい山・丘に登って飲食をして一日遊ぶ。
農作に先立ってのその協力を予約する春の儀礼になっている、
という信仰から出発していると考えられる。
≪「花」とは≫
★「ホ(秀・穂の内容)」「ウラ(兆・占・卜の内容)」と意義が近い。
もともとものの前兆・先触れという意味になる。
「うらもなく吾が行く道に 青柳が萌(は)りて立てれば
もの思(も)いひづつも」
(何気なく私が行く道に、柳が芽吹きだしていたので
忘れていた恋を思いだしたよ――「万」・巻十四・三四四三)
★正式・本物でない意より借り物、いえば物の「先触れ」の意味でもよかった。
「初尾花 はなにみむとし 天の川へなりにけらし 年のを長く」
(初(※)尾花ではないが、一夜妻として会わせようと長年天の川が
邪魔しているのに違いない――「万」巻二十・四三〇八)
(※尾花=ススキの別名・ススキの花穂・ハナススキ)
ホススギ・ハナススキが、同じものであることを考え合わせればわかる。
「見る」は会う、交接するの意。
「雪」・・・稲の花(雪は豊年のシルシとする)と見立てている。
「柊」・・・立ち樹のまま冬祭りの鎮魂歳に引き抜いてくる。
冬花が咲くその咲き方や柊の梢で大地をついて占った。
三月は桜が代表、卯月(四月)には「卯の花」、五月には「皐月(さつき)」
「躑躅(つつじ)」、などなど村から山の花々を遠く眺めて稲の稔りを占い、
花が早くに散ってしまうと大変なので「花鎮祭(はなしずめまつり)」が行われた。
「柳」・・・垂れ枝が多く根のつきやすいもので、一種の花である。
この枝の多いところから正月の飾り物は、すべての花に見立て
られる(餅の花・花の木・繭玉・若木・作り物など)。
このような(削り花・削り掛けなど)のもとの姿は、仙人のついて
来た杖の先のささけたもので、それが「花のしるし」になった。
「卯杖」・・・土地をつつきまわるとその先の方がささけ、
根は土の中でつく。このささけが花のしるしとなる。
「簓(ささら)」・・・卯杖と同じように竹でしたものをいう。
簓も一種の占いの花で、葬式などには髯籠(ヒゲコ)
をつくる、その先の分れ形で占う。
★「粉」=「ハナ」と呼ぶ。
色が黄色なのを稲の花に見立てての予祝い。
「タカハナ」・・・田植えの日に必ず飯にコガシ(=キナコ)をふりかけ食う。
「稲の花」・・・東北地方ではたいてい炒り豆の粉のことをいう。
★「花アテ」・「山アテ」(=山野の花を見て耕作の時期を感じる)
「田の花」=紫雲英(げんげ)・・・ハナとも呼び、田の花の略。
「辛夷(こぶし)」=タネマキザクラ・・・播種の頃を知らせるもの。
★最短・先端・最初の意義の「ハナ」
「ハナザル」・・・「猿のボス(指導者)」のこと。
★神聖なもの、または行事用
「花占」・・・梅や桜の花が横向きに咲けば強風、下向きに咲けば雨、
上向いて咲けば晴れなど。
「赤い花」・・・光る花と感じ、神・精霊のものとする。
(梅や桜の花をみだりに家の庭に植えることを禁じる所もある)
「菫(スミレ)」「鳳仙花(ツマグレ)」
★蘇生・復活・転生の招代・・・魔よけの呪力をも含む
「色のある花」・・・後には仏様に手向ける花となる。
「秋風や むしり残りの 赤い花」(一茶句集)
「手向くるや むしりたがりし 赤い花」(一茶句集)
色のある花は仏様に手向ける花なので、
一茶が愛娘にねだられても与えなかった。
「花輪」「花籠」・・・身体が離れた霊魂(先天魂・後天魂)が戻る。
これらのものが神の憑代に一転すると、
神の意思を示すことになり、邪霊は怖れて寄ってこない。
神を招ぐ折の花は、その作法をするものの象徴となる。
早処女はツツジをかざし、禊の女は藤の花房を身につけていた。
 『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
花は、古くは観賞用のものではなかった。
予祝的な占い・・・お互いの生活の幸運を招くためのものだった。
≪奈良期≫
花を観賞する態度は中国の詩文から教えられた。
【農占の歌】・・・花を讃えたものではなく、山の花の咲き方を見て、
農耕の時期などをさとった歌。
「打ちなびき春さり来らし。山の際(ま)の遠き木末(こぬれ)の
咲きゆく見れば」
(春が来たに違いない。山あいの遥かな梢の花が、
だんだん咲いて行くのを見るとわかる――「万」・巻十・八六五)
生花は、季節の霊魂迎えの式の依代(霊的なものが寄ってきて宿りこむ)
のひとつなのである。ためにそうした季節の変わり目に、祖先の霊魂を
迎えて果たす行事をする日をも「ハナ」という。
「花正月」・・・正月十四日
松や柳の木などを削り、その先端をそらして神棚に上げる日
(「削り掛け」もハナという)
「花ノ内」・・・小正月~月末
「花米」=洗米(神に供える洗った米・饌米)
形は神に供える米であるが、やはり神の憑代であると同時に、
奉献者の霊魂の象徴とも信じている。
「餅花」(繭玉)・・・花米と同意義ながら、後に「飾り」と考えられている呪物
であることは、今だに縁起物になっていることからもわかる。
「山の花」・・・農作の神を、山から迎えとるもの。
根本は農事に関係がある。
【二月十五日のハナ】
二月の第二の望(もち)の日を農事にとりかかる日とし、
各地でハナといい、寺では涅槃の日と呼ぶ。
【四月八日のハナ】
耕作の神である山神迎えとして山野から折りとり迎えて、竿頭などに高く
束ね上げ、「高花」とする。
この日は女も山に早処女(しょうとめ)になるために登るのである。つまり、
卯月八日前後の「花祭」は村の女の山入りの日で、古代には山ごもりをして、
聖なる資格を得るための成女戒をうけたオトメ(早処女)として、山の花
(ツツジ・藤・コブシ・百合など)をそのしるしとしてかざして村に戻る。
【花祭り行事】 岐阜県北設群東栄町地域
岐阜県北設群東栄町地域
 ホームページは→こちら 『花祭』は→こちら
ホームページは→こちら 『花祭』は→こちら
国指定指定重要民族文化財「花祭り」はオニスター君が
アニメーションと写真で解説してくれるそうです。
東栄町地域では、昔は春のとり越し祭りとして初春の「花祭」は
霜月に行われた。 来年の村内生活はこの通りだということを、
山の神人・山の神が演じて見せてくれる。
その折、山苞(〈やまづと〉山の土産物)を持って来てくれる。
「花育て」という行事が演芸種目の一中心となっている。
竹を裂いてその先をいくつにも分けてその先へ花をつけた「花の杖」
をついて、花祭りを行う場所(舞屋という家の土間――舞処〈まいと〉)
を廻る。その土地の精霊がそれに観応して、五穀の花を立派に
実らせるという信仰。
中央の釜には湯がたぎっている(湯立〈ゆだて〉という)、その周辺を
廻るのだが、その人々の中心に山伏姿の「※ミョウド」というものが
おって、「花の壮厳(唱事・唱文の意)」という文句を唱える。
※ミョウド・・・山人で、山から群行してきて杖をついて来て、山へ去る
時にその杖を地面に刺して帰る。その杖から根が生える
と、「花の壮厳」の効果が生じて村の農業生活が豊かに
なるとし、生じないと効力がないと信じた。
この杖は普通、根のある杖をついて来る。桑などは根が無くてもよく根付く。
杖は梢を下にさかさまについて来る。こうする杖を又杖(マタブリ)という。
つまり、花育ての花杖であり、「杖」をもって祝福の効果があるかどうをを
試みる。杖の先に花が咲くとしているのである。
・効果が現れる事・・・「ホ」が現れる、「ウラ」が現れるともいう。
・「花枝」・・・今年の穂の花を予め祝福するためのもの
・「花祭」・・・「花」は穂の花の象徴
≪平安期≫
【ヤスラエ花(鎮花祭)の神事】
 奈良県大神(おおみわ)神社HPは→ こちら
奈良県大神(おおみわ)神社HPは→ こちら
( 参考ブログ「やすらへ、花や」~山の手事情社の道成寺~)
参考ブログ「やすらへ、花や」~山の手事情社の道成寺~)
陰暦3月の落花の時期に行われる。桜の花が散ると疫神がそれに乗じて
病を流行させ、稲の実りも未熟に終わると信じた。
それで、花よ散るな―「やすらへ花や」と囃子詞を繰り返すのである。
・このような「予祝い行事」は平安期には盛んに各社で行われていた。
・元は、桜町中納言が泰山府君(たいざんぶくん)―人の命を司る中国山東省
泰山の神―に、桜の寿命延長祈願をした(「源氏盛衰記」・巻二)ことの本義。
 名古屋市熱田神宮の花の撓(とう)神事
名古屋市熱田神宮の花の撓(とう)神事
 熱田神宮正式HPは→こちら、踏歌神事は→こちら
熱田神宮正式HPは→こちら、踏歌神事は→こちら
成人したての者が花を献じる頭人の行事(滋賀県村落で現行)
などと同様の稲がよく稔れとの豊作呪術なのである。
春の花のもちのよいことで、稲の花の稔りの多いことを示すもの
として予祝いする。
≪池坊の「立花」の起こり≫
「江家次第」の追儺の条に「七夕祭りにある」とある。
「盆花」・・・七月十一日
家ごとに山へ出かけて「盆花」をとってくる。
それに乗って祖霊である精霊は家に来り臨む。つまり、
家いえの神・精霊を迎えとるものが花なのであり、ひいては精霊・
神の憑代(よりしろ)の信仰を保ち得ているものを、「ハナ」と呼んでいる。
 『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
≪参考リンク集≫

 「民族行事」様より→ 4月「春祭り」「鏡の餅搗き歌」など
「民族行事」様より→ 4月「春祭り」「鏡の餅搗き歌」など

 参考youtube→ 播磨暮らし探訪30 頭人行事(八朔祭)
参考youtube→ 播磨暮らし探訪30 頭人行事(八朔祭)

 「信州の伝承文化 長野県無形民族文化財」様HP
「信州の伝承文化 長野県無形民族文化財」様HP
→武水別神社の頭人行事(国選択無形民俗文化財)
【 トンド 】
トンド・ドンドン・ドンダラなどともいう。
すべて囃子調だが、元は火をめぐる足踏みの音から出たようだ。
奈良県山辺郡・三重県の山村地域では、大晦日の夕方に火を焚いてドンドという。
≪正月トンド≫
普通は正月15日に野外で大火を焚く。
トンド正月・ドンド祝い・ドンドヤ(熊本県)などとも呼ぶ。
日取りには、7日・14日・18日・大晦日などがあるが、
この大火の煙に乗り、歳神(正月神・祖先神)は還られるとし、
一方では、虫送りとも考え、松明の火を捨ててくる。
正月に祀る正月様は、トンド焼きの煙に乗って帰るといい、
はるか西の空を高砂の尉(じょう)と姥のような姿が消えて
ゆくとも、長さ2メートル、幅1メートルの大草履を川に流し、
それに神を乗せて帰すなどと、身内の者と別れる親しみを抱いている。
≪主神は道祖神≫
この火祭りの主神は、道祖神になっている。
『古事記』・上巻
――伊邪那岐命が死の国(黄泉国)から、伊邪那美命とその軍勢に
追われ黄泉比良坂(よもつひらさか)の道ふさぎに、大石ひっぱり
だして、離縁を言い渡す。
「その黄泉坂に塞(さぐ)れりし石(千引石〈ちびきいわ〉―道へ引
っ張り出した石(いわ))は、道反(ちがへしの)大神とも号し、
塞坐黄泉戸(さやりますよみどの)大神とも謂す」とある。
『日本紀』・巻一
――その前続きに、「此よりな過(き)ましそとのりたまひて、即ちその
杖を投げたまふ、是を岐神(ふなどのかみ)と謂ふ」とある。
「さえの神」・・・堺目にいる神
「サエ」・・・境・堺の義
「サヤリ」・・・境:堺をする・つけるの意、
境をする樹木をサヤ木(遮木)という。
『記・紀』では石・杖に神が宿り現れた形式による道の神(道祖神)、
道六神・岐神(〈ふなどのかみ〉くなどの神)とあり、仏法では地蔵菩薩
の垂跡だといい、外部の外敵をさえぎり防ぐ意で、サエから遮(せ)き
(=堰き)の神(猿田彦命・天狗)となり、咳を治してくれる神にまでなる。
この神祭りに子供が参加するようになると、主神に代わって小神(眷属
〈けんぞく〉神)・配下の神)が託宣するようになり、次第に信仰祈願を持
ってこの小神に仕え、前もって意外な祟りを避けようとする風習を生じ、
いつとなく道の神は、行旅の愛護者として、仰ぎ敬われることになった。
「道祖神」・・・(※)うながける神・塞の神
男女二神が肩組みをしているものの、女が主で男がそれに
配されている形式に見えるが、女神の手にする徳利は、もと
食物調理器具(杓子か手杵)で、「オナリ神」(水仕〈みずし〉神
―神の仕女)であった。
(※)「うながける」=互いに相手の首に手をかけ親しみあう意
その焚く所――ドンドバ・サエトは村外れ(村境)・道辻・坂の根・橋の袂などで、
この火にあぶった物(餅・団子・芋類)を食えば、年中病気をせぬという。
 『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照



4年ほど前のgooSNS(もう終了したが)で、初めて「どんど焼き」なる
行事があることを知った。その頃は、てっきり「どんど焼き」という
今でも売っている駄菓子のことだとばかり思っていたのだが・・
(コレって単に太鼓のお菓子?みたい)
とにかく、このときは「左義長(さぎちょう)」という言葉が出てこなかった
ので今年まで知らなかった。
ちなみに私の方の(今は無き)実家付近では、たった17件の小さな町
だったからかもしれない(しかもその3分の一は他所から移り住んだ方々
だったように思う)が、大々的な「トンドヤキ」のような行事はなかった。
しかし私は、確かに「トンド」と聞いたことがある。
近所にいた代々農家さんだった家の次女である幼馴染が言っていた。
米を収穫した後に出る籾殻の山、あるいは落ち葉や稲藁のくずなどの
処理で決まった日付けもなく、その都度焼いていたことがあった。
それを彼女は「一緒にトンドあたろうや~♪」と言っていた。
何より、トンドの楽しみはホイルに包んだ芋を忍ばせてあること。
籾殻でゆっくりじっくり焼いた焼き芋は、それはそれは物凄く甘くて美味しく、
大阪市内にKトラックで売りに来る焼き芋やさんの味には満足できなかった。
昔、一度味見で買ったことがあるだけでそれからは買ったことがない。
トンドの焼き芋のあの味は今でも忘れられない!
普通に言う「焚き火」のようなものだと思うが、私はそれを「トンド」
というのだとばかり思っていた。とんどといえば口ずさむ歌がある。
♪ 垣根の垣根の曲がり角~ 焚き火焚き火だ落ち葉焚き~♪
参考に→ http://youtu.be/S9wgi2SlsJA
調べてみれば、この火にあぶった物(餅・団子・芋類)を食えば、
年中病気をせぬという、なるほど、これもとんど行事の一種といえそうだ。
知らず知らずにしてること思えばいろいろあるものですね。



【 リンク集 】
 「どんどやきは日本の国民行事」HP様→ こちら
「どんどやきは日本の国民行事」HP様→ こちら
(NPO法人地域資料デジタル化研究会様)
平成15年より、全国の新聞社WEB版に掲載された記事を主な情報源として、
小正月行事である「どんど焼き」の実施状況を調査し、表形式で比され、
小正月行事「どんど焼き」の全国調査集計(平成25年版)をとられています。
 「PRUNUS なんやん」様ブログ→「どんど焼き」(2013.1.15 記事)
「PRUNUS なんやん」様ブログ→「どんど焼き」(2013.1.15 記事)
1月14日だったのが雨天延期で15日になったそうです。
 どんど焼きの画像検索結果→ こちら
どんど焼きの画像検索結果→ こちら
【 左義長 】
サギッチョ・サンチョ・トンド・オニビ・ホケンギョウ。
三毬杖・三鞠打。正月15日・18日の火祭りをいう。
(今では本来の日に近い土日曜日とかいうところもあるようです)
≪京都≫
カキトンド・・・6日の神年越の夕方に小さく焚くものをいう。
オオトンド・・・14日に大きく焚くものをいう。
この日が重要であったことを「大」は意味する。
ところによっては、14日の方を、左義長といい、
京都とその付近では、もう一度18日にする。
≪九州≫
鬼火焚き・・・7日に焚くのが多い。
大晦日の夕方に焚くのを「トンド」「ドンドヤキ」というところもあり、
年に一度の行事とも限らなかった。
「トンド」は囃子調で、もと足踏みの音からでたらしい。
美しい飾り物があるので、「蓬莱まつり」ともいう。
「サギチョウ」というのも毬杖という祝棒が用いられなくなったため不明なの
だが、本来はただ簡単に、三本の竹、または木の棒の頭部を結んで三脚
にして裾を広げ立てかけたのが三毬杖(さぎちょう)である。
≪関東地方での三毬杖≫
・臨時の火鈎かけや鍋かけ、物干し竿の脚
・刈稲を架け干す稲架
・また広く焼畑や伐採の占有標の一つ
・新墓の上、火葬後には、鎌・石(サギ・チョイシ)を藁縄で
その頂から吊る(落ちた時に死霊は往生するという)
これらは中世以後の作法であり、3本丸太を結び合わせて火祭りの
小屋を組んだからの名で、山から伐り出した木で造ったが、爆音を
聞く目的で竹を用いるようになった。
柱をボクといい、それに心竹を(京都の三毬杖も古くから竹の柱)・
心木と両方があった。その一本が中空に長くつき抜けでていて、
歳神の昇降用(憑代〈よりしろ〉)とし、田面を囲って小屋(サンチョゴヤ・
鳥小屋)とする。
爆竹音などの大きく明るい年はよいという。
所によっては、子供の道祖神祭りの火焚き(サイトヤキや
サイトウバライなどという)と、混同してもいる。
合わせて正月の松飾りやシメ縄など村中のを集め積んで、
焼くことにもなっている。
【 心柱=神の憑代(よりしろ)=御幣(オンペ)】
木の場合・・・オンペ柱(焼かずにとっておく)
竹の場合・・・オンペ竹(この火祭りをオンペ焼きという)
1)正月の神を迎える火の神聖を祝う行事
2)正月を迎えるための忌み籠り小屋を焼き捨てる作法
☆この心柱を村落の守護に必要な地点(道辻・坂の根・橋の袂)
で行い占い、結果的に様々な習俗を生んだものとみられる。
・この火に当たり若返る
・丈夫になる
・心柱が倒れる方角・火勢・焔色・音響でその年の意凶卜する
・餅花、繭玉などものを焼いて食う(力餅という)と風邪をひかぬ
・残りの灰を体になすり付けて病気をよける
 『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照

【 リンク集 】
 日牟禮(ひむれ)八幡宮の左義長祭は→ こちら
日牟禮(ひむれ)八幡宮の左義長祭は→ こちら
ここでの“左義長”とは高さ約3メートルの三角錐の松明〔たいまつ〕の上に赤紙や
くす玉、扇などを飾り、正面に干支にちなんだ「だし」を飾り付けたもの。
町の人々の力作である“左義長”と、信長の踊りの姿に由来するとされる化粧した
若者たちに注目が集まる(信長は身分を隠すために、花笠を被り、女物の
長襦袢を身に着けて踊ったといわれる)。
昨年のお写真、夜空を焦がす炎の中の龍の姿は見事なアートです。
 大磯の左義長祭(2013)は→ こちら
大磯の左義長祭(2013)は→ こちら
大磯の左義長はセエノカミサン(道祖神)の火祭りで、セエトバレエと呼ばれる。
その由来はこちら→イソダドットコム
 新熊野(いまくまの)神社の左義長祭→こちら
新熊野(いまくまの)神社の左義長祭→こちら
(1月15日)
今年は殻つきに鬼の面が付いていたので、つい買ってしまいました。
【節分】
立春の前日およびその行事をいう。
朔望暦である旧暦法では、立春を改暦の目安として、
立春に先立つ朔(ついたち)を元日と立てるのが原則であった
がゆえ、「立春正月」といわれ、立春の日に正月朔(ついたち)
の来る年をとくに賀した。ただ、閏は月が単位であるから、
正月に先立って立春がくることがある。
「年のうちに 春は来にけり。
ひととせをこぞとやいはん、今年とやいはん」 「古今集」巻一(一)
という在原元方の歌は、それをいったもので、立春正月
の感覚を明らかに伝える。
節分の夜を「年越し」といい、節分行事に正月行事を伝える
のは当然であり、正月行事が節分に移ってきたのは逆だ。
☆「立春大吉」とはり出す・・・中国地方
☆ヤイカガシ・・・節分の夜、鰯の頭をヒイラギの枝に刺して
入り口に挿しておく(全国的)
悪臭を放つもので、邪気悪霊を追い払う。
「土佐日記」の元旦の条には、シメ縄に鯔(なよし)
の頭とヒイラギとを挿すことが記されている。
☆ムシノクチヤキ・・・ネギ・ニンニク・毛髪なども焼き、蛇や田畑の害虫
(鳥・獣)の名を唱え、その害を防ぐ呪い。
淡路島・・・豆を一粒づつ炉に放りこみながら、
「猪の口・ウサギの口・蚤の口・蚊の口」と唱える。
☆豆まきの初見
「花営三代記」応永二十二年(1415)正月八日の条
☆豆で「豆占い」「年占い」
豆を平年には12、閏年には13炉の灰の上に
並べて、その焼け方で月々の天候を占う。
☆「お化け(まいり)」・・・京都・大阪・福岡など
厄年の者が厄をはらう厄落としや、厄払いに枠筋、
色町の者が中心になり仮装してそれぞれの神社に詣でる。
※秋田県毛馬内辺りの「化け」
少女が宿に集まって食事してから変装して町を歩いたが、
これは盆の月の7日目の行事。
☆「ノセマゲ」
6・7歳の小女に髷を結い、紅い手がら(結い初めの丸髷
(まるまげ)の根元などにかける赤色のきれ地)など掛け、
少女―娘になったとし、各戸から貰い集めて調理したもの
を皆で食い、厄をはらうとしている。
 これって現代版略式人形の形代ね。
これって現代版略式人形の形代ね。
人形の枠内に家族全員の姓名と数え年を書いて、
この除災招福祈願豆入れ袋に豆を入れて納め、神社で護摩焚きして頂きます。
 ご参考にどうぞ!
ご参考にどうぞ!
obiログ過去記事→「節分のお化け」(2012.1.20 記)
「お化け」についての我がエピソードなど詳しく載ってます。
リンク先様にて実際に行われたお写真など見れます。
 『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
『日本民族語大辞典』文学博士石上堅:著(桜楓社)参照
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
忌み・物忌み・精進のことを「ヒ」いう。
火・日・水についての清浄さを保つ事が中心になるからである。
≪ヒアケ≫
7日目をいう。
忌み明き=産後・葬式のヒアキともなる
≪ヒノウチ≫
忌(ヒ)の期間=赤(出産)・白・黒(死亡)不浄の期間
日(ひ)・水(ひ)・火(ひ)の内=忌中(きちゅう)のこと
≪ヒダチ≫
先天魂のヒが本来の状態を取り戻し、その霊力・生活力
を発揮する意がある。
産後のヒダチというのもこの忌が終わり、水・日・火を
新たにする時の名で、「肥立ち」の宛字の解説ではわからぬ。
≪ヒノベ≫
月経閉止・先天魂の分離を意味し、懐胎をあらわす。
≪ヒアイ(火相)≫
水相・日相ともいう。
忌である火・日・水の災厄などの折、避難通過をするため
家の両脇に設けてある、約1メートルずつの細道のことをいう。
東京・・・「ヒアワイ(=ヒアハヒ)」
東北地方・・・「ヒヤコ」など
物忌み「ヒ」の根本は、日・水・火の他に災厄を及ばぬよう
にとの遠慮にある。特に忌中の日・水・火には外部の人が
近づくのを避けると共に、常時のそれらと交わる事を忌み嫌う。
≪ヒゴヤ≫
火小屋(忌小屋)といい、ヒヤマ・ヒモヤ・タマともいう。
女性の忌みにこもる場所であり、
主屋から離して設ける小屋である。
月々だけでなく、産褥の折にも使用する。
神人・巫女などに、日(ヒ)を名とするのも、先天魂の「ヒ」と
物忌みの「ヒ」との印象によるのである。
ご参考に!
関連obiログ過去記事→ 「忌≪いみ・いむ≫ ☆ 1 」へ
関連obiログ過去記事→ 「忌≪いみ・いむ≫ ☆ 2 」へ
 『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著
『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著 

大昔の女性に対する「忌み」って、今でいう生理休暇・
産前産後休暇みたいなものも含まれているのでしょう。
神々と話をできるのは女性のみとされていたし、また
神から命を授かる神秘的な身体をもつ女性を尊く有難いものと
いう潜在意識が備わっていたのかもしれないなあと思います。
八百万の神々がいるこの日本においては、農家では、
女性は男よりも無くてはならぬ労働力とされていたものです。
そしてまた、今は世間からはないがしろにされがちな家事・育児
ですが、ちゃんと大昔の人々はこの大事な労働力(仕事)に
お給料代わりのもの(米・作物など)が支払われていたんですよね。
といっても税金代わりの年貢をよけたものを皆で分けるというような
方法だったのでしょうけどね。
けれど、毎日が辛い仕事だったからこそ、仕事場でさしさわりが
ないように何かと「忌み」というかたちで休暇があった。
今回、「忌み」を調べてみて、「嫌われる」=「仕方がなく避ける」という
ことを知った時、今までとは全く違った昔の生活感が観えてきました。
昔の時代は男尊女卑だったなんていうけれど、これこそ女性に対して
の本当に理解する意味での「忌み」休暇だったのではなかったかと・・
どうどうと「忌み」にこもる「女の家」などは性教育そのものでしょう。
それを男側としても見守ってきたし、男の子としても自覚が持てた。
つまり、女性に対するいたわり、ねぎらいの心さえも自然に備わった
のではなかったのだろうかとつくづく思いました。
現代の生理休暇・産前産後休暇・育児休暇など
有難いものが、ちゃんと出来ているのに、日本では未だに
それらを取りにくい社会に対しての矛盾を感じています。
もちろん今は男女同権という名のもと、生理休暇以外は
男女ともとれるようになってきていると思いますが、
まだまだ実際には取れない会社も多々あるかと思います。
男と女とは身体のつくり自体が違うのだということ、
それを差別、あるいは男女同権と勘違いしてはならないこと、
改めて子供には教えるべきだと思いました。
性教育さえも生活上でしてきた昔の日本、改めて昔の人は凄かった!
今の勉強だけに対する教育熱心さとの違いを改めて感じています。
鬱という病気が多くなった日本・・
医療が発達しすぎて病気は治り、長生きはすれど、
精神的な社会の補足がまだまだ足りない日本・・
まだまだ矛盾だらけの日本・・
これから何処に向かって往くのだろう。。。
≪ 日忌み(ヒイミ) ≫
生産に携わらぬ日のことをいい、物忌みを続ける日としている。
☆最も厳重な「日忌み」・・・「6月晦日のナゴシ」
一年の切れ目であるり、
この日を特に「イミ」ともいう。
人々は海水に浸り、またはそれを汲んできて飲み清め身を祓い、
その幸福を牛馬にもわかち与え、後々には司祭者の意味に用い、
忌みが終わった後の職の讃め詞として「オオ」を加えて、
「オオイミ」「オオミ」といい、春日(和珥〈わに〉)の大祝(おおはふり)
の称号ともなった。
「イムコ」・・・大嘗祭に奉仕する斎女
「イムぺ(斎部)」・・・「物イミ・大物イミ」の名を、伊勢神宮その他の
「社人」の意に用い祭祀関係を総称していう。
「清浄=近づけぬ」という思想感がある。
≪夜(ヨ・ヨル・ヨラ)=新たな日≫
「忌みもの」は約して「ヨモノ」といわれる。
「ヨ」は宵の延長、夕方の後で古くは新たな日、
ひいては、新たな年の入り方のこと。
神の憑(ヨ)りてくる時であり、人々が清まわりのために、
忌み籠っているとき、すなわち、ヨ――斎・忌み・夜を中心にして――
夜深く訪れてくるとされる。
神祭りが宵宮(ヨミヤ)から開始される理由でもある。
(前夜祭・斎忌の意・ショウジン入りともいう)
「ヨモノ」を鼠・狐・狸とするのも「夜物」の義ではなく、
形容詞は、「(※2)ユユシ(忌々し)」で、祭礼の夜籠もりを「(※3)ヨミヤ」・
「(※4)ヨド」というのと同じ。これはヤ行の発音とわかる。よって、
「イミ」・「イム」は、計画あって自ら進んで拘束生活に入ることになる。
・鼠の忌詞・・・ヨルノヒト・ヨルドリ・ヨメドノ・ヨモコドノ・
ユルノヒト(ヨルノヒトの訛)など。
・狐の夜詞・・・・・ヨルノワカイシュ
岐阜県――夜分キツネと口に出すと履物など隠されるといわれる。
東京西郊――夜、玄関に履物を揃えるようにといわれる。
・ヨボリ・ヨブリ・・・松明を振って魚を集めとる夜の魚漁りをいう(岡山・東京)
・死者の着物・・・3日目に洗濯し、一週間水をかけては「夜干し」といい
わざわざ北向きに夜干す。 (長崎・東京・四国・他)
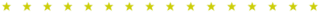
【注釈】
(※1)「斎(ユ)」・・・神秘で霊的な呪力を持っているという信仰上の語で、
これを具有するための準備・動作にも従って用いられる。
清浄を中心にしての戎慎・物忌みの意味。
「イ」と発音、清浄な・斎戎されたなどの意を含有する。
↓
つまり、庶民がたやすく近づくことができないということ。
(※2)「忌々し(ユユシ)」・・・〔形容詞〕:近づきがたい状態を示している
〔命令法〕:「ユメ(慎)」
〔活用語〕:「ユマワリ」
〔修飾語〕:「ユザサ(斎笹)」・「斎庭(ユニワ)」・
「ユツイワムラ(湯津巌群)」
(ユツ=井戸のこと)
(※3)「宵宮(ヨミヤ)」・・・ユウ(夕)・ヨイ(宵)などもユイ(斎日)で
宵宮(ヨミヤ)の行われる時間をさす。
日本の祭りは夕方から始まり翌朝に終わる。
祭礼用語として夕方=昨夜、朝=明朝のこと。
(※4)「ヨド」・・・結人・ユイ人(ユヒと)・交換共同作業仲間のことをいう。
連衆・仲間の意。
正月十五日の晩、田植装束で家々を廻り予祝しえ歩く一団を、
タウエヨド・田植踊などという例もある。
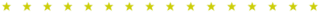
≪ 忌みの「しるし」≫
「オミゴロモ(小忌衣)」・・・その時期につける物
「褌(ちはや)・褶(しびら)の類」・・・大嘗祭に参加する官人の礼服の上につける物
・「ちはや」=たすき。もと、巫女(みこ)の用いたものをいった。
巫女が神事に奉仕するときに着た服。白布で作る。
・「しびら」=衣服の上から裳(も)のように、腰に巻きつけて着るひざ上
までの衣。略儀のもので主に下級の女房の間に用いられた。
その一例で、袖に山藍を用いて、食物の型を摺りだしている、
これが忌みの「しるし」でもあった。
≪ 精進落し ≫
この忌みのまま、すなわち精進のまま人中に出ることはできない。
「精進落し」をしてから人中に出る。
その時、普段着(マナ箸)とは別の精進箸(イモイ箸)で、
海の物(生臭さ物)を食わねば、この忌みは落ちぬと信じている。
喪の明け・盆の時も精進落しをする。盆の時期の漁も、両親を祝福
しにいく生御玉(イキミタマ)の行事も、この忌みの考えに発している。
・「精進」・・・中世の外来語
内容はこのように古く、イモイ・イワイ・イマイと呼ばれ
幸福な結果を予期する禁欲生活であり、もとはイミであった。
・忌みの内容が禁忌に転じたのは、未知の外界に対する一種の
対策後で、忌みがあったため。
・力弱い動物などが常に遁走潜匿に生涯を費やすのに反して、
人々は一定最小限の条件をさえ守っていれば自在に行動しても
いささかも恐れる事なしと確信できた結果のことで、人々の勇気の
根源を養うものとなり、迷信ではない。
≪忌みを気にかけなくなった原因≫
・一般に経験が精確になったこと
・守らなくとも格別の災いは無かった例を知り、それを記憶したため
・異郷人との接触や違った習俗で養われた者が今までの法則をたびたび
破って見せてくれたこと
・忌みの仕事を引き受けてくれる代行者が減ったこと
(異郷人や仲間の中から出た事)
などなど、忌みの不安が人々から無くなっていったからであろう。
≪ 今も残る産の忌み ≫
・産――生誕当座の忌み、ことに産屋の汚れ(赤不浄・白不浄)
を非常に嫌ったが、完全な方法は立たなかった。
・この生誕の忌みは外国にない。
・その忌み明けは、22・23日目のミヤマイリ(ウブヒアケ・ヒアケ)
として行なわれている。
☆しかしながら、忌むべき者の行動もその願いどおりにならぬことに
次第になってきた、一方、儀式や禁忌のやかましい条件が次々と
案出されてなるべく人間の生活に役立ちそうな便宜さを取り入れ、
見慣れない訪問者さえをも最もよい時期に迎えようとした。
(例:クリスマス・バレンタインデーなど)
≪ 豆知識 ≫
この「忌み」の形容詞「イミジ」の訛音
西国地方・・・「イビシイ」
東国地方・・・「イッシイ」
↓
文字に示すと「イシイ」
それが食物に限って、特に敬語をつけた女性用語「オイシイ」となった。
これは、中世以後の上方語「美味」の意で残った。
☆ご参考に!
関連obi過去記事はこちら→ 「忌≪いみ・いむ≫ ☆ 1 」へ
関連obi過去記事はこちら→ 「忌≪ひ≫ ☆ 3」へ
 『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著
『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著 























