さて、下着なんですが、今回は下半身についてのみにします。
昭和7(1932)年12月16日、日本橋白木屋百貨店(元・東急日本橋店)で
起こった 「白木屋の火災」 をご存じでしょうか?
参考URL;http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa_38.htm
それまでは下着をつけなかった女性が、裾がまくれ上がるのを防ごうと
手を離してしまい、何人も亡くなったそうです。
それ以来、女性が下着着用するようになった、と言われています。
今でも着物の時は穿かない方もいます。
でも、穿くのに慣れてしまって、穿かないと気持ち悪い人がほとんどです。
今は、和装用下着がいろいろでています。
参考URL; http://fuuryusi.cool.ne.jp/underwear.htm
参考URL; http://www.click-6.com/
≪肌に密着する順番≫
着物用パンツ → 肌襦袢(腰巻) → 長襦袢 → 着物
【おまけ】 ↓↓ なお、和装ブラジャーについては、ここが理解しやすいです。
参考URL; http://e-wazakka.com/html/report_wbra.htm
****************************
最後に、も一つ、気になることが・・・
女性には毎月、必ずやってくるものがありますよね。
(不規則な方もいらっしゃいますが・・)
その時はどうしていたと思います?
実は私は経験済みです。三度も・・・。
一度目は、小学五年生のとき、亡き実家の母が作ってくれました。
子供ながらに、(え~、こんなんで大丈夫?)と思いました。
二度目は、長男を産んだとき。
そして、三度目は次男を産んだとき。
売ってるんですね~、お産用が。 ーーー もう、わかりましたよね

今までに着付けをした中で、
特に若い娘さん方がよく言う言葉がありました。
「4~5時間我慢できるから、トイレ我慢します。」 
人式の着付けの場合、90%以上 の人がそうでした。
そして、100%の人が普段穿いているショーツでした。
一応、ラインが目立たないようにと、皆さん気をつけておられましたが・・ 
振袖の場合のトイレの行き方は、袖を前でゆるく結びます。
後ろで結ぶのはちょっとひとりでは無理ですから。
(普通の着物の時は、帯板のところに袖をはさむか、ピンチで帯に留めておきます)
そして、一枚一枚着物の裾をめくっていきます。
終われば、その逆で戻していきます。
その都度、ちゃんと整えるのを忘れないで下さいね。
そして後ろの帯の垂れがめくれていないか、手探りで確認してください。
以上、トイレの行き方でした。
慣れてくれば、もっと自分なりの方法が見つかるでしょう
和装の時は時間がかかるので、少し早めに行くといいですよ。
ちなみに私は全部いっきにあげて抱え込むタイプ。
サイドが紐に近いぐらいのショーツを愛用♪
慣れると案外できるもんです。
皆さん、我慢しないでちゃんと行きましょう


でないと他の病気にかかっちゃいますよ。

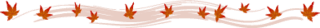
もっと詳しく知りたい方、画像付き解説を見つけました。
↓↓↓
懇切丁寧に順を追って紹介されています。
股割ショーツの話なども参考になります。
(2010.11.18 追記)
第十四話、≪試験≫
「では、今日は一時間目総復習の後、二時間目にテストを行います。」
「テストは、ペーパーテスト40分、振袖の着せ付けと桧扇20分です。」
「ペーパーテスト後、モデル役は長襦袢を羽織ったまま用意して、
着せ付け役は長襦袢を着た状態に準備して待って下さい 」
」
とうとう、着付けのテストが、緊張の中始まった。
ペーパーテストはどんな問題が出たか、なぜか全く覚えていない。
ただひとつ覚えているのが、
『将来、着付けとどのように係わって行きたいか 』
』
というような問題かどうかは覚えていないが、そんな答えを書いた記憶が残っている。
・・で、着せ付けの方はというと、
『桧扇』というと、振袖用変わり結びの基本型の一つ「立て矢系」の一種である。
三基本型中、一番形が整えにくい分野でもある。
基本型1.「文庫系」・・(一番簡単なんだよね~ 基本は。)
基本は。)
例)文庫・片流し・一文字・雅・平安桜
基本型2.「お太鼓系」・・(左右バランスがちょいと難しいかなぁ )
)
例)ふくら雀・後見・扇重ね・花筏・熨斗太鼓
基本型3.「立て矢系」・・(上下バランスかなり難しく、整えにくいんだよね~ )
)
例)立て矢・桧扇・リボン立て矢・立て矢蝶
さすがに、最終段階試験にふさわしいものを選んでくる。
しかも、長襦袢からだともう時間が足らない。
幸いなことはベルト使用 これが腰紐使用なら到底無理
これが腰紐使用なら到底無理
猛練習の甲斐あって、なんとか間に合った。
たった一枚の、私が自分で買った振袖をこんなに使うことになろうとは・・
その強い怨念・・いや!因縁のこもった振袖がなんだか私をここまで
導いてくれたような気さえしたものだった。
しかも、二年前の成人式には、姪っ子にも貸してあげて喜んでくれた。
その前にも誰かに貸した覚えがある。
我ながら、くたびれにくいものを選んだものだと、今になって思う。



(当時、ただ気に入って購入しただけだと思うが・・)
 やっぱり、着物って素晴らしい
やっぱり、着物って素晴らしい

つづく。。。
第十三話、≪経営指導科≫
「経営指導科受講に際しての心得事、意義、目的意識など、
少し説明させて頂きます。・・」
「では、3分間スピーチとしまして、自己紹介してもらいましょうか 」
」
(えー、3分もでけへんわ~。 )
)
高等師範修了者、または終了見込者を対象とした人に、自宅開校の資格取得、
なおかつ経営していける高度な講師を養成する講座ができた。
高等師範に引き続き、私達が第一期生として、受講することとなった。
教本はなく、毎回参考資料のプリントが配られた。
その日授業の内容によって着物を着ていかなければならない。
当学院だけでなく、他の学院からも来るので恥ずかしい真似はできない。
先生として動いている人のほうが多かった第一期生。


科目は全部で七つ。
1.話法・・・表現力・対応力・説得力 (解っちゃいるが喋られな~い )
)
2.経営・・・着物講習会の演出法 (そんなにうまくは行かないよ )
)
3.礼法・・・立ち居振る舞い、敬語、電話の掛け方 (一応大丈夫・・ かあ )
)
4.和裁・・・肌襦袢作成、半襟つけ (これだけは自信があるんだな )
)
5.ヘアーメイク・・・実際相手にするんだって (知らないよ、帰れなくなったって )
)
6.講義・・・教授法について (ちんぷんかんぷんぷん  )
)
7.実技・・・おー これだけはしっかり習いましょ
これだけはしっかり習いましょ
いつまで、着付けは続くのか

ちょっと嫌気がさす日もあったわさ

やっとこれが終われば開放か ・・の前にテストがありました。
・・の前にテストがありました。
つづく。。。
第十二話、≪花嫁の着付け≫
「初めて、花嫁衣装ができたのは室町時代。婚礼は神聖なるものとして
白地の表着、帯、打掛を着るようになったのが、婚礼の始まりです。・・」
「では、二人ひと組になって、前手と後手に別れて着せつけていきましょう 」
」
「じゃあ、私がぁ、お化けになるわね~ 」
」 
高等師範科で最も興味深かったのが、花嫁の着付けである。
突然、『お化け』なんて言葉が出てきて、え~、どういう意味と、
生徒達はわいわい言い出した。
「私もお化けなりた~い 」 (爆笑)
」 (爆笑)
一番年配の生徒が言った。
おばあちゃんが派手な衣装を着ることを、お化けというらしい・・。
ふーん、なるほど。(納得)ーーーいや、失礼
私は一番若手だったの。やること成すこと全て初耳。
しかも、高等師範の教科書は肝心なところが全て白紙。
なんという、不親切さ・・ まいったよ~
もちろん、解かっていますとも。
表現力の勉強の一つってことは。。。
結婚してから、こんなに勉強するとは思わなかったな。

そして、着付けは次の段階へと進むのである。
つづく。。。
第十一話、≪高等師範科≫
「みなさん、おはようございます。これより、第一回、高等師範科を開校致します。」
「担当講師とサブの講師の紹介と、生徒さんの紹介をしましょう・・」
「では、授業要領をご説明いたします。」
まだ、生徒さんを受け持つ半年ぐらい前のことである。
手結びを軸とした、主に『変わり結び』の基本技術を教える
『高等師範科』という新しい科ができた。
当然のように、私にも話がきた。
手結びは、基本はOK (でも、見ただけでも結べれるようなりた~い
(でも、見ただけでも結べれるようなりた~い )
)
まだよく理解できてないとこもあるよね。(そうやんね~ )
)
だいたいでしてみるけど。(やっぱ、仕上がり、みっともな~い )
)
だから、着付けをもっとよく理解できるようになりたいんやん

しかし、ここで唯一の難関 ーー夫の猛反対。
ーー夫の猛反対。
「もう着れるのに、なんでー 」 (私は人にも着せたいのっ!)
」 (私は人にも着せたいのっ!)
「子供どうすんねん 」 (おばあちゃんにみてもらうやんか!)
」 (おばあちゃんにみてもらうやんか!)
「とにかく、あかん あかん
あかん 」 (なんでやねん!)
」 (なんでやねん!)
高等師範は学院へ通うことが必要だったが、主婦が家を空けるということが、
許せなかったようだ。まだ、次男が幼稚園児だったこともある。
それに自営業だったことも理由の一つか・・
このころの夫はなんだか、考えが古臭く、頑固だった。
ーーーこうなりゃ、最後の手段。
ーーー夫の弱みにつけこんで、丸めこむしかないね。。
そそくさ~と私は義母に相談しに行った。・・そう、夫は母に弱いのだ。
効き目はてきめん
めでたく冒頭の高等師範科へと進めたのであった。
今も昔も、義母は私の味方であり、
実の親娘と間違われるぐらいである。


つづく。。。
第十話、≪確認≫
「明日○月○日、午後一時からでしたね。間違いございませんね
では、お伺い致しますので宜しくお願いします。」
「はい、お待ちしております。 」
」
「では今日、午後一時前に最寄りの駅に着いたら一度お電話しますね。」
授業の約束日・時間は、前回には取り付けておくのだが、一度、
家を出る時、慌ててしまって、うっかり確認の電話をするのを忘れたことがあった。
時間どおりにお宅へ伺ったのだが、お留守だった。ということがあった。
それからというもの必ず、確認の電話をするようにしていた。

ところが・・である。何度かけても電話に出ない
家に行っても留守。学院にも連絡なし。
ーーーうっそ~ 信じられな~い
信じられな~い (な~に考えてんでしょ!)
(な~に考えてんでしょ!)
ーーー折角着物着て来たのに~ (やっと、着付けできる!言ってたのにぃ。)
(やっと、着付けできる!言ってたのにぃ。)
と、初めは思うのだが、すぐに 、
『急な用事でもできたのだろう。もう帰って来るかも、後10分・・』
と思い直して、電話のある喫茶店で好きな本を読みながら待っていたり、
初めて来た所だったら、近くを散策したりして楽しんでいた。

いつまでも腹立たしく思うのは心に余裕がないから・・・
どんなに悪態をつく人でも、必ず一つは良いところがあるもんだ。
そう思って付き合ってみると、あ~ら 不思議・・
不思議・・
どんどん、良いところが見えてくるのである。

当時まだ、携帯電話も今のように広まってなかったので、
公衆電話が連絡手段だったが、探すのも一苦労だった。
・・・もしあの頃、ブログをやっていたなら、
カメラ片手に、ブログネタでも探しながら散策できて、
もっと楽しかったかも知れないなあ。。。



つづく。。。
第九話、≪わがまま≫
「だって、先生 今日しんどいねんもん。
今日しんどいねんもん。 」
」
「でも、ちょっとだけでも授業させてね。
さっ、一度でもいいから、体動かしましょうよ 」
」
「折角先生来てくれはったんだから、お話しましょうよ~ 」
」
出たよ 出たっ
出たっ
何よりおしゃべり好きな大阪のおばちゃんの本性が。。。
・・・唖然である。
違うでしょ!折角を使うなら「授業しよう。」じゃないの?
可笑しいよ、この人はっ・・。
しゃべりだしたら、 もう~どうにも止まらない・・
もう~どうにも止まらない・・
そうなる前に少しでも、授業を進めるのだ (負けるものか!)
(負けるものか!)
この生徒さんに限り、戦闘モードでお宅訪問である。
ーーー初めて本性表したときは、負けてしまったが・・。


(もう少し、授業の方の戦闘ならなんとかなったのだが・・)
得てしてこういう人は、何につけ出来る人であることが多い。
案の定、着付けも上手だった。
一度習ったけど、忘れたのでもう一度習いたいという人だった。
思うに忘れたのではなく、普段、着ないからそう思い込んでいるだけ、
じゃあないの
ーーーしかし、いろいろな生徒さんがいるものである。
ーーー今回の方は、まだ好感が持てる方である。
つづく。。。
第八話、≪授業≫
「少しでも、着付けを習ったことありますか 」
」
「習ったけど忘れたってならないように、体で覚えていきましょうね。」
「頭で考えずに、手が勝手に動くようになるまで毎日練習して下さいね。
じゃあ、一緒にしてみましょうか 」
」
一度はやったことある。でも着れない人が多いのである。
折角習うのだから、生徒さんにとってはやっぱりベテランの先生が
いいと思われるのは当然のこと。(見た目、年配が得 )
)
そういや、私はベテランの先生をお願いしますっ。と言った覚えがある。
しっかりと教えてもらいたいので、とまで言ったのも思い出した。
自分が生徒になる前のことを思い出して、
自分のような生徒だったらいややなと、急に怖くなった。
勝手なものである。立場が違えば、こうも変わるものか
学院長の手ほどきで、「あー言えば、こー言う」 なんて方法も
少しはマスターした。(ちょっと、理屈っぽくなったかも・・)
質問攻めにあった時の逃げ方などもバッチリ (うまくいくかしら?)
(うまくいくかしら?)
OK OK
OK 大丈夫
大丈夫 大丈夫
大丈夫 (ドキドキ、どきどき。。
(ドキドキ、どきどき。。 )
)
半ば、自分に元気をつけながら授業を重ねて行った。
ーーー初めての生徒さんは、無事このまま最後まで行きそうだ。
ーーーさて、今度の方は・・っと。
つづく。。。
第七話、≪着装指導講師≫
「すっごくきれいに着れるよう、なってきはったね~
覚えも早いし。。素質あるから先生やってみませんか 」
」
「えっ、でもまだまだ自信ありませんし、教えるなんて・・。」
「誰でも最初は自信ないのは当たり前ですよ。でも、人に教えることにより
自分の確かな技術となっていくものだと思いませんか 」
」
当時、まだ高等の科ができていなかった。
復習講座へやってくる生徒の中から、学院長の目にとまった人だけが
声をかけられ、先生の道へと進むことができたのである。
ほめ上手な学院長に、おだて上手な講師陣。

ついその気になって、『着装指導講師』、(このとき初めて知ったのだが、
着装を指導する先生のことを、そう呼ぶらしい←そのままやん)になったのである。
この時代、生徒上がりの講師は少なく求人募集の講師の方が多かった。
こうして、着付けの生徒さんを受け持つこととなったのである。
その頃の私は、
教えるなんてとんでもない。(聞いてる方が大好きなのよ~  )
)
だって、話の進め方がわからない。(ほんとは話、へたなのよ )
)
うわ~、どうしょうしゃべれな~い。(・・・沈黙・・・)
どうして、どうして先生になったのさ。。

ー--と、内心ひやひやの連続だった。
ここで役にたったのが、復習会の講師陣のたわいない会話だった。
何でも好奇心を持って聞いておくのも為になるなあ。
後は、学院長直伝の、長時間にわたるトーク技術
ーーーこれが一番つらかった~
しかし、これが一番人生に役立っているなあと今になって思う。


つづく。。。






















