今日気になることを会社のママたちが話していました。
ここいら辺の小学校は地区ごと集まって集団登校するのです
が、2学期になるので、上級生は不登校の子を誘って連れて
きてあげるよう校長先生から言われたそうです。
1年生ですでに不登校とはなぜなんでしょう。
友達できない、いじめられる、面白くない、落ち着けないなど
あるとおもいますが、原因を突き止めて解消してあげなければ、
また一緒だと思うのですけど・・・はっきり聞いてないから、
なんとも言えませんが、もしかしたらいろいろ試した結果?
かもしれません。最近はこういう子どもが増えているそうです。
明日はこれに関連づく本を読んだので、少し書いてみようと思います。
今日はもう寝ます。
Playback Part 1
山口百恵 プレイバックpart2~イミテーション・ゴールド
youtubeからどうぞ↓
http://www.youtube.com/watch?v=LI0VxVmLY58&feature=related
山口百恵 - 曼珠沙華(完全版)
別名「彼岸花」お彼岸のときに咲くから、と幼い時聞きました。
しかし、かなり嫌われものでした。毒があるからでしょうか。
田んぼのあぜ道でよく見かけた花でした。
独特な花の形・真っ赤な花に魅了されました。
私は好きだったので、この歌が出た時嬉しかったですね。
百恵ちゃんの歌はすべて思い出の歌です。
帯ちゃんシリーズ、第三弾!
今回は、帯ちゃんことさっちゃん自身が想い出語りをしています。
さっちゃんは彼との結婚を考え始めます。
するとやはり・・・、気になることが脳裏をかすめるのでした。
引き続き、『 さっちゃんと父 』、どうか宜しく、お見知り置き下さい。。。

≪其の19≫ 突然の告白
「ふーん、これお母さんの写真?」
ちょっとぉ今、目をそらせたやろ~、
どこ見てたの~や~ね。うまくごまかしちゃって・・・・・
「うん!そう!・・・・・・・ねえ、私に似てると思う?」
「え・・・と、どうかなあ?・・・」
そうやんね~!急に言われたら考えるやんね~。
「あんまり、似てないやろ!」
「え、そうかなあ・・・?」
なにゆうねんこのこは???なんて思ってるだろうな~
「・・・本当の親と違うねん。両方とも血が繋がってないねん。」
「えっ!!・・・」
とうとう言っちゃったぁぁあああ~~~
このあとどうすりゃいいのさこのわたし~~~

12月の父の手術から後、彼からは毎日のように電話があった。
今は携帯なんて自分の部屋でもできる電話があって、思いっきり
おしゃべりしてても文句も言われずにすむが、私たちのころは、
家族の前で彼女にTELはあたりまえの光景だった。
家族のほうがそばを離れてくれたりしていたものだった。
彼が私の処への電話中に、毎回のように
「一回遊びにおいで~!」というお母さんの声がしていた。
一度、受話器を奪い取って
「母で~~す。1回、顔見せに来てね!待ってるワン!」
と言ったこともある楽しそうなお母さんだった。
その翌年のお正月15日、成人式の日、私は彼の迎えを待って、大阪の
住吉大社へお参りをしてから、彼のお宅訪問となったのである。

付き合いだして7か月が過ぎたころ、彼の家が以外と大きかったことが
気になっていた。当時ゴルフショップの名残りの入口や金物屋から
電気関連を加えていったような家電製品製造事務所玄関、工場
出入口が横並びにあり、奥行きも結構あろうかと思われた。
私は、ホントのこというと今時古いと言われるかもしれないが、あの
楽しかったお正月のパーティー以来、身分違いを感じていたのである。
だから、初めて会った時のインスピレーション(=私はこの人と結婚
するかも知れない)が、もしかしたら錯覚かもしれないと思い始めていた。
・・・・・もしも別れがあるなら・・・・・
私が彼に秘密を打ち明けたときか、彼が両親に打ち明けた時、
そう思っていた。前者はあり得ない、その自身があった。
気になるのは後者。両親・親戚全てから、もしかして猛反対を
受けるかもしれない。その時彼はどうするだろうか。
「駆け落ち」そんな言葉も頭をよぎった。しかし、これは絶対に
避けなければならない。なにより、父を置いてゆけない。
それに私の血が許さなかった。私は・・・
私から始まるルーツを、血の繋がりを、
幸せな家庭を・・・・・創りたかったのである。
納豆がらみでもうひとつ。印象に残っているものがこれでした。
最初から見たわけではなかったので、納豆がらみ以外を覚えて
いませんが、大阪の天神祭りで有名な、大阪天満宮にある亀池
という池で、納豆菌の実験をしたというのを聞いたのです。
ニュースで聞いたように思ったんですが、違うかも知れません。
これが本当かどうかはネット検索ででてきませんでした。
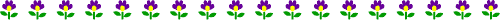
日経スペシャル「ガイアの夜明け」 2006年12月5日放送 第241回
http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber/preview061205.html
![]()
「中国“水の危機”を救え! ~海を渡る日本のエコ技術~」
【納豆パワーで水質浄化】
「水槽の中に入れておくだけで、長期間水が濁らないというブロック
が、観賞魚好きの人々の間で話題になっている。
そのブロックを作ったのは、従業員わずか5人の熊本のベンチャー
企業と福岡のコンクリートブロック会社だ。
ベンチャー企業「ビックバイオ」の阪本恵子社長は、河川の汚染など
自然環境の悪化に危機感を抱く元専業主婦。
水質悪化の元となる有機物やアンモニアなどを分解する
納豆菌群の存在を知り、ブロック会社を経営する古賀雅之さんと
共同で納豆菌をコンクリートの中に閉じ込める技術を開発。
水質浄化ブロックを商品化した。このブロックを河川や池の底に
並べれば、納豆菌が水中の有機物を食べ、水を浄化してくれる。
この水質浄化ブロックは、大掛かりな装置を必要としないことから、
環境対策予算に限りのある新興国の注目を集め、これまでにマレ
ーシアの国家プロジェクトで採用された実績を持つ。そして、「巨大
市場中国にもニーズがあるはず・・・」と次なる目標を定めた。小さ
な企業の技術は、巨大な中国市場で認められるのか。」(引用)
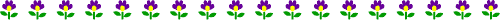
納豆菌ブロック(エコウオータークリーン) はこの番組の後、
大反響があったみたいですね。今回検索してみてびっくりしました。
サプリメントとしても納豆菌 というのが売られていました。
もともと納豆は体に良いといわれていますから、注目しないわけがないですね。
納豆菌と腸内細菌 (http://www.nattoukin.jp/nattou/index.html)
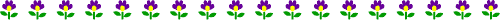
http://www.tokachi.co.jp/kachi/03nou/3-1.html
月刊 現代農業2008年8月号 「あいちゃん」でバラのウドンコ病が減る
http://www.ruralnet.or.jp/gn/200808/kant.htm
ここで出てくる市販の納豆菌農薬とはボトキラー®水和剤でした。
ボトキラー®水和剤
http://www.idemitsu.co.jp/agri/biseibutsu/botokira/index.html
出光興産 から始まった、納豆がらみ検索、やっと終わります。
出光さんちょっと好きなので・・。
http://www.ikiikigarden.com/t_01.html
テラコッテムは高吸水性ポリマーという水を吸収する物質が中心と
なっています。ほら紙オムツでおしっこを戻さないタイプがあるでしょう。
基本的にはあれと同じ物質です。でも紙オムツは水をもどさない。
このテラコッテムは水を適度に吸収し適度なタイミングで戻します。
http://www.ikiikigarden.com/t_seibun.html
テラコッテムは10年もの間、製品の効果が持続するそうです。 10年経てば植物の根が充分に張って役割を終え、役目を終えた テラコッテムは分解され土に帰ります。環境汚染の無害性は、 各種試験のデータより証明済みとのことです。
1983年に、ウィリアム・ヴァン・コッテム博士 とゲント大学(ベルギ http://www.ikiikigarden.com/cottem.html ー)の植物形態学、 分類学、生態実験室の研究者チームが、西 アフリカのサハラ地帯の不毛な土地に、いか に少ない量 の水分で植物を栽培するかという方法の研究を開始したことから 始まったようです。
・成長促進材
・肥料
・高吸水性樹脂
・キャリア


昔、私がみたのはこれだったように思います。
「粉1キロが、水1トンを吸収?」
1994年、9月。
九州大学農学部、原助教授の研究室
http://www.idemitsu.co.jp/idemitsujin/10.html
「耳掻き一杯ほどの白い粉で、1000倍ぐらいまで吸収できる。
純度を上げれば5000倍まで吸収できる。しかも、吸水性ポリマーは
納豆の糸の成分、つまりアミノ酸でできているから、土にまいたっ
て、自然に分解されるから地球にも優しい。夢はね、いつかこの
ポリマーで、砂漠の緑地化を実現することなんだ。」
このときは、納豆の糸(ポリグルタミン酸、再生産可能なバイオ
ポリマー)からということに驚きましたね。

納豆樹脂=納豆の糸に放射線(コバルト60、ガンマ線)
リンク有 を照射するとできる。
↓ 100%天然素材・エコマテリアル
(生分解性、吸水性、可塑性を特徴とする)
透明なハイドロゲル=納豆樹脂が水を吸収すると膨潤してできる。
納豆のネバネバ1gで5Lの水を蓄えることができる。
これは市販の紙オムツの5倍の吸収力。
これが、ジェル状の美容製品から、紙オムツ、砂漠の緑化
へと研究されてきたようです。しかしこのネバネバということ
から納豆を使うという発想からして凄いことだなあと思います。マテリアルです。現在、「食べられる容器」の試作にも成功しています

ちなみに普段よく使われている紙オムツや生理用品などは
こちらの方が多いみたいですね。
日本触媒/紙おむつ向け高吸水性ポリマー
http://mytown.asahi.com/hyogo/news.phpk_id=29000200803190001
この不思議な物質の開発に当初からかかわってきた同社吸水性
樹脂研究所の上席研究員、入江好夫さん(59)は「実は失敗と
偶然の産物なんです」と打ち明ける。
自ら試作品の紙おむつを付けて何百回とおしっこをしたそうです。
身をもって実験しながら改良を重ねたそうで、やはり自分で経験
するのが一番よくわかるものなんですね。
そういや介護で初めてのおしめを嫌がる人がよくいると聞きますが、
薦める側の人(介護人)は一度、自分ではいてみて気持ちを
知ってみるのもいいかなと思いましたね。
http://www.shokubai.co.jp/product/akua_ca.html
【参考に】
紙オムツが漏れない理由
↓↓↓
http://www.caremanagement.jp/kao/special/special02.html
http://www.ktv.co.jp/s-concept/080824_06.html
昨日夕方の関西TVの番組でしたが、サウジアラビアの紅海の
海水を引いて海老の養殖をしているのを見ました。
えぇぇ~~??って感じでついついみてしまったのですが、昔は
マングローブという植物のあるところで養殖をしていたので、それが
進んだのかと思いきや、何もないところでの養殖といいます。
取材地であるNPC社は1999年創業の企業。
エビ養殖事業のあり方が問われていた時代に、およそ200億円
を投じて不毛の地である砂漠を開拓、海岸線で60キロにもわたる
広大なエビ養殖場を始めた。東京ドーム、513個分の養殖池。
育てられているのは、学名がインディカスというホワイト系のエビ。
このエビが一番この海水に合っていたと言います。
≪砂漠にプラントがある2つの理由≫
① 不毛の地を有効活用できるから
② 隔離された環境だからこそ叶う完全管理。
エビの交配から孵化するため、何かあったときに、27代まで
さかのぼっての原因を調べられるといいます。
そして必要なエサも全て自前で作られているので、安全性が高い。
夜中に水揚げをして鮮度が落ちないうちに処理を行います。
最大25トンの処理能力がある加工場で、鮮度を保ったまま冷凍されます。
エコな世界一の安全な海老と言っておられました。
日本でも「アラジン魔法のエビ」として販売されているようです。
(↑↑↑リンクしています)
こちらは「アラジン魔法のエビ」だけでネット販売しています。(追記)
↓↓↓
http://item.rakuten.co.jp/meidoaomori/otamesiebisetto/
海老臭くなく、身がぷりぷりでなにより美味しい、
とお店の店長さんが言ってられました。
凄いですね。ちょっと注意して見つけたいです。
家紋検索できるホームページを見つけました。
http://www.asgy.co.jp/information.html
ただし、このサイトで表示している家紋・家名の数量・分析は
当社の営業エリア内(東京・埼玉・神奈川・千葉各都県)での
受注に基づいたものだそうです。
葬儀のデータを元にしているため、全ての姓、全ての家紋を
網羅することはできないし、 漢字での検索では、基本的に
俗字・外字には対応してないそうです。
地域の違う方は参考程度に見た方がいいですね。
我孫子姓の家紋 検索結果
 |
| 丸に隅立て四つ目 |
|---|
安孫子姓の家紋 検索結果
 |
 |
 |
| 丸に鞠挟 | 丸に星梅鉢 | 丸に片喰 |
|---|
私もやってみましたが、実家も嫁ぎ先も、難字とまでは
いかないのですけど、少々少ない苗字ですので嫁ぎ先は
検索不能でした。実家はやはり関西とは違うようです。
この会社の地方での葬儀データからなので、近くの方なら
確率が高くなるかもしれませんね。
あ、そうそう、「久留子(くるす)紋」なんて変わった紋もありました。
聞いたことない家紋も結構ありました。
ちょっと面白いホームページです。
苗字を調べてみて、いろんな人の苗字に対する意見を見てきた。
「よさみ」から始まって、「あびこ」これはたくさんあったな。
「鮑子」に関係して、もっとあとからと思っていたのが先に例が出て
しまって、「魚介珍姓」まで説明を必要としてしまった。
やっとひと区切り付いたって感じでちょっと休憩。

ネットで検索していて思ったことを少し。
自分のが地名に関係なかったし現在残ってるのも関係ないように
実際と結び付かない。あるいは地名と一緒で土地のものであると
証明されてるみたいなものだ。など・・様々な意見があった。
私は、土地は自然風化現象で何十年、何百年と、どんどん変わ
っているのだから、苗字をつけた最初の人がここは海だったから
それにちなんだものをつけたとて、何百年あとはどこを見渡しても
海はなかったり、山が噴火して谷になっていたり、それはあって
当然だと思う。今は残っていないからと書類や当地を実際調
べた処で本当のところはわからない。そう思っている。
たかだか、私が生きてきた何十年の間でさえ、凄い町の変
わりようだ。遥か昔の文献が全て残っているわけがない。
小さな村のある一人の人の言うことなどいちいち全て書き印
せるわけがないと思うからである。
私が参考にしている丹羽基二氏の辞典もご自分で歩かれて
集計されたようだが、当時と住所が変わっていたりしている。
すでに無くなってしまった土地も多々あろうかと思う。

要するに何が言いたいかというと、推定でものを言うのならば、
人が一生をかけて残したものを間違いであるというのはどうか
ということ。間違ってるところもあるだろうが、合っているところも
あるだろうと思うのです。少し自分勝手な意見とであったので、
私の主張をさせていただきました。
私は丹羽氏の考えに納得できるものを感じ、その研究を
尊敬する者です。よって、ありがたく使わせて頂いています。
賛同できる方のみご覧になって頂ければそれで満足です。
























