≪ 日忌み(ヒイミ) ≫
生産に携わらぬ日のことをいい、物忌みを続ける日としている。
☆最も厳重な「日忌み」・・・「6月晦日のナゴシ」
一年の切れ目であるり、
この日を特に「イミ」ともいう。
人々は海水に浸り、またはそれを汲んできて飲み清め身を祓い、
その幸福を牛馬にもわかち与え、後々には司祭者の意味に用い、
忌みが終わった後の職の讃め詞として「オオ」を加えて、
「オオイミ」「オオミ」といい、春日(和珥〈わに〉)の大祝(おおはふり)
の称号ともなった。
「イムコ」・・・大嘗祭に奉仕する斎女
「イムぺ(斎部)」・・・「物イミ・大物イミ」の名を、伊勢神宮その他の
「社人」の意に用い祭祀関係を総称していう。
「清浄=近づけぬ」という思想感がある。
≪夜(ヨ・ヨル・ヨラ)=新たな日≫
「忌みもの」は約して「ヨモノ」といわれる。
「ヨ」は宵の延長、夕方の後で古くは新たな日、
ひいては、新たな年の入り方のこと。
神の憑(ヨ)りてくる時であり、人々が清まわりのために、
忌み籠っているとき、すなわち、ヨ――斎・忌み・夜を中心にして――
夜深く訪れてくるとされる。
神祭りが宵宮(ヨミヤ)から開始される理由でもある。
(前夜祭・斎忌の意・ショウジン入りともいう)
「ヨモノ」を鼠・狐・狸とするのも「夜物」の義ではなく、
形容詞は、「(※2)ユユシ(忌々し)」で、祭礼の夜籠もりを「(※3)ヨミヤ」・
「(※4)ヨド」というのと同じ。これはヤ行の発音とわかる。よって、
「イミ」・「イム」は、計画あって自ら進んで拘束生活に入ることになる。
・鼠の忌詞・・・ヨルノヒト・ヨルドリ・ヨメドノ・ヨモコドノ・
ユルノヒト(ヨルノヒトの訛)など。
・狐の夜詞・・・・・ヨルノワカイシュ
岐阜県――夜分キツネと口に出すと履物など隠されるといわれる。
東京西郊――夜、玄関に履物を揃えるようにといわれる。
・ヨボリ・ヨブリ・・・松明を振って魚を集めとる夜の魚漁りをいう(岡山・東京)
・死者の着物・・・3日目に洗濯し、一週間水をかけては「夜干し」といい
わざわざ北向きに夜干す。 (長崎・東京・四国・他)
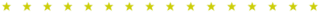
【注釈】
(※1)「斎(ユ)」・・・神秘で霊的な呪力を持っているという信仰上の語で、
これを具有するための準備・動作にも従って用いられる。
清浄を中心にしての戎慎・物忌みの意味。
「イ」と発音、清浄な・斎戎されたなどの意を含有する。
↓
つまり、庶民がたやすく近づくことができないということ。
(※2)「忌々し(ユユシ)」・・・〔形容詞〕:近づきがたい状態を示している
〔命令法〕:「ユメ(慎)」
〔活用語〕:「ユマワリ」
〔修飾語〕:「ユザサ(斎笹)」・「斎庭(ユニワ)」・
「ユツイワムラ(湯津巌群)」
(ユツ=井戸のこと)
(※3)「宵宮(ヨミヤ)」・・・ユウ(夕)・ヨイ(宵)などもユイ(斎日)で
宵宮(ヨミヤ)の行われる時間をさす。
日本の祭りは夕方から始まり翌朝に終わる。
祭礼用語として夕方=昨夜、朝=明朝のこと。
(※4)「ヨド」・・・結人・ユイ人(ユヒと)・交換共同作業仲間のことをいう。
連衆・仲間の意。
正月十五日の晩、田植装束で家々を廻り予祝しえ歩く一団を、
タウエヨド・田植踊などという例もある。
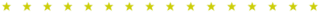
≪ 忌みの「しるし」≫
「オミゴロモ(小忌衣)」・・・その時期につける物
「褌(ちはや)・褶(しびら)の類」・・・大嘗祭に参加する官人の礼服の上につける物
・「ちはや」=たすき。もと、巫女(みこ)の用いたものをいった。
巫女が神事に奉仕するときに着た服。白布で作る。
・「しびら」=衣服の上から裳(も)のように、腰に巻きつけて着るひざ上
までの衣。略儀のもので主に下級の女房の間に用いられた。
その一例で、袖に山藍を用いて、食物の型を摺りだしている、
これが忌みの「しるし」でもあった。
≪ 精進落し ≫
この忌みのまま、すなわち精進のまま人中に出ることはできない。
「精進落し」をしてから人中に出る。
その時、普段着(マナ箸)とは別の精進箸(イモイ箸)で、
海の物(生臭さ物)を食わねば、この忌みは落ちぬと信じている。
喪の明け・盆の時も精進落しをする。盆の時期の漁も、両親を祝福
しにいく生御玉(イキミタマ)の行事も、この忌みの考えに発している。
・「精進」・・・中世の外来語
内容はこのように古く、イモイ・イワイ・イマイと呼ばれ
幸福な結果を予期する禁欲生活であり、もとはイミであった。
・忌みの内容が禁忌に転じたのは、未知の外界に対する一種の
対策後で、忌みがあったため。
・力弱い動物などが常に遁走潜匿に生涯を費やすのに反して、
人々は一定最小限の条件をさえ守っていれば自在に行動しても
いささかも恐れる事なしと確信できた結果のことで、人々の勇気の
根源を養うものとなり、迷信ではない。
≪忌みを気にかけなくなった原因≫
・一般に経験が精確になったこと
・守らなくとも格別の災いは無かった例を知り、それを記憶したため
・異郷人との接触や違った習俗で養われた者が今までの法則をたびたび
破って見せてくれたこと
・忌みの仕事を引き受けてくれる代行者が減ったこと
(異郷人や仲間の中から出た事)
などなど、忌みの不安が人々から無くなっていったからであろう。
≪ 今も残る産の忌み ≫
・産――生誕当座の忌み、ことに産屋の汚れ(赤不浄・白不浄)
を非常に嫌ったが、完全な方法は立たなかった。
・この生誕の忌みは外国にない。
・その忌み明けは、22・23日目のミヤマイリ(ウブヒアケ・ヒアケ)
として行なわれている。
☆しかしながら、忌むべき者の行動もその願いどおりにならぬことに
次第になってきた、一方、儀式や禁忌のやかましい条件が次々と
案出されてなるべく人間の生活に役立ちそうな便宜さを取り入れ、
見慣れない訪問者さえをも最もよい時期に迎えようとした。
(例:クリスマス・バレンタインデーなど)
≪ 豆知識 ≫
この「忌み」の形容詞「イミジ」の訛音
西国地方・・・「イビシイ」
東国地方・・・「イッシイ」
↓
文字に示すと「イシイ」
それが食物に限って、特に敬語をつけた女性用語「オイシイ」となった。
これは、中世以後の上方語「美味」の意で残った。
☆ご参考に!
関連obi過去記事はこちら→ 「忌≪いみ・いむ≫ ☆ 1 」へ
関連obi過去記事はこちら→ 「忌≪ひ≫ ☆ 3」へ
 『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著
『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著 
「忌(いみ)」
他との接触を避けねばならぬ者とそれを取り巻く者との間に、絶対に
守られなければならぬ信仰感覚によって保ち持続される状態をいう。
≪物忌みの展開≫
・三重県度会(わたらい)郡→「忌(うま)れ」
・香川県三豊あたり→「忌(おそ)れ」
・広い意での呼び方→「忌(ひ)」・「服」=ブク・ボク(服忌の服の意)
・「穢(けが)れ」も「清さ」も「忌」
これらの忌を犯すと、罰・祟りを受けた。
中世以後には「物忌(ものいみ)」という語を多く使う。
① 忌を守らねばならぬ状態をいう。
祭りに奉仕する者がすべての外から来るものを
避けようとする場合。
② 忌を守る任務にあたる者をいう。
物忌の父・母、物忌役の娘や巫女を言う場合。
③ 特別に清いものをいう。
神の用にしか立てぬものにつけておく一種の徴章(しるし)や、
忌衣の模様のような場合。
古くから忌(ひ)は人に属するもの・日・土地に属するものなどがあり、
その制限はよく似ている。
山の神の春秋の祭りの日は午前中山に入ってはならないとか、
地神祭りの「金忌(かないみ)」とは農耕用の金物をいっさい使わぬこと
などは、「イミ」とか「ダチ(火物ダチ・青物ダチ)」と呼び、
ショウジン(鶏精進)ともいう。
≪忌みの内容変化≫
「イミ」・・・嫌(きら)うというのではなく、一日中行いを謹んで、
農作などを控えるということ
「ナエミノイワイ」・・・播種後四十九日・五十日目に苗をとらず
祝うとし、「苗厄(なえやく)」ともいう。
神が苗代へ降り賜うと信じたゆえであろう。
すなわち、「ヤク」と「イミ」と「イワウ」の連関が考えられる。
忌を犯すと身に罰・祟りを受けた印象は、斎戒を意味する事から禁忌
の意となり、転じて厭悪(=いまわし)の意義さえ生じた。この過程には、
神が人の間に天降られるために人は銘々謹慎したのだが、後には畏怖
のあまりそうすると考えるようになり、伊豆諸島のように海南坊(カイナンボウ)
などの怪物・異人などの来臨を説くこととなった。
≪別火生活≫
〔壱岐の島の例〕
葬式時、身内の一定の者だけが分け食う物が、「火の飯」といわれる。
「火」・・・「忌」の義
「火が悪い」・「火が清い」などと用いる。
「ヒデ」・・・忌飯料・香典を意味する。
忌むものは、別火の生活をするゆえに、「イミ」のことを「火」ともいう。
正月十五日に、青少年戒の行事のひとつに、浜・野などに籠をつくり、
そこで煮炊きしたものを食い合う(イソモチヤキ)こと、自分の家の火を
用いぬ盆籠・辻飯なども、忌火(別火)思想の現われであり、通例月毎
の下弦の一夜は、物忌みの日であり、その次の日に祭りを行う。
全国で行われている、「とんど」・「どんどやき」など。
↓↓
「とんど・どんどやき・左義長へ (後日更新予定)
「忌≪いみ・いむ≫ ☆ 2 」は→ こちら
「忌≪ひ≫ ☆ 3 」は→ こちら
 『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著
『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著 
【梵語 samraj ・チベット語 samlarjas】
サムライといい、王者・武士を意味する。
稲水(いなひ)命は「古事記」によっても、
海に入り鉏持(さひもち)命になったとある。
これらのサム・サヒは、剣・刀の義で、それを持っている者のことになる。
「さぶ」・・・「覚む・醒む」に関連する内容を含む語
「さぶろう」・・・「伽」の本義に通じるもの
そのもののそばにくっついていて邪霊が犯さぬように
心配りをし、命令に応じてどんな呪法でも、作法でも
行える態勢をとっていることをいう。
自然と敬語・丁重な味がつきまとう。
☆「紫式部日記」
「よゐの僧のさぶらふ御屏風をおしあけて、
この世にはかうめでたきことまだえ見じと言ひ侍りし」
夜中護身役として勤める僧が同候しておられる御屏風を開けて、
「この世でこんなに立派なものはご覧になったことがありますまい」
☆新潟県東蒲原郡地域
毎年付きまといやってくる台風を、藁人形であらわし、
「サブロウドノ」と呼び、6月27日に村はずれで各家から
子供も大人も出て、コウセン(麦こがし)を供えて祭るのも
邪霊除却の心からの態勢が感じられる。
≪男文と女文≫
この「候」の多くなってきたのは流行の一つで、
古いもの・正統のものほど少ない。
「女文」の流行につれて――
男名であっても女房宣(女房が書いたもの)は、「さぶろう」を
語尾に洒落・気分的につけたのを、男子がマネをし増してきて、
軽い対話的な味を感じさせた。
元来、気張った古風な堅さが、「そろ」といいたくなる慣れ親しむ
消息文・会話体―口語体の砕けたものに変わったのである。
その一方には、
「御座り奉る」式の男文が固い文語体の候文になったのが、
往来文の「候」は剛直な一定の型を作り、女文のは、
「一筆しめし参らせ候」にはじまり、懸想文も一定の型を、
やはり律文的な柔軟な味を含めて保っていたのである。
 『日本民族語大辞典』石上堅:著 参考
『日本民族語大辞典』石上堅:著 参考 

なんと!!
サムライという語も始まりは仏教語からだったのね~、驚きでした!
「候文は日本語ですョ。」と昔、師匠がおっしゃっていました。
なるほどね~♪
男性が想いを寄せる女性に出す恋文にはやはり
優しく聞こえる柔らかい言葉が必要だったのでしょう。
流行るものってやはり今も昔も似てるのですね~♪
ようこそ
おしゃべり広場☆ 4 へ
いつの間にかもう秋!
突然のブログ長期休暇になってしまいました。
皆様にご心配おかけ致しまして申し訳御座いません。
しかしながら留守中にもご訪問戴ける方々がいらっしゃること
嬉しいかぎりで有難く思っております。
感謝!!
この夏、異常な天候に悩まされ続けましたが、
皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?
季節の変わり目のさらなる変化の多いこれからの季節、
どうぞ皆様、お体に気をつけてくださいませ~♪
勝手気ままな更新の我ブログで御座いますが、
これからも宜しく御贔屓のほど、お願い申し上げます。
いつも有難う御座います。



〔初めてのご訪問の方へ〕
ココは、
ブログ記事に関係なくおしゃべりできる場です。
何方様でも参加できます。
もちろんブログに関することでも OK!
お気軽にどうぞおしゃべりしていってくださいな~♪
宜しければ、
gooブログ新機能「読者登録」も宜しくお願いします。
(2013年7月より開始)
 ご参加者様へお願い事!
ご参加者様へお願い事! 
1)常識あるネチケットでよろしくお願い致します。
2)アダルト・勧誘・商用のみのご参加はお断りしております。
3)日本語ならば外国人の方でも参加可能です。
お約束を守れないコメントは、
管理人の独断と偏見で削除致しますので
ご了承戴きたく願います。
~~~~下記更新履歴 2013-01-01 09:13:00~~~~
皆様、新年明けましておめでとう御座います。
旧年中はご訪問頂き、また楽しいおしゃべりをさせて頂き、
感謝と共にお礼申し上げます。本当に有難う御座いました。
本年も引き続きご贔屓受け賜りますように
宜しくお願い申し上げます。
今年一年、皆様方に幸多かれと祈ります!
2013年 【癸巳】 睦月
~~~~下記更新履歴 2012-12-26 21:25:00~~~~
今年も残り僅かとなりました。
この年末に衆議院選挙で政権が変わるという、
慌しい師走となりましたがいかがお過ごしでしょうか。
今年一年、ご訪問・コメント戴きました皆様方、
いろいろとお世話になり本当に有難うございました。
来年も変わりなきお付き合いのほど
よろしくお願い申し上げます。
それでは何方様も
良い年末年始をお過ごしくださいませ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
2012年4月2日
NHKスペシャル「人体“製造” ~再生医療の衝撃~」
http://www.at-douga.com/?p=5154
前に見た指を再生させる魔法の粉の正体が動画としてありました。
2010年03月28日に放送された、
NHKスペシャル「人体“製造” ~再生医療の衝撃~」を紹介です。
(所要時間:約50分)
赤く光る珊瑚の遺伝子を組み込まれた豚、
くらげの遺伝子を組み込み緑に光る遺伝子を持った鼠、
人の肝臓を豚の体内で作る研究もしている。
豚が選ばれたのは成長が早い上に、大きさが人間に似ているからだとか・・
自分の遺伝子を持った細胞が他の動物の体内で作れるなんて凄い!
本当にどこまで人間は医療技術を進ませることができるのか、
これなら臓器提供者を待つ必要なく、しかも年をいったときに若い頃の
自分の幹細胞で臓器を取替えることができるなんて日がくるかもしれない。
そして、親の愛情がさらなる扉を開く・・
本当に衝撃の動画でした。
最先端の技術を考えるとき、いつも亡き漫画家手塚治氏を思い出す。
博士号をも持つ彼は、化学でも医療でも本当に先見の明があったんだなあ
子供の頃見た漫画の部分部分が現実として少しづつ現れてきていることを
驚くと共に、改めて彼の凄さを感じ日本人として誇りに思います。
しかしそれとともに、人間の欲望の凄さを思わないではいられません。
御炊(みかしき)
≪炊・爨(かし・かしぎ)≫
かしぎ・爨・カシワ(柏)。カシギの原型がカシ(炊)である。
カシグ・・・葉などに包み、湯に入れて蒸すことをいう。
その葉がカシワ・カサノハであり、
カサが椀・椀の蓋などの意になった。
カシギ・・・炊事・食物を作ること。
山村・漁村で、これに当たる若者・少年をカシギという。
≪カシギは山小屋・船舶の炊事役≫
カシギは山神や舟玉様の奉仕者となるがゆえに、舟が遭難
してもカシギだけは不思議にも死を免れると信じていた。
飯櫃の蓋をとり、右手に蓋、その真ん中に左手の杓子で、
飯粒をのせ供える。この役をまた「飯を食おう」ということを、
「マエロ(参ろう)」というゆえ、「マイロシ」ともいう。
≪カシギは火の神と縁が深い≫
カシギの少年は、心の汚れのない純真な徒が食物をつかさどり、
火を神聖に保つ資格ありとされたのである。こうして神に初物を
献じるために、神に愛され身に降りかかる危難を免れている。
すなわち、カシキは神に仕え神を祀るもので、これにあずかる者が、
神意を得るために行う歌舞が、「殊舞」である。
【殊舞(たつつまい)】
起ったりしゃがんだりして舞うゆえというが、家の精霊を小人
(こびと)としていた時代――今のザシキワラシにあたる――
の侏儒舞(ヒキウドマイ)の古いもので室寿(むろほ)ぎの折、
家長の祝福のために小さいものが舞い出たこと・小人舞・
「顕宋紀」である。
この歌舞は、風を呼ぶ神技と後々にはなり、カシキは
風を呼ぶ呪法になっている。
 『日本民族語大辞典』石上堅:著
『日本民族語大辞典』石上堅:著 
苗字いろは歌 (伊) 古代珍姓珍釈篇へ
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
東北関東大震災復興支援クリック募金も行われています。
↓↓↓

いつもありがとうございます!
【 おみくじ 】
神社・・・御神籤(御籤・御御籤とも)
寺院・・・御仏籤
くじ=偶然を利用して物事を機械的かつ公平に決める方法のこと。
おみくじ=「くじ」に神意を求める方法
普通のくじとは違う一線を画すが為に、
丁寧語の「御」「神」という文字を入れる。
≪おみくじの誕生≫
平安時代の末ごろ
物事の善し悪し、重要事項の決定、勝敗の決定、後継者人選、
物事の順序の決定などの際、神の意思を知るための方法として始まった。
≪主なやりかた≫
短籍方法・・・竹・木片・紙片などに人名・事項などを書いておき、
神様に祈ってから、ひとつを引き出す。
≪神社のおみくじは鎌倉時代から≫
☆南北朝の歴史物語中の記述・・・『増鏡(ますかがみ)』
「四条天皇崩御の知らせを受けた第3代執権の北条泰時が
鶴岡八幡宮でおみくじを引いて、後継の君を決めた」
☆室町時代の中ごろ(正長元年〈1428〉)
将軍・足利義持の急死のため、次期将軍決定のための
くじ引きが、京都の岩清水八幡宮で行われ、足利義教(よしのり)
が第六代将軍となった。
コレ以後今日に至るが、神様の目前でくじ引きを行うことで、
神意をより正確に把握する目的があったと思われる。
≪おみくじは神意の表れ≫
つまり、単なる吉凶判断は禁物ということ。
今後の生活に生かすべきもの。
大吉・・・油断大敵
「あとは下がる」と考えて気を引き締めるべき。
凶・・・・・新たな出発点
「自分を見つめなおすチャンスをもらった」と考えればよい。
読み終えたおみくじを境内の樹木に結びつけるのも悪くないが、
神様からのメッセージとして自戒の意味で持ち歩き、
新しいおみくじを引いたとき、神社に納めるのが最良のやり方である。
 『図解知ってるようで意外と知らない 神社入門』 渋谷申博:著
『図解知ってるようで意外と知らない 神社入門』 渋谷申博:著 

あらら~、
今まで大吉だけを一年間のお守り代わりに
財布に入れて持ち歩き、吉凶や吉でも
あんまりよくないこと書いてあったら
境内の樹木に災難祓いに結び付けていたけれど、
ちょっと考え方違うみたいですね~。
自戒のため・・・かぁ、
じゃあ、
どっちかいうと全ておみくじは持っていた方が良いみたい、
だって何が書いてあったか忘れちゃうもんね~。(笑)
去年のを「有難う御座いました」と
新年にお納めする方がいいってことね。
あ、去年でなくても、良くないのは
次に引いたときに納めればいいのか、
次からはそうしようっと♪
大吉でも油断大敵!
わかっちゃいるけどやっぱり喜んじゃいますね。
【 八坂神社の由来 】
平安京遷都以前東山一帯に住んでいた渡来人の八坂造
(やさかのみやつこ)の氏寺に起源する。(八坂神社由来より)
八坂神社はながらく、「祇園社」「感神院」などと称したが、
明治維新の神仏分離にともなって、「八坂神社」と改称した。
 八坂神社公式HP→ こちら
八坂神社公式HP→ こちら
(伝説)
八坂氏の祖先、伊利之使主(いりしおみ)が、656年に朝鮮半島から
移住してきて新羅の神をまつった。この新羅の神がのちの素戔鳴尊
(すさのおのみこと)と同一の神様であるとされ、これが八坂神社になった。
この伝説により祇園信仰の本社争いなるものがあったらしく(今も続いて
いるのかな?)、広峯神社(姫路市)の記事に祇園信仰の本社争いのこと
が書かれている。 (姫路市)広峯神社記事はこちら→ ◎京都・八坂神社との関係
(姫路市)広峯神社記事はこちら→ ◎京都・八坂神社との関係
(戸原様HPより)
【 八坂 】
八坂神社や八坂の塔がある京都市の東側の山麓の一帯。
古代には「愛宕(おたぎ)郡八坂郷」と呼ばれていた。
現在では東山区に、八坂上町の小地名(町名)だけが残っている。
≪大和時代のやさか≫
古代には、八坂氏という中流豪族に支配されていたが、
八坂の地名は八坂氏にちなむものではなく、呪術的な意味をもつもの。
説1)坂を下ると異界に入り込むことがあるという迷信から
坂の多い東山山麓地帯を異界に繋がる地で「八坂」。
説2)様々な悪霊を鎮魂する地が「やさか」
「安らかに魂を休息させる処(ところ)」が「安息処(やさか)」。
かつて東山山麓で、人々に災いをなす霊魂を集めてしずめる
まつりが行われて来た。そのため「安息処」と名づけられ、
読みやすい「八坂」の表記になったという。
【 八坂の塔 】
古くは八坂寺と呼ばれたが、聖徳太子が建立したものとも
八坂氏がひらいたものとも伝えられている。
八坂寺は古代の大寺院だったが、平安時代に有力寺院どうしの
抗争にまき込まれて消失した。
その後、臨済宗(鎌倉時代の禅宗の一つ)の寺院として
永観寺(えいかんじ)と改名された。
何度かの焼失と復興を繰り返したのちに、1440年に建てられた
八坂の塔 を残すだけになってしまった。
 『意外な歴史が秘められた関西の地名100』 武光誠:著参照
『意外な歴史が秘められた関西の地名100』 武光誠:著参照 
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
東日本大震災 復興支援クリック募金もあります。
↓↓↓

いつもありがとうございます!
新年おめでとう御座います。
昨年中はお世話になり有難うございました
本年もよろしくお願い申し上げます。
2013年初詣 京都八坂神社
いつもの初詣いって参りましたが、
なんと、おみくじは何十年ぶりかの凶でした~。
ま、これ以上、下はないから落ち込まないほうですが、
我家の場合、
廻りの家族へ受難の火の粉が降りかかるようです。
25年以上前のときは、マーちゃんが
元旦早々かゆいかゆい病にかかりました。
(正式に診てもらってないから病名わかんないけど)
今日は案の定・・
ゆうちゃんが事故!
え~~! 大丈夫かぁ~~~?
とびっくりしたのですが、
自分の車だけだったので誰も怪我もなくよかったです。
ダーリン:「ゆうちゃんも凶やったらしいでぇ~~(笑)」
私:「人乗せてる時ぐらいもっと運転気をつけんとぉ~!」
いや~~、なんにしても
笑える不幸でよかった、よかった!!
ゆうちゃんたちも京都八坂神社行ってきたらしいです。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
東北関東大震災復興支援クリック募金も行われています。
↓↓↓

いつもありがとうございます!





























