2か月に一度開催される築地居留地研究会の研究報告会、3月のテーマは「築地居留地と近代音楽――讃美歌と青年たちの出会い」だった。講師は築地居留地研究会理事で明治学院大学元客員教授の中島耕二さん、昨年11月の「築地居留地ツアー」と同じ先生だった。
築地居留地は日本に7つある居留地のひとつで一番遅く1869年に開市した。横浜や神戸のように貿易がメインにならなかったが、キリスト教各派の教会やミッションスクールが多く存在した。西洋文化の入口となり、讃美歌をはじめ西洋音楽が神戸・横浜と並び、ここから広がった。
この日は講演だけでなく、合唱や独唱、エクスカーションもある充実した楽しめるプログラムだった。なお下記のなかで、山田耕筰についてはこの日の講演以外に自伝も参考にした。
●日本の洋楽はペリーとともに
日本の近代音楽(西洋音楽)は1853年7月のペリーの浦賀来航の時点から始まった。この軍艦には軍楽隊も乗り込んでおり、ペリーは熱心なプロテスタント信者だったので、一行は讃美歌539番「あめつちこぞりて」を合唱した。
日本が開国し横浜に居留地ができると、本国から聖職者も呼び寄せられた。宣教師兼医師のヘボンは1863年に横浜でヘボン塾を開いた。ヘボン塾と関係の深い教会が住吉町教会(現在の横浜指路教会)で、西村庄太郎(1864―1931)少年が通っていた。女性宣教師からオルガンを習いあっという間に演奏技術を身につけ、住吉町教会のオルガニストを務めるまでになった。
●築地大学校の4人の青年たち
やがてヘボン塾の後継のバラ学校が1880年に築地に移転し、築地大学校となった(居留地7番)。
隅田川沿いの築地大学校跡地にはいまはマンションが建つ
西村もそれに同行し築地にやってきた。築地大学校の授業はすべて英語だった。このころ官軍ではない士族の子弟は官僚では出世できそうにないので、別の道、すなわち英学(英語)を身につけ最先端の知識で勝負しようと進取の気性に富む青年たちが、日本全国からこの学校に集まった。
そのなかに音楽のセンスに優れた3人の青年がいた。3人とも西村と同年代だった。 築地大学校の生徒は新栄教会に行くことになっていた。1873(明治6)年設立の日本で二番目に古い教会だ。西村は、大学校や新栄教会で3人の青年に楽譜の読み方やオルガンの基礎などの手ほどきをした。 築地大学校を卒業後、3人が3人とも音楽取調掛(現在の東京芸大音楽学部)に進学し、日本の音楽教育のキーマンとなった。
一人は納所弁次郎(1865―1936)である。納所は岐阜の士族だが、築地で生まれた。2人いた姉がクリスチャンで幼いころから讃美歌を聞いて育った。築地大学校や新栄教会でも讃美歌漬けとなり、音楽取調掛卒業後、母校や学習院の教員になり、言文一致唱歌を広めた。有名な曲では「うさぎとかめ」や「桃太郎」(ただし岡野貞一作曲ではない曲。田辺友三郎作詞のほう)がある。、また官立学校の教員だったので「旅順陥落軍歌」「仁川の海戦」などの軍歌も作曲した。「うさぎとかめ」は讃美歌461番有名な「主、われを愛す」のリズムやメロディと似たところがある。
2人目は小山作之助(1864―1927)である。小山は新潟生まれで築地大学校で英学を学ぶため16歳で上京し、納所とともに新栄教会の礼拝にも出席した。音楽取調掛卒業後、長く母校の教授を務め、滝廉太郎を育てた。唱歌では「夏は来ぬ」、軍歌では「敵は幾万」の作曲で有名だ。
3人目は前橋出身の内田粂太郎(1861-1941)だ。17歳でヘボン塾の後継バラ学校に入り、築地移転に伴い築地大学校や新栄教会に通った。音楽取調掛卒業後、いったん郷里の群馬師範学校に勤めたあと音楽取調掛に戻り、三浦環や山田耕筰を教えた。唱歌では「秋景」(あきげしき)、その他「孔明」「紫式部」などを作曲した。さて3人の音楽の先輩、西村庄太郎は札幌農学校に進学したが、父の急死で中退し横浜の外国商社で働いた。お茶の貿易で成功し、アメリカ出張中に高峰譲吉と出会い、タカジアスターゼの日本での販売権を許され、友人2人と作った会社が三共(現・第一三共)だった。音楽の道ではないが、西村もこうして立身出世を遂げた。 また3人が進学した音楽取調掛は1879年に設置され、伊沢修二(1851―1917)が掛長(のち1887年に東京音楽学校に改編され初代校長)だった。伊沢は長野県高遠出身で16歳で上京しジョン万次郎に英語を学んだが、万次郎が欧米に出張したあいだ、カロザース宣教師夫妻の英語塾で学んだ。カロザースの塾は、まだ築地居留地がなく築地の雑居地にあった。つまり伊沢は、西村らより10歳以上年長だったが、やはり築地に通っていたわけで、この地は日本の西洋音楽や音楽教育と縁があるということだ。
●銀座育ちの北村季晴
明治も中期になると、井上馨の欧化主義推進などで、上流階級の家庭では洋服・ベッドの洋風の生活が進み、音楽の世界でも管弦合奏の演奏など西洋音楽が根付くようになった。そんななか北村季晴(1872―1931)は静岡生まれだが、家族の転居で5歳から銀座で育った。居留地にあった東京一致神学校のフルベッキ宣教師からオルガンを習った。北村は東京一致英和学校(築地大学校の後継)に入学したが、この学校が白金に移転し明治学院になったとき、ヘボンに「音楽を目指すならこの学校より東京音楽学校のほうがよい」と勧められ転校した。卒業後、青森や長野の師範学校で教えた。作曲では日本初のオペラ「露営の夢」「ドンブラコ」や長野県民にいまも愛唱される「信濃の国」で有名である。師範学校退職後は東京音楽学校の嘱託や三越少年音楽隊の指導をした。
●大塚淳と山田耕筰
大塚淳(すなお 1885-1945)という音楽家がいる。両親とも熱心なクリスチャンで一人息子の淳を連れて新栄教会に通い、淳は明治学院卒業後、東京音楽学校に進学した。卒業後、慶応義塾のワグネル・ソサィエティの常任指揮者、新交響楽団(現在のN響)、満州国新京交響楽団の常任指揮者などを務めた。慶応新応援歌の作曲や慶應義塾塾歌の編曲も手がけた。
大塚の母は山田耕筰の母の妹なので、大塚と山田は従兄弟に当たる。しかも山田の1歳年長と年も近かった。さらに山田の姉(のちのガントレット夫人恒)は一時大塚家の養女であった縁もあった。
山田耕筰(1886―1965)は東京・本郷生まれだが2歳のころ横須賀に転居した。一家そろって熱心なクリスチャンだった。7歳まで横須賀で暮らしたが、芝の次姉夫婦の家に移りヤングマン宣教師の第二啓蒙小学校に通った。しばらくして病気がちの父も上京しヤングマンの聖書学館の仕事を手伝い始め、入舟町の第一啓蒙小学校構内に家族で移り住んだ。やがて一家は居留地6番Bのヤングマンの自宅に住みこんだ。山田耕筰の自伝「はるかなり青春の調べ」(かのう書房 1985年)によれば「広い芝生の真中に、とても大きな樫の木のある家だった」とある。

ヤングマンの屋敷があった居留地6番Bも跡地もやはりマンションになっていた
また当時は日清戦争の時期で軍歌の「福島中佐シベリア遠征の歌」「従軍看護婦の歌」を好んだ。自宅では毎日両親や姉が英語で讃美歌を歌い、連れられて行った新栄教会で讃美歌を聞き、洋館から流れるピアノの音楽に心を動かされ、帆前船の船頭が自分の親船を呼ぶ声も聞こえた。父の転地療養で1896年に千葉の幕張に転居するので、耕筰が築地にいたのは10歳までのわずか2-3年のことのようだ。しかし、これら居留地の「音」が耕筰の旋律の原点となった。
父の死後、耕筰は巣鴨の自営館に入り活版印刷の仕事などをした。自営館は働きながら学ぶ苦学を主義とする田村直臣牧師が経営していた。なお耕筰は1900年に数寄屋橋教会で田村牧師から洗礼を受けている。1901年には長姉・ガントレット恒夫妻に引き取られ関西に移り、関西学院に入学、大塚淳のアドヴァイスを受け、1904年に東京音楽学校に入学した。
その後の活躍はいうまでもないが、「この道」「からたちの花」「赤とんぼ」「待ちぼうけ」「あわて床屋」など有名な歌曲・童謡を多く作曲し、オペラ、交響曲、管弦楽曲、室内楽曲、明治大学など校歌の作曲も数多い。また日本交響楽協会や東京フィルハーモニーを設立し指揮したことでも知られる。講演は「築地居留地は近代日本の西洋音楽の発展を担った青年たちを育んでいった重要な場所だった」という言葉で締めくくられた。

この講演のなかで、聖路加国際大学聖歌隊の学生たちにより、讃美歌539番「あめつちこぞりて」、354番「かいぬしわが主よ」、小山作之助作曲「夏は来ぬ」、461番「主われを愛す」、納所弁次郎作曲「うさぎとかめ」、山田耕筰作曲「この道」、そして「聖路加国際大学校歌」の7曲が披露された。讃美歌の影響をメロディを通して実感できた。とくにわたくしには「白楊の緑すがしく 学び舎は 光みちたり いざ友よ つどいはげまん 人の世に 愛をもたらす・・・」の校歌が、詩も讃美歌風であることもあるのだろうが、讃美歌そのものに聞こえた。講演で紹介された日本の作曲家が全員男性であったのと比較して、合唱したのは全員若い女性たった。偶然のことだが、これも明治と21世紀の築地の対比を目で見るようだった。
また長野県出身の方がいて、突然の指名で北村季晴作曲「信濃の国」を独唱された。「信濃の国は十州に 境連ぬる国にして」で始まり、信州の山、川、湖、原など自然と観光が織り込まれ、県歌にふさわしい詩でできていた。そして参加者全員で山田耕筰作曲「赤とんぼ」の2番、4番を歌った(1番は聖歌隊による合唱)。変化に富む講演となった。

その後、旧・聖路加病院正面で恒例の記念写真を撮り、エクスカーションとして居留地跡地に向かった。新栄教会の跡地、山田耕筰一家が一時住んでいたヤングマンの家があった6番B、築地大学校があった7番、ユニオンチャーチのあった17番、古いレンガ塀やガス灯を見て回った。桜の開花宣言から2日目で、チラホラ咲く花をながめることができた。日本人作曲家が幼年時代や青年時代に歌ったり耳に入った讃美歌のメロディは、その後自分がつくる曲のベースとなり、実を結んだ。その背景として、築地居留地のキリスト教会やミッションスクールの存在があったことに留意すべきことがよくわかった土曜の午後だった。
●アンダーラインを引いた語句はリンクを貼っている。なかには音楽が出てくるものもあるのでお楽しみに。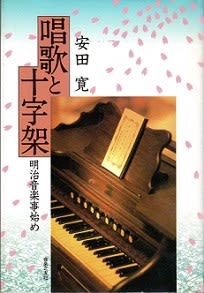
☆講演のなかで、讃美歌と小学唱歌の関係をミステリー仕立てで描いた「唱歌と十字架 ――明治音楽事始め」(安田寛 音楽之友社1993)という本が紹介された。日本で初めて唱歌教科書「小学唱歌集」初編が発刊されたのは1882年で、アメリカ人のお雇い外国人ルーサー・ホワイティング・メーソンが編纂し伊沢修二が助手を務めた。全部で33曲あり、はじめの12曲はメイソンのチャートが出典で音階練習のようなもの、5曲はメーソンがアメリカで作った教科書に収録されたもの、4曲は日本人が作曲したもので、西洋歌曲は残る12曲になる。そのうちじつに5曲が日本で古くから歌われた讃美歌のメロディと一致した。
しかし歌詞は純日本風、天皇讃美の歌詞もある。その背景には、文部省内の洋学派と儒教派の熾烈な闘いがあったからだそうだ。 その他、「たんたんたぬきの」は讃美歌687番「まもなくかなたの」、「むすんでひらいて」は一般にルソー作曲といわれそれは事実だが、当時アメリカで「グリーンヴィル」という曲名で親しまれた讃美歌でもあった。
讃美歌がどのように日本の唱歌に取り込まれたのか、著者は、横浜山手のフェリス女学院、西宮の神戸女学院、伊那市上伊那郷土図書室、ボストン公共図書館、メーン州リューイストンなど世界の都市を巡り、その謎をひとつずつ解き明かす。
築地居留地は日本に7つある居留地のひとつで一番遅く1869年に開市した。横浜や神戸のように貿易がメインにならなかったが、キリスト教各派の教会やミッションスクールが多く存在した。西洋文化の入口となり、讃美歌をはじめ西洋音楽が神戸・横浜と並び、ここから広がった。
この日は講演だけでなく、合唱や独唱、エクスカーションもある充実した楽しめるプログラムだった。なお下記のなかで、山田耕筰についてはこの日の講演以外に自伝も参考にした。

●日本の洋楽はペリーとともに
日本の近代音楽(西洋音楽)は1853年7月のペリーの浦賀来航の時点から始まった。この軍艦には軍楽隊も乗り込んでおり、ペリーは熱心なプロテスタント信者だったので、一行は讃美歌539番「あめつちこぞりて」を合唱した。
日本が開国し横浜に居留地ができると、本国から聖職者も呼び寄せられた。宣教師兼医師のヘボンは1863年に横浜でヘボン塾を開いた。ヘボン塾と関係の深い教会が住吉町教会(現在の横浜指路教会)で、西村庄太郎(1864―1931)少年が通っていた。女性宣教師からオルガンを習いあっという間に演奏技術を身につけ、住吉町教会のオルガニストを務めるまでになった。
●築地大学校の4人の青年たち
やがてヘボン塾の後継のバラ学校が1880年に築地に移転し、築地大学校となった(居留地7番)。

隅田川沿いの築地大学校跡地にはいまはマンションが建つ
西村もそれに同行し築地にやってきた。築地大学校の授業はすべて英語だった。このころ官軍ではない士族の子弟は官僚では出世できそうにないので、別の道、すなわち英学(英語)を身につけ最先端の知識で勝負しようと進取の気性に富む青年たちが、日本全国からこの学校に集まった。
そのなかに音楽のセンスに優れた3人の青年がいた。3人とも西村と同年代だった。 築地大学校の生徒は新栄教会に行くことになっていた。1873(明治6)年設立の日本で二番目に古い教会だ。西村は、大学校や新栄教会で3人の青年に楽譜の読み方やオルガンの基礎などの手ほどきをした。 築地大学校を卒業後、3人が3人とも音楽取調掛(現在の東京芸大音楽学部)に進学し、日本の音楽教育のキーマンとなった。
一人は納所弁次郎(1865―1936)である。納所は岐阜の士族だが、築地で生まれた。2人いた姉がクリスチャンで幼いころから讃美歌を聞いて育った。築地大学校や新栄教会でも讃美歌漬けとなり、音楽取調掛卒業後、母校や学習院の教員になり、言文一致唱歌を広めた。有名な曲では「うさぎとかめ」や「桃太郎」(ただし岡野貞一作曲ではない曲。田辺友三郎作詞のほう)がある。、また官立学校の教員だったので「旅順陥落軍歌」「仁川の海戦」などの軍歌も作曲した。「うさぎとかめ」は讃美歌461番有名な「主、われを愛す」のリズムやメロディと似たところがある。
2人目は小山作之助(1864―1927)である。小山は新潟生まれで築地大学校で英学を学ぶため16歳で上京し、納所とともに新栄教会の礼拝にも出席した。音楽取調掛卒業後、長く母校の教授を務め、滝廉太郎を育てた。唱歌では「夏は来ぬ」、軍歌では「敵は幾万」の作曲で有名だ。
3人目は前橋出身の内田粂太郎(1861-1941)だ。17歳でヘボン塾の後継バラ学校に入り、築地移転に伴い築地大学校や新栄教会に通った。音楽取調掛卒業後、いったん郷里の群馬師範学校に勤めたあと音楽取調掛に戻り、三浦環や山田耕筰を教えた。唱歌では「秋景」(あきげしき)、その他「孔明」「紫式部」などを作曲した。さて3人の音楽の先輩、西村庄太郎は札幌農学校に進学したが、父の急死で中退し横浜の外国商社で働いた。お茶の貿易で成功し、アメリカ出張中に高峰譲吉と出会い、タカジアスターゼの日本での販売権を許され、友人2人と作った会社が三共(現・第一三共)だった。音楽の道ではないが、西村もこうして立身出世を遂げた。 また3人が進学した音楽取調掛は1879年に設置され、伊沢修二(1851―1917)が掛長(のち1887年に東京音楽学校に改編され初代校長)だった。伊沢は長野県高遠出身で16歳で上京しジョン万次郎に英語を学んだが、万次郎が欧米に出張したあいだ、カロザース宣教師夫妻の英語塾で学んだ。カロザースの塾は、まだ築地居留地がなく築地の雑居地にあった。つまり伊沢は、西村らより10歳以上年長だったが、やはり築地に通っていたわけで、この地は日本の西洋音楽や音楽教育と縁があるということだ。
●銀座育ちの北村季晴
明治も中期になると、井上馨の欧化主義推進などで、上流階級の家庭では洋服・ベッドの洋風の生活が進み、音楽の世界でも管弦合奏の演奏など西洋音楽が根付くようになった。そんななか北村季晴(1872―1931)は静岡生まれだが、家族の転居で5歳から銀座で育った。居留地にあった東京一致神学校のフルベッキ宣教師からオルガンを習った。北村は東京一致英和学校(築地大学校の後継)に入学したが、この学校が白金に移転し明治学院になったとき、ヘボンに「音楽を目指すならこの学校より東京音楽学校のほうがよい」と勧められ転校した。卒業後、青森や長野の師範学校で教えた。作曲では日本初のオペラ「露営の夢」「ドンブラコ」や長野県民にいまも愛唱される「信濃の国」で有名である。師範学校退職後は東京音楽学校の嘱託や三越少年音楽隊の指導をした。
●大塚淳と山田耕筰
大塚淳(すなお 1885-1945)という音楽家がいる。両親とも熱心なクリスチャンで一人息子の淳を連れて新栄教会に通い、淳は明治学院卒業後、東京音楽学校に進学した。卒業後、慶応義塾のワグネル・ソサィエティの常任指揮者、新交響楽団(現在のN響)、満州国新京交響楽団の常任指揮者などを務めた。慶応新応援歌の作曲や慶應義塾塾歌の編曲も手がけた。
大塚の母は山田耕筰の母の妹なので、大塚と山田は従兄弟に当たる。しかも山田の1歳年長と年も近かった。さらに山田の姉(のちのガントレット夫人恒)は一時大塚家の養女であった縁もあった。
山田耕筰(1886―1965)は東京・本郷生まれだが2歳のころ横須賀に転居した。一家そろって熱心なクリスチャンだった。7歳まで横須賀で暮らしたが、芝の次姉夫婦の家に移りヤングマン宣教師の第二啓蒙小学校に通った。しばらくして病気がちの父も上京しヤングマンの聖書学館の仕事を手伝い始め、入舟町の第一啓蒙小学校構内に家族で移り住んだ。やがて一家は居留地6番Bのヤングマンの自宅に住みこんだ。山田耕筰の自伝「はるかなり青春の調べ」(かのう書房 1985年)によれば「広い芝生の真中に、とても大きな樫の木のある家だった」とある。

ヤングマンの屋敷があった居留地6番Bも跡地もやはりマンションになっていた
また当時は日清戦争の時期で軍歌の「福島中佐シベリア遠征の歌」「従軍看護婦の歌」を好んだ。自宅では毎日両親や姉が英語で讃美歌を歌い、連れられて行った新栄教会で讃美歌を聞き、洋館から流れるピアノの音楽に心を動かされ、帆前船の船頭が自分の親船を呼ぶ声も聞こえた。父の転地療養で1896年に千葉の幕張に転居するので、耕筰が築地にいたのは10歳までのわずか2-3年のことのようだ。しかし、これら居留地の「音」が耕筰の旋律の原点となった。
父の死後、耕筰は巣鴨の自営館に入り活版印刷の仕事などをした。自営館は働きながら学ぶ苦学を主義とする田村直臣牧師が経営していた。なお耕筰は1900年に数寄屋橋教会で田村牧師から洗礼を受けている。1901年には長姉・ガントレット恒夫妻に引き取られ関西に移り、関西学院に入学、大塚淳のアドヴァイスを受け、1904年に東京音楽学校に入学した。
その後の活躍はいうまでもないが、「この道」「からたちの花」「赤とんぼ」「待ちぼうけ」「あわて床屋」など有名な歌曲・童謡を多く作曲し、オペラ、交響曲、管弦楽曲、室内楽曲、明治大学など校歌の作曲も数多い。また日本交響楽協会や東京フィルハーモニーを設立し指揮したことでも知られる。講演は「築地居留地は近代日本の西洋音楽の発展を担った青年たちを育んでいった重要な場所だった」という言葉で締めくくられた。

この講演のなかで、聖路加国際大学聖歌隊の学生たちにより、讃美歌539番「あめつちこぞりて」、354番「かいぬしわが主よ」、小山作之助作曲「夏は来ぬ」、461番「主われを愛す」、納所弁次郎作曲「うさぎとかめ」、山田耕筰作曲「この道」、そして「聖路加国際大学校歌」の7曲が披露された。讃美歌の影響をメロディを通して実感できた。とくにわたくしには「白楊の緑すがしく 学び舎は 光みちたり いざ友よ つどいはげまん 人の世に 愛をもたらす・・・」の校歌が、詩も讃美歌風であることもあるのだろうが、讃美歌そのものに聞こえた。講演で紹介された日本の作曲家が全員男性であったのと比較して、合唱したのは全員若い女性たった。偶然のことだが、これも明治と21世紀の築地の対比を目で見るようだった。
また長野県出身の方がいて、突然の指名で北村季晴作曲「信濃の国」を独唱された。「信濃の国は十州に 境連ぬる国にして」で始まり、信州の山、川、湖、原など自然と観光が織り込まれ、県歌にふさわしい詩でできていた。そして参加者全員で山田耕筰作曲「赤とんぼ」の2番、4番を歌った(1番は聖歌隊による合唱)。変化に富む講演となった。

その後、旧・聖路加病院正面で恒例の記念写真を撮り、エクスカーションとして居留地跡地に向かった。新栄教会の跡地、山田耕筰一家が一時住んでいたヤングマンの家があった6番B、築地大学校があった7番、ユニオンチャーチのあった17番、古いレンガ塀やガス灯を見て回った。桜の開花宣言から2日目で、チラホラ咲く花をながめることができた。日本人作曲家が幼年時代や青年時代に歌ったり耳に入った讃美歌のメロディは、その後自分がつくる曲のベースとなり、実を結んだ。その背景として、築地居留地のキリスト教会やミッションスクールの存在があったことに留意すべきことがよくわかった土曜の午後だった。
●アンダーラインを引いた語句はリンクを貼っている。なかには音楽が出てくるものもあるのでお楽しみに。
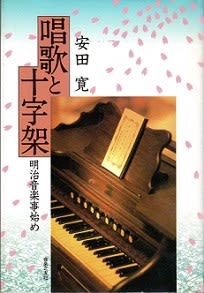
☆講演のなかで、讃美歌と小学唱歌の関係をミステリー仕立てで描いた「唱歌と十字架 ――明治音楽事始め」(安田寛 音楽之友社1993)という本が紹介された。日本で初めて唱歌教科書「小学唱歌集」初編が発刊されたのは1882年で、アメリカ人のお雇い外国人ルーサー・ホワイティング・メーソンが編纂し伊沢修二が助手を務めた。全部で33曲あり、はじめの12曲はメイソンのチャートが出典で音階練習のようなもの、5曲はメーソンがアメリカで作った教科書に収録されたもの、4曲は日本人が作曲したもので、西洋歌曲は残る12曲になる。そのうちじつに5曲が日本で古くから歌われた讃美歌のメロディと一致した。
しかし歌詞は純日本風、天皇讃美の歌詞もある。その背景には、文部省内の洋学派と儒教派の熾烈な闘いがあったからだそうだ。 その他、「たんたんたぬきの」は讃美歌687番「まもなくかなたの」、「むすんでひらいて」は一般にルソー作曲といわれそれは事実だが、当時アメリカで「グリーンヴィル」という曲名で親しまれた讃美歌でもあった。
讃美歌がどのように日本の唱歌に取り込まれたのか、著者は、横浜山手のフェリス女学院、西宮の神戸女学院、伊那市上伊那郷土図書室、ボストン公共図書館、メーン州リューイストンなど世界の都市を巡り、その謎をひとつずつ解き明かす。
























