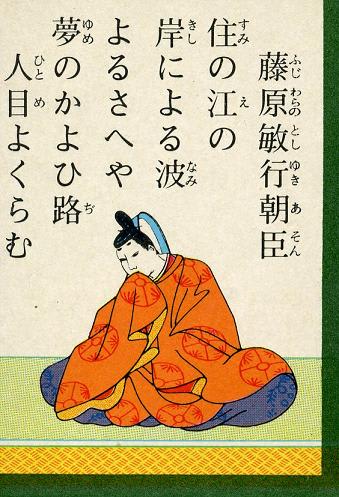その時に、9月20日が「バスの日」ということを初めて知りましたが、今日はこの「バスの日」について調べてみました。
「バスの日」とは、日本で初めて営業バスが京都市内を走ったことに由来し、1987年(昭和62年)に日本バス協会が制定した記念日です。
営業バスの運行は1903年(明治36年)9月20日に、京都の二井商会により、蒸気自動車を改良した乗合自動車で、日本で初めて始まったようですが、明治37年1月には経営破たんで営業を終えています。
その後、1987年(昭和62年)10月の全国バス事業者大会でこれを記念して「いつでも、どこでも、みんなのバス」をテーマに、9月20日を「バスの日」と定めたものです。
・バスの日のポスターです。(日本バス協会HPより)

このポスターのメッセージは、
『今年は「バスでエコ」、環境にやさしく、子供からお年寄りまで親しまれるバス』 を表現しているそうです。
特に、燃料高騰などで厳しい経営に陥っている地域バスをもっと利用し、支援してもらえるよう、緊急メッセージを入れてお願いをしています。
「木炭バス」の思い出
バスといえば、今では見られない、バスの後ろから煙を吐いて走る「木炭バス」を思い出します。
木炭バスとは、バスに積載した木炭ガス発生装置による一酸化炭素と僅かに発生する水素を動力として走るバスです。
・これが木炭バスです。(ウィキペディアより)

日本では燃料用の原油が不足した戦時下の1940年代に使用されていました。
木炭ガス発生装置によるガスの熱量が小さいことや、温度が高くなり吸気効率が落ちるなどの構造上の問題があって、エンジンの発生出力は極めて低く、上り坂では乗客が降りてバスを手で押すといった光景も見られたそうです。
戦後、配給制度が撤廃されて燃料調達が容易になると、瞬く間に新造されたバスに淘汰され姿を消しましたが、田舎の方では暫くは公共交通機関として走っていました。
・バスの後ろに取り付けられている木炭ガス発生装置です。

私の田舎(岡山県笠岡市)でも、戦後間もない頃、木炭バスが走っていたのを記憶しています。形はボンネットタイプのバスで、後部外側に木炭ガス発生装置を搭載しています。
エンジンの出力が低いためエンストをよく起こします。そのときにはボンネットの前に始動用のハンドルを差込み、ぐるぐる回して手動でエンジンを始動させていました。
今では想像もつかないでしょうが、戦中、戦後の貧しい時代にはこのようなおんぼろバスでも公共交通機関として立派に活躍したものでした。
今日は「木炭バス」の名称すら聞いたこともない読者の方たちに、戦後の貧しい一幕をご紹介しました。