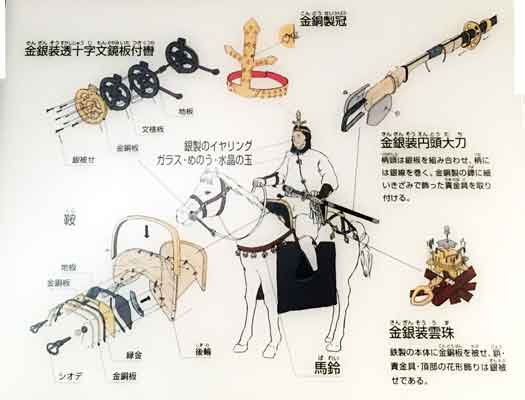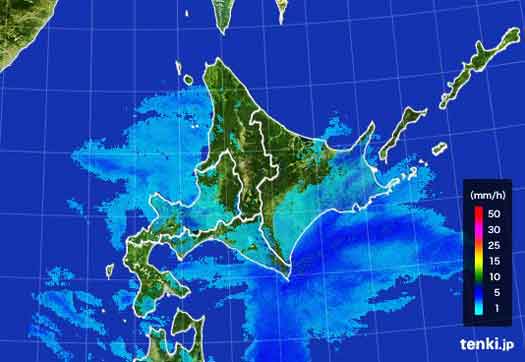ときどき、書斎的な仕事が集中してくる時期があります。
根を詰めて、論理的あるいは説明的な構築をしなければならない時期。
そういうときには、会社からも近い元事務所でもある自宅書斎で呻吟。
いわゆる「創作」的な仕事というのは、なぜか「行き詰まる」(笑)。
で、よく「ゴロッと横になる」。そうすると、ベッドが必要になる。
ということで、本日はふとんと毛布の上下関係。
ちょっと飛躍して無理矢理感ハンパないかも知れませんが、お許しを(笑)。
わたしは生まれてから半分、30年間ほどは
いまの羽毛ではなく、綿のふとんにくるまれておりました。
そういうころには、毛布というのはカラダに直接触れていた。
その上に綿の布団が乗っかっていた。
で、30数年前頃に、ふとんが羽毛布団に変わった。
ちょうどわが家を新築した当時にも当たっていたので、
家中高断熱で、羽毛布団だけでずっと過ごすことが多かった。
その後出張が極端に増えてきて、旅先の布団も羽毛が多くなったけれど、
寒い時期になると、出張先ホテルでは夜の寒さに耐えられなくなってきた。
そこで「あの、毛布ください」と頼んで、掛けて寝る機会が増えてきた。
そのころから羽毛布団の下に毛布を掛けるか、
それとも羽毛布団の上に掛けるか、考えるようになった。
当初は、それ以前のように中に入れる掛け方をしていたのですが、
どうも具合が良くない、違和感が増してきたのですね。
羽毛布団の肌ざわり・寝心地に慣れたせいなのか。
で、一度、羽毛布団の上に毛布を掛けてみた。
そうすると、羽毛布団の体感と毛布の保温性がマッチして
まことにちょうどいいということに気付いて、
以来、ずっと上に掛けるようにしている次第。
ただ、なんとなく体感的にそうしているだけだったので、
世間常識的にはどうなのか、あんまり知識がなかった。
自分はちょっと常識的ではない特殊な寝具利用習慣なのではないかと、
内心ちょっと不安なまま、ここ30年間以上過ごしてきていた(笑)。
こういう「ちょっと自分は違うのかなぁ」感の疑問解消には
インターネット情報というのは、まことにちょうどいい。
で、わたしのような疑問を持っている人も多いことを知りました。
いろいろな情報を総合すると、やはりわたしの体感は常識的なのだそうです。
羽毛布団では、毛布は上にかけた方が合理的とのこと。
長年の喉の奥の支障が解消したような、晴れ晴れ気分であります(笑)。
日本人の寝具が羽毛布団の登場で大きく変わったことが
こうした生活習慣の変化を生んだのでしょうが、しかし、
こういった変化は、情報としてあんまり拡散はしていないと思われますね。
閑話休題のテーマでした。 さて、書斎仕事、集中するぞ!
根を詰めて、論理的あるいは説明的な構築をしなければならない時期。
そういうときには、会社からも近い元事務所でもある自宅書斎で呻吟。
いわゆる「創作」的な仕事というのは、なぜか「行き詰まる」(笑)。
で、よく「ゴロッと横になる」。そうすると、ベッドが必要になる。
ということで、本日はふとんと毛布の上下関係。
ちょっと飛躍して無理矢理感ハンパないかも知れませんが、お許しを(笑)。
わたしは生まれてから半分、30年間ほどは
いまの羽毛ではなく、綿のふとんにくるまれておりました。
そういうころには、毛布というのはカラダに直接触れていた。
その上に綿の布団が乗っかっていた。
で、30数年前頃に、ふとんが羽毛布団に変わった。
ちょうどわが家を新築した当時にも当たっていたので、
家中高断熱で、羽毛布団だけでずっと過ごすことが多かった。
その後出張が極端に増えてきて、旅先の布団も羽毛が多くなったけれど、
寒い時期になると、出張先ホテルでは夜の寒さに耐えられなくなってきた。
そこで「あの、毛布ください」と頼んで、掛けて寝る機会が増えてきた。
そのころから羽毛布団の下に毛布を掛けるか、
それとも羽毛布団の上に掛けるか、考えるようになった。
当初は、それ以前のように中に入れる掛け方をしていたのですが、
どうも具合が良くない、違和感が増してきたのですね。
羽毛布団の肌ざわり・寝心地に慣れたせいなのか。
で、一度、羽毛布団の上に毛布を掛けてみた。
そうすると、羽毛布団の体感と毛布の保温性がマッチして
まことにちょうどいいということに気付いて、
以来、ずっと上に掛けるようにしている次第。
ただ、なんとなく体感的にそうしているだけだったので、
世間常識的にはどうなのか、あんまり知識がなかった。
自分はちょっと常識的ではない特殊な寝具利用習慣なのではないかと、
内心ちょっと不安なまま、ここ30年間以上過ごしてきていた(笑)。
こういう「ちょっと自分は違うのかなぁ」感の疑問解消には
インターネット情報というのは、まことにちょうどいい。
で、わたしのような疑問を持っている人も多いことを知りました。
いろいろな情報を総合すると、やはりわたしの体感は常識的なのだそうです。
羽毛布団では、毛布は上にかけた方が合理的とのこと。
長年の喉の奥の支障が解消したような、晴れ晴れ気分であります(笑)。
日本人の寝具が羽毛布団の登場で大きく変わったことが
こうした生活習慣の変化を生んだのでしょうが、しかし、
こういった変化は、情報としてあんまり拡散はしていないと思われますね。
閑話休題のテーマでした。 さて、書斎仕事、集中するぞ!