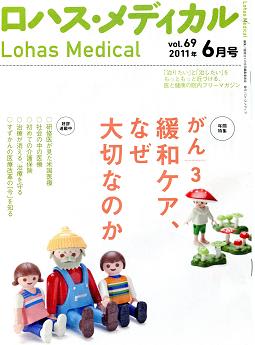ロハスメディカル6月号
とまりぎ
医療機関で無料配布している。
また社会福祉士熊田梨恵氏の「初めての介護保険」に目を向けた。
介護が必要になったとか、必要になりそうだと感じた本人はもちろんのこと、家族も初めての場合どうしたらいいのか見当もつかない。
そういうときに相談する相手を紹介している。
1.ケアマネジャー(介護支援専門員)
居宅介護支援事業所や施設などにいる。介護保険を使える最適なサービスを考えてケアプランを作成してくれる。
2.相談員
各施設やデイサービス事業所などにいる。ケアマネジャー、社会福祉士、介護福祉し、ホームヘルパー1級などの資格をもっている人が多い。
3.福祉用具専門相談員
福祉用具のレンタルや販売する事業所や企業にいる。体の状態に合った福祉用具が選べるよう相談できる。
4.地域包括支援センター職員
各市区町村にある相談窓口にいる。
5.市区町村担当職員
役所の担当窓口にいる。何でも相談できる。
6.社会福祉協議会職員
社協で通じるそうだが、地域によって異なるが役所ではやっていないことまで対応している。
7.民生委員
地域によってなり手が少なく、出来る範囲がちがってくる。
8.医療ソーシャルワーカー
医療機関の中にいて、転院、退院後のことについて相談できる。
といろいろあるが、まったく何も知らない場合、役所の担当窓口で聞いてみると案外よく教えてくれる。
踊子歩道
とまりぎ
幹事の計画では滝も全部見たし、昼食が済んだら踊子歩道を湯ヶ野あたりまで歩いて行こうとしていたようだ。
とにかく「わさび丼」と書いてある「かどや」へ入る。
皆が「かどや」で思い出すのが、相模湖駅前の「かどや」だ。

ビールとこんにゃくおでんを平らげて、わさび丼と言うが早いか鮫皮の山葵おろしをひとつづつ渡され、これでそれぞれ山葵をおろすのだそうだ。
葉の付け根のところを取って、そこから擦りはじめる。どうも早い人と遅い人がいて、早いのは鮫皮が新しいおろし器のようだ。
丼にはご飯の上に「おかか」がかかっている。この上に擦った山葵をのせ、別の皿にくれた海苔佃煮、わさび漬け、味噌を好みで乗せ、醤油もお好みで食べる。山葵はカライだけでなく甘みを感じる。
これで丼だけだと400円だから安い。
七滝のうちの大滝近くの食事処「かどや」だ。電話0558-35-7290
おまけにシーズンのニューサマーオレンジをひとつづつくれて、これもいただいて昼食をおしまいにした。
さて、これから歩きはじめる。

踊子歩道はループ橋の下を通る。


河津川に沿って上がったり下りたりしながら、あるときはつり橋で越えたりして、湯ヶ野までたどりついた。小雨が降ってきたようだが、気にならない程度の霧雨だ。
バス停を見るともう歩く気はなくなり、20分ほど待って乗り込んだ。
帰りの車中で、万歩計を持っている人たちの平均値では1万5千歩ぐらいになった。前日の城ヶ崎も数字はほぼ同じかもしれないが、二日目の方が坂も階段も多く疲れを感じた。
伊豆の踊子の道だから、川端康成が歩いたであろう道を逆方向に歩いたことになる。
運動になった旅で、皆の記憶に残ることだろう。
河津七滝
とまりぎ
河津駅から修善寺行きのバスで、河津七滝(だる)へ行く。
河津では滝のことを垂水(たるみ)と言ったことから変化したタル(ダル)と言うのだそうだ。
一度七滝の入口、河津七滝バス停へ入り、戻って河津ループ橋を廻ってから、国道414号線の途中、水垂(みずたれ)バス停で降りる。
上から急な階段を下りると、最初の釜滝(かまだる)。落差22mで水しぶきがかかる。


二番目にエビ滝(えびだる)。

三番目蛇滝(へびだる)。


四番初景滝(しょけいだる)。

ここまでが山道を歩く感じがある。ここから下は比較的平坦だ。

五番かに滝(かにだる)。

六番出会滝(であいだる)。荻入川が滝の連なる本谷川へ合流して河津川になるところで、ふたつの滝を出合滝というのだそうだが、合流したちょっと下流の流れを写した。

七番大滝(おおだる)。落差30mで七滝のうちで最大の滝。

途中、「わさび丼」をやっている店を見つけておいたので、全員五人でここへ入ることにした。
伊豆高原
伊豆高原
とまりぎ
城ヶ崎海岸駅から伊豆高原駅まで、一駅電車に乗る。
伊豆高原駅は伊豆高原の保養施設の入口になっているから、大きな駅だ。

駅前に足湯があるので入る。泉質の分析表があって、ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩泉というれっきとした温泉だ。夕方4時過ぎに係の人が清掃に来たので出る。


上から線路を眺めていたら、見慣れた東急のマークがついている。
伊豆急は東急グループのようだ。
駅前に宿泊予約のソレイユ伊豆の車が迎えに来ていて、これで10分ほど揺られるうちに宿に着いた。
場所が近いから泉質は似ているが、成分総量が駅前の足湯よりずっと多い温泉へ入って、食堂では6時からの夕食の前に生ビールで乾杯。
部屋へ戻って、すぐに睡眠に入った人もいる。
テレビは全部ディジタル受像機になっていて、画面が大きい。この基金はゆとりがあるようだ。

翌朝、見覚えの天城富士の名がある大室山が間近かだ。2010年には国の天然記念物になったのだという。
昔サボテン公園へ来たときに、登った記憶がある。
グランパル公園も近いが、寄らずにまた伊豆高原駅へつれていってもらう。

展望席のある列車が停まっている。
JRの特急も乗り入れている。
ここから河津駅まで乗って、河津七滝を見ようという計画である。
城ヶ崎
城ヶ崎
とまりぎ
富戸(ふと)港の先へ行くと、海に迫出した城ヶ崎へ入る。

「ぼら納屋」という店が城ヶ崎へ入る場所の目印になっている。


駅から歩いてきたあたりが見える。 岩の上に釣り人がいる。

波が荒く、岩へぶつかって白波が立つ。
廻りこむと灯台の頭が見え、手前につり橋。


定員100名、小錦関26名分の表示にはしゃれが効いている。

ここがよく観光地としてTVに出てくるところだ。
やはり観光客の一番多いところだ。
幹事以外は始めてきたところで、それなりの感興がある。
少し奥へ入ると灯台があり、登る。これがきつい。

灯台についてのデータが、一番上に出ていた。
ここから城ヶ崎海岸駅まで、別荘地の中の緩い坂道を上がる。
富戸駅から歩く
とまりぎ
車中では持ち寄った酒とツマミで話はあっちこっちへ分散したが、昼過ぎに目的の施設へ行く駅にはふたつばかり手前の伊豆急線富戸(ふと)駅で降りる。
海は駅よりも大分下にあるから、下り坂の道をしばらく歩く。
車の通る道からちょっと引っ込んだところに小さなスーパーマーケットがあり、その奥に見えたのが三島神社だ。


神社から振り返ると、海が真下に見える。
伊豆七島が見えるかと、目を凝らしたが大島も見えなかった。

御島神社が三島神社に変ったようだ。
スーパーマーケットで食糧を調達して、海へ向う。

途中の電柱に「津波に注意、この地区は海抜21.0m」とある。
東日本の大津波以後に貼ったのだろうか。
たしかに海から近い。
よく見ると、あたりの電柱にはそれぞれ数字が違った同じような板が着けられている。
このあたりは東海沖地震が起きることを想定しているようだ。

海岸の岩の上で昼食にする。
対岸を見ると、釣のひとがいる。
ちょっと波風が荒いが、釣れているのだろうか。
軽い昼食を済ませると、海伝いの道を南へ向うことにした。
幹事は保養施設へも何回か泊まっていて、このあたりの地理に詳しい様子だった。

富戸港へたどり着き、意外に大きな遊覧船がここから出ているのを見る。
城ヶ崎遊覧船であることがわかったのは、帰りに城ヶ崎海岸駅まで行って、駅にある看板を見たときだったが。
東京駅
東京駅
とまりぎ
改修工事中の東京駅丸の内側の建物の屋根が、姿を現した瞬間だ。

わずか数分前には幌で覆われていたところが開かれていく。
目の前の屋根は、北口だ。
辰野金吾設計当時に近い形へ戻したようだ。
重要文化財だから、改修にも気を使っていることだろう。

もう一つの南口の屋根は、すでに覆いをとっていた。
北口と南口は丸みを帯びていて、優雅な雰囲気がある。
中央口は見えないが、昔の直線的な形になっているはずだ。
東海道線と伊豆急を乗り継いで、東伊豆にある基金の保養施設へ行くために、東京駅7番線のホームから見たところだ。
「とまりぎ」の5人がいつもは中央線の高尾駅へ集合するのだが、はじめての東海道線を使っての旅に集った。
さあ、出発だ。
浦和の湿地帯
とまりぎ
京浜東北線と武蔵野線が交差する南浦和駅から東には、南北に湿地帯が連なっている。
芝川の流れよりも西側に細いのだが下流で芝川へ合流する川が通っている。
芝川には並行する見沼代用水という運河が両側にあって、低いところを流れる芝川と運河との間で、江戸時代にはパナマ運河と同じ原理で船を運行させていた。
日暮里から出ている都営交通舎人ライナーの終点が見沼代親水公園という駅名になっているから、流れはつながっているようだ。
一方、芝川は荒川へと注ぐ。
南浦和駅より武蔵野線でひとつ東の東浦和駅からちょっと歩くと、この芝川の通船堀跡を見ることができる。


湿地帯の向こう側の家々が見える。
ここを歩いて渡ることができ、過去に小島屋という鰻の有名店へ行ったことがあった。
ほかにも鰻の店はいくつかあって、このあたりが昔から鰻の産地だったようだ。
南浦和駅まで高台へ上がって歩く途中、民家の中に大きな建物があった。


学校のようだ。
武蔵浦和駅
とまりぎ
浦和には「浦和」が入っている駅名が多い。京浜東北線の北から北浦和、浦和、南浦和、埼京線の北から中浦和、武蔵浦和、この二本に交差して武蔵野線の東から東浦和、南浦和、武蔵浦和、西浦和のようになっている。
南浦和と武蔵浦和は交差した駅なので、JRだけで全部で七駅になる。
もうひとつ埼玉高速鉄道の終点に、浦和美園という駅もある。
今回は、このうちの武蔵浦和駅で乗り換えてみた。
埼京線は大宮まで新幹線と並行しているので、新幹線が通過するところを見ることができる。

武蔵野線へ乗り換えのためには、下へ降りる。
府中本町方面行きの電車は、通路からも見える。
西船橋方面行きへは、左側の階段を使って奥のホームへ行く。

西船橋方面行きホームから、府中本町方面行きホームを見る。

視線を上にすると斜めに交差する埼京線のホームと、その先の新幹線の架線が見える。

武蔵野線を通る貨物機関車だ。
府中本町で見たのと同じような景色だが、機関車だけが通り過ぎていく。
良く観ると、あのときの同じ機関車だ。

武蔵野線のホームが濡れているので、上の屋根を見ると雨が少し漏れている。
今どきの雨には、なるべく当たらない方がいい。
福島原発からの距離は220kmぐらいだろうか。
ここから一駅の南浦和で降りる。
ある会社を訪問するのだが、その社長はマネージャーとして「もしドラ」にあるようにドラッカーの書いている「真摯さ」を生来身に着けているのだろうか。
判断は難しいが。
NHK教育テレビの6月の水曜日は、ドラッカーの「マネジメント」をとりあげて4回の放映がある。第一回は6月1日(水)22:00~22:25だった。
第二回は6月8日(水)の同じ時間だ。時間が合わない人には、再放送もある。
出生と死亡
とまりぎ
6月2日の日経新聞によると、2010年の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に生むとされる子供の人数)は1.39だった。
2009年の出生率は1.37であったから、若干上昇した。(上昇は二年ぶり)
出生数から死亡数を引いた自然増加減数はマイナス12万6千人となり、4年連続で人口は減少した。
死亡者数については、119万7066人で、前年より5万5201人増加。
死因別では「がん」が35万3318人(29.5%)でトップ。
その部位別では男性は肺がんが5万369人で最も多く、胃がんが3万2928人、大腸がん2万3914人。
女性は大腸がんが2万314人、肺がん1万9409人、胃がん1万7185人の順だった。
全体で二番目に多い死因は心疾患で18万9192人(15.8%)、ついで脳血管疾患の12万3393人(10.3%)で、三大死因で全死因の55.6%になり半数を超えている。
いま手塚治虫のブッダが上映中だ。
ブッダの時代から「生老病死」について説いていて、現代仏教にも受け継がれている。
親が二人いて、その親が四人いて、十代遡るだけでその世代の祖先は1024人になる。
夫婦が子供を二人生んだとすれば、同じく十代後には子孫は1024人だ。
その流れの中心に、自分が今ひとりいるのだと考える。この世に生れてきた意味は深い。
そこへ現代は、人口減少が重くのしかかってきた。
府中本町駅
とまりぎ
府中の南にJR府中本町駅がある。
南部線の途中駅であり、府中競馬場の最寄り駅のひとつだ。
武蔵野線ができてからは始発駅で、埼玉県と千葉県を通り京葉線に合流して、最長東京駅まで延々と走る。向い側のホームに停車中の電車は、東京行きになっている。


間を貨物列車が通る。
多摩川から南側は、南武線とは別の貨物専用線を通り、武蔵小杉で一緒になる。
この府中本町駅から北側では、武蔵野線と同じ線路を通るので、ホームの目前を通過する貨物列車を見ることがある。
京王線との乗り換えは、府中から一駅の分倍河原駅で南武線へ乗り換えると府中本町までは一駅だ。
府中は人口が増えて分倍河原駅から立川寄りに、「西府」という新駅ができたのは最近のことだ。
府中
とまりぎ
京王線府中駅近くには、大きな欅(けやき)並木が続く道がある。
途中に八幡太郎義家の像が建っている。

並木に挟まれた車道はいつのころからか、南方向への一方通行になっている。
外側の歩道は、自転車と歩行者に分けられている。

さらに南へ行くと、旧甲州街道を越えたところに大国魂神社がある。
通りがすっきりしたなと思って、よく見ると電信柱が見えない。地下を通したようだ。
境内には武蔵国府跡の碑もある。

5kmほど北には国分寺の史跡もあり、古くから栄えたところだったのだろう。
大国魂神社の門には、今まで気がつかなかったが菊の紋が入っている。
府中には自動制御理論を指導してくれた先生がお住まいだったが、数年前に亡くなられた。奥の深さを感じさせてくれたが、「人生の短さについて」セネカにあるように短かった。