 ☆緑豆の煮ものです。甘く煮ましたのでアンコを食べてるみたいです。
☆緑豆の煮ものです。甘く煮ましたのでアンコを食べてるみたいです。☆薬膳
こんばんは!!
暑くなってきましたね。さすがにバテそうです笑 梅雨時の湿気もたまらなく嫌いでしたが今は温度が上がって暑さが加わりました。中医的には六邪のうちの「湿邪」に「暑邪」が重なって最も不快な季節と言えるでしょう。身体も耐えかねるようになるのも仕方がないと今更ながらに思います。汗をかきすぎると体力の消耗というより「気」を消耗してしまい、怠さや眠気に悩まされるものです。私などは夏の朝風呂は大好きなのですがここ数年はサッと体表の冷えを取る程度にしています。風呂上りに汗をかきすぎると返って気の消耗が激しくて「気虚」状態に陥るのです。朝から疲れてはたまりません(;^_^A 中医を学ぶようになってやっとそのことが理解できたというところです。昨夏ころからは要領よく過ごせるようになってます。今年も結構、元気です。要領ですね(;^_^A
さて、こんな湿邪と暑邪のダブルパンチに悩まされるときに何をご紹介しようかなと考えてました。先日、薬膳の先生がお持ちになっていた緑豆の煮もの(緑色のアンコ)を作ってみようと思い立ちました。日本ではあまり馴染みがないと思うのですが中国では夏バテ対策によく食べられるそうです。小豆のあんこに似ています。添付の写メです。冷たい飲み物で身体を冷やすのも良いですが身体の熱を取り利尿しながら脾胃も守るというのはいかがでしょう。
30分くらい水に浸しておいて水を取り替え、クタクタと炊き上げました。私は面倒なので圧力鍋でシュシュッとしましたのであっという間にできあがりました。甘味は生薬の甘草と少しのお砂糖です。アンコを食べている感じです♪
緑豆の効能を書いておきましょう。
〇性味・・・涼性で甘い
〇帰経・・・心・胃
〇効能・・・清熱解毒 利水消暑 止渇(喉の渇きを抑え)
利尿しながら身体の熱を下げ、解毒も!!喉の渇きも抑えてくれる!!
ただ胃腸が弱くて冷え性で下痢気味な人には向かないそうです。











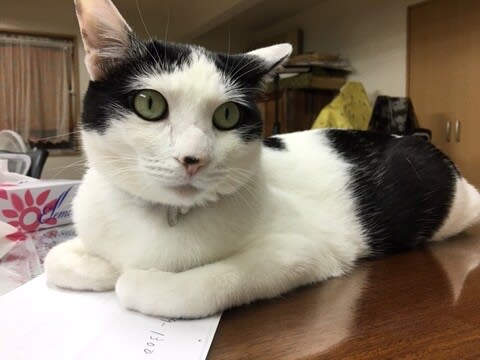

 ➡
➡ 



