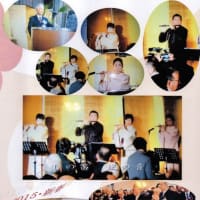11月に入ると自分の地域の神社も祭が行われる。
神社の秋祭が盛大に行われることは、秋の風物詩としていいものだと思う。
しかし違和感があって鬱陶しいのが、自治会から回ってくる「祭の準備」というものだ。
違和感の理由はほぼ二つある。
一つは「神社行事」は「宗教行事」であり、キリスト教、仏教、その他、多数の宗教文化を持つ人達がいて、現代では日本人全員が「神社」の「氏子・信徒」ではないことだ。
大げさに持ち出すこともないのだが「何人も宗教行事への参加を強要されることはない。また参加しない者を差別してもならない」という「信教の自由」の基本的人権原則があることだ。
これを無視するのが自治会による「神社行事」への協力要請と「氏子意識の強要」だ。
そもそも寺社の「寺請精度」「氏子制度」は時の権力者や幕府により「戸籍」と「年貢」の掌握の為に整備されたという背景がある。
現代ではそれは不用になったので「地域友好・地域おこし」という大義名分が掲げられた。
しかし「地域友好・地域起こし」は現代においては「宗教色」の無いものが好ましい。
多くの市民は口には出さないが、そう思っている。
その背景にはマンションや新興住宅地には、旧来の地元の人達以外に、他の地域から多くの人達が流入していることがある。
これらの「旧来の地元民」でない人達は、違和感があって「神社行事」には参加していない。
自分は生まれてから現在まで、神社のお祭の夜店に遊びに行ったおぼえはあるが、自分が「神社の氏子」であると思ったことは無い。
神社行事は「民俗文化財」として「氏子」が運営すればいいので、自治会が関与するものではないと思う。
なぜなら「公共的組織」に宗教色を持ち込むことは禁じられているからだ。
神社行事は「氏子」が行い、寺の行事は「檀家」が行えばよい。キリスト教行事は「クリスチャン」が行えばいいのである。
神社行事における縄張りや紙をぶらさげることにも違和感がある。
自分が「神社の氏子」であるという意識を持ったことがないからだ。
自分の親達は「商売の邪魔になる」というので神社行事の縄張りや紙をいつも取り払っていた。
もう一つの理由としては「市民公共団体」は政治活動、宗教的活動、営利活動を行ってはならないという規定があることだ。
より多くの人達の市民活動、地域活動への参加を促すためには「政治色、宗教色、営利色」があってはならないからだ。
神社行事への自治会からの寄付強要は「神社の営利活動」と看做すこともできる。
氏子の皆さんにとっては「純粋な寄付行為」なのだが「氏子意識のない大多数の人達」にとっては「神社の営利活動」にしか見えない。
多くの人達が迷惑と感じ、苦情を洩らしておられる。
ここに見られるのは「神社行事は宗教行事」ではないという誤りと、神社行事は「地域行事」なのだから自治会が全面協力するのが「当然」という誤りがあることだ。
「神社行事は宗教行事」であり「自治会」は特定の宗教行事に参加協力をする必要は無いということだ。
当然のことながら「氏子」による「民俗文化財」である神社行事の保存は大切なことだと思う。
しかし現代の「地域」「自治会」は特定の神社の「氏子」ばかりではない、ということを念頭において自治会運営がなされることが必要になっていると思う。
現代の地域住民が望んでいる「地域おこし」は「宗教色」の無いカーニバルや歴史発掘、特産物の開発などであろうと思う。