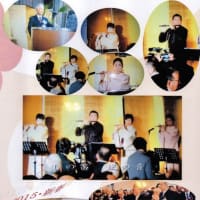30年くらい前に播磨出身の黒田如水という軍師を知って以来、如水の人物像、人生観、処世術・・・などにずっと興味を持っていた。
この人物の優れているところは「常に大局観に立ち」「物事・考え方に固執せず」「臨機応変、柔軟な思考」で「生き抜く」ところだと見ていた。
その典型が「キリシタンの洗礼」を受けたにもかかわらず、秀吉のキリシタン禁令が出ると、さっさと改宗したところだ。
ものごとにこだわりなく「さっさと捨てる」潔さとこだわりの無さが如水にはある。
それは宗教的信条や意地の為に「命を無駄にしてはならぬ」という「現実主義」のあらわれであり「死んではどうにもならぬ」という如水特有の現実主義であるようにも見える。
朝鮮戦役の無謀を秀吉に諌めて、危うく切腹を命ぜられそうになった時、
「意地を通して死ぬわけにはまいりませぬ。この命どうかお助けいただきたい」と秀吉にひれ伏す如水の現実主義は見事だ。
この時代なので「家臣・領民を守る」という大義が如水には第一だったのかもしれない、という推測もある。
しかし如水の徹底して「生き抜く」という死生観は戦国時代にあっては珍しいほど合理的だ。
ひょっとして「いかに才覚ある人も死しては生ける犬におとる」という格言まで知っていたのかも知れないなあと思うことがある。
現代人はたいていそうだが、死んでは元も子もないというのが、今では当たり前だ。
自分の祖父は太平洋戦争開戦前まで国際航路の船長だった。
サンフランシスコ、ニューヨーク、シドニー、マカオ、香港・・・など世界中を見て知っていた。
太平洋戦争の開戦にあたって、工場が林立する大工業国アメリカなどに勝てるはずがないと祖父は思った。
多くの日本輸送船団が「お国の為」と南方輸送の任にあたって撃沈され、莫大な犠牲者が出た。
祖父は「お国の為など馬鹿らしい。命あっての物だね」とさっさと船長を辞めて、木材を扱う山師になった。
祖父は宗教や思想や押し付けの愛国心などには見向きもしなかったようだ。
「生き抜く」という「現実主義」が信条だった。
だから如水の生き方と祖父の生き方は、なにか似てるなあと思うことがある。
ともあれ、黒田如水の柔軟な思考。
ものごとに固執、こだわりなく、さっさと捨てるという賢明な現実主義。
「死後の世界」に救いを求める曖昧な死生観ではなく「現実を生き抜くという明確さ」が如水の「死生観」であり「信条」であり「哲学」であったのではなかろうかと思う。