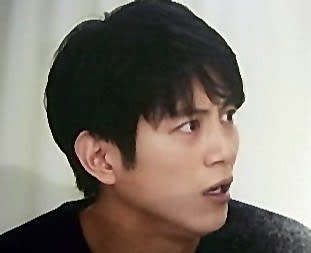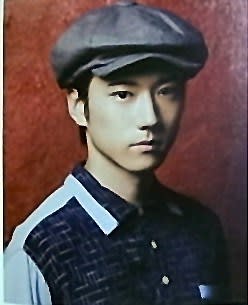ある演劇評論家が新橋演舞場の「オセロ―」を観て、こう評した。
「蜷川幸雄直系のシェイクスピアを、新橋演舞場に丸めて、糖衣錠にしたような芝居だ」
この発言は的をついている。今回の「オセロ―」をひと言で評すれば、まさにこれにつきる。
さらに私がつけ加えるならば、シェクスピア劇のストレートプレイとは言い難い。
中村芝翫を座長とする「商業演劇」だと云うしかない。
新橋演舞場では、シェイクスピア劇の上演は30年ぶりとか。
演出には”蜷川イズム”を受け継いだ井上尊晶。
さらに、坪内逍遥のお孫さんだという河合祥一郎が本公演のため新たに翻訳したという。
音楽は「ユーミン」で知られた松任谷正隆。コーラスの入った音楽は芝居を盛り上げた。
美術は中越 司、照明には原田 保とすべてが、かつての蜷川カンパニーである。
そして、すべてが蜷川幸雄の真似事。序幕のゴンドラの発想、二幕目では、大階段あり、ホリいっぱいの満月。
三幕目では舞台全体がミラー張りなど、キリがない。

オセロ― 中村芝翫


デズデモーナ 壇 れい イヤゴー 神山智洋
芝翫のオセロ―は序幕から終幕まで、うねるような起伏を忌憚なく演じたことは評価したいが、問題は台詞である。
たしかに窮地に立ったとき、オセローは非現実的な台詞を云う。
これは歌舞伎とあいつながるものがある。歌いあげても負けないところがシェイクスピアの凄さであり、台詞の勢いが違う。
昨今、台詞を歌う役者が少なくなった。
私は台詞を謳いあげることに異存はない。
しかし、それが歌舞伎でいう「物語」になっては、いかがなものか疑問がのこる。
だから、あまり歌舞伎を知らない人までが、オセロ―のセリフは”歌舞伎調”だと云うのは是非もない。
観客を巻き込むエネルギーが芝翫にはたしかにある。
しかし多くの疑問をのこした芝翫の”オセロ―”であった。
俗に「イヤゴー役者」という言葉がある。
つまり「オセロ―」という芝居はイヤゴーが動かしているといってもよい。
従来から、イヤゴー役には”いぶし銀”といわれるような年かさの役者が演じてきた。
今回は若手の神山智洋の起用である。逆にこれが成功した。
初めは今井 翼が配役されていたが、病気療養のため降板。そのための代役である。
神山は初日はかなり噛んでいたらしいが、見違えるように”悪の塊”を演じきった。
長台詞の滑舌のよさ、体のキレ、それに大階段を登るときの、神山の「タタタァ」が観ていて心地よく
、そして凄い。
20代という若さもあるが、体幹がまったくブレない。
しかも、あまり小細工はせず、若さで役にぶつかっているところに好感がもてた。
壇 れいのデズデモ―ナが秀逸。
従来からデスデモ―ナ―は元宝塚女優がやることになっているらしい。蜷川幸雄の「オセロ―」には黒木瞳だった。
壇れいは、はじめ純白のシンプルなドレスで花道から登場。あまりの雪のような美しさに場内からため息がもれる。
ことに壇れいの唄う”柳の歌”は絶品だった。
後半オセロ―に一抹の不安を抱きつつも最後の最後までオセロ―のことを信じ、愛し続ける。
そんなデスデモーナの心の揺れと、つらぬく愛をみごとに表現した。


エミーリア 前田亜季 ヴェニス公爵 田口 守
ブラバンショーの辻萬長、複雑な感情をにじませて好演。
歌舞伎の勘九郎の奥さんの妹だというエミリアの前田亜季も、あまり出しゃばらずに脇役に徹し、素直に演じた。
今後に期待したい。

河合 宥季
ほかに注目したいのが新派の女形である河合宥季。
キャシオ―の情婦であるピアンカ、乳母、棺女、ヴェニスの兵士の4役をこなす。
中でも「棺女」がいちばんよかった。
台詞こそないが、序幕のゴンドラで棺を抱えて泣き崩れる老婆の役。
蜷川バリの役をうまくこなした。お疲れサマというよりほかはない。


演出の井上尊晶さんにサインしてもらいました
最後になるが、終幕の不可解な演出に疑問がある。
「急ぎましょう、帰国を。重い心でせねばなりません、つらい報告を。」
この終幕に恰好のセリフで緞帳をきるべきだった。
またロドヴィーコーを演じた大石継太も哀しみを刻みながら、おさえた台詞はじつにうまかった。
なのに、突然、上手下手から刺客とおぼしき大勢が乱入して、イヤゴーが蘇生するというシーンが付く。
これは何のためか。まったくの蛇足である。
この不可解な井上演出に、レッドカードをつき付けたい。

(2018・9・20 新橋演舞場で所見)