『ほぼ週刊映画コラム』
今週は
最後まで謎が解明されない不条理劇
『複製された男』
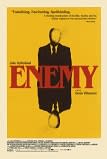
ここで一言
「1度見ただけでは理解できないはず」
byドゥニ・ヴィルヌーヴ監督
詳細はこちら↓
http://tvfan.kyodo.co.jp/feature-interview/column/889283
過日、妻と共に福島県の裏磐梯を訪れた。
磐梯山付近を舞台にした映画

さて、磐梯山付近を舞台にした映画で最も印象深いのは久松静児監督の『警察日記』(55)だ。磐梯山の麓、猪苗代湖の近くにある警察署を舞台にした群像劇で、人情警官役の森繁久彌をはじめ、東野英治郎、三島雅夫、殿山泰司、織田政雄、十朱久雄、伊藤雄之助、左卜全、多々良純、杉村春子、飯田蝶子、沢村貞子といった名脇役たちと、若き日の三國連太郎、宍戸錠、岩崎加根子、小田切みき、そして子役の二木てるみ等が見事なアンサンブルを奏でる。
久松演出は、のんびりし過ぎてだれるところもあるのだが、同じようにアイルランドの田舎の村を舞台にした群像劇である、ジョン・フォードの『静かなる男』(52)をほうふつさせる余裕と楽しさがある。そして、さまざまな人々がそれぞれの思いを胸に町を去るラストシーン。汽車が出るプラットホームに、少々頭のいかれた元校長(東野)のバンザイの声が響くところは、おかしさと切なさが同居して胸に残る。舞台は違うが『祭りの準備』(75)のラストで江藤潤を送り出す原田芳雄のバンザイもこれに重なるものがあった。


他にも清水宏監督、大河内伝次郎主演の人情劇『小原庄助さん』(49)があり、西部劇に出てくるような磐梯山を舞台にした小林旭主演の『赤い夕陽の渡り鳥』(60)では、主題歌「赤い夕陽の渡り鳥」のほか「アキラの会津磐梯山」も聴ける。そして衣笠貞之助監督の日ソ合作映画『小さい逃亡者』(66)は、現地ロケはなかったものの、民謡「会津磐梯山」がストーリーの重要な鍵を握る。最近の『バルトの楽園』(06)でも磐梯山近辺でロケが行われたそうだ。
登場人物がとにかく“走る”マラソン映画を2本
まずは珍しく公開されたオランダの映画『人生はマラソンだ!』から。
ロッテルダムで自動車修理工場を営むギーアは滞納した税金を払うため、3人の中年従業員と共にイチかバチかの賭けに出る。ある資本家との間に「ロッテルダムマラソンで全員が完走できたら借金を肩代わり。できなければ工場を譲る」というスポンサー契約を取り付けたのだ。それぞれが問題を抱える4人の生活とマラソンにのめりこんでいく様子を交差させて描く男たちの再生物語。『がんばれ!ベアーズ』(76)『ロッキー』(76)『クール・ランニング』(93)といった過去のスポーツ映画が描いてきた「結果よりも努力の過程が大事なのだ」という“敗北の中の栄光”がテーマとなる。
全くマラソン経験のない4人をエジプトからの移民で元マラソンランナーだった若者がコーチをするという設定も面白いが、そこにさり気なく人種や性差別の問題も盛り込んでいる。メタボ腹の中年男たちが徐々にマラソンランナーらしくなっていく心身の“変化”が見どころとなる。
ちなみに、ロッテルダムマラソンはカルロス・ロペス(ポルトガル)やベライン・デンシモ(エチオピア)が当時の世界最高を記録し、日本の谷口博美が優勝したことでも知られる有名な大会だ。
もう一本は現代風時代劇とも言うべき『超高速!参勤交代』
舞台は江戸時代。現在の福島県いわき市に位置する小藩・湯長谷藩が参勤交代を終えた直後に再度の参勤交代を命じられる。その裏には湯長谷藩の取り潰しを狙う幕府老中の悪だくみがあった。果たして5日間のうちに彼らは江戸にたどり着けるのか…というお話。セリフも含めて現代風の要素を盛り込んだコメディー時代劇。『のぼうの城』(12)に似た味わいがあり、地方から中央に物申すという裏テーマも隠されている。
湯長谷藩の面々は、何とか定められた期日内に江戸までたどり着こうととにかく走る。だから途中までは“長距離走”を見るような楽しさがあるのだが、彼らが走る姿を見せるだけでは映画にならないと思ったのか、幕府の隠密に邪魔をさせたり、佐々木蔵之介扮する藩主が深田恭子の宿場女郎と恋仲になるなどさまざまな“困難”を仕込んでいる。時代劇だからすごろくかと思いきや、コンピューターゲームの感覚の方が近いかもしれない。そこがニュー時代劇たる所以。こちらとしては彼らがひたすら走る姿を見たかった気もするのだが…。
さて、マラソンを描いた映画と言えば、市川崑のドキュメンタリー『東京オリンピック』(65)に登場する、アベベや円谷幸吉の姿を追ったマラソンのシーンが印象深い。

他にも、オリンピックでのマラソンをクライマックスとした『栄光への賭け』(70)、南アフリカ産でフランク・シナトラの歌をテーマソングとした『マイ・ウェイ』(76)、ボストンマラソンに出場した主婦ランナーを描いた『マイ・ライフ』(78)、マイケル・ダグラス主演の『ランニング』(79)などがある。よくマラソンは人生に例えられるが、これらの映画はどれもマラソンを通して主人公の再生をテーマにしている。そういえば、森一生監督、勝新太郎主演の珍品時代劇『まらそん侍』(56)もあったっけ。
「映画で見る野球 その2」チーム編
まずは弱かったクリーブランド・インディアンスが映画のおかげで本当に強くなった? 『メジャーリーグ』3部作(89~98)。変化球が打てない強打者、球は滅法速いがノーコンのリリーフ投手ら個性的な選手が多数登場する。中でも『2』(94)でとんねるずの石橋貴明が演じた日本からの助っ人タカ・タナカが傑作だった。

デトロイト・タイガースの名選手の黄昏をロイ・シャイダーが好演した『ファイナル・イニング』(83)。原題はズバリ『タイガー・タウン』だ。ケビン・コスナーが引退を決意した試合で完全試合を達成するタイガースの大投手を演じたのが『ラブ・オブ・ザ・ゲーム』(99)。こちらはマイクル・シャーラ原作の『最後の一球』の方が主人公の心理をきめ細かく描いていた。

アナハイム(旧カリフォルニア)・エンゼルスのスカウトの姿を描いたのが『ドリーム・ゲーム/夢を追う男』(91)。主人公が逸材を求めて旅するアメリカ各地の草の根野球の様子がベースボールの裾野の広さを感じさせる佳作だった。天使がエンゼルスに助太刀する『エンジェルス』(94)は心温まるファンタジーのリメーク版。

まだまだあるぞ。『がんばれ!ルーキー』(93)は腕のけがが元で何故か剛速球が投げられるようになった少年がシカゴ・カブスに入団する話。“少年版”の『春の珍事』(49)だ。一方、『リトル・ビッグ・フィールド』(94)は少年がミネソタ・ツインズのオーナーになるという夢物語。子供も金や名声に毒されるという苦さも描かれる。
新人時代のロバート・デ・ニーロが白血病に侵されるキャッチャーを演じた『バング・ザ・ドラム』(73)。架空のチーム名は何とニューヨーク・マンモス! ユニフォームなどを見るとモデルがヤンキースなのは明らかだ。
そして『ナチュラル』(84)でロバート・レッドフォード演じる遅れてきたルーキー、ロイ・ハブスが入団するのがニューヨーク・ナイツ。ハブスのモデルは八百長事件で球界を追われたシューレス・ジョー・ジャクソンだと言われる。レッドフォードの打撃フォームの美しさに思わず目を奪われる。バーナード・マラマッドの原作『奇跡のルーキー』とは違うハッピーエンドが心地良い。ベースボール・ムービーの最高傑作の一本だ。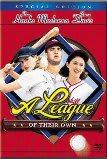
幻の女子プロリーグを扱った『プリティ・リーグ』(92)のチーム名はかわいくピーチズ。ジーナ・デイヴィス、ロリ・ペティら女優たちがきちんと野球をプレーする姿が素晴らしい。ちなみにトム・ハンクスが演じた監督は架空の人物。
最近ではブラッド・ピットが、スモールボールを提唱したオークランド・アスレチックスのゼネラルマネージャー、ビリー・ビーンを演じた『マネーボール』(11)がある。ブラピに加えて、ビーンの片腕役のジョナ・ヒル、アート・ハウ監督役のフィリップ・シーモア・ホフマンも好演を見せた。
クリント・イーストウッドがアトランタ・ブレーブスのベテランスカウトを演じたのが『人生の特等席』(12)。エイミー・アダムス演じる彼の娘も野球狂という設定で、マニアックな野球クイズにもすらすら答えるという面白いシーンがあった。彼女の名前はヤンキースの至宝ミッキー・マントルから採られていた。
ドキュメンタリータッチで“普通の人々”を描いた視点が新鮮

1963年11月22日、午後12時38分。ジョン・F・ケネディ米大統領がテキサス州ダラスでのパレード中に射殺された。その2日後、射殺犯とされたリー・ハーヴェー・オズワルドも警官のジャック・ルビーに射殺され、事件の真相は、陰謀説も含めて今も謎に包まれている。タイトルは、撃たれたケネディと撃ったオズワルドが共に瀕死の状態で運ばれた病院の名前を指す。
本作は、ERの担当医師、看護師、暗殺の瞬間を偶然8ミリカメラで捉えた愛好家、大統領のシークレットサービス、地元FBI捜査官、オズワルドの家族を中心に、事件前後の4日間を描いた群像劇。
暗殺の真相を推理した『ダラスの熱い日』(73)や『JFK』(91)、オズワルドの側から描いたテレビムービー『大統領を撃った男』(77)などとは違い、事件に巻き込まれた“普通の人々”の動静をドキュメンタリータッチで描いた点が新鮮に映る。ただ発生からすでに半世紀以上が過ぎ、関係者のほとんどが物故しているところに、時の流れの無常を感じるところもある。
ところで、本作のプロデューサーの一人はトム・ハンクスで、息子のコリンを医師役で出しているが、その彼がなかなかいい味を出している。ほかにも同じく医師役のザック・エフロン、婦長役のマーシャ・ゲイ・ハーデン、カメラ愛好家役のポール・ジアマッティ、FBI捜査官役のビリー・ボブ・ソーントン、オズワルド役のジェレミー・ストロング、オズワルドの兄役のジェームズ・バッジ・デール、オズワルドの母役のジャッキー・ウィーバー…、と渋い俳優たちが皆好演を見せてドキュメンタリータッチを助長する。
ジャーナリスト出身のピーター・ランデスマンはこれが監督デビュー作。雑多な人々が登場する群像劇を、多角的な視点から90分余りにまとめ上げた手腕はなかなかのもの。今後への期待大だ。
§マイ・シネマパラダイス・カマタ§
かく言う私は、1976年(昭和51)から1984年(昭和57)まで蒲田近くの矢口という街で暮らした。この頃はちょうど我が高校から大学時代に当たり、浴びるように映画を見ていた時期とも重なる。当時、蒲田にはたくさんの映画館があり随分とお世話になった。今はそのほとんどがこの世から消えたが、この機会に少し思い出してみたい。


蒲田駅の東口には美須興行が川崎と並行して展開していた映画館街“ミスタウン”があり、東宝(プラザ③)、松竹(ロキシー④)、東映(トーエイ②)といった各社の封切館が軒を連ねていた。
『犬神家の一族』(76)『ダイナマイトどんどん』(79)『二百三高地』(80)『日本の熱い日々 謀殺下山事件』(81)『蒲田行進曲』(82)…。そして『男はつらいよ』シリーズも随分ここで見た。川崎のミスタウンはチネチッタへと変貌したのに蒲田のミスタウンは今や跡形もない。何とも寂しい限りだ。
蒲田駅西口の線路沿い、今の東京工科大学の辺りに洋画3本立ての「蒲田パレス座(⑥)」があり、サンライズ通りには4本立ての「蒲田アポロ(⑦)」があった。ここで映画を見る時はまさに1日掛かりだった。
パレス座やアポロでの印象的なプログラムは、例えば、『ピラニア』(78)『ザ・ドライバー』(78)『タッチダウン』(77)の三本立て、『クルージング』(79)『ラスト・ワルツ』(78)『アメリカン・ジゴロ』(80)の三本立て、『未来元年・破壊都市』(79)『宇宙の7人』(80)『アルタード・ステーツ/未知への挑戦』(79)の三本立て、『タップス』(81)『未知への飛行』(64)『天国の門』(81)の三本立て…。ポルノ映画もたまに見た。
当時は安価な料金でたくさんの映画が見られることを単純に喜んでいたのだが、実はここらはゲイのたまり場で、オールナイトなどは特に危険だったということを後から知って驚いた。怖いもの知らずの紅顔の美少年?がよく無事でいられたものだ。
また、アーケード商店街内の蒲田文化会館には東宝系と東映系の二番館「カマタ宝塚(⑨)」と「テアトル蒲田(⑧)」があり、前者で『隠し砦の三悪人』(58)『用心棒』(61)『椿三十郎』(62)という黒澤明監督作の3本立てを見たことは今も鮮烈に覚えている。この2館は今も健在だという。久々に訪れてみようかなどと思うのはもはや郷愁に過ぎないのだろうか。
先日、久しぶりに大田区の蒲田を訪れる機会があり、自分の思い出も含めて「映画との関わりが深い街・蒲田」について書いてみた。
§昔、蒲田に撮影所があった!§
現在、JR蒲田駅の発車メロディーには「蒲田行進曲」が使われている。これはその昔、蒲田に「松竹キネマ蒲田撮影所」があったことに由来する。撮影所は1920年(大正9)に創設され、島津保次郎、牛原虚彦、野村芳亭、清水宏、五所平之助、小津安二郎、成瀬巳喜男といった名監督を輩出。小市民の日常を明るく描く“蒲田調”と呼ばれる作風を確立し、蒲田は“キネマの都”と呼ばれた。また、スターシステムの導入により、栗島すみ子、田中絹代らの女優が活躍。彼女たちは蒲田近辺の久が原などに居住し、池上線や目蒲線の沿線ではロケもよく行われたという。
ところが昭和に入ると周辺に町工場が増大。騒音が録音を妨げ、煤煙による被害も甚大なものとなった。撮影所長の城戸四郎は撮影所を神奈川県の大船に移転することを決め、1936年(昭和11)蒲田撮影所は17年間の映画製作に幕を降ろすことになる。大田区史は「蒲田は工業都市を選択し、キネマ(映画)という文化を失った」と記している。


§映画製作者たちへの賛歌「蒲田行進曲」§
ところで「蒲田行進曲」という曲はもともとアメリカで上演されたオペレッタのために作られた曲。これに堀内敬三が日本語の歌詞を付け、五所平之助監督の『親父とその子』(29)の主題歌としたが、いつしか松竹蒲田撮影所の社歌のようになっていったという。明るいメロディーに映画への夢と愛に満ちた七五調の歌詞を乗せたこの曲は心地良く耳に残る。
1 ♪虹の都 光の湊 キネマの天地
花の姿 春の匂い あふるるところ
カメラの目に映る かりそめの恋にさえ
青春燃ゆる 生命(いのち)は踊る キネマの天地
2 ♪胸を去らぬ 想い出ゆかし キネマの世界
セットの花と 輝くスター 微笑むところ
瞳の奥深く 焼き付けた面影の
消えて結ぶ 幻の国 キネマの世界
3 ♪春の蒲田 花咲く蒲田 キネマの都
空に描く 白日の夢 あふるるところ
輝く緑さえ とこしえの憧れに
生くる蒲田 若き蒲田 キネマの都
その後「蒲田行進曲」は、つかこうへい原作、深作欣二監督の『蒲田行進曲』(82)で映画製作者たちへの賛歌として久しぶりに復活。映画も大ヒットしたが、諸事情から松竹製作にもかかわらず撮影は東映の京都太秦撮影所で行われた。松竹にしてみれば庇を貸して母屋を取られたような複雑な心境だったのではあるまいか。
1986年、蒲田から大船への移転50周年を記念して、松竹蒲田撮影所を舞台にした山田洋次監督の『キネマの天地』が製作され、「蒲田行進曲」がテーマ曲として使われた。現在は蒲田駅の発車メロディーとして親しまれているこの曲は、長い間巡り巡ってやっと故郷に帰ってきたことになる。




§蒲田が登場する映画§
また『キネマの天地』のほかに蒲田が登場する映画として、地元の産婦人科を舞台にした渋谷実監督の『本日休診』(52)、主人公の夫婦が住む街として登場する小津安二郎監督の『早春』(56)、最初に蒲田操車場で被害者の死体が発見される松本清張原作、野村芳太郎監督の『砂の器』(74)、ヒロインが蒲田周辺を巡る廣木隆一監督の『やわらかい生活』(06)などがある。松竹の映画が多いのはスタッフに土地勘があったためか、それとも不思議な縁に導かれたからなのか。
今やかつて蒲田に撮影所があったことを示すものはほとんどないが、撮影所跡地の大田区民ホールに『キネマの天地』製作の際に造られた「松竹橋」のレプリカと撮影所の復元ジオラマがあり、わずかに往時をしのぶことができる。まさに兵どもが夢の跡。
以前、あるWEBサイトに連載していた幻の映画コラムを転載。
このコラムは、毎回「こんな映画が観たい」という主旨で編集者がお題を決め、こちらがそれに関連付けた映画関係の人物をテーマに映画を3本紹介し、野球に関係する事柄をサブタイトルに付けるという落語の三題噺のようなユニークな企画だった。というわけで、コラム全体のタイトルは『名画投球術』となった。初回のお題は「たまには幸せになれる映画が観たい」ということでフランク・キャプラを選んだ。
名画投球術No.1「たまには幸せになれる映画が観たい」フランク・キャプラ
今回のテーマにピッタリの監督がいる。その名はフランク・キャプラ。若い映画ファンには少々なじみが薄いかもしれないが、現在作られている“ハートウォームもの”と呼ばれる映画やドラマはすべて、彼の映画の影響下にあるといっても過言ではない。彼の映画は主人公を絶望的なピンチに陥らせておいてラストでそれを奇跡的に救うという非常に分かりやすいものが多いが、その奥には鋭い人間観察の目が光っている。


今回はそんな彼の作品の中から直球2本、変化球1本をご紹介する。なお『ポケット一杯の幸福』は、『一日だけの淑女』(1933)に続いてキャプラ自身2度目の映画化(原作はデイモン・ラニアン)。ジャッキー・チェンも『奇蹟』(1989)としてリメークしているので、見比べてみるのも楽しいかもしれない。
まずは直球勝負 『ポケット一杯の幸福(1961・米)』
ニューヨークの貧しいリンゴ売りの老女・アニー(ベティ・デイビス)の娘(アン・マーグレット)が、留学先のスペインから伯爵家の御曹司の婚約者を連れて帰国することに。困ったのはアニーだ。実は彼女、娘を安心させるために「自分は貴婦人だ」と偽っていたのだ。そんなアニーを救うためにお人好しのギャング、デュード(グレン・フォード)が、仲間や知り合いを集めて彼女を貴婦人に仕立てる大作戦を敢行するのだが…。
初めは果たして作戦は成功するのか? というところに興味がいくのだが、やがてアニーのために右往左往する人々の善意が心に染みてくる。ここで本当の幸せとは「身分や貧富ではなく、自分に対して他人がどれだけ心を砕いてくれるか」ということなのだと気づくはず。作戦の成否は観てのお楽しみ。
続いて豪速球 『素晴らしき哉、人生!(1946・米)』
理想主義者のジョージ(ジェームス・スチュワート)は、町を牛耳る悪徳資本家のポッター(ライオネル・バリモア)に対抗し、父の会社=庶民に味方する貧しい住宅金融会社を引き継ぐ。愛妻メアリー(ドナ・リード)や良き隣人たちに恵まれたジョージだったが、不運が重なって田舎町からは一歩も外に出られない。そしてクリスマス・イブに大金を紛失したことから人生に絶望し、自殺を決意する。そんな彼の前に見習い天使クラレンス(ヘンリー・トラバース)が現れ、ジョージが存在しなかった世界を見せる…。
もちろん実際にはあり得ない話だが、ここから先の奇跡を見ればタイトル通りの人生の素晴らしさや意義に気づき、人が人に与える影響力の大きさ、家族や友人の大切さを実感できるはず。自分が存在しなかった世界=悪夢から覚めたジョージと共に、観客もラストシーンまで一気に「生きていることの幸せ」が味わえる。
最後は変化球『毒薬と老嬢(1944・米)』
婚約者(プリシラ・レイン)を披露するため、二人暮しの伯母(ジョセフィン・ハル、ジョーン・アディア)を訪ねたモーティーマ(ケーリー・グラント)。ところが二人には「貸間あり」の新聞広告で釣った身寄りのない老人たちを、毒入りワインで安楽死? させるという困ったクセがあった。彼は自分にも伯母たちと同じ精神異常の血が流れていると思い込み、必死になって婚約者に秘密を知られまいと画策するが……。
普段は“人間の善意”を前面に押し出すキャプラが唯一撮ったブラック・コメディー。高齢化社会の今あらためて見るとゾッとしたりもするが、人間は笑っている時は日常の不愉快な出来事も生活の苦労もほんの一瞬だが忘れられる。そう、笑っている時、人は幸せなのだ。ならばこの映画を観て、一時でも憂さを晴らして大笑いしてみては。
プロ野球のペナントレースもいよいよ佳境に入る。というわけで、野球=ベースボールを扱った映画について書いてみようと思う。
「映画で見る野球 その1」実在の選手編

まず実在の選手を描いたものとしては、ゲーリー・クーパーが不治の病に倒れたニューヨーク・ヤンキースの至宝ルー・ゲーリッグを演じた『打撃王』(42)、ジェームス・スチュワートが事故で片足を失いながら奇跡のカムバックを果たしたピッチャー、モンティ・ストラットンを演じた『甦る熱球』(49)がある。どちらも監督はサム・ウッドで、野球映画というよりも夫婦ものの名作。古き良き時代のヒーロー話だ。前者で妻のエレノア・ゲーリッグを演じたテレサ・ライトと同じく後者でエセル・ストラットンを演じたジューン・アリスンは、終戦直後の焼け跡世代のアイドルだったという。


ウィリアム・ベンディックスがベーブ・ルースそっくりだったという『ベーブ・ルース物語』(48)と黒人初のメジャーリーガーを本人が演じた『ジャッキー・ロビンソン物語』(49)は残念ながら見ていない。変わったところでは神経症に侵されたボストン・レッドソックスのジミー・ピアソルをいかにものアンソニー・パーキンスが演じた『栄光の旅路』(57)という珍品も。これはなんだか父子の葛藤を描いたアメリカ版の『巨人の星』のようだった。

テレビムービーにも佳作がある。伝説の黒人投手サチェル・ペイジを描いた『ドント・ルック・バック=伝説の速球王/サッチェル・ペイジ物語』(81)ではルイス・ゴセットJr.がペイジ役を好演。ピッチング・フォームがそっくり! そして片腕のメジャーリーガー、ピート・グレイをキース・キャラダインが魅力的に演じた『ア・ウィナー・ネバー・クワイエット=片腕のヒーロー・大リーグへの道』(86)もある。こちらもキャラダインがちゃんと片腕で打ったり守ったりしていたのには驚いた。


ところで、こうした伝記映画は時代の変化と共に、名選手の単なるヒーロー話としてではなく、彼らの屈折も描くようになった。シューレス・ジョー・ジャクソンたちが巻き込まれた1919年のワールドシリーズのブラックソックス・スキャンダルをドキュメンタリータッチで描いた『エイトメンアウト』(88)。ベーブ・ルースの恥部も含め、ジョン・グッドマンが見事なそっくりさんぶりを披露した『夢を生きた男/ザ・ベイブ』(91)。問題児タイ・カッブを憎みきれないろくでなしとして描きトミー・リー・ジョーンズが好演を見せた『タイ・カップ』(95)。これらは野球映画というよりむしろ人間ドラマで、その描き方には賛否が分かれるところだろう。
そして昨年はジャッキー・ロビンソンとブルックリン・ドジャースのオーナーのブランチ・リッキーを中心に描いた『42~世界を変えた男~』(13)が公開された。まさに多士済々。次回はチームを中心に描かれたものをピックアップしてみようと思う。
(旧マイブログ『ペーパーバックライター/桑畑四十郎』の記事に加筆訂正)



















