インド映画『チェイス!』に主演したアーミル・カーンとヴィジャイ・クリシュナ・アーチャールヤ監督に取材。
シカゴを舞台にした『フレンチ・コネクション』(71)をほうふつとさせる激しいアクションと、サーカスを背景にした人間ドラマが展開する。主人公のキャラクターには『バットマン』や『スパイダーマン』の影響も感じられる。もちろん、インド映画十八番の踊りの場面も満載。カーンが大学生を演じたコメディー『きっとうまくいく』(09)とは違う形でインド映画の新たな可能性を示した一作。
詳細は後日。
インド映画『チェイス!』に主演したアーミル・カーンとヴィジャイ・クリシュナ・アーチャールヤ監督に取材。
シカゴを舞台にした『フレンチ・コネクション』(71)をほうふつとさせる激しいアクションと、サーカスを背景にした人間ドラマが展開する。主人公のキャラクターには『バットマン』や『スパイダーマン』の影響も感じられる。もちろん、インド映画十八番の踊りの場面も満載。カーンが大学生を演じたコメディー『きっとうまくいく』(09)とは違う形でインド映画の新たな可能性を示した一作。
詳細は後日。
名画投球術 No.9「(食欲の秋)食欲増進作用のある映画を観たい」チャールズ・チャップリン
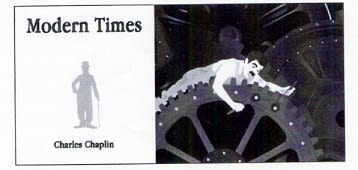
俗に三欲(物欲、食欲、性欲)といわれる人間の欲求の中で、もっとも根源的なものは食欲だろう。ほかの二つはほどほどに我慢できたり代用も利くが、食事だけは毎日取らずにはいられないし、食いだめもできない。食べなければ人間、生きてはいけないのだから。
映画の中でも食事のシーンは重要な役割を果たす。それによって登場人物の置かれている環境や、生活水準、心情などを観客に一目で知らせることができるからだ。そして映画史上最も食べることに敏感で、食事することを至芸の域にまで高めて見せたのがチャールズ・チャップリンである。幼少期の極貧生活に裏打ちされた凄味さえ感じさせるその芸は、豪華な料理を見せられる一時の快楽よりも、より直結した部分で私たちの食欲を刺激する。
盗塁? 盗み食い? 『犬の生活(1918・米)』

職探しに失敗した浮浪者チャーリーは、野犬の群れから自分と境遇が似ている一匹の野良犬=スクラップスを助け出す。それが縁で彼らのおかしな共同生活が始まる。ドタバタ・コメディーからストーリー性のあるコメディーへ、チャップリンの移行期の一作。原題の「a Dog's Life」には“惨めな生活”という意味も含まれている。
この映画に登場する食材はホットドッグ。職にあぶれ、空腹の主人公がスタンドで売っているホットドッグをつい盗み食いするシーンが圧巻。店主の目をくらまし、最初は罪の意識から少しずつ、だが結局は全部食べ尽くしてしまう本性をチャップリンが見事に表現。ファストフードの代表であるホットドッグが彼の芸にかかるとすごいごちそうに思えてくる。
なんとスパイクを… 『黄金狂時代(1925・米)』

舞台はゴールドラッシュに沸くアラスカ。この地にやって来た浮浪者チャーリーの一攫千金の夢とはかない恋が、ギャグとスリル、そしてペーソスで描かれる。チャップリン初の長編で、彼の作品の中でも最高傑作と評されることが多い。
登場する食材はなんとチャップリンのトレードマークである“ドタ靴”。山小屋に閉じ込められたチャーリーと相棒が、飢えをしのぐためになんと革靴を食べるのだ。上皮と底をナイフとフォークでステーキのように器用に切り分け、靴ひもをフォークを使ってスパゲッティのように皿に載せ、釘をフライドチキンか魚の骨のようにしゃぶる。一瞬豪華なディナーと見紛うばかりの究極の食事? 靴がおいしく見えるなんて! ほかにもパンとフォークを使ったダンスシーンも有名だ。
管理野球か、管理社会か 『モダン・タイムス(1936・米)』

大工場のオートメーション化に神経を狂わされた工員チャーリーの受難を通して、金と時間と機械に支配された近代社会を痛烈に風刺した、チャップリン最後のサイレント映画。製作から60年余を経た現代にも通じるところが少なくない、先見の明を感じさせる傑作。
この映画には、食事中も流れ作業の手を止めさせないための自動給食機が登場する。その実験の被験者となるチャーリー。いすに固定された彼は、無理やりスープを飲まされ、自動ナプキンで口元をこすられ、回転するトウモロコシを押し込まれる。やがて機械が故障し、大爆笑となるのだが、このシーンを見ると、日頃当たり前だと思いがちな「自分の手で自由に好きなものが食べられる幸福」を感じずにはいられない。

『サンバ』のオリヴィエ・ナカシュ監督を取材。
『最強のふたり』のナカシュ&エリック・トレダノ監督と主演のオマール・シーが再びトリオを組んだ。今回は、国外退去を命じられた不法労働者を主人公にした人間喜劇で、タイトルは主人公の名前から付けられている。
詳細は後日。
名画投球術 No.8.「(読書の秋)原作より面白い映画が観たい」大林宣彦
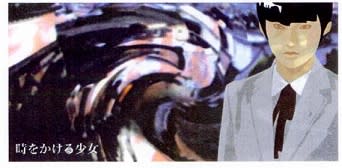
先に原作を読むと、映画化されたものが素直に楽しめなかったり、登場人物や背景が自分の中で作られたイメージに合わない、と感じる人は少なくないだろう。大げさに言えば、読者の数だけ心の中に異なった映像が存在するわけで、たった一人の映画監督が作り出す映像と一致するはずもないのだ。だからこそ、原作に対して自分が抱いたイメージを満たしてくれたり、覆してくれる映画と出会った時の喜びは大きい。
児童文学作家・山中恒原作の『おれがあいつであいつがおれで』=『転校生』(1982)や『なんだかへんて子』=『さびしんぼう』(1985)を、淡いラブロマンスに仕立て上げた大林宣彦は、良くも悪くも原作をぶち壊して独自の映像世界を作り出す。今回紹介する3本もそれぞれ大林色に染められたものばかりだ。
プリティ・リーグ 『時をかける少女(1983・日本)』

放課後の理科実験室でラベンダーの香りをかいだことをきっかけに、芳山和子はタイム・トラベラーに。未来人と彼女の淡い初恋と学園生活を描いたファンタスティックで切ないラブロマンス。
原作は筒井康隆のジュブナイル(少年少女向け)SF。原田知世の映画デビュー作ということもあり、大林はアイドル映画の手法を用いながら、自身の故郷・尾道に舞台を移し、ノスタルジックな背景を構築。一方で、当時の最新特撮を駆使して、読書では想像の域を出なかったタイムトラベルという非現実を映画の中に取り込んだ。先にドラマ化されたNHKの少年ドラマシリーズ『タイム・トラベラー』と見比べてみるのも楽しい。
フィールド・オブ・ドリームス 『異人たちとの夏(1988・日本)』

結婚に失敗した中年の脚本家・原田が、故郷の浅草で12歳の時に死別した両親と再会したことから始まる、懐かしくも切ない奇妙な生活とは…。渇ききった現代人の日常に潜む孤独と幻想が描かれる。
原作は山田太一。作者が脚本家だけあってもともと映像がイメージしやすい原作ではある。だがこの映画は、夏の風景、浅草という街が持つ独特の懐かしい雰囲気を見事に映し出した映像、そして主人公を演じた風間杜夫、若き両親役の片岡鶴太郎、秋吉久美子の巧みな演技が相まって、映画ならではの表現力の素晴らしさをあらためて感じさせてくれる。特に両親との別れのシーンは絶品だ。
ボーイズ・オブ・サマー 『青春デンデケデケデケ(1992・日本)』

1965年、香川県観音寺。ラジオから流れるベンチャーズのギターサウンドにしびれた高校生が、ロックバンド結成に燃える様子を描いた青春群像劇。
原作は芦原すなおの直木賞受賞作。非現実を映像化することを得意とする大林だが、この映画ではあえてドキュメンタリー的な手法を用いて田舎町の高校生たちの日常を活写している。多彩な登場人物たちの点描も面白い。加えてリズミカルな編集と楽曲で観客を乗せ、違和感なく1965年にタイムスリップさせる。映画を見終わった後、ベンチャーズの「パイプライン」が心地良く耳に残るはず。音楽もまた(読書では得られない)映画が持つ強力な武器のひとつなのだ。

名画投球術 No.7. 「いろんな不倫が見てみたい」デビッド・リーン
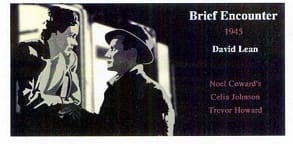
“不倫”という言葉を辞書で引いてみると「異性関係において道徳に外れること」とある。道徳とはいかにも古めかしいが、男女を問わず、許されない恋に走ることはそれこそ太古からあり、人間とはルールに縛られるほど、逆に情熱を燃やす悲しい性を持っている。
とはいえ現実ではそう簡単に不倫できるわけもなく、虚構や願望の産物である映画は、発生から現在に至るまでその代弁者となってきた。
『戦場にかける橋』(1957)や『アラビアのロレンス』(1962)といったスペクタクル映画の巨匠デビッド・リーンは、一方で優れた恋愛(特に不倫)映画を手掛けてきた。彼にとっては不倫こそが恋愛における最大のスリルであり、スペクタクルだったのかもしれない。
ホームイン 『逢びき(1945・英)』

平凡な主婦(シリア・ジョンソン)と妻子のある医師(トレバー・ハワード)が、ふとしたきっかけから知り合い、週に一度、木曜日ごとに逢びきを重ねる。
つかの間の許されない恋をリアルかつ丁寧に描き込んだメロドラマの傑作。ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番」が効果的に使われている。
互いに後ろめたさを感じ、びくびくしながら、それでも会わずにはいられない二人。けれども最後の一線はどうしても超えられない。慎ましいというか奥ゆかしいというか、昨今のドロドロした不倫劇を見慣れた観客は歯がゆい思いを抱くかもしれない。
そして、最後はそれぞれのホーム(家庭)に帰っていくのだが、果たして二人はこの後、“逢びき”を忘れて幸福な家庭生活を続けられるのだろうか? 踏みとどまる不倫も一種残酷なのでは、と考えさせられる。
若手&ベテラン 『情熱の友(1948・英)』

恋愛と結婚は別と割り切って年上の大実業家(クロード・レインズ)と結婚したヒロインが、昔の恋人(トレバー・ハワード)と再会し、再び情熱をかき立てられて悩み抜く。
スイスの避暑地を舞台に女性心理の機微を巧みに描いた佳作。原作はSF作家として名高いH・G・ウェルズ。
前出の『逢びき』では、特に結婚生活に不満のない男女が陥るやるせない不倫を描いたリーンが、一転して「愛情か? 経済力か? 幸福な結婚生活とは?」という女性にとっての永遠のテーマに鋭く迫る。
しかもヒロインを演じるのは、リーンの妻のアン・トッド。いかに女優とはいえ、自分の妻に不倫を演じさせたリーンの心境やいかに。後に二人が離婚したのはまた別の話だが。
ツープラトン『ドクトル・ジバゴ(1965・米・伊)』

ボリス・パステルナークの同名小説を映画化。ロシア革命前後の動乱期を背景に、医師であり詩人でもある主人公ジバゴ(オマー・シャリフ)の生涯を、二人の女性(ジュリー・クリスティ、ジェラルディン・チャップリン)への愛を通して描いた壮大な叙事詩。モーリス・ジャールの「ラーラのテーマ」が美しい。
踏みとどまる不倫、女性の側から見た不倫と続いた後は、男性側から見た不倫である。主人公のジバゴがまったくタイプの違った二人の女性の間で揺れ動く姿を、一種のロマンとみるか、煮え切らない男の身勝手とみるか…。
ロシア革命という激動の時代を背景に、男はロマンチストで女はリアリストである、という真理を語った一編としても捉えられる。
リーンは後にアイルランドを舞台にした大作『ライアンの娘』(1970)でも飽くことなく不倫を描いた。
ハリソン・フォードの演じ分けのコツはヘアスタイルにあり?
巨大IT企業のCEO同士の争いに巻き込まれ、スパイとしてライバル会社に入社した一人の若者(リアム・ヘムズワース)。彼の運命やいかに…。見どころは、ヘムズワースの活躍に加えて、『エアフォース・ワン』(97)以来となる、ハリソン・フォードとゲイリー・オールドマンによるベテラン対決。
その一方、ニューヨーク、イースト川を隔てたブルックリンとマンハッタンの格差という構図は、かつて『サタデー・ナイト・フィーバー』(77)でも色濃く描かれていたし、叩き上げの労働者の父親(リチャード・ドレイファス)と成り上がりを夢見る息子の対立は、『ウォール街』(87)のマーティン&チャーリー・シーン親子の姿とも重なる。というように、本作は、ITという最先端の企業の裏側を描いてはいるが、ストーリー自体はオーソドックスな造りになっている。
ところで、70歳を過ぎたハリソン・フォードが本作では丸刈りで登場する。
その姿を見ながら、『心の旅』(91)を見た際に書いたメモのことを思い出した。
~ハリソン・フォードの役に対する演じ分けのコツはそのヘアスタイルにある。この映画でも、前半の敏腕弁護士時代は、珍しく髪をオールバックにすることで、この男の持つ嫌らしさや思い上がりを強調している。一転、事故で記憶を失い、子供のように無垢な心を持った男に生まれ変わった後は、ソフトな真ん中分けにして、いつもの好漢に戻ってみせる。もちろんこれが演じ分けのコツの全てではないが、やはり見た目は大事なのだと思わされる。~
今回の丸刈りにもちょっと驚かされた。
実は正統派の西部劇!?

『テッド』(12)のセス・マクファーレンが監督・主演した西部劇。下ネタ満載の下品極まりないギャグのオンパレードに、西部劇ファンの中には眉をひそめる向きもあろうが、風景描写やセット造りには手を抜いていない。ここが重要。こうした一種のパロディーものは、背景に手を抜いた瞬間、興ざめして笑えなくなるからだ。
原題は「西部で死ぬには100万の方法がある」。つまり、かっこいい西部劇の世界ではなく、死が身近にあるマイナスイメージの西部が舞台というわけだが、マカロニウエスタンのパロディーではないところがいい。
モニュメント・バレー、ニューメキシコでの本格的なロケ、壮大なテーマ曲と真っ赤なばかでかいタイトル文字、サルーン(酒場)の様子、けんか、銃の修業、最後の決闘、といった西部劇の約束事が網羅され、いい女=シャーリーズ・セロン、悪い女=アマンダ・セイフライド、悪役=リーアム・ニーソン、という西部劇の典型的な人物を登場させている。
さらに、名脇役のマット・クラーク、『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』(90)のクリストファー・ロイド、『ジェロニモ』(93)のウェス・ステュディ、そしてラストには○○が登場とゲストで楽しませるサービスもある。うわべは下品だが、実はきちんと計算した上でふざけている正統派の西部劇なのだ。もっとも我々日本人には理解不能なギャグがあるのは否めないが。
