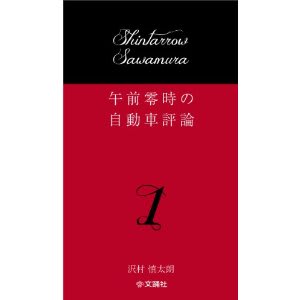
私が有料メールマガジン購読している、モータージャーナル。
http://motorjournal.jp/
その筆者の1人である、沢村慎太郎さんがこれまで配信してきたメルマガに加筆したものが、
ついに本になることになりました。
早速、アマゾンで注文しました。
ネットや雑誌の評論が、いかに「提灯記事」と化しているかがよくわかります。
自称「クルマ好き」の方、必読の書籍ですよ~
=========================================================
(以下、メルマガのサンプル)
■感動のガヤルド 沢村慎太朗 2011.06.26
歳のせいもあるのだろうが、クルマに乗って感動することは滅多になくなった。
ところが最近、めずらしくも深く感動することになった。ランボルギーニ・ガヤルドである。
ご存知のように、ガヤルドは、親会社アウディが送り出すR8とプラットフォームやパワートレインなどの主要メカニズム要素をそっくり共用している。スーパーカーの歴史の中では異例で、知る限り初めてのことだと思う。
スーパーカーの世界は個性がいのち。にもかかわらず主要メカを流用するならば、あとの仕立ての段階で、どういう作り分けをするかが勝負になってくる。
アウディは、乗用車に軸足を置くメーカーらしい判断をした。
まずガヤルドの4WD駆動系をに手を加え、より前輪が利くようにした。具体的には、前輪と後輪の回転差を増やしたのだ。
ガヤルドは、フロントとリアをビスカスカップリング一発で結んでいる。この構成だと、前輪と後輪に回転差が出たときだけビスカスが滑って拘束力が発生し4WDとなる。実用車の、いわゆる生活4駆と呼ばれる仕様の多くが、仕掛けのシンプルさからこのビスカス一発方式を採っている。
しかしこのままでは、真っ直ぐ走っていて前輪と後輪に回転差が生じてないときには4WDにはならず、2WDのままである。だからランボルギーニは、前輪と後輪の外径や駆動系のギア比を変えて、最初からビスカスが引きずるようにした。これで真の意味のフルタイム4WDの完成である。 ちなみに、ガヤルドの場合その回転差の割合は5%。アウディはこれを10%にした。前輪に常に1割以上トルクを濃く入れておいて、地面のとコンタクト増強を図ったのだ。
それに加えて、前輪は大キャスタ化によって転舵時ネガキャン移行率の増加を図り、逆にリアサスはロール時に同種車たちよりも対地キャンバが崩れやすいジオメトリとし、さらにはロール軸も前下がりにした。つまり旋回特性をオーバーステア方向に向けたのだ。
これによって不足するスタビリティは、4WDによるマージンを下敷きに、電制でアンダーステア方向に押さえ込むことで補完する。R8でESPをカットすると、とりわけ高速コーナーではかなりスリリングな機動になる。
ジェット戦闘機は、F-16ファイティングファルコン以来、ひたすら機動性と小回り旋回性に特化した基本メカニズム設計をしておいて、そのために起きる安定性の欠如は、各種操縦デバイスをコンピュータで制御することで確保している。これに似た考え方である。
そんな風にして、R8はハンドルで曲がりやすいミドシップに仕上げられた。ミドシップは幾つもの美点の裏側に、前荷重依存性というネガをもつ。前輪荷重の変化しろが大きく、その多寡によって旋回特性が明確に入れ替わるのだ。そして、前荷重を使いこなすのはそう簡単なことではない。
スーパーカーを高価な遊び道具としてしか認識していないひとびとに、それを要求するのは無理だ。しかし、昔も今もスーパーカーの上顧客は、お金持ちで派手な生活を送るセレブレティであり、彼らに前荷重などと言っても話は通じないし、通じたとしても訓練を重ねて身に着けようなどとは夢にも思わないだろう。しかし、R8のような仕立てなら、前荷重など使いこなせなくても、かなりの割合でクルマの能力を発揮させることができる。
それだけでなくアウディは、R8に柔らかめのサスペンション・セッティングや、硬軟の幅の広い電制ダンパーまで与え、快適性に配慮した。全高も高めに採り、キャビンの居住性も確保した。
こうしてR8は、70年代で言うプレイボーイカーとして超一流のスーパーカーになった。セレブならぬ自動車評論家までが軒並み「運転しやすい」などと呑気なコメントをした。小学生の感想文と言われても仕方ないだろう。
そういうR8対してガヤルドは、ひたすら骨っぽいセッティングを選んできている。
まず、サスペンションを思い切り硬めた。ガチガチのアシなどという表現があるが、まさしくそれ。初期型のR35系GT-Rのスポーツモードに近いが、あれよりもバネ下は暴れ、不整路ではタイヤは簡単に地面とのコンタクトを失い、クルマは跳ね飛び回ろうとする。音振も、放置なのでは思わされるほど、キャビンをノイズが間断なく襲う。優雅に流すなどという次元とは無縁のクルマである。
おまけに、ステアフィールからブレーキまでが、かなりの負荷領域まで踏み込んだときに、ようやくリニアリティや連携が取れ始めるという仕上がりにガヤルドはなっていた。つまり、ガンガン踏んでいかないと、美味しいところが味わえないのだ。
そして、操縦性はミドシップ4WDのセオリーどおりである。
ガヤルドは、先述のようにR8よりもデフォルトの前後拘束力が少ない。あくまで主役は後輪で、前輪はそれを陰で補う黒子のように仕事をする。だから基本的な旋回機動は、前輪が切った方向にハナを引っ張る感覚はあるものの、LSDを効かせて外ににじり出ながらも車体を前に押していく後輪のほうがカギになる。言い換えれば、アクセルをとことん踏んで行ったときに、それを可能にする状態を前輪が内助して整える。明らかにそんな風に狙いを定めて仕上げたシャシーである。
そういうクルマだからガヤルドは、R8よりも間違いなく速い。R8は、ミドシップの利点を何割か目減りさせることを覚悟で、あの扱いやすい仕上がりにしている。そして、そのR8の上限を超えたところになってガヤルドは本領を発揮するのだ。
これには恐れ入った。
スーパーカーの顧客は目を三角にしてクルマと格闘するようなことはしない。そこまで踏まないのだ。さらに言えば、ランボルギーニの支持層は、鬼面ひとを驚かす派手な外観や、フェルッチオが捏造して喧伝した反フェラーリの伝説などの、いわば衣の部分を重視する傾向が強く、スポーツカーとして扱って性能をとことん追求するようなストイシズムは薄いきらいがある。
にもかかわらずランボルギーニは、そういう支持層のプロファイルなんか無視するかのように、これ以上ないような辛口の仕上げを施してきたのだ。新車試乗会の<技術>説明に、マーケティング屋がしゃしゃり出てきて能書きを垂れる現代のこの業界では考えられないクルマ作りだ。すばらしい。恐れ入るしかないではないか。
しかし恐れ入っただけで、まだそれは感動ではない。
感動は、2WDバージョンに乗ったときに訪れた。
LP550-2と名づけられた後輪駆動ガヤルドは、ステアリングを切ったときの反応が4WDバージョンとは明らかに違っていた。その際のリアの踏ん張りが、ずっと軽いのである。もちろん2WDゆえ、前荷重依存性はっきりと現出しているし、後輪LSDのイニシャルトルクは強く、とりあえず初期には後輪は粘ろうとする構えを見せる。しかし、きちんとフロントを地面に押さえつけておいて決然と操舵すれば、クルマは結び目がはらりと解けるように俊敏に回り込んでくれる。そこからパワーを入れればLSDが利いて、さらに後輪はスリップアングルを増しつつ強烈に立ち上がる。ひたすら曲がることに特化したシャシーなのだ。その旋回機動は陶然とするほど美しい。
4輪駆動で企画して作ったクルマを、後輪駆動に改変する。そんなとき、普通なら誰でもスタビリティのマージンを上げる方向で考えるだろう。しかしランボルギーニはそうしなかった。ミドシップの最大の優位点であるヨー慣性モーメントの少なさを磨き上げるほうに特化してきた。R8とガヤルドのあいだの予め設定された差異。その差異を、さらに先鋭化させた2WDバージョンを作る。そんなランボルギーニ実験部隊の心意気に感動したのだ。これに感動しなくて、何に感動しろというのだ――。
日々の仕事の中で求めているのは、本当はこうした感動なのです。いつも自動車雑誌では、受けた印象と、メカ要素の構築を結びあわせることで筋道立った試乗記をと思いながら書く。だけれど、クルマに取り憑かれた人生を送ってきたひとりの男として、本当に望んでいることはそれじゃなかったりする。筋道立った追及の先に見えてくる理屈なんぞ超えた感動。ごく稀にだけど出会うことがあるそれを求めて今日もクルマに乗っているのです。
例えば、評価者としての立場でクールに言ってしまうなら、ランボルギーニ・ガヤルドは、その洗練度においてフェラーリ458イタリアには水を開けられているのは確かで、どちらがと訊かれれば間違いなく458に軍配を上げることになるでしょう。でも458イタリアには、感心はしたけれど、感動はなかった。ガヤルドLP550-2には感動があった――。
ですが、どんなに鮮やかな感情が心に浮かんだとしても、一生懸命それを文章にしたとしても、自動車雑誌がそういうことをテーマにした原稿を依頼してくることはありません。比較試乗の企画なら、要するにどちらが上かという結論に向けて一直線に原稿を書くことになります。そうやって、はっきりした結論を出すのも楽しい仕事だけれど、それだけじゃ漏れてしまうことがある。そして、そうやって漏れてしまうことが大事に思える。伝えたい。だから、こういう場を作りました。
感動だけじゃなく、他にも取材をしていて原稿を書いていて、心に浮かぶことはたくさんあります。クルマ好きで行こうと腹をくくって人生を送っている皆さんと、それをこの場所で分け合いたい。皆さんが愛するクルマとのあいだに生んだ感動や懊悩や幸福感を分けてもらいたい。トークライブやQ&Aが、その場所になることでしょう。Autocar Japan誌でQ&Aコーナーは何年もやってますが、そちらよりも、もっと互いの距離が近くて体温が伝わる極私的な場になると思います。今から楽しみで仕方ありません。
■鉄チンホイールとプリウスα 沢村慎太朗 2011.06.26
おれがまだ免許取りたてのガキだったころ、ちょっと郊外へ行くと、空中浮遊しているクルマを見ることができた。
いや別に反重力装置を装備していたわけではない。空力性能がヒサンで揚力が働いたあけく車体がリフトして、ついに宙に浮き上がったというわけでもない。クルマは動かずに止まっていたのだ。コンクリートブロックの上に乗っかって――。
そしてブロックの上のクルマは、タイヤとホイールがなかった。そう。アルミホイールをギられてしまったのだ。失礼。ギるってのは昔の俗語で、盗むの意味。それはともかく、今は見ない光景である。あのころはアルミホイールは偉いアイテムだったのだ。普通のクルマは、みな鉄チンホイールだった。気張ってカネ貯めてアルミホイールを買う。つける。自慢。しかし、油断して人気のない暗がりに停めて、ちょっと目を放した隙に空中浮遊の刑に遭って、バイト代の結晶であるところのアルミホイールが見事に消える。このままじゃ走れない、帰れないじゃんか。懐かしくも、しょーもない昭和のヒトコマだ。
さて、2011年の現在、アルミ泥棒の話をあまり聞かないのは、たいがいのクルマがアルミホイールを履くからだろう。標準で鉄チンを履いているのは、安い小型車の、そのまた思い切り安いグレードくらいである。
ただし、別に安くもないのに鉄チンを履いている場合もたまにある。例えば、先日デビューして、たったひと月のあいだに5万2000台を受注したとトヨタが自慢するプリウスαがそうだ。
かつてαがつかないほうのプリウスを作るとき、トヨタは燃費いのちに徹するあまり、ドライバビリティまでシカトを決め込むだけでなく、燃費向上のために空気抵抗まで気にした。
ちなみに、欧州勢のようなダウンサイジング過給エンジンという手口は、あまり止まらず渋滞も少なく、走り続けられる欧州のような道路環境のほうが高燃費を出す。ハイブリッドは、発進&停止が多い渋滞路で本領を発揮して燃費がよくなるが、高速で走り続けるとエンジンが回ってばかりいるので、下手するとデキのいいエンジン車に負ける。なのに高速で効いてくる空力までツメるとは、なんと涙ぐましい――以前そう言ったら、「30km/hでもちゃんと空力は効くんです」とトヨタの実験屋さんに切り返された。まあ言ってる意味は分かりますけど。
話を戻そう。些細な部分の空気抵抗まで削りに削ろうと血マナコになったプリウスは、ホイールの形も頑張った。アルミホイールなのに、わざわざ空気抵抗を減らせる形にしたホイールキャップをつけたのだ。
というわけで、プリウスは全グレードがアルミホイール標準装着である。ところが、今度のプリウスαは、2列5座バージョンのほうの最廉価グレードが鉄チンホイールを履く。プリウスαには3列7座と2列5座のふたつのバージョンがあるが、前者はファミリー向けで、後者は荷室の大きさを生かしてワゴン的に使おうというひと向けに設定されたと思しい。ということは、2列5座バージョンの最廉価グレードは、ワゴンというか営業ライトバン仕様みたいな想定なんですかね。だから鉄チンなんですかね。
そう思ったおれは、プリウスαの試乗会でトヨタのひとに訊いてみた。同サイズのアルミホイールと鉄チンホイールで調達コストは、かなり違うんでしょうねえと。
「そのー、実はほとんど変わらないです」
え、そうなんですか。
じゃあ何故わざわざ鉄チンを装着するのか。鉄チンホイールは、どうしてもアルミより面剛性が落ちる。ホイールの面剛性が落ちるとアシ周り起因のノイズが増える。これはトヨタの技術者の提出した論文で知ったことだったりします。一方で、エンジンが止まってることが多いハイブリッドは、他の部分のノイズが目立ちやすくて、その対策に普通のエンジン車よりも苦労する。であれば、音振面では有利なアルミホイールを全車装着したほうが、ずっと楽だったでしょうに。
と、横にいた音振屋さん「えー、まあそうなんです」と苦笑い。
だとすると、わざわざ鉄チンを履かせるのは、グレード差別を明確にするためですか。
「ありていに言ってしまえば、そういうことになるのですが……」
おれがありていに言ってしまえば、こういうことになる。鉄チンホイール標準装着は、一番安いやつを買ったお客へのお仕置きである。見た目もダサければ、音振もよくない。一番安いやつ買ったから、そういうことになるのよ。次は、アルミ履いた、もっと高いグレードをどうぞ。そういう商売上の戦術の上で鉄チンホイールは用意されているわけである。別にコスト要件ではないのだ。
たまたまプリウスαの試乗会で聞いた話だったからトヨタが例に挙がっただけで、他社でも話は同じだろう。
だが、考えてみれば、普通のプリウスの方は、こんなことはしていない。先ほど書いたように全車アルミホイール標準装着だ。燃費最優先でグリップがスカな185の15インチ履いた205万円の“L”でもアルミホイール。本気なのだ。出来上がった物体は、クルマとしては疑問符がいくつもつくけれど、脇目も振らずに作り込んだ燃費マシンとしての存在意義は認める。
一方で、プリウスαは鉄チン仕様がある。
3列シートのハイブリッドが欲しかったひとたちと、営業バンに使えるハイブリッドが欲しかったひとたちが一斉に飛びついて1ヶ月で5万2000台も受注してしまったプリウスα。名前もカッコもなんだかプリウスの兄弟に見える。しかし、プリウスαとはつまりそういうクルマなのだ。おまけに、ホイールベースで8cm、全長で15cmほど長いだけなのに、車重は150kgも重い。そこでも本気の匂いは嗅げない。燃費の究極への挑戦ではなく商売。プリウスとプリウスαを同じクルマの車体バリエーションだと思って買ってはいけない。











