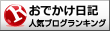多摩御陵
大正天皇の御陵
大正天皇が皇太子の時小坂鉱山を訪れた。
明治41年9月15日小坂鉱山専用鉄道が開通する1週間前である。

松姫像
武田信玄の4女。
上洛果たせず、信玄、元亀4年(1573年)無念の死を迎える。
武田を継いだのは、松姫の異母兄、勝頼。が、勝頼軍は天正3年(1575年)長篠の戦いで、織田、徳川の連合軍に完敗。武田家は衰退の一途をたどる。極め突きは天正10年(1582年)松姫のかっての婚約者、織田信忠が甲斐に攻めてくる。攻めるも守るも万策尽きた勝頼は松姫に、甲州街道沿い、八王子へ逃れるよう勧め、天目山で自害する。1567年織田家よりぜひ信長嫡男 信忠の正室にと望まれ婚約するも、信玄上洛を阻む家康との「戦い」さらに家康のバックボーン信長とも関係は悪化。7歳にして婚約は破棄され、不運な生立ち、松姫は追われるように甲斐を後にし八王子の心源院に陰棲、そのまま仏門に入り、信松尼となる。21歳。
56歳の死を迎えるまで養蚕、絹の織物を近在の人々に教え、八王子市が絹の織物の街として発展したのは、信松尼の存在があったからでしょう。
松姫のお墓は本堂の裏ある墓地、高台で「にっこりほほ笑んでいる」と思わせるような雰囲気で建立されています。
甲州街道の山、谷、山、谷・・日が昇っても、鬱葱とした道を凛とした姿勢で甲斐から八王子まで歩き続けた松姫は、どんな思いを胸で呟いていたでしょう・・・・痛いですよね。

信松院門

信松院観音堂。
松姫、1590年大久保長安の財力を借り建立。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児玉道場(児玉猪太郎185年頃創設)秋田県花輪村小枝指
父猪太郎の死後、高慶が道場を継ぐ。その高慶、柔道5段、剣道5段の腕前。
「児玉高慶]の名を有名にしたのは、大正14年5月宮内省剣道特別試合で昭和天皇摂政治宮殿下の御前試合で、陸軍戸山学校の教官、加藤文一、京都武專校長、西久保弘道を破り一躍名を馳せ日本一の武道村」と新聞に報道されたほど。
柔道は嘉納治五郎、剣道は中山博道に師事。夫人「なお」は十和田毛馬内出身、情報活動で、日清戦争前夜、殉難した石川伍一の弟 海軍中佐、日露戦争で戦死した「寿次郎」の一人娘。
芥川賞第1回受賞者の「石川達三」とは「いとこ関係」になる。
「なお」は高慶が41歳で病魔に侵され、この世を去った後、高慶も師事した中山博道師範に神童夢想流杖術の皆伝を受け、花輪、大館の婦人会や女学校で教え、晩年は東京で老後を過ごす。
児玉道場には、ブログ掲載の「太田節三」節三の甥にあたる法務省剣道師範の「横田正行」8段、佐藤貞治7段、佐藤金之助8段、加藤庄一、などそうそうたる剣客が巣立っている。節三に柔道を進めた兄六郎も児玉道場の門下生であった。

高幡不動に咲く木瓜の花。