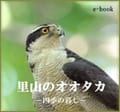あるオオタカの森、活動が鈍くなってきた。 抱卵が近いようである。 この辺りでは、通常3月末~4月頭に抱卵に入る。 ようやく森に静けさが戻り、一段落と言ったところである。
オオタカは2月~3月によく鳴くので、趣味のカメラマンが営巣林に入り、写真を撮ろうと追いかけまわす事による営巣放棄が、抱卵前のこの時期最も多く後を絶たない。 だが、抱卵に入れば鳴かなくなるので、見つかる確率はぐっと低くなるのである。
撮影をするには、まず周辺の地形や環境条件、彼らの習性、習慣、行動および、鳴き声の意味などを充分把握しなければならない。 そうすれば、おのずとどこに行けば会えるかが分かるのである。
安易に営巣木に近づいてはいけない。 また、追い回したり、無理な撮影をしてはいけない。 営巣木周辺は非常に警戒しているから特に注意が必要だ。
無理はせず優しい目で見守ることにしよう。 人もタカも同じ生き物である、互いに尊重しあえば心は通じるものと思っている・・・・。

一緒にいることが多い、仲良しペア。

カラスを警戒し、臨戦態勢をとる♂。

枝で休む♀。

花にメジロ。春本番だ。