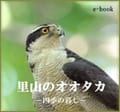オオタカの撮影で、絶対に行かないところがある。 それは、巣作り、交尾の時期から抱卵、育雛まで趣味・遊びのカメラマンが集まり、大勢で営巣木を取り巻き長時間(3時間も4時間も)撮影している場所である。 このような場所には絶対に行かない。
このように営巣木の周りで何時間も撮影していると、オオタカは必ず営巣放棄する。と、思っていた方がよい。 放棄しなかったら、それはラッキー、たまたま個体差大で性格がのんびりやで、気にしなかったのだと思った方がよい。 そのように成功しても2~3年が限度だ。 やがてその場は荒らされ居なくなる。
カメラマンたちは感じていないだろうが、営巣放棄させたらそれはカメラマンの責任、カメラマンとして恥ずかしいことだ。と、思っている。 カラスのせいだなどと責任転嫁する人達がいるが、ほとんどがカメラマンの責任である。 だから私はそのような場所には一切行かない。 営巣放棄が目に見えている。
営巣地は他にもある。 そこにカメラマンが居たとしても、オオタカのプロ同士なら互いに邪魔はしない。 育雛写真なども撮るが、撮影時間は15~20分以内、それで十分だ。 3時間4時間などは言語道断。 何時間粘っても、ストレスを与えるだけで、何もいいことはない。 ほとんど鳴き声で動きを予想し、必要な時だけ撮ればよいのである。
カメラマンは彼らの命と対峙していることを常に考えるべきである。 命に責任を持ち、安易な撮影は慎むべきと考える。
という事で、9月中旬になると狩場にオオタカが現れ始める。 10月も後半になると、新たな繁殖シーズンが始まる。 どのようなシーンに出会えるか、出会う確率を上げるにはどうしたらよいのか、などを考えながら、素晴らしい写真を目指して撮影しよう・・・・。ではないか。