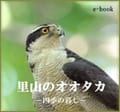空気が澄みきって、抜けるような青空だ。 だが吹く風は冷たい。 白い息を吐きながら尾根の上まで登る。 やがて朝日が昇ってくる。 今年最後となる朝日だ。
霜柱を踏みながら歩くと、ウソが枝先で鳴いていた。 ルリビタキの♂も鳴いている。 綺麗な鳥達にもようやく出会えたのである。 と、言うことで、今年最後の鳥見は、来年につながるような気がした。
元旦に立てた目標は、達成できたろうかと考える。 いくつか有ったが、今までに無かったオオタカのシーズンを通した生態写真集は、ようやく発表することが出来た。 次は何をしようかと思うのであった・・・・。

枝先で鳴くウソ。

林のアオジ。

枝にとまるルリビタキ。

人懐っこいヤマガラ。

木の股にたまった水を飲むメジロ。

真っ青な空を行くハイタカ。

森の主のオオタカ。

土を起こす霜柱。