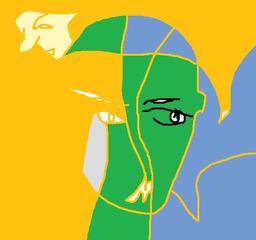
■「言う」から「聞く」へ
ふと思う。
ちゃんと人の話を聞くことは、お互いにとって大事だ。
相手の話を聞くということ。
簡単なようで実際は行われていない。
自分の意見を強く持つこと、はっきり主張すること。
そういうことばかりが教えられている。
言うことも大事だけど、聞くことも大事だ。それは相補的なもの。
「言う」から「聞く」へ
仕事でもなんでもそうだけど、人の話をちゃんと聞くだけで、よりよくなることはいっぱいある気がする。
■話すこと、物語り
人は話したい何かを持っている。
その人が気付いているときもあれば、気付いていないときもある。
話すことによって、その人の人生の物語は編みこまれていく。
何度も話していると、それはひとつの型となる。それが物語だ。
自分の物語は、不条理なこともいいことも悪いことも、全てを包む込む必要がある。
だから、それなりに大きく包み込むものになる必要がある。
誰かの物語を参考にすることはできるけど、自分の物語は自分で編み込んでいかないといけない。
親であっても、人の物語を勝手に作ってはいけないと思う。
■ありのままを聞く
人の話を聞くこと。
自分の視点で勝手に解釈したり構造化したり位置づけしたり分析したりすると、生の素材を損ない、自分風味に味付けしてしまう。
そうではなくて、その話をありのままに、ニュートラルな立場で、話そのものを聞くことが大事なんだと思う。
人の話をちゃんと聞くことは、相手を受け入れることにつながる。
それが聞き上手。
聞き上手には、徳がある。だから、人が集う。
長く口を閉ざしていることを話し始める最初は、臨界点のようなポイントがある。
ちゃんと話を聞かない人によって、口は閉ざされたのだろう。
もちろん、こじ開ける必要はなくて、適切な時が満ちるのを待つのは大事だ。
「話すことなんて何もない」という人も、向き合う相手のありかた次第でその閾値は下がる。
口は、永遠に閉ざされるものではない。
鳥かごに閉じ込められた鳥が大空にはばたくような勢いで、その人の口から混ぜこぜのかたまりが洪水のようにあふれてくることがある。
その濁流の中でもたじろがず、しっかり目を見据え、その流れを阻害せず、ただ聞くことが大事だ。
自分の解釈や分析で損なわず、ありのままの話を聞く。
人は何かを話したい。それには、相手が必要だ。
壁の前で話すのには限界があるのだろう。
聞く相手が存在することで、話すことができる。
自由に話していると、統一性のなかった話もあるところに落ち着いていくんだと思う。
■序破急→落居(らっきょ)、成就
世阿弥は世界に「序破急」のリズムがあると言う。
*******************
世阿弥:序破急
序『心耳を開く』、破『見物諸人一同の目前感応の成就』(「拾玉得花」)、急『即座一同の妙感をなす処』(「三道」)
*******************
世阿弥は、森羅万象全てに序破急のリズムがあるという。
本来そうあるべき経過を完了して落着くことを、「落居」して「成就」するという。
落居は「落ち居る」。成就とは「成り就く」。
鳥のさえずり、虫の鳴き声も、その本分のままに鳴くのは序破急。
それは、無心のままで成就に達している。
人間の手も足も指の動きも、それぞれひとつひとつにも序破急がある。
序破急が正しく連続して展開すると「落居」する。
そのことで、見る側、見られる側の心が「成就」するのだと。
自分の考えって、話したり、書いたり、聞いたりしていると、いつのまにかまとまってきて(「落居」)、自分でも納得する形になる。それを相手も納得したら「成就」する。
そして、その人特有のリズム(序破急)も確かに感じる。
人の話を阻害せずに聞くことは、ありのまま話すことにもつながる。
そのことでその人の物語ができるんだと思う。
その人の「序破急」のリズムは、物語という形でその人に「落居(らっきょ)」・「成就」するんだろう。
■耳をすます、聞く
ちゃんと人の話を聞くことは大事だ。
前にブログにタクシー運転手の話を書いたときもふと思った。
→『タクシーとわたし』(2010-06-27)
夜中に病院で当直をしていても思う。
とにかく、話を聞いてほしいという人が多いんだと思う。
夜の水商売もそういうものなのかな。
人は、書くことやその他の表現でも一部は満たされるとは思うけれど、話すことでその人のものとなっていくのだと思う。物語として落居する。
聞くことは、コミュニケーションの基本だ。
言うことや主張することばかり教えられるけれど、聞くことは見落とされ、軽んじられやすい行為のような気がしている。
ふと思う。
ちゃんと人の話を聞くことは、お互いにとって大事だ。
相手の話を聞くということ。
簡単なようで実際は行われていない。
自分の意見を強く持つこと、はっきり主張すること。
そういうことばかりが教えられている。
言うことも大事だけど、聞くことも大事だ。それは相補的なもの。
「言う」から「聞く」へ
仕事でもなんでもそうだけど、人の話をちゃんと聞くだけで、よりよくなることはいっぱいある気がする。
■話すこと、物語り
人は話したい何かを持っている。
その人が気付いているときもあれば、気付いていないときもある。
話すことによって、その人の人生の物語は編みこまれていく。
何度も話していると、それはひとつの型となる。それが物語だ。
自分の物語は、不条理なこともいいことも悪いことも、全てを包む込む必要がある。
だから、それなりに大きく包み込むものになる必要がある。
誰かの物語を参考にすることはできるけど、自分の物語は自分で編み込んでいかないといけない。
親であっても、人の物語を勝手に作ってはいけないと思う。
■ありのままを聞く
人の話を聞くこと。
自分の視点で勝手に解釈したり構造化したり位置づけしたり分析したりすると、生の素材を損ない、自分風味に味付けしてしまう。
そうではなくて、その話をありのままに、ニュートラルな立場で、話そのものを聞くことが大事なんだと思う。
人の話をちゃんと聞くことは、相手を受け入れることにつながる。
それが聞き上手。
聞き上手には、徳がある。だから、人が集う。
長く口を閉ざしていることを話し始める最初は、臨界点のようなポイントがある。
ちゃんと話を聞かない人によって、口は閉ざされたのだろう。
もちろん、こじ開ける必要はなくて、適切な時が満ちるのを待つのは大事だ。
「話すことなんて何もない」という人も、向き合う相手のありかた次第でその閾値は下がる。
口は、永遠に閉ざされるものではない。
鳥かごに閉じ込められた鳥が大空にはばたくような勢いで、その人の口から混ぜこぜのかたまりが洪水のようにあふれてくることがある。
その濁流の中でもたじろがず、しっかり目を見据え、その流れを阻害せず、ただ聞くことが大事だ。
自分の解釈や分析で損なわず、ありのままの話を聞く。
人は何かを話したい。それには、相手が必要だ。
壁の前で話すのには限界があるのだろう。
聞く相手が存在することで、話すことができる。
自由に話していると、統一性のなかった話もあるところに落ち着いていくんだと思う。
■序破急→落居(らっきょ)、成就
世阿弥は世界に「序破急」のリズムがあると言う。
*******************
世阿弥:序破急
序『心耳を開く』、破『見物諸人一同の目前感応の成就』(「拾玉得花」)、急『即座一同の妙感をなす処』(「三道」)
*******************
世阿弥は、森羅万象全てに序破急のリズムがあるという。
本来そうあるべき経過を完了して落着くことを、「落居」して「成就」するという。
落居は「落ち居る」。成就とは「成り就く」。
鳥のさえずり、虫の鳴き声も、その本分のままに鳴くのは序破急。
それは、無心のままで成就に達している。
人間の手も足も指の動きも、それぞれひとつひとつにも序破急がある。
序破急が正しく連続して展開すると「落居」する。
そのことで、見る側、見られる側の心が「成就」するのだと。
自分の考えって、話したり、書いたり、聞いたりしていると、いつのまにかまとまってきて(「落居」)、自分でも納得する形になる。それを相手も納得したら「成就」する。
そして、その人特有のリズム(序破急)も確かに感じる。
人の話を阻害せずに聞くことは、ありのまま話すことにもつながる。
そのことでその人の物語ができるんだと思う。
その人の「序破急」のリズムは、物語という形でその人に「落居(らっきょ)」・「成就」するんだろう。
■耳をすます、聞く
ちゃんと人の話を聞くことは大事だ。
前にブログにタクシー運転手の話を書いたときもふと思った。
→『タクシーとわたし』(2010-06-27)
夜中に病院で当直をしていても思う。
とにかく、話を聞いてほしいという人が多いんだと思う。
夜の水商売もそういうものなのかな。
人は、書くことやその他の表現でも一部は満たされるとは思うけれど、話すことでその人のものとなっていくのだと思う。物語として落居する。
聞くことは、コミュニケーションの基本だ。
言うことや主張することばかり教えられるけれど、聞くことは見落とされ、軽んじられやすい行為のような気がしている。










私は人のはなしを聴きたい。
その人が今のその人に至ったまでの過程に興味があるのだと思います。
さきほどもBSハイビジョンでやっていた「南米1周 165日の旅」の中で、世界中から集まった年齢も国籍も違う人たちを見ていると、彼らひとりひとりがその旅に出る前にどんな生活を送っていて、どんな動機でこの旅に出ることを決めたのかにとても興味があるなあ、と思っていたところです。
どんな人生を送ってきたのか聴かせてほしい欲ってなんなんでしょうね。
決して物珍しさとか、野次馬根性的な動機ではないと思うんですよ。
その人の物語を知りたい。
そこに面白い、面白くないもないし、良い悪いもない。
と言いつつも知らない間に自分のフィルターをかけてしまって、都合のいいように解釈を与えてしまっているのかな。。。
ありのままに聴く、かぁ。。。
ありのままを受け止めつつ、そこに暖かさを生じさせたい、と思うのは自己満足かな。
おやすみなさい。
はなしを聴きたい側の人なのですね。きっと聞き上手なのでしょう。
聞くことは、相手を受け入れることですし、待つ必要があるもので。
その世界を阻害しないように、そっと耳を澄ますような感じで。
Chieさんがおっしゃるように、夜の新幹線で、家の中の光を見ていると、それぞれに物語があり、人生があり、そのことにふと思いをはせてしまいますよね。
そのときもなんか異次元に連れて行かれるような不思議な気がします。
お医者さんには不向きなタイプでしょうね^^;
聴き上手な人、いますよね!そういう人だと話しながら癒されます。
でも話したくないのに何故か距離感が掴めなかったり間が持たなくて、あれやこれや話をしてしまうこともありますけど、これも一種聴き上手な人になるののかな?
ところで小説の「告白」は読みました?
同じ事でも言う側と聴く側(もしくは単に違う立場)の捉え方やニュアンス、さらには本質までもがすれ違ったり交差している様子が描かれていて興味深い作品でした。
まあ確かに、僕もプライベートでは相手によって変えますけどねぇ。
仕事では、医者は自分の意見ばっかり言うタイプが多くて、たいていにそれはすれ違いを生むことが多くて、よく話を聞くようにしてます。患者さんには患者さんなりの持論があって、それは正しいとか正しくないとかではなくて(間違ってる!って言ってほしいようなニュアンスがある人にはあえて言いますけど)、そういう現実を生きているわけで、向こうの考えを阻害しないように、うまく誘導するような感じですね。
この辺は、阿吽というか、なかなか言語化しにくいけど、誰もが多かれ少なかれ無意識にやってることだとも思うわけです。
『でも話したくないのに何故か距離感が掴めなかったり間が持たなくて、あれやこ
れや話をしてしまうこともありますけど、これも一種聴き上手な人になるののか
な?』
まあこれは聞き上手というより、「なんとなく間が持たない」というだけかも。笑
でも、そういう間を感じるのも、言ってみれば不思議ですよね。
こちらはそういう間とか空白が空くのがイヤで必死にしゃべっても、向こうはその間とか隙間をなんとも思わないこともあるだろうし。
確かに、お互いあまり知らない人同士で無言で何分も向き合うっていうのは、確かに気まずいけど。笑
ほんとの聞き上手って、思わず予定外のことはなしてみたり、そして話した後に自分がすごくすっきりして気持ちよかったりする、そんな感じだと思いますねぇ。
自分のいろんな場所を引き出されるという感じ。浅いとこも、深いとこも。そしてそれがイヤでは全然無くて。
小説の「告白」、まだ読んでないです。
映画がなんか好評みたいですよね。松たか子の。
小説版ではけっこうエグイって前評判があったんで見てないけど、なかなか面白そうですねぇー。
ベストセラーになったり賞をとってる本、「天地明察」「猫を抱いて象と泳ぐ」「悼む人」・・ちょこちょこ買ってるけど、積ん読でまだ読んでないー。
「考えるんじゃない、考えさせるんだ」(ちょっとエヴァ風だけど、内容は逆かな?)と前の部長さんに教えられたことも思い出しますね。
また、ちょうど先週、英語の授業を受けたんですけど、そのとき、ディスカッションの練習みたいなのをしたんですが、その先生は今までと真逆で、「とにかく、人の話をさえぎるんだ!何か相手が言ったら、No! I don't think so!と言え!他のアイディアを投げてもいい!とにかく誰かが話したら、すぐにその話をさえぎって自分が話せ!」と言われて、実際やってみたんですが、げんなりしました。。泣
でも、やってみてわかったんですが、この「人の話をさえぎる方法」ってうちの外人よく使います。ミーティングしてて、自分が話そうとすると割って入ってきて、とにかく自分の意見を言う(内容が正しくないことを言っていても、自分が話すことがアピールになると思っているのかしら?)。
言うことも大事だけど、聞くことも大事だ。それは相補的なもの。ほんとそう思います。だから、双方のバランスが取れるような話し方を自分がコントロールしながら、会話が成り立つように持っていってみようかなぁと、このブログと英語教室を通して思いました。聞いてくれる人だったら同じくらい聞くけど、しゃべり倒す人にしゃべり倒してみるって感じです。
cultureの違いもあるかもしれませんけどね。。
攻めと受け。
みたいなものかな。
攻めは攻撃的だし、なんかかっこいいし、派手で目立つんだけど、あるところからその限界を感じる。
っていうのも、結局は自分の脳みそで考える範囲の中でしか、物事は展開していかないんだよね。自分の秩序ある箱庭でしかなくて。
聞くって行為。
それは真剣にやると、ほんとに相手の人生を追体験するほどの力があって、そういう他者の視線を取り入れることで、ぐっと世界は広く豊かになる。
患者さんと接してて、医者の視点にとらわれないように、実用面でもすごく意識してるよ。
お互い、人と接する仕事である以上、そこははずせないと思うんだよね。
外人とか朝生の話をさえぎる人。
正直、やれやれと思うけど(村上春樹風)、まあこの人も誰かの話は聞かないかわりに、自分の話は聞いてほしいんだろうなぁとは思うので、だまって聞くようにしてます。相手が疲れ果てていやになるまで、聞き続けます。笑