
東京国立近代美術館でやってる「パウル・クレー ― おわらないアトリエ」(PAUL KLEE: Art in the Making 1883-1940)を見てきた。
■
<展覧会HPより>
---------------------------
スイス生まれの画家パウル・クレー(Paul Klee, 1879-1940)は、長らく日本の人々に愛され、これまでにも数多くの展覧会が開催されてきました。
それらの展覧会では作品の物語性や制作上の理念が詩情豊かに詠われ、多くの人々にクレーの芸術の魅力を伝える役割をはたしました。
国立近代美術館で初となる今回のクレー展では、今までの展覧会成果を踏まえた上で、これまでクローズアップされてこなかった「クレーの作品は物理的にどのように作られたのか」という点にさまざまな角度から迫ります。
この観点から作品を見てみるならば、視覚的な魅力を体感できるのみならず、その魅力がいかなる技術に支えられているのか、ということまでもが明らかになるでしょう。
クレーは1911年から終生、制作した作品の詳細なリストを作り続けます。
1883年、画家4歳のときの作品を手始めに、約9600点もの作品からなるこのリストには、作品のタイトルのみならず、制作年と作品番号、そして使用した材料や技法などがこと細かに記されています。
「何を使い、どのように作ったのか」ということは、この画家にとってきわめて重要な関心事だったのです。
その「制作プロセス」を、クレーは、アトリエ写真というかたちで記録に留めたり、自ら「特別クラス(Sonderklasse)」と分類した作品を模範作として手元に置いたりしながら、生涯にわたって検証し続けました。
具体的な「技法」と、その技法が探究される場である「アトリエ」に焦点を絞り、クレーの芸術の創造的な制作過程を明らかにしようする本展において、鑑賞者は、ちょうど画家の肩越しに制作を垣間見るような、生々しい創造の現場に立ち会うことになるでしょう。
スイスのパウル・クレー・センターが所蔵する作品を中心に、ヨーロッパ・アメリカ・国内所蔵の日本初公開作品を数多く含む約170点で構成されます。
---------------------------
■
クレーはすごく好きな画家だ。
この人の絵を見ていると、なにか物語が始まりそうな予感をいつも感じる。
絵をみるだけで、その深いイメージ世界から自動的に物語りが紡ぎだされてくるようで。
ふと、小川洋子さんの言葉を思い出す。
==================
小川洋子「物語の役割」(ちくまプリマー新書)
『(想像の中で)廃墟に立って浮かび上がってくる映像を観察する。じっと目をこらし、見えてくるものを描写する。
人間の内面という抽象的な問題にとらわれず、目で観察できるものにひたすら集中する。
そこから初めて、目に見えないものの存在が言葉に映し出されてくるのでは、と思っています。』
==================
(⇒小川洋子「物語の役割」(2011-05-29))
小川さんが物語りを書くとき。
浮かんできたイメージ世界を克明に詳細に記す。細密画家のような視線で。
そうすると、自動的に物語が動き出すとのことだ。
村上春樹さんも、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」文藝春秋 (2010/9/29)の中で似たような記述をしていた気がする。
いい文学作品は、映像が見え、音楽までもが聞こえてくるものだ。
第6感までも含めて人間が持つ感覚を総動員する。
■
物語世界と言語世界はイメージ世界を媒介にして連結される。
人と人とが分かりあう時、共感する時。
そこには深いイメージの共有があるのだと思う。だからこそ、異質なものがつながる。
言葉はあくまでも言葉。
コトバはあくまでもコトバで、コトバハアクマデモコトバ.
あいうえお、かきくけこ、さしすせそ・・で構成される言葉。
abcdefghi・・・で構成される言葉。
その記号の組み合わせから構成される言語世界の中で、言葉が相手に伝わるときには、言葉を触媒として互いの深い場所で何かイメージが共有されるのだと思う。
だから、相手に伝わることもあるし、伝わらないこともある。
ときには言葉を使わなくても伝わることもある。
それは、深い場所で同じイメージが共有されたということだ。
<楽しかった!>、<おもしろかった!>、<嬉しかった!>・・・
<つらかった>、<かなしかった>、<さびしかった>・・・・・
正でも負でも、自分が体験していないにも関わらずに相手の感情を共有できるのは、自分が持つ似た感情を追体験しつつ、その情景や風景をイメージしているからだと思う。そうして、別々の人間の間で、感情が共有されていく。
「イメージ」は、寝ている時に見る「夢」のようなものだ。
ある程度「意識」しないと、それは意識世界に上がってこない。無意識世界は深海のように深いから。
夢を夢として認識できるのは、無意識の深海から意識の浅瀬に上がってきた一部だけだ。
それ以外は、なかなかわからない。
無意識の奥底に湧き起こるイメージを意識化すること。
その営みは、「夢を見る」という形で毎日体験している。
それを意識しているか、意識してないかの違いに過ぎない。
寝て「夢を見る」以外にも、起きて「絵を見る」事は同じような体験をしているのだと思う。
「絵を見る」事は、起きたまま「夢を見る」ことと似ている。
クレーのように無意識深くの洞窟から湧き起こるイメージを共有するには、こちらも意識を束ねる力を緩くしないといけない。
意識をスルスルとほどいて、見る。
だから、こちらもなんだか眠くなる。
寝ているのか起きているのか、起きているのか寝ているのか。
その両方が重なる状態くらいが丁度いい。
日常の意識レベルと違う状態で絵を見るから、自分の奥深くに刻印されて長く残るイメージがある。
イメージの世界は、自律性を持って動き出す。
それを言語を使って外に出すと、まるで物語のようにして感じられるものになるのだ。
だから、クレーの絵を見ると、いつも物語を感じる。
そこに、そこに特有のリズムや躍動を、そこに自律的な世界を感じる。
■
今回のクレー展は、見たことない絵が多かった。クレーは射程が広い。
クレー自身が「絵を描くとはどういうことか」と、自分の制作活動そのものをセカンド自分として上から俯瞰してみている。その過程が今回の展覧会では紹介されていた。
クレーの脳の中の劇場を好意で見せてもらっているようだ。
7月31日(日)まで東京国立近代美術館で開催中ですが、ここまで大規模なものは今後開かれないかもしれないので、是非遊びに行ってみてください。絵ハガキもたくさん買ってしまいました。
P.S.
クレーの絵は、物語を感じる。絵本の絵のようで。
だから、谷川俊太郎さんが詩を寄せて作られた絵本がある。これらの本はとても好きです。ふと見返します。
●パウル・クレー(著),谷川俊太郎(著)「クレーの絵本」講談社ARTピース(1995)

●パウル・クレー(著),谷川俊太郎(著)「クレーの天使」講談社ARTピース(2000)

画集はこれを持ってます。
●スザンナ・パルチュ「クレー」TASCHEN(2003) (画集と言えばやっぱりTASCHEN!)

●前田富士男、宮下誠、いしいしんじ(著)「パウル・クレー 絵画のたくらみ」(とんぼの本) [単行本]

神保町の美術書コーナーに行くたび、いつも惹かれるのはこれです。
●フェリックス・クレー「パウル・クレー 遺稿、未発表書簡、写真の資料による画家の生涯と作品」みすず書房(2008) \6090

●パウル・クレー「クレーの日記」みすず書房(2009) \8925
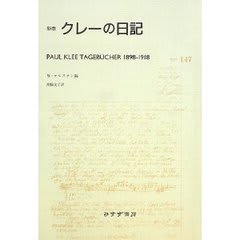
みすず書房の重厚感も含め、いつも欲しいんだけど高いんですよね。6000円と9000円ですから!
しかも、古本屋でも探しても安くならないのです。値が落ちないのです。これはすごいこと。
だからこそ、いつも迷う。そして、今現在も買っていません。
いつか、ご飯食べる時もメニューの値段見ずに頼めるようになったら、コンビニおにぎりで100円と140円のがあってもなんのためらいもなく140円のおにぎりを買えるような裕福な自分になったら、いつか買いたいなー。
=========================
パウル・クレー『色彩は私を永遠に捉えた、私にはそれがわかる。この至福の時が意味するのは、私と色彩はひとつだということ。私は、画家だということ」
=========================
パウル・クレー『左手は右手ほど巧みではない。 だからしばしば右手より役立つのだ。』
=========================
パウル・クレー『芸術とは、目に見えるものを複製することではない。 見えないものを見えるようにすることだ。』
=========================
■
<展覧会HPより>
---------------------------
スイス生まれの画家パウル・クレー(Paul Klee, 1879-1940)は、長らく日本の人々に愛され、これまでにも数多くの展覧会が開催されてきました。
それらの展覧会では作品の物語性や制作上の理念が詩情豊かに詠われ、多くの人々にクレーの芸術の魅力を伝える役割をはたしました。
国立近代美術館で初となる今回のクレー展では、今までの展覧会成果を踏まえた上で、これまでクローズアップされてこなかった「クレーの作品は物理的にどのように作られたのか」という点にさまざまな角度から迫ります。
この観点から作品を見てみるならば、視覚的な魅力を体感できるのみならず、その魅力がいかなる技術に支えられているのか、ということまでもが明らかになるでしょう。
クレーは1911年から終生、制作した作品の詳細なリストを作り続けます。
1883年、画家4歳のときの作品を手始めに、約9600点もの作品からなるこのリストには、作品のタイトルのみならず、制作年と作品番号、そして使用した材料や技法などがこと細かに記されています。
「何を使い、どのように作ったのか」ということは、この画家にとってきわめて重要な関心事だったのです。
その「制作プロセス」を、クレーは、アトリエ写真というかたちで記録に留めたり、自ら「特別クラス(Sonderklasse)」と分類した作品を模範作として手元に置いたりしながら、生涯にわたって検証し続けました。
具体的な「技法」と、その技法が探究される場である「アトリエ」に焦点を絞り、クレーの芸術の創造的な制作過程を明らかにしようする本展において、鑑賞者は、ちょうど画家の肩越しに制作を垣間見るような、生々しい創造の現場に立ち会うことになるでしょう。
スイスのパウル・クレー・センターが所蔵する作品を中心に、ヨーロッパ・アメリカ・国内所蔵の日本初公開作品を数多く含む約170点で構成されます。
---------------------------
■
クレーはすごく好きな画家だ。
この人の絵を見ていると、なにか物語が始まりそうな予感をいつも感じる。
絵をみるだけで、その深いイメージ世界から自動的に物語りが紡ぎだされてくるようで。
ふと、小川洋子さんの言葉を思い出す。
==================
小川洋子「物語の役割」(ちくまプリマー新書)
『(想像の中で)廃墟に立って浮かび上がってくる映像を観察する。じっと目をこらし、見えてくるものを描写する。
人間の内面という抽象的な問題にとらわれず、目で観察できるものにひたすら集中する。
そこから初めて、目に見えないものの存在が言葉に映し出されてくるのでは、と思っています。』
==================
(⇒小川洋子「物語の役割」(2011-05-29))
小川さんが物語りを書くとき。
浮かんできたイメージ世界を克明に詳細に記す。細密画家のような視線で。
そうすると、自動的に物語が動き出すとのことだ。
村上春樹さんも、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」文藝春秋 (2010/9/29)の中で似たような記述をしていた気がする。
いい文学作品は、映像が見え、音楽までもが聞こえてくるものだ。
第6感までも含めて人間が持つ感覚を総動員する。
■
物語世界と言語世界はイメージ世界を媒介にして連結される。
人と人とが分かりあう時、共感する時。
そこには深いイメージの共有があるのだと思う。だからこそ、異質なものがつながる。
言葉はあくまでも言葉。
コトバはあくまでもコトバで、コトバハアクマデモコトバ.
あいうえお、かきくけこ、さしすせそ・・で構成される言葉。
abcdefghi・・・で構成される言葉。
その記号の組み合わせから構成される言語世界の中で、言葉が相手に伝わるときには、言葉を触媒として互いの深い場所で何かイメージが共有されるのだと思う。
だから、相手に伝わることもあるし、伝わらないこともある。
ときには言葉を使わなくても伝わることもある。
それは、深い場所で同じイメージが共有されたということだ。
<楽しかった!>、<おもしろかった!>、<嬉しかった!>・・・
<つらかった>、<かなしかった>、<さびしかった>・・・・・
正でも負でも、自分が体験していないにも関わらずに相手の感情を共有できるのは、自分が持つ似た感情を追体験しつつ、その情景や風景をイメージしているからだと思う。そうして、別々の人間の間で、感情が共有されていく。
「イメージ」は、寝ている時に見る「夢」のようなものだ。
ある程度「意識」しないと、それは意識世界に上がってこない。無意識世界は深海のように深いから。
夢を夢として認識できるのは、無意識の深海から意識の浅瀬に上がってきた一部だけだ。
それ以外は、なかなかわからない。
無意識の奥底に湧き起こるイメージを意識化すること。
その営みは、「夢を見る」という形で毎日体験している。
それを意識しているか、意識してないかの違いに過ぎない。
寝て「夢を見る」以外にも、起きて「絵を見る」事は同じような体験をしているのだと思う。
「絵を見る」事は、起きたまま「夢を見る」ことと似ている。
クレーのように無意識深くの洞窟から湧き起こるイメージを共有するには、こちらも意識を束ねる力を緩くしないといけない。
意識をスルスルとほどいて、見る。
だから、こちらもなんだか眠くなる。
寝ているのか起きているのか、起きているのか寝ているのか。
その両方が重なる状態くらいが丁度いい。
日常の意識レベルと違う状態で絵を見るから、自分の奥深くに刻印されて長く残るイメージがある。
イメージの世界は、自律性を持って動き出す。
それを言語を使って外に出すと、まるで物語のようにして感じられるものになるのだ。
だから、クレーの絵を見ると、いつも物語を感じる。
そこに、そこに特有のリズムや躍動を、そこに自律的な世界を感じる。
■
今回のクレー展は、見たことない絵が多かった。クレーは射程が広い。
クレー自身が「絵を描くとはどういうことか」と、自分の制作活動そのものをセカンド自分として上から俯瞰してみている。その過程が今回の展覧会では紹介されていた。
クレーの脳の中の劇場を好意で見せてもらっているようだ。
7月31日(日)まで東京国立近代美術館で開催中ですが、ここまで大規模なものは今後開かれないかもしれないので、是非遊びに行ってみてください。絵ハガキもたくさん買ってしまいました。
P.S.
クレーの絵は、物語を感じる。絵本の絵のようで。
だから、谷川俊太郎さんが詩を寄せて作られた絵本がある。これらの本はとても好きです。ふと見返します。
●パウル・クレー(著),谷川俊太郎(著)「クレーの絵本」講談社ARTピース(1995)

●パウル・クレー(著),谷川俊太郎(著)「クレーの天使」講談社ARTピース(2000)

画集はこれを持ってます。
●スザンナ・パルチュ「クレー」TASCHEN(2003) (画集と言えばやっぱりTASCHEN!)

●前田富士男、宮下誠、いしいしんじ(著)「パウル・クレー 絵画のたくらみ」(とんぼの本) [単行本]

神保町の美術書コーナーに行くたび、いつも惹かれるのはこれです。
●フェリックス・クレー「パウル・クレー 遺稿、未発表書簡、写真の資料による画家の生涯と作品」みすず書房(2008) \6090

●パウル・クレー「クレーの日記」みすず書房(2009) \8925
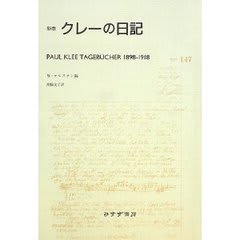
みすず書房の重厚感も含め、いつも欲しいんだけど高いんですよね。6000円と9000円ですから!
しかも、古本屋でも探しても安くならないのです。値が落ちないのです。これはすごいこと。
だからこそ、いつも迷う。そして、今現在も買っていません。
いつか、ご飯食べる時もメニューの値段見ずに頼めるようになったら、コンビニおにぎりで100円と140円のがあってもなんのためらいもなく140円のおにぎりを買えるような裕福な自分になったら、いつか買いたいなー。
=========================
パウル・クレー『色彩は私を永遠に捉えた、私にはそれがわかる。この至福の時が意味するのは、私と色彩はひとつだということ。私は、画家だということ」
=========================
パウル・クレー『左手は右手ほど巧みではない。 だからしばしば右手より役立つのだ。』
=========================
パウル・クレー『芸術とは、目に見えるものを複製することではない。 見えないものを見えるようにすることだ。』
=========================









