
アントニオ・タブッキの「インド夜想曲」白水Uブックス(1993/10)を読んだ。面白かったー。
=============
<出版社/著者からの内容紹介>
失踪した友人を探してインド各地を旅する主人公。
彼の前に現われる幻想と瞑想に充ちた世界。
インドの深層をなす事物や人物にふれる内面の旅行記とも言うべきこのミステリー仕立ての小説を読みすすむうちに読者はインドの夜の帳の中に誘い込まれてしまう。
イタリア文学の鬼才が描く12の夜の物語。
=============
なんと言っても、須賀敦子さんが翻訳。訳自体もいいんだろうな。
元々は、アラン・コルノー監督の映画版「インド夜想曲」を職場の方に偶然借りたのが最初でした。
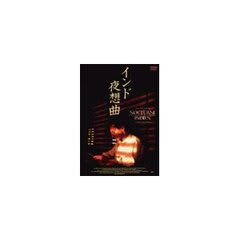
かなり面白くて、思わず2回見てしまった。
原作の小説も読んでみたくなって、読んだら合わせて二度美味しい感じだった。
原作を超える映画を作るのは難しいですけど、これはもしかしたら映画の方がいいんじゃないかと思うほど。
映画の映像表現が詩的で幻想的で、常に予感に満ちた映像表現でよかった。
あんまり解説すると面白くないんだけど,自我egoと自己selfとか、自分の中にある「影Shadow」、人間の「たましい」の話のように思った。
ユング的ですね。ちなみにヘッセも名前だけすこし出てきます。
シャミッソーの「影をなくした男」岩波文庫 (1985/3/18) に出てくるシュレミールの物語のようでもある。
言葉づかいも映像もイメージに満ちててすごくよかった。自分の中にもイメージが立ちあがり、イマジネーションがかきたてられた。
ガルシア・マルケスとか村上春樹さんに近い世界観。
自分は、やはり幻想文学というか、magic realismとか言われるような小説が好きなんだろうな。
小説世界があまりに「現実」世界に忠実だと、その世界観に入り込めない自分がいます。
自分としては、この現実世界を、自分なりに一生懸命生きているつもりです。
この懸命に生きている現実世界を、あえて安いレプリカとして複製するのは、作家の脳に取り込んだ「箱庭」だけを「現実だ」と押し付けられたような気がする。
あえてそんな風に現実のレプリカとしてリプレイする必要があるのかな、と思う。
心が動かない小説世界(→これは自分の問題なのでどうしようもない)には、そういう模造品のくすんだ香りがします。
脳内での幻(マーヤ)として「偽の現実」を複製するくらいなら、その前にこの生きてる現実世界でやるべきことがたくさんあると思います。
この生きている現実では、利他行為とか思いやりとか優しさとか慈悲とか愛情とか・・・・・行為としてすべきことがたくさんあるように思うのです。この世界はとかく忙しい。
だからこそ、小説世界ではこの現実とは違う「現実」を、生きたい。
それは、この現実を包み込むスケールを持った巨大な空間がいい。できれば、この現実の時間や空間の尺度が意味をなさないほどの場所が理想です。そんな世界にこそ入り込みたいと、切実に思うのです。それは絵画でも同じ。
それは、この生きた現実をさらに豊かで膨らんで感じさせてくれる触媒のようなもの。
それは、この現実に複雑で濃い陰影を織りなして倍音を聞かせてくれるよう絵画的で音楽的なもの。
それは、見えない世界を見せてくれる神秘的なもの。
そんな小説世界をこそ読みたいものです。(あくまでも個人的な趣味の問題ではあります。)
だからこそ、自分が求めるものと作家が提示するものとが、鍵と鍵穴のように符合するととても心地よい気持ちになるものです。
そういう意味で、このアントニオ・タブッキも、ガルシア・マルケスも、ドストエフスキーも、ヘッセも、村上春樹さんも・・・すぐれた小説家からは、この現実世界をスッポリ包み込んでしまうような多層で多重な世界観を感じます。
・・・・・・・・・
インパクトが強かったシーンがある。
映画の方がより印象的だった。
ジャイナ教の預言者という女性が出てくる。
ちなみに、ジャイナ教とは、釈迦(シッダールタ)と同時代のマハーヴィーラ(ヴァルダマーナ)が開祖のインド特有の宗教。あらゆるものに生命を見いだして、動物、植物はもちろん、地・水・火・風・大気にまで霊魂(ジーヴァ)の存在を認める。だから、不殺生(アヒンサー)が徹底されていて、あらゆる行動において生命を殺めていないかどうか、歩くのにも呼吸するのにも細心の注意を払う。だから、ジャイナ教の信者の方々はインドに行くとすぐにわかる。ヒンズー教徒とは全然違う雰囲気をまとっている。 学生時代にインドを旅したときにも、ジャイナ教の方々の、宗教的な生き様は特に印象深かったのを覚えている。まさにインドの深さだと思った。 ジャイナ教は、断定的な判断を避けて、つねに相対的に考察することも教義の中心になっている。こういう風に争わず対立を避ける宗教こそ、いま学ぶべきことが多い宗教のように思える。
ところで、そういうインドの神秘を体現するジャイナ教。
そのジャイナ教の流浪の預言者は、姿形も異形の相をしている。(小説では兄の設定だった。映画ではインパクト強かった。)
その預言者は、未来も過去も全てが見えると言う。
その預言者に5ルピーを払い主人公が尋ねる。
「自分が探している友人はどこにいるんだ?」
すると、その預言者は答える。
「あなたはここにはいない。」
「自分が聞いているのは友人のことだ。僕はここにこうしているんじゃないか。」
預言者は答える。
「あなたはここにはいない。あなたのアートマンはここにはいない。」
「それじゃ、アートマンってなんだ?」
預言者の姉を連れた少年はにっこり微笑んで答える。
「The soul. 個人のたましいのことです。」
・・・・・・・・・・
「アートマン」という概念自体も、インドの神秘性を体現していると思う。
アートマンは、「最も内側 (Inner most)」が語源の言葉で、人間の最も深い内側にある根源のこと。真我とも言われる。まさに「Soul(魂)」とも言える。
アートマンは、<知るものと知られるもの>の二元性を越えているので認識の対象にはならないとされています。
ちなみに、そのアートマン(The soul:たましい)は、宇宙の根源原理のブラフマンと同じとされて、そのことを「梵我一如」と表現します。
インド哲学は深いですね。歴史の重みを感じます。
この辺りのインドの世界観を漫画で体感したい方は、諸星大二郎先生の「孔子暗黒伝」(→元々は1977年の作品!) なんかを強くお勧めします。ちなみに、この本は「暗黒神話」(→1976年の諸星大二郎先生のデビュー作!)とつながっているので、同時に読まないといけません。タイトル名はおどろおどろしいですが、そんなことよりもとにかくすごすぎる作品です。
本題に戻ります。
アントニオ・タブッキ「インド夜想曲」の中では、この「アートマン」のやりとりが、一番印象的なシーンだった。
次は、シュタイナーで有名な神智学協会の人との対話とか。無宗教のインド人医師との対話とか。
他にも色んなシーンが断章的に出てきます。イメージを重ねる感じで物語は進む。
そのイメージをどう組み立てるかは、見る側に委ねられていると思う。
ある意味では無責任で、ある意味では自由。
自分はこういう自由度の高い作品が好きです。押し付けられるのは好きではないもので。読者の自由意思に任される感じが好きです。
映画のDVDはなかなか入手困難なようなので、とりあえずは入手しやすい小説がおすすめです。(文字は大きめで、150ページ程度で読めます。)
ふと別世界の異次元に運ばれたい夜更けなんかに読むといいかもしれません。
-----------------------------------------
アントニオ・タブッキ「インド夜想曲」
『夜熟睡しない人間は多かれ少なかれ罪を犯している。彼らはなにをするのか。夜を現存させているのだ。』(モリス・プランショ)
-----------------------------------------
『これは不眠の本であるだけではなく、旅の本である。不眠はこの本を書いた人間に属し、旅行は旅をした人間に属している。』
-----------------------------------------
『盲目の知識は不毛の土壌しか作らない。
狂気の信仰は自分の祭儀の夢を生きるだけで、あたらしい神はただひとつの言葉に過ぎない。
信じてはならない。あるいは求めてはならない。すべては神秘だ。』
-----------------------------------------
=============
<出版社/著者からの内容紹介>
失踪した友人を探してインド各地を旅する主人公。
彼の前に現われる幻想と瞑想に充ちた世界。
インドの深層をなす事物や人物にふれる内面の旅行記とも言うべきこのミステリー仕立ての小説を読みすすむうちに読者はインドの夜の帳の中に誘い込まれてしまう。
イタリア文学の鬼才が描く12の夜の物語。
=============
なんと言っても、須賀敦子さんが翻訳。訳自体もいいんだろうな。
元々は、アラン・コルノー監督の映画版「インド夜想曲」を職場の方に偶然借りたのが最初でした。
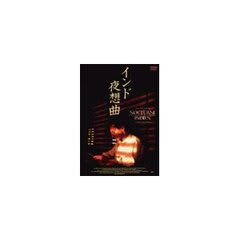
かなり面白くて、思わず2回見てしまった。
原作の小説も読んでみたくなって、読んだら合わせて二度美味しい感じだった。
原作を超える映画を作るのは難しいですけど、これはもしかしたら映画の方がいいんじゃないかと思うほど。
映画の映像表現が詩的で幻想的で、常に予感に満ちた映像表現でよかった。
あんまり解説すると面白くないんだけど,自我egoと自己selfとか、自分の中にある「影Shadow」、人間の「たましい」の話のように思った。
ユング的ですね。ちなみにヘッセも名前だけすこし出てきます。
シャミッソーの「影をなくした男」岩波文庫 (1985/3/18) に出てくるシュレミールの物語のようでもある。
言葉づかいも映像もイメージに満ちててすごくよかった。自分の中にもイメージが立ちあがり、イマジネーションがかきたてられた。
ガルシア・マルケスとか村上春樹さんに近い世界観。
自分は、やはり幻想文学というか、magic realismとか言われるような小説が好きなんだろうな。
小説世界があまりに「現実」世界に忠実だと、その世界観に入り込めない自分がいます。
自分としては、この現実世界を、自分なりに一生懸命生きているつもりです。
この懸命に生きている現実世界を、あえて安いレプリカとして複製するのは、作家の脳に取り込んだ「箱庭」だけを「現実だ」と押し付けられたような気がする。
あえてそんな風に現実のレプリカとしてリプレイする必要があるのかな、と思う。
心が動かない小説世界(→これは自分の問題なのでどうしようもない)には、そういう模造品のくすんだ香りがします。
脳内での幻(マーヤ)として「偽の現実」を複製するくらいなら、その前にこの生きてる現実世界でやるべきことがたくさんあると思います。
この生きている現実では、利他行為とか思いやりとか優しさとか慈悲とか愛情とか・・・・・行為としてすべきことがたくさんあるように思うのです。この世界はとかく忙しい。
だからこそ、小説世界ではこの現実とは違う「現実」を、生きたい。
それは、この現実を包み込むスケールを持った巨大な空間がいい。できれば、この現実の時間や空間の尺度が意味をなさないほどの場所が理想です。そんな世界にこそ入り込みたいと、切実に思うのです。それは絵画でも同じ。
それは、この生きた現実をさらに豊かで膨らんで感じさせてくれる触媒のようなもの。
それは、この現実に複雑で濃い陰影を織りなして倍音を聞かせてくれるよう絵画的で音楽的なもの。
それは、見えない世界を見せてくれる神秘的なもの。
そんな小説世界をこそ読みたいものです。(あくまでも個人的な趣味の問題ではあります。)
だからこそ、自分が求めるものと作家が提示するものとが、鍵と鍵穴のように符合するととても心地よい気持ちになるものです。
そういう意味で、このアントニオ・タブッキも、ガルシア・マルケスも、ドストエフスキーも、ヘッセも、村上春樹さんも・・・すぐれた小説家からは、この現実世界をスッポリ包み込んでしまうような多層で多重な世界観を感じます。
・・・・・・・・・
インパクトが強かったシーンがある。
映画の方がより印象的だった。
ジャイナ教の預言者という女性が出てくる。
ちなみに、ジャイナ教とは、釈迦(シッダールタ)と同時代のマハーヴィーラ(ヴァルダマーナ)が開祖のインド特有の宗教。あらゆるものに生命を見いだして、動物、植物はもちろん、地・水・火・風・大気にまで霊魂(ジーヴァ)の存在を認める。だから、不殺生(アヒンサー)が徹底されていて、あらゆる行動において生命を殺めていないかどうか、歩くのにも呼吸するのにも細心の注意を払う。だから、ジャイナ教の信者の方々はインドに行くとすぐにわかる。ヒンズー教徒とは全然違う雰囲気をまとっている。 学生時代にインドを旅したときにも、ジャイナ教の方々の、宗教的な生き様は特に印象深かったのを覚えている。まさにインドの深さだと思った。 ジャイナ教は、断定的な判断を避けて、つねに相対的に考察することも教義の中心になっている。こういう風に争わず対立を避ける宗教こそ、いま学ぶべきことが多い宗教のように思える。
ところで、そういうインドの神秘を体現するジャイナ教。
そのジャイナ教の流浪の預言者は、姿形も異形の相をしている。(小説では兄の設定だった。映画ではインパクト強かった。)
その預言者は、未来も過去も全てが見えると言う。
その預言者に5ルピーを払い主人公が尋ねる。
「自分が探している友人はどこにいるんだ?」
すると、その預言者は答える。
「あなたはここにはいない。」
「自分が聞いているのは友人のことだ。僕はここにこうしているんじゃないか。」
預言者は答える。
「あなたはここにはいない。あなたのアートマンはここにはいない。」
「それじゃ、アートマンってなんだ?」
預言者の姉を連れた少年はにっこり微笑んで答える。
「The soul. 個人のたましいのことです。」
・・・・・・・・・・
「アートマン」という概念自体も、インドの神秘性を体現していると思う。
アートマンは、「最も内側 (Inner most)」が語源の言葉で、人間の最も深い内側にある根源のこと。真我とも言われる。まさに「Soul(魂)」とも言える。
アートマンは、<知るものと知られるもの>の二元性を越えているので認識の対象にはならないとされています。
ちなみに、そのアートマン(The soul:たましい)は、宇宙の根源原理のブラフマンと同じとされて、そのことを「梵我一如」と表現します。
インド哲学は深いですね。歴史の重みを感じます。
この辺りのインドの世界観を漫画で体感したい方は、諸星大二郎先生の「孔子暗黒伝」(→元々は1977年の作品!) なんかを強くお勧めします。ちなみに、この本は「暗黒神話」(→1976年の諸星大二郎先生のデビュー作!)とつながっているので、同時に読まないといけません。タイトル名はおどろおどろしいですが、そんなことよりもとにかくすごすぎる作品です。
本題に戻ります。
アントニオ・タブッキ「インド夜想曲」の中では、この「アートマン」のやりとりが、一番印象的なシーンだった。
次は、シュタイナーで有名な神智学協会の人との対話とか。無宗教のインド人医師との対話とか。
他にも色んなシーンが断章的に出てきます。イメージを重ねる感じで物語は進む。
そのイメージをどう組み立てるかは、見る側に委ねられていると思う。
ある意味では無責任で、ある意味では自由。
自分はこういう自由度の高い作品が好きです。押し付けられるのは好きではないもので。読者の自由意思に任される感じが好きです。
映画のDVDはなかなか入手困難なようなので、とりあえずは入手しやすい小説がおすすめです。(文字は大きめで、150ページ程度で読めます。)
ふと別世界の異次元に運ばれたい夜更けなんかに読むといいかもしれません。
-----------------------------------------
アントニオ・タブッキ「インド夜想曲」
『夜熟睡しない人間は多かれ少なかれ罪を犯している。彼らはなにをするのか。夜を現存させているのだ。』(モリス・プランショ)
-----------------------------------------
『これは不眠の本であるだけではなく、旅の本である。不眠はこの本を書いた人間に属し、旅行は旅をした人間に属している。』
-----------------------------------------
『盲目の知識は不毛の土壌しか作らない。
狂気の信仰は自分の祭儀の夢を生きるだけで、あたらしい神はただひとつの言葉に過ぎない。
信じてはならない。あるいは求めてはならない。すべては神秘だ。』
-----------------------------------------









