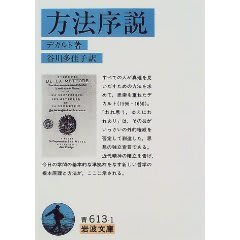
デカルトの「方法序説」(岩波文庫 訳:谷川多佳子)を輪読したのでその感想を書きたい。
タイトルは有名すぎるほど有名だけど、なかなか読む機会がなかった。
なんだかんだの縁で読んでみると、デカルトがどういう人なのかは雰囲気だけでも伝わってきた。
■「方法的懐疑」
デカルトは「方法的懐疑」というのを言っている。
高校時代に倫理の授業で習って、それ以降好きな言葉でもある。
「方法的懐疑」が極端に行くと、全てを疑い、全てが信じられなくなる。
全てのものが嘘で虚構で張りぼてで・・・ってなり出すと、寄る辺が何もなくなり、空虚の世界に引き込まれて現実の世界には戻れなくなってしまう。
デカルトはそういう安っぽい虚無主義・ニヒリズムに陥ることを薦めているわけではない。
思考の方法の初めとして(方法序説!)、まず物事を一度疑ってかかり、それでも自分が信じれるもの、そういうものを追及せよ。と言っていると思う。
正式には、『理性を正しく導き、学問において真理を探究するための 方法序説』とタイトルに書いてあるし。
その疑うプロセスというのは、ものごとの本質に迫る営みでもあるけど、同時に自分の過去全てを含めた全体としての自分と向き合うプロセスのことだし、表面的なものではなくて自分の奥深く奥深くに迫っていくプロセスのことでもあると思う。
自分にとっての『真・善・美』は何かということ?
まあ簡単にいえば、「懐疑原理主義者」ではなくて、「常識を疑う」「当たり前のものを疑う」というようなことが出発点になるだろうし、それはとても納得できる。
「物事を一度ひっくり返してみて、また元に戻す」って言う思考プロセスを最近試しているんですけど、それとすごく似ていて自分の最近の感覚に近い。
一度物事をまるっきりひっくり返してみると、今まで見ていた風景は全く違って見える。そうして相対化してみることで、今まで自分がとらわれていたものの本質が何だったのかをふと立ち止まって考えてみる。
でも、そのままだとアッチの世界に行ったままなんで、また裏に返して元に戻してみると、元々の世界が何故だか少し違って見え始める。
こういう思考方法は一見当たり前のように見えても、普段の時間に追われる生活では容易に忘れやすいし、常識とか言葉とか慣例とか場の空気とかに流されて、疑いすらしないものも実は多い。
そこをまず「方法的懐疑」で疑ってみることは、すごく意義あることだと思える。もちろん、単なる虚無主義とかニヒリズムに陥らないようにバランスをとらないといけなくて、その塩梅が大事なんですけどね。
裏に返して元に戻る。疑ってみて考え直してみる。
それは一度世界を自分でほどいてみて、再度自分で編みなおしてみる作業に似ていて、その作業はいづれ誰もが必要ば作業なんだと思うんですよね。
それは単に時期が遅いか早いかの違いであって、一般的には衝撃的な挫折や悲しみが訪れると予期せずとも必然的に世界がほつれるんだと思います。
それはいいとか悪いとかじゃなくて、そういうものが人生に組み込まれているんでしょうね。
それにしても、「方法序説」が出た当時の1637年において、この「方法的懐疑」は相当に衝撃だったんぢゃなかろうか。
神とかキリスト教とか階級制度とか貧富の差とか・・・・、
絶対的なものの名の元に、殺人、戦争、魔女狩り、粛清、差別・・・・いろんなものが正当化される方法として利用された時代があって、そんな不合理なシステムも含め、全てを疑ってかかって自分の頭で考えるっていうのは、明らかに時代を変える思想の一つになっただろうし、それは血となり肉となり、意識上に登らないようなものとして当時の人々にうっすらと影響を与えていったのかもしれない(当時の人がデカルトの本自体を読めなくても、読んだ人が感じた熱気のようなものはきっと伝わっていくものだっただろうし・・)。
■「からだ」
岩波文庫ではP47に「からだ」への記述がある。
************************
わたしは一つの実体であり、その本質ないし本性は考えるということだけにあって、存在するためにどんな場所も要せず、いかなる物質的なものにも依存しない、と。
したがって、このわたし、すなわち、わたしをいま存在するものにしている魂は、身体(物体)から全く区別され、しかも身体(物体)より認識しやすく、たとえ身体(物体)が無かったとしても、完全に今あるままのものであることに変わりはない、と。
************************
ここは自分には違和感があった。
方法的懐疑で全てを疑った先に、考えている自分だけは疑えない。
そこで立ち現われてくるのが「我思う、ゆえに我あり」(原文のフランス語でJe pense, donc je suis. ラテン語でcogito, ergo sum コーギトー・エルゴー・スム、cogito - 私は思う、ergo - それ故に、sum - 私は在る)というもの。
そこから意識や理性や精神を第一義に考えて、デカルトから「心身二元論」は始まったとはよく聞きます。
この辺りから、「精神と物質」「霊と肉」「こころとからだ」「意識と無意識」・・・のように二つに分割して、別々に論じて考えていこうというきっかけにはなったのかもしれない。
ある物事を理解するために、まず要素に分割して、それぞれを考えるとわかりやすいよーってこと。
デカルト自体が、P28の4つの規則の中でも、
『ものごとを小部分に分割して行って(第2の規則)、単純で認識しやすいものから階段を上るように複雑なものに昇っていく(第3の規則)』という形で触れてますしね。
でも、一度分離させてそれぞれを考えたら、もう一回元に戻して統合しないといけないんじゃないかと思う。
人間が「精神と物質」「霊と肉」「こころとからだ」「意識と無意識」が渾然と一体化している存在であり、そのアワイの領域にいると思っているから、ふとそう感じてしまう。
こう言う風に部分に分けて全体を把握するっていう手法は、サイエンスの思考にぴったり合うわけですが、今当たり前にやっている思考形式が、デカルトが物事を理性で付きつめて、疑った先に自分で組み立てた思考方法に由来してるっていうのはすごいことだと思います。1637年の当時から370年も強い影響力を持っているわけだから。
確かに、医者として働いていると、物事を分割して簡略化・モデル化して考えるのは科学の基本的な思考方法で当たり前のように毎日やっている。
もう当たり前のことすぎて、いまさら常識として疑わなくなっている。
だから、今度はデカルトへのお返しとしても、デカルト的思考方法そのものを、方法的懐疑でもう一度疑って考え直して、自分の頭で統合しなおさないといけない時期なんでしょうね。
それが、学際的であることの本質なんだと思う。
既存の学問分野を横断して組み替えしていくという意味で。
■心臓
心臓を生業にしている自分としては、第5部で心臓論が延々と出てくるのには驚いた!
そういう意味では、デカルトも「からだ」とか「身体」の問題にも最終的には行きたかったのかなぁとか思いましたね。
ウイリアム・ハーヴイという人が、心臓の筋肉が膨張収縮することで、ポンプのように全身に血液を送り出して、血液は循環しているという考えた。
(→1628年:『動物における血液と心臓の運動について(Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus)』)
これは今の医学では当然となっている考えだけれど、当時は古代ギリシャのガレノスの説(「通気系」が空気由来の動脈血を全身に運んで、「栄養配分系」が栄養を運ぶ2系統になっていて、肝臓で発生した血液は人体各部まで移動してそこで消費されると考えられていた。グルグル回る循環の概念は全くなかった)が広く信じられていた。
そんなおかげで、当時のデカルトも心臓の働きを違うように考えていたらしい。
デカルトは、心室にある熱で心臓が膨張収縮する、「熱機関説」を信じていた。心臓を時計の運動の比喩で説明していたりもして、人体を機械と同じようなものと考えていたみたい。
この辺りが、「からだ」とか「身体」に関する、デカルトと自分の考えとのズレになるのかなぁとも思っています。
人体は機械であるという考えは、半分正しいけど半分間違っていると思うし。
まあそれにしても、作者脚注のP124のところにも、
『健康の維持こそ、わたしの研究の主な目的でした』(ニューカッスル侯宛書書簡1645年10月)
ってデカルトが自分で言っているくらいだし、理性で徹底的に疑ったり考えたりできるのは、自分が健康であったり、元気であったり、自分が生きているってこと自体が大前提になるわけで、デカルトがもう少し長生きしていれば人体や身体やからだに関しても、方法的懐疑でさらに深く突き詰めて考えていくつもりだったのかもしれませんけどね。
■
『方法序説』は読んでみると意外に量も少ないのです。(脚注を抜くと全6部で103ページしかない)
デカルトの言説で矛盾しているところや飛躍しているところも多いなぁとは思いましたけど、なんとなくデカルトの知的誠実さのようなものはひしひしと感じました。
ちなみに、『方法序説』は1637年の作品ですが、日本では江戸時代の徳川幕府の時代であって、島原の乱が勃発している年なんですよね。日本のアニミズムな神仏習合の国において、キリスト教問題が社会問題になってたというのも、同時代の出来事としては面白い!
タイトルは有名すぎるほど有名だけど、なかなか読む機会がなかった。
なんだかんだの縁で読んでみると、デカルトがどういう人なのかは雰囲気だけでも伝わってきた。
■「方法的懐疑」
デカルトは「方法的懐疑」というのを言っている。
高校時代に倫理の授業で習って、それ以降好きな言葉でもある。
「方法的懐疑」が極端に行くと、全てを疑い、全てが信じられなくなる。
全てのものが嘘で虚構で張りぼてで・・・ってなり出すと、寄る辺が何もなくなり、空虚の世界に引き込まれて現実の世界には戻れなくなってしまう。
デカルトはそういう安っぽい虚無主義・ニヒリズムに陥ることを薦めているわけではない。
思考の方法の初めとして(方法序説!)、まず物事を一度疑ってかかり、それでも自分が信じれるもの、そういうものを追及せよ。と言っていると思う。
正式には、『理性を正しく導き、学問において真理を探究するための 方法序説』とタイトルに書いてあるし。
その疑うプロセスというのは、ものごとの本質に迫る営みでもあるけど、同時に自分の過去全てを含めた全体としての自分と向き合うプロセスのことだし、表面的なものではなくて自分の奥深く奥深くに迫っていくプロセスのことでもあると思う。
自分にとっての『真・善・美』は何かということ?
まあ簡単にいえば、「懐疑原理主義者」ではなくて、「常識を疑う」「当たり前のものを疑う」というようなことが出発点になるだろうし、それはとても納得できる。
「物事を一度ひっくり返してみて、また元に戻す」って言う思考プロセスを最近試しているんですけど、それとすごく似ていて自分の最近の感覚に近い。
一度物事をまるっきりひっくり返してみると、今まで見ていた風景は全く違って見える。そうして相対化してみることで、今まで自分がとらわれていたものの本質が何だったのかをふと立ち止まって考えてみる。
でも、そのままだとアッチの世界に行ったままなんで、また裏に返して元に戻してみると、元々の世界が何故だか少し違って見え始める。
こういう思考方法は一見当たり前のように見えても、普段の時間に追われる生活では容易に忘れやすいし、常識とか言葉とか慣例とか場の空気とかに流されて、疑いすらしないものも実は多い。
そこをまず「方法的懐疑」で疑ってみることは、すごく意義あることだと思える。もちろん、単なる虚無主義とかニヒリズムに陥らないようにバランスをとらないといけなくて、その塩梅が大事なんですけどね。
裏に返して元に戻る。疑ってみて考え直してみる。
それは一度世界を自分でほどいてみて、再度自分で編みなおしてみる作業に似ていて、その作業はいづれ誰もが必要ば作業なんだと思うんですよね。
それは単に時期が遅いか早いかの違いであって、一般的には衝撃的な挫折や悲しみが訪れると予期せずとも必然的に世界がほつれるんだと思います。
それはいいとか悪いとかじゃなくて、そういうものが人生に組み込まれているんでしょうね。
それにしても、「方法序説」が出た当時の1637年において、この「方法的懐疑」は相当に衝撃だったんぢゃなかろうか。
神とかキリスト教とか階級制度とか貧富の差とか・・・・、
絶対的なものの名の元に、殺人、戦争、魔女狩り、粛清、差別・・・・いろんなものが正当化される方法として利用された時代があって、そんな不合理なシステムも含め、全てを疑ってかかって自分の頭で考えるっていうのは、明らかに時代を変える思想の一つになっただろうし、それは血となり肉となり、意識上に登らないようなものとして当時の人々にうっすらと影響を与えていったのかもしれない(当時の人がデカルトの本自体を読めなくても、読んだ人が感じた熱気のようなものはきっと伝わっていくものだっただろうし・・)。
■「からだ」
岩波文庫ではP47に「からだ」への記述がある。
************************
わたしは一つの実体であり、その本質ないし本性は考えるということだけにあって、存在するためにどんな場所も要せず、いかなる物質的なものにも依存しない、と。
したがって、このわたし、すなわち、わたしをいま存在するものにしている魂は、身体(物体)から全く区別され、しかも身体(物体)より認識しやすく、たとえ身体(物体)が無かったとしても、完全に今あるままのものであることに変わりはない、と。
************************
ここは自分には違和感があった。
方法的懐疑で全てを疑った先に、考えている自分だけは疑えない。
そこで立ち現われてくるのが「我思う、ゆえに我あり」(原文のフランス語でJe pense, donc je suis. ラテン語でcogito, ergo sum コーギトー・エルゴー・スム、cogito - 私は思う、ergo - それ故に、sum - 私は在る)というもの。
そこから意識や理性や精神を第一義に考えて、デカルトから「心身二元論」は始まったとはよく聞きます。
この辺りから、「精神と物質」「霊と肉」「こころとからだ」「意識と無意識」・・・のように二つに分割して、別々に論じて考えていこうというきっかけにはなったのかもしれない。
ある物事を理解するために、まず要素に分割して、それぞれを考えるとわかりやすいよーってこと。
デカルト自体が、P28の4つの規則の中でも、
『ものごとを小部分に分割して行って(第2の規則)、単純で認識しやすいものから階段を上るように複雑なものに昇っていく(第3の規則)』という形で触れてますしね。
でも、一度分離させてそれぞれを考えたら、もう一回元に戻して統合しないといけないんじゃないかと思う。
人間が「精神と物質」「霊と肉」「こころとからだ」「意識と無意識」が渾然と一体化している存在であり、そのアワイの領域にいると思っているから、ふとそう感じてしまう。
こう言う風に部分に分けて全体を把握するっていう手法は、サイエンスの思考にぴったり合うわけですが、今当たり前にやっている思考形式が、デカルトが物事を理性で付きつめて、疑った先に自分で組み立てた思考方法に由来してるっていうのはすごいことだと思います。1637年の当時から370年も強い影響力を持っているわけだから。
確かに、医者として働いていると、物事を分割して簡略化・モデル化して考えるのは科学の基本的な思考方法で当たり前のように毎日やっている。
もう当たり前のことすぎて、いまさら常識として疑わなくなっている。
だから、今度はデカルトへのお返しとしても、デカルト的思考方法そのものを、方法的懐疑でもう一度疑って考え直して、自分の頭で統合しなおさないといけない時期なんでしょうね。
それが、学際的であることの本質なんだと思う。
既存の学問分野を横断して組み替えしていくという意味で。
■心臓
心臓を生業にしている自分としては、第5部で心臓論が延々と出てくるのには驚いた!
そういう意味では、デカルトも「からだ」とか「身体」の問題にも最終的には行きたかったのかなぁとか思いましたね。
ウイリアム・ハーヴイという人が、心臓の筋肉が膨張収縮することで、ポンプのように全身に血液を送り出して、血液は循環しているという考えた。
(→1628年:『動物における血液と心臓の運動について(Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus)』)
これは今の医学では当然となっている考えだけれど、当時は古代ギリシャのガレノスの説(「通気系」が空気由来の動脈血を全身に運んで、「栄養配分系」が栄養を運ぶ2系統になっていて、肝臓で発生した血液は人体各部まで移動してそこで消費されると考えられていた。グルグル回る循環の概念は全くなかった)が広く信じられていた。
そんなおかげで、当時のデカルトも心臓の働きを違うように考えていたらしい。
デカルトは、心室にある熱で心臓が膨張収縮する、「熱機関説」を信じていた。心臓を時計の運動の比喩で説明していたりもして、人体を機械と同じようなものと考えていたみたい。
この辺りが、「からだ」とか「身体」に関する、デカルトと自分の考えとのズレになるのかなぁとも思っています。
人体は機械であるという考えは、半分正しいけど半分間違っていると思うし。
まあそれにしても、作者脚注のP124のところにも、
『健康の維持こそ、わたしの研究の主な目的でした』(ニューカッスル侯宛書書簡1645年10月)
ってデカルトが自分で言っているくらいだし、理性で徹底的に疑ったり考えたりできるのは、自分が健康であったり、元気であったり、自分が生きているってこと自体が大前提になるわけで、デカルトがもう少し長生きしていれば人体や身体やからだに関しても、方法的懐疑でさらに深く突き詰めて考えていくつもりだったのかもしれませんけどね。
■
『方法序説』は読んでみると意外に量も少ないのです。(脚注を抜くと全6部で103ページしかない)
デカルトの言説で矛盾しているところや飛躍しているところも多いなぁとは思いましたけど、なんとなくデカルトの知的誠実さのようなものはひしひしと感じました。
ちなみに、『方法序説』は1637年の作品ですが、日本では江戸時代の徳川幕府の時代であって、島原の乱が勃発している年なんですよね。日本のアニミズムな神仏習合の国において、キリスト教問題が社会問題になってたというのも、同時代の出来事としては面白い!










それを目指す理性
最終的には精神だからね、
と言うことで
デカルト自身の気が楽になったりする面も
あったのかなあ
原理とは、と考え出す理性には、より純粋な科学的好奇心を感じるけれど
本質とは、と求道する理性には、混沌に身構える切迫感を感じる
確かに、とりわけ後者の理性は
堅牢な身体でなきゃもたなさそうだ
いろんなデカルト論とか読んでると、実際デカルトは剣術とかも強かったそうだけど、病弱だったようなのですよね。朝寝の習慣があったりして、最後は女王の家庭教師か何かして、朝早く寒いとこに出て行ってカテキョーしないといけない羽目になり、それで体調崩して死んじゃったみたいなこと書いてあったし。
「からだは正直」とはよく言ったもんで、自分の身体の問題はすぐ表に出ますよね。おなかがいたいとか頭がいたいとか気分がだるいとか。
そんな身体の声に素直に耳を貸さないと、理性や精神一本やりでいくと、かならず破綻をきたすような気がします。
さすがに、ずっと残る名言を含んだ書だけあって迫力を感じました。それに、要点が明快に記されているのが実にいいですね。第2部の四つの規則が、近代科学を発達させる契機になったのかと思うと感慨深くもなります。
それから二元論は、唯心論と唯物論という両極端に陥らない素晴らしい思想だと思います。
しかし、批判すべき点もあります。第4部にあるようにデカルトは一神教の絶対的な神を前提としているし、余りにも楽観的な進歩主義も見受けられます。
そのように簡単に短所が見つかりますが、『方法序説』の長所の面は現代では当たり前の事になっているため、不当に批判されやすいのかもしれません。時代状況を考えるとデカルトは大きな貢献をしたのだと思います。
そして現代では、科学の力が圧倒的に強くなったため唯物論が一般的になっているが、もちろんそれは思想を「統合」することはできないという状況ではないでしょうか。
では人間はこのまま専門化・細分化された科学を突き進めていくとしたらつまらない事だと思います。しかし、現代科学はコンピュータとインターネットにより情報革命を起こしました。そして物質ではなく情報が重要になっています。
人類の知識を結び付けているネット上で、それらの知識を「統合」し全ての基礎となるような、新しい情報体系が生まれるかもしれない。満月の夜にそんな妄想をしてしまいました。その時こそ二元論が復活したと言えるのでしょう。
書き込みありがとうございます。
『方法序説』の記述は今よんでも斬新ですよね。
自分で書いていることを一つ一つ反省しながら、そして噛み締めながら書いているような気がします。
確かに、デカルトは一神教の絶対的な神を前提としていて、そのこと自体を「方法的懐疑」で徹底的に疑っていないところに、少し違和感を感じました。
ただ、神を本格的に疑ってかかることは、当時の状況では火あぶりや死刑になったり、もし自分が死ぬ直後に発刊しても自分の親戚が一族皆殺しにされる危険性があったり、そんな危うい状況下だったから、あえて言語化しないようにしたって可能性もありますよねー。
そんな状況で、ああいう「考え方の枠組」を提供したっていうのは、直接的ではなく間接的にものすごい影響与えていますよね。
人間の考え方次第で世界が反転しうるものだと思いますが、世界そのものを反轉させるより、人の考え方を反転させていくことで、結果として世界を変えたという意味で、すごい人なんだと思います。
デカルトがいうとこの『方法的懐疑』で疑わないと、もう常識になって疑いすらしない概念なんていっぱいあるのだと思いますし。
科学の世界で生きている自分としては、常に科学に対して半信半疑であろうと思っています。科学原理主義者になってしまうと、全てが物質や粒子など、部分的な集合で全体が説明されると思ってしまう。その反動で、過剰なオカルトや神秘思想にいってしまう対極も生まれてしまうんだと思いますしね。
僕らが使用している人体という、自然そのものが、すでに部分だけでは全体を説明できない代表的なものであって、理性だけで説明できないのが人間だと思います。
理性だけで考えると、殺人も暴力も全ては意味がないことですが、現実は巷にありふれているものですし。
養老先生が言うように、僕は「こころ」は脳の機能に過ぎないと思っています。物質で説明できるものではないと思っています。
例えば、心臓はモノとしてある。血管もモノとしてある。でも、「循環」はモノとしてない。物質に還元できない。
なぜなら、それは心臓と血管いうモノが作り出す「機能」を「ことば」で表現したのに過ぎないものであって、 それは物質やモノのレベルに還元できるわけはないと思うのですよね。これが、この世の全てはモノや物質からできていると説明しがちな唯物論の大きな限界のひとつだと思います。「ことば」で説明した時点で、何かモノがあるように錯覚してしまうんですよね。
愛とか希望とか平和とか、全てことばであって、モノではないわけですからね。脳がことばを介して作り出す機能に過ぎないんだと思います。
ことばによって、精神と物質という風に二元論で二つのパーツに分けて理解する。精神だけでもないし(唯心論)、物質だけ(唯物論)でもない。
そのアワイの領域に生きているんだと思います。
竹内先生が好きなことばで言えば、「みずから」と「おのずから」 のアワイなんでしょう。
でも、僕らの脳みそは、その二つが同居している状態を言語化するのが不可能なので、便宜的に精神と物質という二つのことばに分解して表現しないといけない。それが脳がもつ限界だし、僕らはそんな有限な脳が、全ての思考の源になっていて、それ自体を疑いすらしないということに、もっと自覚的でないといけないと思います。
自分の脳は、自分の脳の能力以上のことはできなくて、そんな有限性の上で、人間という全体性は成立しているんだと思います。
人間の有限性の分かりやすい例は、身体であって、そこが科学の現状を突破する鍵だと自分は睨んでいます。