日本近代文学の森へ (144) 志賀直哉『暗夜行路』 31 「答える事のいやな問い」 「前篇第一 七」 その5
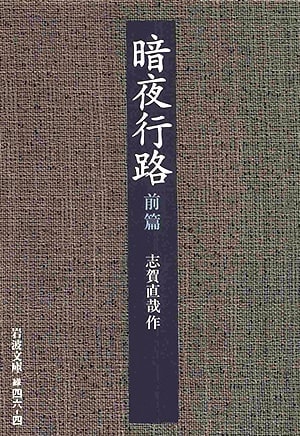
2020.2.11
「老妓」と緒方の会話が続く。
緒方は話の運びからは全然、突然に、
「今、蕗子(ふきこ)、いるかい?」といった。
老妓はふッといいつまった。ちょっと表情が変った。緒方の方も何気なく見せているが一種緊張した顔つきをしていた。謙作はこの間話に出た芸者の事だろうと思った。
「旅行してます」老妓は漸く答えた。その調子は傍で聞いても如何にも嘘らしかった。
それでも緒方は、
「何処へ?」と訊いた。
女はまた答えにつまった。
「塩原じゃあないかと思うの」そして老妓は不自然に話を外らし、塩原や日光辺の紅葉がまだ早いとか晩いとかいう事に持って行った。緒方はそれきり、忘れたように蕗子という女の事はいわなかったが、謙作はその老妓が一卜かどの苦労人らしい高慢な顔をしながら、緒方の軽く訊く言葉に一々ドギマギした様子を何となく滑稽に感じた。
ここで出て来る蕗子という芸者は、緒方のお気に入りだが、別の金持ちの男とも昵懇になっている。その蕗子のことを持ち出されて、「一卜かどの苦労人」らしい老妓が、うまく応対できなくてドギマギする様子を、少ない言葉で実に見事に描きだしている。
「老妓はふッといいつまった。」と、まず老妓の「沈黙」のさまを描く。書かれてはいないが、当然、その老妓の口元が目に浮かぶ。次に「ちょっと表情が変った。」とその表情をさっと描き出す。どう変わったのかは具体的には書かない。その短い文が二つ続いて後に、「緒方の方も何気なく見せているが一種緊張した顔つきをしていた。」と、今度は緒方の表情を描くことで、二人の間の緊張関係を際立たせる。そして、最後に謙作の推測を書き込むことで、緊張したシーンがカチッと「ズームアウト」する。見事なものだ。
「一卜かどの苦労人」らしい老妓なら、こんな場面には何度も遭遇しているだろうに、それでもドギマギしてしまう。その滑稽さは、人間そのものの滑稽さでもある。
そうこうしているうちに、「千代子」という芸者がきた。
食事の済む頃に漸く千代子という芸者が来た。前からいる老妓とは反対に大きな立派な女だった。ちょっと小稲の型で総てがずっと豊かで美しかった。そして何よりもその眼ざしに人の心を不思議に静かにさす美しさと力がこもっていた。謙作は特にその眼に惹きつけられた。
この頃の謙作は、とにかく目の前に現れる女に次から次へと惹きつけられる。手当たり次第といったところだ。そういう自分への反省がこう語られる。
暫くして二人はその家を出た。品川の東海寺へ行く緒方とは彼は赤坂見附の下で別れた。それから彼は見附を上って、的(あて)もなく日比谷の方ヘ一人歩いて行ったが、その時、彼の胸を往来するものは、今見た美しい千代子の事ではなくて、かえって今までそれほど思わなかった清賓亭のお加代の事が切(しき)りに想われた。「ちょっとでもいいから君を呼んでくれというので」といった緒方の言葉を彼は幾度となく心に繰返した。
登喜子といい、電車で見た若い細君といい、今日の千代子といい、彼は近頃ほとんど会う女ごとに惹きつけられている。そして今は中でも、そんな事をいったというお加代に惹きつけられている。
「全体、自分は何を要求しているのだろう?」
こう思わず思って、彼ははっとした。これは自分でも答える事のいやな、しかし答える事の出来る問いだったからである。
「答える事のいやな、しかし答える事の出来る問い」なんてずいぶんと回りくどい言い方だけど、まあ、とにかく女性との肉体関係を「要求」しているわけだ。しかしその本能的な「要求」を、謙作は、どうしても認めたくないのだ。
ところで、ここに出て来る「東海寺」というのは、北品川に現存している寺で、徳川家光が創建し、沢庵が開山に迎えられたという由緒ある禅寺で、その旧境内にある「東海寺大山墓地」には、賀茂真淵やら、板垣退助やら、島倉千代子やらの墓があるという。こんど行ってみよう。
















