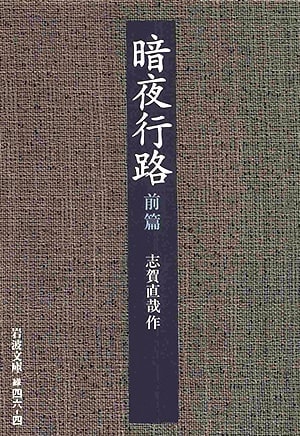日本近代文学の森へ (143) 志賀直哉『暗夜行路』 30 「老妓」 「前篇第一 七」 その4
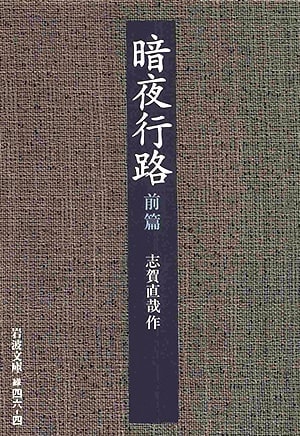
2020.2.2
「西緑」で遊んでいるうちに、自分が「下らない人間」に成り下がったように感じた謙作だったが、その翌日、夕方にやってきた緒方がこんなことを言った。
「それはそうと一昨日はとうとう帰らなかったのかい」と緒方がいった。
「どうして?」
「お加代という人がちょっとでもいいから君を呼んでくれというので、十時過ぎに俥を迎えに寄越したが、聴かないかい?」
謙作は顔を赤くした。お加代が如何(どう)いう気持でそんな事をいったか? それとも誰も時々そういう調子を見せるのか? そういう事が彼にはさっぱり見当がつかなかった。
彼は初めて会った時、既にお加代には多少惹きつけられた。ただその何となく荒っぽい粗雑な感じは、一方では好き、他方では厭に思っていた。それは深入りした場合きっと不愉快なものになるという予感からも来ていた。第一今の自分の手には余る女という感じから、興味は持てたが、それ以上には何とも考えていなかった。その上に、お加代にとってのその日の自身を思うと、プラスでもマイナスでもないただ路傍の人に過ぎなかったと思い込んでいただけに今緒方からそれを聴くと変に甘い気持が胸を往来し始めた。
しかし彼はそれを出来るだけ隠そうとした。
彼はしかし一方でちょっと不愉快を感じた。何故お栄でも女中でもそれを自分にいわないか。毎日単調な日暮しをしているお栄にとって、俥を持たして迎えに寄越すという事でも、或る一事件になり得ない事ではない。勿論これはいい忘れをしているのではなぃ。故意に黙っているのだ。女中にまで口留してあるのだと思った。
「一昨日」は、「西緑」で謙作は緒方と遊んでいたのだが、緒方はトランプに嫌気がさして先に帰ってしまった。謙作は帰らずにそこに残り翌日に家に帰ったのだが、夕方になるとまた「西緑」へ出かけ、そこで「下らない人間」になったもんだと思ったわけで、その夜帰宅した。その翌日、緒方がやってきて、こんなことを言ったのだ。どうも時間の進行がゆるやかである。
緒方は、お加代が謙作に気があるようなことを言ったわけだが、謙作もお加代のことが気になっていたので、その話は満更でもなかったわけだ。
ただ、お加代は「手に余る」女だと謙作は感じていた。この女とかかわるとヤバいなあと思ったわけだが、それはかえって謙作の気持ちをそそることでもあり、しかし、そんな「ヤバい女」が朴念仁の謙作に好意を持つとも思えないから、「お加代にとってのその日の自身を思うと、プラスでもマイナスでもないただ路傍の人に過ぎなかったと思い込んでいた」のだ。この「思い込んでいた」というのは、「思い込もうとしていた」というほうが正確かもしれない。
そのお加代が「ちょっとでもいいから」謙作を呼んでくれと緒方に言ったということを聞いた謙作は、そりゃ、悪い気はしない。つまり「変に甘い気持が胸を往来し始めた」のである。けれどもその気持ちを謙作は「出来るだけ隠そうとした」。なぜだかよく分からないが、そんなことで鼻の下をのばすのは男の沽券に関わるということだろうか。どこまでもウブな謙作である。
ちょっといい気分になった謙作だが、その一方で「不愉快」も感じる。でました! 「不愉快」。お栄はどうしてそれを自分に言わないのか。お栄には、そんな些細なことでも十分に「一事件」で、それは謙作のためにならないと考えて女中にまで口止めして、お加代との仲をさこうとしたのではないか、と謙作は邪推する。被害妄想である。そしてその被害妄想は、お加代に傾いていく自分に一種の罪悪感を感じているからこそだろう。
緒方と謙作は、外へ出て、「山王下の料理屋」へいく。
きちんとした《なり》の女中が床の活花を更(か)えに来た。軒近くいる二人からは遠かったので、女中は床の前に坐って仔細らしくその位置を、眺めては直し、眺めては直ししていた。
「とにかく、例の婆さんを呼んでくれないか」と緒方は女中に声をかけた。「それから千代子かしら……」
女中は古い方の花を廊下へ出してから、また畳へ膝をついて黙って《いいつけ》を待った。
「じゃあ、その二人」と緒方がいうと、女中はお辞儀をして出て行った。
間もなくその婆さんといわれた芸者が入って来た。四十以上の脊せて小柄な少し青い顔をした如何にも酒の強そうな女だった。そしてよくしゃべる女だった。
「料理屋」に行っても、この連中は芸者を呼ぶ。しかも昼間だ。贅沢な話である。
それにしても、「婆さん」と呼ばれた芸者は、「四十以上」とある。「以上」なのだから、50かもしれないし、60かもしれないけど、まあ40代だろう。それが「婆さん」である。
「飯を食ったら直ぐ帰るからネ。千代子の方もちょっと催促してくれ」膳を運ぶ女中に緒方はこういった。
「ねえ。それはそうとお供は何時出来るの?」とその老妓がいった。
緒方はそれに答えずに謙作の方を向いて、
「今度、この婆さんと一緒に吉原へ行く約束をしたよ。この間の話をしたら、大変讃(ほ)められたよ」といった。
「仲の町の芸者衆でお遊びになればもう本物です」老妓はこんな事をいって笑った。
緒方と老妓とは謙作の知らぬ人の噂を二人でしていた。老妓はよくしゃべった。そしてその間々に時々甲高い真鍮を叩くような笑い声を入れた。それが変に人の気持を苛立たせた。
地の文でも「老妓」である。そうか、40過ぎると「老妓」なのか。そういえば岡本かの子の「老妓抄」って小説があるが、この「老妓」って60ぐらいだろうと漠然と思っていたが、もっと若いのかもしれない。調べなくちゃ。(読んでみたが、年齢は分からなかった。でも40代ではなさそうだ。たぶん60以上。)
それにしても、「飯を食ったら直ぐ帰る」のに、なんで芸者を二人も呼ぶのか。呼べばそれなりの金がかかるのに、なんてこと言うのは野暮なんだろうけど。
ところで先日、さる会議の後、まだ30代の気鋭の国文学者二人と飲んだとき、「いやあ、『暗夜行路』は面白いなあ。」と言ったら、「そうかなあ。昔読みましたけど、面白くなかったなあ。」と一蹴されてしまった。「若いときにざっと読んだだけでしょ。それじゃあ面白くないよ。ゆっくり読めば面白いよ。」って言ったけど、まあ、こんなにゆっくり読むなんて、若い人にはできないだろうなあ。たとえできたとしても、「得るもの」があるかどうかおぼつかない。
そもそもあんたには「得るもの」があるのか、って彼らなら聞きたいだろう。その答は、「ある」としかいいようがない。もっとも、それは、これからの人生に「役立つ」ものではない。というか、「得るもの」はこれからの時間の中に「ある」のではなく、ただいまこの時に「ある」。志賀直哉が残した言葉に、いちいち、ああでもないこうでもないと想像を巡らしながら時間を過ごす。その想像の中に、様々な人間達が生まれては消え、消えては生まれる。その想像のうちに、志賀直哉という人間の心のひだがおぼろげながら見える。それだけで、十分に「得ている」のである。