
私は1960年代末の生まれなので、ボビー・ダーリンのことは殆ど知りません。映画中の曲を聴いて「これもそうだったんだ」と思い当たるくらい。なんたって見に行った理由が
ケヴィン・スペイシーが
「スピク」の主題歌を
歌っているのを
予告で見たから、だったりするんですわ。そんな私にも、ケヴィンが、いかに彼、ボビー・ダーリンを愛しているかがわかりました。たんなる伝記映画ではありません。主演・監督・脚本・製作の四役をこなしてまでこの映画を作ったのは、自分は彼がとても好きだということ、彼のスゴさを世界の人に知らしめたい、と思ったからではないでしょうか。このテの感情で作られた作品は、だいたいが内輪受けで終わるのですが、これは違います。ケヴィンの、ある意味ミーハー的な熱がこちらにも伝わり、なんかわからないうちに、自分もボビーが好きになっちゃったかもよーーー、なんて気持ちさせてしまうのです。
内容としては、もう本当に、彼の一生をなぞった話。ボビー自身を主役に彼の自伝映画を撮ろうとするところから話は始まり、少年時代の「彼」を相手に、ボビーが生い立ちを語っていく。リュウマチ熱のせいで心臓を悪くし、それでも母の願いのもと、ショー・ビジネスの世界に入る。自身の出生の秘密がわかるころ、ヴェトナム戦争でアメリカも国としての挫折を味わい、ショーの世界もクラブからドームへと変わっていく。ロック系のポップスというのかな、そんな曲を歌っていた彼も反戦歌を歌い、客に「路線を替えやがって」と野次られ、それでも歌い続け、37歳で死ぬ。そんな話が、彼の歌と、ミュージカル的な踊りの場面で綴られていきます。歌も踊りも吹き替え無し。ボビーを知っている人に言わせると、ケヴィンはボビーにソックリだそうで。
ラスト、「『(本名の)ウォルデン・ロバート・カソット』は死んだが『ボビー・ダーリン』は今でも歌い続けている」と表示されます。これこそがケヴィンがもっとも言いたかったことかも。好きな歌手、ってのは、自分の中では一生、生き続けていくものなのですよね。
私は、ケヴィン・スペイシーという役者は、達者だとは思うけど、公開作品を一応チェックしよう、というほどファンではありません。そんなレベルの私にさえも、彼の、ボビーに対する情熱が届きます。いいだろう、ステキだろう、君もきっと好きになるよ、そんな声が聞こえてきました。この映画は、この声を聞かせるためにあるんでしょうね。好きなことを語っている人って、幸福感に満ちあふれていることがあるでしょう?その幸福な気持ちが、見ている側にも伝染してくるようで、こちらまで幸せな気分になりました。
ケヴィン・スペイシーを始め、出演者や画面が、違和感なく50~60年代ってのもスゴイと思いました。「五線譜のラブレター」は、『スタイリッシュ』に当時を再現、ってカンジなのですが、こちらは、ボビーが生きていた頃に撮られたと言われても不思議じゃないような、そんな「絵」「色合い」。この映画のケヴィンは、往年のジーン・ケリーと並んでも、かなりしっくりきそう。それを意識して作り上げたとしたら、偉いもんだなあ、と思いました。

【補記】
「スピク」 → 「スピークイージー」。「三文オペラ」の宝塚版。

























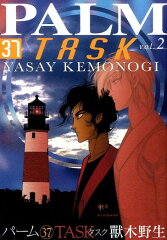



![Wings (ウィングス) 2013年 06月号 特別付録 永久保存版小冊子「プチ・パームブック」[雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61in8ViynvL._SL160_.jpg)


