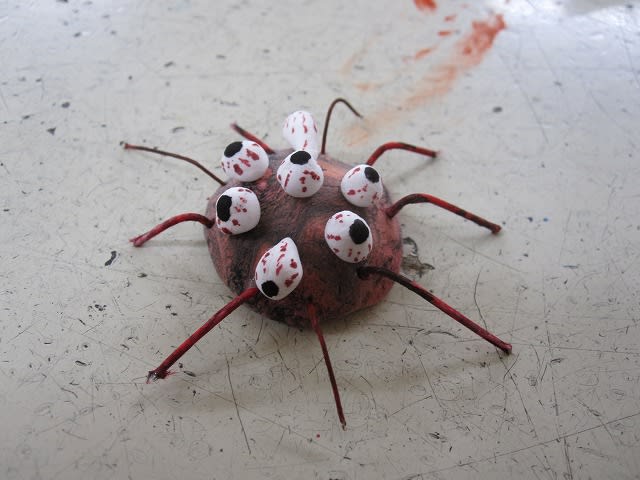小林隆児氏の発達障害の子供の観察では、母親の近くにいると
居心地が悪そうにして離れたがり、遠ざかると寂しそうに母親を伺うと有る。
そのような「甘えたいのに甘えられない」状態で、宙吊りになっていることが
その後の様々な特徴に繋がるとのこと。
乳幼児期から、近づきたいのと遠ざかりたいのが常に混じっていて
どっちつかずで、状況に即した行動に文節化していかないのだろう。
結合に向かう部分と、分離に向かう部分が常に同時に混在して、
本人も、その2つの感覚に翻弄されているのだろう。
そのため、好きと嫌いも曖昧な状態が続いているのだろう。
好きと嫌いが曖昧だと、自他境界を持てずに、常に外部からの刺激に
翻弄されるのではないのだろうか?
そのことが感覚過敏などの基に有るのではないのだろうか?
「結合と分離の結合」とは、その2つの極を持ち、ある程度のことを
決められる余裕のある状態を指すのだろう。
好きとか嫌いとかを持つ余裕すら無いと、他者と鏡像的関係を持ち
その他者を真似たりするところへ行かず、何かを学んだりすること
繋がらないのだろう。
居心地が悪そうにして離れたがり、遠ざかると寂しそうに母親を伺うと有る。
そのような「甘えたいのに甘えられない」状態で、宙吊りになっていることが
その後の様々な特徴に繋がるとのこと。
乳幼児期から、近づきたいのと遠ざかりたいのが常に混じっていて
どっちつかずで、状況に即した行動に文節化していかないのだろう。
結合に向かう部分と、分離に向かう部分が常に同時に混在して、
本人も、その2つの感覚に翻弄されているのだろう。
そのため、好きと嫌いも曖昧な状態が続いているのだろう。
好きと嫌いが曖昧だと、自他境界を持てずに、常に外部からの刺激に
翻弄されるのではないのだろうか?
そのことが感覚過敏などの基に有るのではないのだろうか?
「結合と分離の結合」とは、その2つの極を持ち、ある程度のことを
決められる余裕のある状態を指すのだろう。
好きとか嫌いとかを持つ余裕すら無いと、他者と鏡像的関係を持ち
その他者を真似たりするところへ行かず、何かを学んだりすること
繋がらないのだろう。