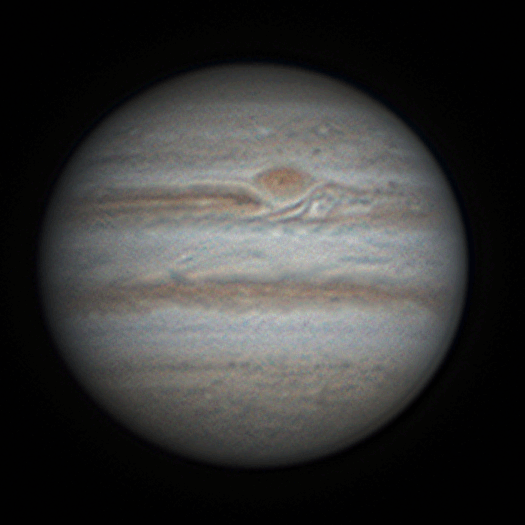昨日、木星が衝(外惑星が太陽と正反対の方向に来た状態)となりました。今が観測に最適な時期ってことになります。
そこで日付が4日へと変わる時間帯に久々に望遠鏡を用いた拡大撮影を行いました。得られた画像がコレです。

【木星 2023.11.03 24時台】
タカハシμ-180+2.5倍バローレンズ+ADC+CMOSカメラ(ZWO ASI1600MC-cool),UV/IRカットフィルター,
合成F値=30,タカハシEM-200Temma2M赤道儀,取得動画の1000/2000フレームをAS!3にてスタック×10セット,
WinJUPOSにてDerotation処理コンポジット,Registax6でwavelet処理
この季節にしては気流が割と安定してたのか像の揺らぎは少なめで、まずまずの出来映えだったような気がします。
上方やや左の明るくて丸いヤツは衛星ガニメデで、木星面にその影を落としているところでした。
なお、スタック用の動画10本の取得後に、気流がさらに落ち着いた感じだったんで、もう1本だけ撮影した動画から
作成した画像がこちら。

動画1本のみからのスタッキングなので細部の描出がイマイチですが、ガニメデは公転に伴う移動によるブレが少なく、
表面の濃淡が認められる画像となりました。個人的に衛星表面の模様を捉えたのは初めてのことで舞い上がってます。
となると、衛星の模様については木星の自転に合わせたDerotation処理を行わない方がイイんじゃね?って思いきや、
その処理を行うソフト"WinJUPOS"の最新版だと、どうやら衛星の動きまでも考慮したコンポジット処理が可能らしく、
衛星本体もその影も横に伸びたイメージとならずに済むらしいので、いずれ試してみたいものです。
ところで、惑星撮影ネタの記事で恒例の高層風速マップをチェックしてみたら・・・

ジェット気流は九州の西あたりで何故か南北に分岐し、関東周辺では弱まっていたみたいです。
それが好シーイングの理由でしょうかねぇ。でも週明けには気流の速い部分が関東上空にも来て悪条件になりそうです。
まあ、像の揺らぎを左右するファクターは他にもあるので、あくまで参考程度ですけどね。