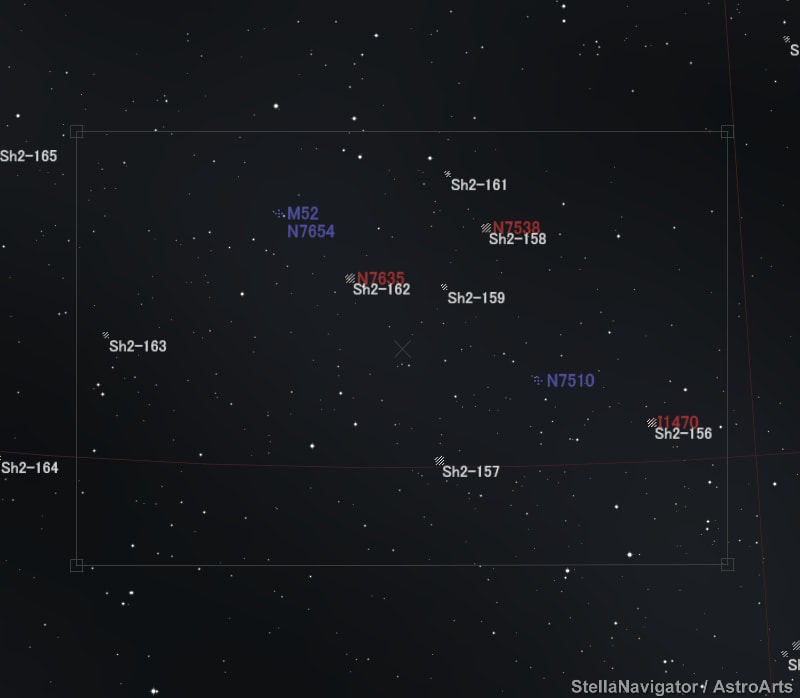1日おいて撮影した木星です。

【木星 2020.8.30 20時台】
タカハシμ-180望遠鏡+2.5倍バローレンズ+ADC+冷却CMOSカメラ(ZWO ASI1600MC-cool),合成F値=30,
タカハシEM-200Temma2M赤道儀,約1分40秒間のキャプチャー動画から約2500コマをAS!2にてスタック,
Registax6でwavelet処理
この日は南中する時間帯に大赤斑が前面に見えてました。
ただ、残念なことに夕方以降に広がってきた「かなとこ雲」崩れとみられる薄雲の邪魔が入り、
スッキリしない空模様の上に気流も安定せず、像が時々暴れる状態でした。
大赤斑を前面に捉えた前回の撮影時(6/9)よりはマシな画像になりましたけど、なんかイマイチな感じ。
なかなか好条件で大赤斑を撮れる機会に恵まれないなぁ・・・