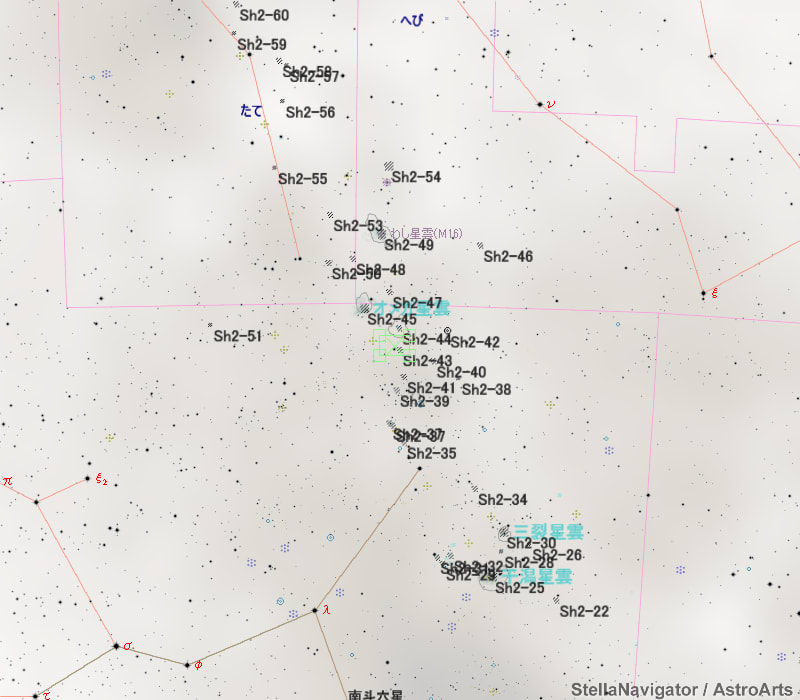シリーズで紹介している五島プラネタリウムのリーフレットの第5弾は1977年3月配布のものです。




表紙(1ページ目)には写真ではなく星座絵が掲載されてました。春分点のあるうお座とその隣のみずがめ座の
部分を切り出したものです。
2ページ目には「星空の四季」と題した解説があり、太陽の天空上での通り道である黄道とそれが通っている
黄道星座についての記述があります。当月の上映時には星座と太陽を同時に投影して1年でどのように太陽が
動いていくのか解説していたと記憶してます。実際の空では太陽が明る過ぎて背景の黄道星座が見えたりは
しませんので、プラネタリウムならではの見せ方だったように思います。
3ページ目の「3月の星座」の解説では、へび年にちなんで春の星座である「うみへび座」にスポットを当てた
説明があります。神話上では9つの頭を持つ化け物ですが、仲良しである巨大な化け蟹とともにヘルクレスに
退治されてしまい、哀れに感じた女神ヘラが空に上げて星座にしたとされてます。実際の星空でも、かに座と
うみへび座は並んで見えます。ちなみに、全天88星座の中で最も領域の広いのはうみへび座だったりします。
但し、2等星と3等星が1個ずつある他は暗い星ばかりで全く目立ちません。比較的有名な天体としてはM83、
NGC3242があります。