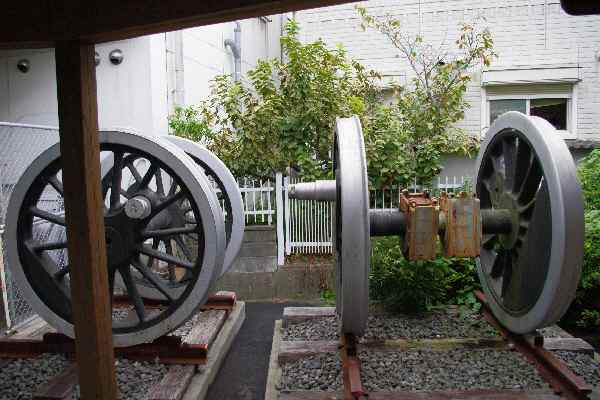我が家の庭で収穫した果実です。

11月始め、みかんが熟れました。
温州みかんです。

収穫です。
木で熟したおいしいみかんです。

レモンも、黄色く色づきました。
酢の物、焼き魚、焼酎などに少しづつ使用しています。

11月下旬、カリンが色づきました。

カリンの実。

収穫です。
今年は20個以上収穫しました。

カリンジュースを作りました。
カリンを切って、氷砂糖を入れます。水は入れません。
冷暗所に数ヶ月置くと、ジュースが出来ます。
のどにいいので、風邪をひいたとき飲むといいです。
左は、去年作ったカリンジュース。

今日の絵手紙。

11月始め、みかんが熟れました。
温州みかんです。

収穫です。
木で熟したおいしいみかんです。

レモンも、黄色く色づきました。
酢の物、焼き魚、焼酎などに少しづつ使用しています。

11月下旬、カリンが色づきました。

カリンの実。

収穫です。
今年は20個以上収穫しました。

カリンジュースを作りました。
カリンを切って、氷砂糖を入れます。水は入れません。
冷暗所に数ヶ月置くと、ジュースが出来ます。
のどにいいので、風邪をひいたとき飲むといいです。
左は、去年作ったカリンジュース。

今日の絵手紙。