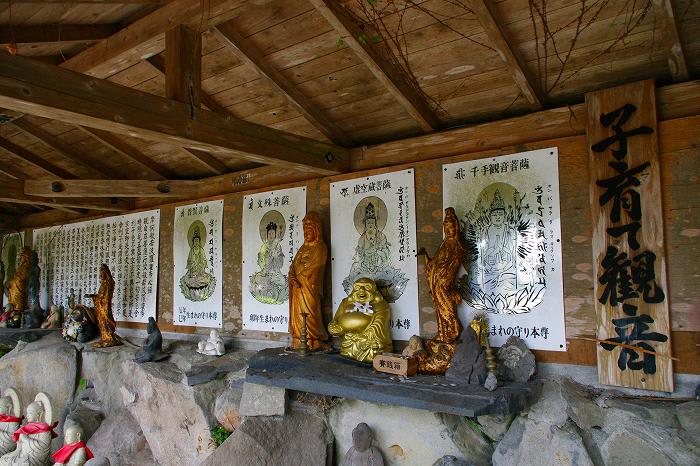指宿市にある揖宿神社のクスノキを紹介します。

鳥居の両側にクスノキが見えます。ここにはクスノキの巨木が8本あります。

揖宿神社社殿。

代表的なクスノキを見ていきます。これは、鳥居をくぐって右にあるものです(最初の写真の右の木)。

根元。

別の角度から見たものです。

社殿に向かって左にあるクスノキです。

根元。

社殿の奥にあるクスノキです(2枚目の写真の右の木)。

根元。データはありませんが、これが一番根回りが大きいようです。
これらのクスノキは、開聞岳噴火の時、開聞岳から3本を植栽したと伝えられています。それからすると樹齢千年以上ですが、実際は700~800年と推定されています。

神社の前にあるムクノキです。
幹周り:3.1m 樹高:21.1m 樹齢:300年

別の角度から見る。

根元。補修跡があります。

奥に、忠魂碑などの石碑があります。