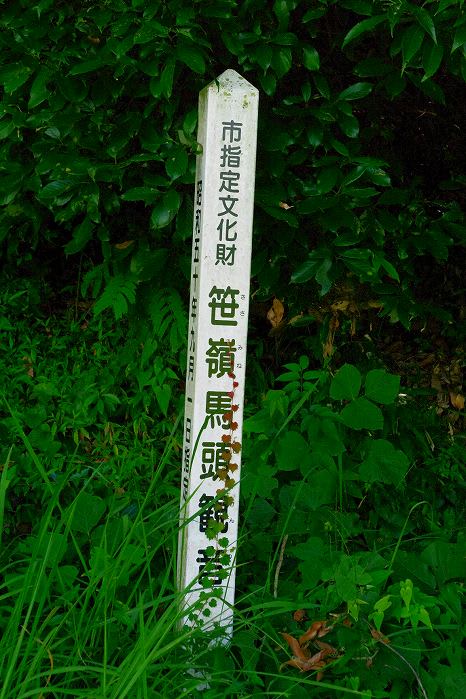秋も深まってきた10月下旬、野山で見かけた花たちです。

ホシアサガオ(星朝顔) ヒルガオ科
花は五角形の星形をしており(名前の由来)、中心が濃い赤紫です。普通のアサガオより小さいです。

ヒメアザミ(姫薊) キク科
普通のアザミより花が小さく、茎は長く、全体に華奢な感じのアザミです。

イナカギク(田舎菊) キク科
花はやや小さく、葉の切れ込みはありません。九州南部のものは、サツマシロギクとも言うようです。

サザンカ(山茶花) ツバキ科
今の時期、生け垣のサザンカはよく見ますが、これは山で見かけたサザンカです。

チャ(茶) ツバキ科
サザンカの花とよく似ています。

ヤクシソウ(薬師草) キク科
名前は、薬師如来に由来するようです。

カラスウリ(烏瓜、ウリ科)の実
食べられませんが、鮮やかな赤で、山を彩ってくれる実です。花もレースのようで、きれいです。

ツワブキ(石蕗 ) キク科
これから次々に花を咲かせ、晩秋の野を彩ってくれます。

トキワハゼと同じゴマノハグサ科のようですが、名前がわかりません。
花は、1cmくらいと小さいです。田んぼの畦に咲いていました。