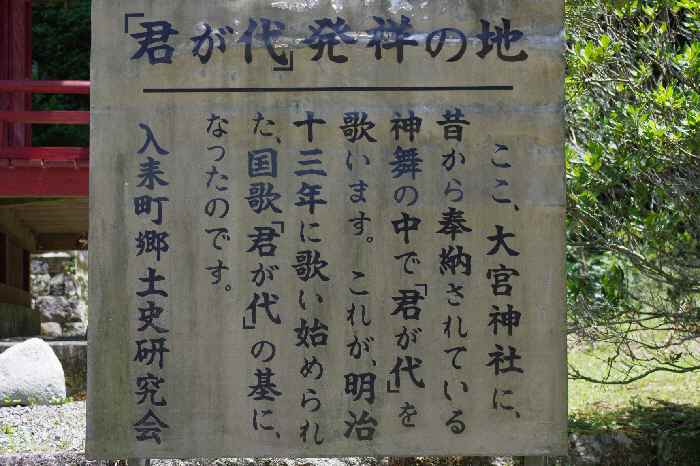永野金山跡の続きです。

胡麻目坑から精錬所まで、鉱石をトロッコ電車で運搬していましたが、その鉄橋の橋脚です。
大正3年の建設ですが、当時鹿児島県で一番高い鉄橋で、見物に来る人が多かったそうです。川は九郎太郎川です。

左岸の橋脚。

右岸の橋脚。

当時の鉄橋です。(案内板より)
人が歩いています。

上級幹部の事務所だった鉱業館への入口です。

鉱業館の跡。

鉱業館です。(案内板より)
明治45年、西郷隆盛の息子の菊次郎が8代館長に就任しています。
昭和33年まで使われていたそうです。

鉱業館跡の隣にある精錬所跡。(鉱業館跡は下の道路をまっすぐ行ったところにある)

前の写真の高台にある精錬所跡。石垣やコンクリートが残っており、廃墟となっています。

精錬所跡には大きなプールがあり、今も水が注がれています。