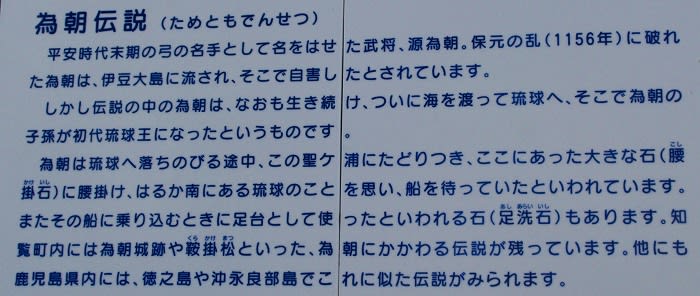就職して最初の赴任地は滋賀県だった。
その夏、先輩に誘われて、乗鞍岳に夏スキーに行った。
といっても、南国育ちの私は、スキーなどやったことはもちろん、見たこともないので、観光で付いて行ったのだ。
山頂付近には、7月だというのに雪が残っていた。
先輩たち3人は、駐車場付近から斜面を滑り降りていった。
私はしばらくそれを見ていたが、一人で山頂に登ることにした。
21~22歳くらいの若い女性が登っていたが、私に
「お一人ですか」
と声をかけてきた。
私は、4人でスキーに来たが、自分は滑れないので山に登っている、と答えた。
それをきっかけに、二人で話しながら山頂を目指した。
彼女は京都の人で、一人旅だと言った。
雅やかな京都弁を話す女性は、鹿児島から出てきたばかりの田舎者の私には、少しまぶしく感じられた。
山は、夏だというのに軽装では寒いくらいだった。
私は、持っていたヤッケを彼女に着せてやった。
そして、乗鞍岳山頂で、赤いヤッケ姿の彼女の写真を撮った。
それから何日かして、思いがけなく、会社にいた私に彼女から電話があった。
雑談で会社名を言ったので、彼女はそれを覚えていて、電話番号を調べて電話してきたのだ。
「もうすぐ祇園祭があるので、見に来ませんか」
という誘いだった。
約束の日の夕方、京都駅で待ち合わせ、彼女の案内で祇園を散策してから、祇園祭を見た。
私は、京都は初めてで、お上りさん状態だった。
古い町並みの祇園と鴨川の流れ、宵闇に浮かび上がる豪華な山鉾。
むせかえるような人いきれの中で、京都の女と二人でそれを見ている・・・
私は、そんな状況に飲み込まれ、ぼおっと酔ったような気分になった。
京都祇園祭を見たのは、これが最初で最後だった。
その後、彼女との間は進展することもなく、それっきりになった。
ちなみに私は、先輩の指導で、その年の冬からスキーを始め、デビューは伊吹山スキー場だった。その後、金沢、仙台、長野と転勤先でも楽しんだ。
スキー道具は鹿児島まで持ってきたが、スキー場に行く機会がないまま時は過ぎ、やがて処分してしまった。