
なにも語るべきことはない。書くべきこともない。
それでも、わたくしは50日を超える日々を過ごしても、詩人「清水昶」について考えている。
どこかで「言葉にしたい。」という願望が消えない。詩を書くものの悪い癖だ。
突然過ぎる訃報にうろたえ、泣いた数日。そして「偲ぶ会」にも行った。
多くの詩人の「追悼文」を読み、「追悼の挨拶」も聞いた。
それらはわたくしにとっては、意味をもたない。
それらはほとんどが、故人と自身との固有の思い出であり、経緯である。
それらはわたくしには共有できるものではない。
それよりも到底共有できない言葉の方が、わたくしを震撼させる。
たとえば共に暮らした方の「死なせてしまった…。」という苦しみの言葉。(自宅にて突然死。断じて自死ではない。)
そして兄上さまだけが知っている、詩人の幼少年期の「あきらチャン」の生き生きとした描写。
亡霊になってはじめて
人間は生きているみたいになつかしい
……という詩の一節がある。清水昶詩集「詩人の死」からの引用です。
「どうして死者に対して、そんなに熱くなれるの?」とわたくしは尋ねたことがある。
「これくらい人間を震撼させ、熱くさせるものはないからね。」と。
「ガリバーの質問」を書いた詩人の、これが答えだった。
今頃は、あなたはどのあたりを彷徨っていらっしゃるのか?
そして、ご自分の「死」に対して、熱くなっていらっしゃいますか?うろたえていらっしゃいますか?
それとも、そろそろお父上やなつかしい方々にお会いできましたか?
あなたの詩は息遣いやら鼓動やら涙やら、一層音高くなって我が書棚で生きています。
某詩人の「清水昶の詩がどこまで生きのびるのか、見届けようではないか!」という朗々とした声とともに。
《つぶやき》
これできちんと書けたとは到底思えない。しかし階段は1歩上がれたとも思う。










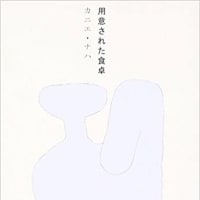









詩塾での御指導は初心者には心細かったですが、詩人の生き方を見せてくださいました。
昶さんは「先生」にはなれませんでした。
その代わり、わたくしたちと対等の立場にいらっしゃることを、少しも気にしていませんでしたね。そこが昶さんの魅力ですね。