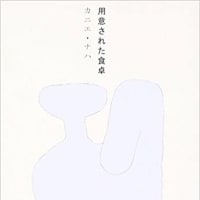筆者の「高橋たかこ」は1978年生まれ。スウェーデン・ストックホルム大学人文学科卒業。
ストックホルム在住25年(この本が出版された2000年時点での数字であるから、そのまま在住であるならば38年在住?)。
通訳、翻訳、毎日放送レポーター。2人のお子様も今は30歳前後?
確認したいことがあるけれど、Googleには出てこないし、Amazonでは「高橋たか子」ばかりでてくる。
(いやはや、たか子さんの本は膨大にある。改めて驚いている。)
とにかく読了。(図書館の本である。)
13年前のスウェーデンのいじめ対策であるから、現在ではどの位の推移があるのだろうか?
日本の13年前と比較すればいいのだろうか?
福祉先進国と言われるスウェーデンにおいても、「いじめ」は7人に1人の子供が関係しているとのこと。
日本における「通信簿」というものは、スウェーデンでは中学2年から始まるとのこと。
子供たちが、成績においてはじめて篩にかけられるのは高校受験である。
もちろん定期試験もなく、スウェーデンの子供たちは突然始まる成績競争を迎えることとなる。
スウェーデンの「いじめ対策」は日本よりも進んでいたと思われる。
それは国が主導権を行使して、組織化され、命令系統も学校現場へ早急に下る仕組みになっている。
また親たち、子供たちの「いじめ対策」に向かう様々な活動は日本よりもはるかに活発である。
しかし、「いじめ」の根底に動かし難くある「第三者の見て見ぬふり」は、日本でもスウェーデンも変わりはない。
これが一番の障害となることはあきらかなのではないか?
いじめる側の子供がどうしてどのようにして、そこに存在するのか?
それは両親の愛情が歪みなく、子供を抱いていたか?ということに尽きると思う。
スウェーデンはすでに、大家族の時代から核家族へ、さらに日本よりもはるかに高い離婚率である。
核家族は分子家族へ向かってゆくのではないか?
子供たちは、急いで大人にならなければならないところに追い込まれているのではないか?
「急いで大人になる。」ということは、子供にとっては「強くなる。」ということで、
その「強さ」の意味をを間違えるのだ。
そうして「いじめっ子」は子供世界を支配し、「いじめられっ子」を増殖させていく。
さらに「見て見ぬふりの子」を増殖させる。
自然に普通に愛されて育った子供にとっては、「いじめ」は想定外の体験である。
「いじめる心理」を理解できないし、「いじめをやめて。」と言っても、やめてはもらえない。
まずは「いじめっ子」を育てないことから出発しなくてはならないが、それは、どだい無理なこと。
ねばり強く、子供たち、親たち、学校などなど、さまざまな活動を通して対処するしかないだろう。
スウェーデンに始まった「オンブズマン」活動もその1つのやり方だと思うし、
行政、法律などが深く関与するというやり方もあるが、そのどれもが完璧ではない。
人間が人間として向き合うことを忘れないようなものでありたい。
(2000年・株式会社コスモヒルズ発行)