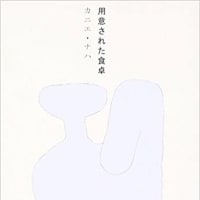GWを過ぎた時期を選び、桜の名所だという情報も無視して、桜若葉の時期に旅の日程を決めました。
1週間前から、ひたすらネットの「仙北市の天気予報」を見ていましたが、
旅行中に雨の降らない日は1日もありませんでした。
秋田県は日本で1番雨の日が多いとのこと。予報では「晴れ」「曇り」でも、雨は降りました。
まずは小雨の桧木内川(ひのきないがわ)に沿って散歩。約2キロの桜並木だそうですが、桜若葉が美しい。
それから、小雨のなかの散歩&武家屋敷通りの下見。(ゆっくりと歩いたのは最後の日でした。)

《ホテルの窓から》

《桧木内川》

《石黒家》

《松本家》
田沢湖にも行きましたが、風雨が強く冬のように寒い。
湖畔の散歩もままならず。
レストハウスの窓辺で、船に乗るまで時間を過ごしながら…。

《雨に濡れたガラスに桜の花びら。窓の外には湖畔の葉桜》
以下は主なメモです。
仙北市立角館町平福記念美術館
平福穂庵(ひらふくすいあん)(1844~1890) 、平福百穂(ひらふくひゃくすい)(1877~1933)親子を顕彰した美術館です。
「撮影はご遠慮下さい。」という美術館のマナーはありますが、あまりにも美しいので
美術館員さんにおたずねして「ピアノだけでしたら」と撮影許可を頂いた写真です。

《樺細工をほどこしたピアノ。あああああ~欲しい!》
平福穂庵は明治期の日本画家。羽後国角館(秋田県)生まれ。通称順蔵。郷里で初め武村文海に円山四条派の絵を学ぶが、ほぼ独学を通した。
文久1年(1861)から京都に遊学し,師につかず風景写生や古画の模写に専念、慶応2(1866)年帰郷する。
明治維新後,各種の博覧会で受賞、「乞食図」「乳虎図」など。
また明治5年(1872)北海道に旅行し、以後アイヌの図を多く制作。
また自ら一時勤めた荒川銅山を「荒川鉱山全景」として描くなど、社会派的な意識と行動が認められる。平福百穂 はその子。
平福百穂の絵画の出発点は父親の指導であった。父亡き後も師と後援者には恵まれた方であった。
平福百穂は1903年頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動、歌集「寒竹」を残す。歌誌「アララギ」の装丁および
アララギ歌人の歌集の装丁も手掛ける。
さらに、現在も使われている岩波書店の出版物の裏表紙中央に配された「岩波」の壺形マークは平福百穂のデザインである。
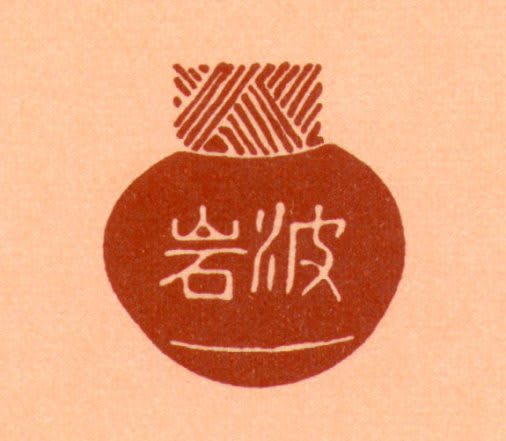
新潮社記念文学館
佐藤義亮(さとうよしすけ(ぎりょう))(明治11年・1878年~昭和26年・1951年)は、新潮社の創立者。雑誌「新潮」を発行した。
仙北市角館町の岩瀬町出身です。
代表的な作家の原稿がそのまま展示されています。
たとえば、太宰治の「心中失敗」のメモなど。
しかし不思議に思ったのは、大江健三郎のものは何もないことでした(写真すらも)。
ああ。書きながら気がついた。すべて亡くなった方ばかり???
《おまけのお話》
ホテルでの3日間、ロビーで120円で買った新聞は「秋田魁新報」でした。
保守的風土性の強いこの土地で、批判力を失わない新聞とのこと。
何故行先が「会津」に続き「角館」なのか?そして「武家屋敷」なのか?
長州出身の同行者の「タマシイのジュンレイ」なのか?
1週間前から、ひたすらネットの「仙北市の天気予報」を見ていましたが、
旅行中に雨の降らない日は1日もありませんでした。
秋田県は日本で1番雨の日が多いとのこと。予報では「晴れ」「曇り」でも、雨は降りました。
まずは小雨の桧木内川(ひのきないがわ)に沿って散歩。約2キロの桜並木だそうですが、桜若葉が美しい。
それから、小雨のなかの散歩&武家屋敷通りの下見。(ゆっくりと歩いたのは最後の日でした。)

《ホテルの窓から》

《桧木内川》

《石黒家》

《松本家》
田沢湖にも行きましたが、風雨が強く冬のように寒い。
湖畔の散歩もままならず。
レストハウスの窓辺で、船に乗るまで時間を過ごしながら…。

《雨に濡れたガラスに桜の花びら。窓の外には湖畔の葉桜》
以下は主なメモです。
仙北市立角館町平福記念美術館
平福穂庵(ひらふくすいあん)(1844~1890) 、平福百穂(ひらふくひゃくすい)(1877~1933)親子を顕彰した美術館です。
「撮影はご遠慮下さい。」という美術館のマナーはありますが、あまりにも美しいので
美術館員さんにおたずねして「ピアノだけでしたら」と撮影許可を頂いた写真です。

《樺細工をほどこしたピアノ。あああああ~欲しい!》
平福穂庵は明治期の日本画家。羽後国角館(秋田県)生まれ。通称順蔵。郷里で初め武村文海に円山四条派の絵を学ぶが、ほぼ独学を通した。
文久1年(1861)から京都に遊学し,師につかず風景写生や古画の模写に専念、慶応2(1866)年帰郷する。
明治維新後,各種の博覧会で受賞、「乞食図」「乳虎図」など。
また明治5年(1872)北海道に旅行し、以後アイヌの図を多く制作。
また自ら一時勤めた荒川銅山を「荒川鉱山全景」として描くなど、社会派的な意識と行動が認められる。平福百穂 はその子。
平福百穂の絵画の出発点は父親の指導であった。父亡き後も師と後援者には恵まれた方であった。
平福百穂は1903年頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動、歌集「寒竹」を残す。歌誌「アララギ」の装丁および
アララギ歌人の歌集の装丁も手掛ける。
さらに、現在も使われている岩波書店の出版物の裏表紙中央に配された「岩波」の壺形マークは平福百穂のデザインである。
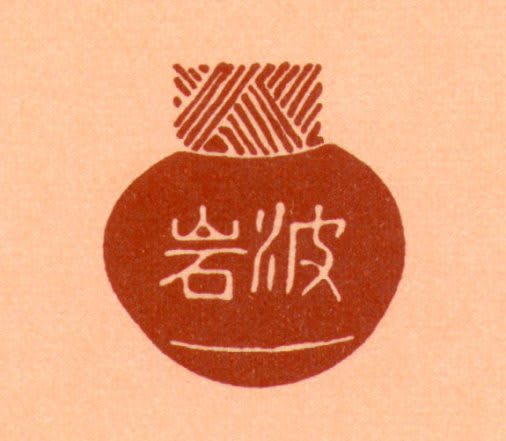
新潮社記念文学館
佐藤義亮(さとうよしすけ(ぎりょう))(明治11年・1878年~昭和26年・1951年)は、新潮社の創立者。雑誌「新潮」を発行した。
仙北市角館町の岩瀬町出身です。
代表的な作家の原稿がそのまま展示されています。
たとえば、太宰治の「心中失敗」のメモなど。
しかし不思議に思ったのは、大江健三郎のものは何もないことでした(写真すらも)。
ああ。書きながら気がついた。すべて亡くなった方ばかり???
《おまけのお話》
ホテルでの3日間、ロビーで120円で買った新聞は「秋田魁新報」でした。
保守的風土性の強いこの土地で、批判力を失わない新聞とのこと。
何故行先が「会津」に続き「角館」なのか?そして「武家屋敷」なのか?
長州出身の同行者の「タマシイのジュンレイ」なのか?