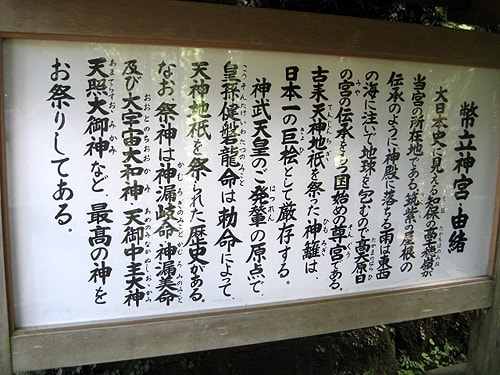ケイのオヤジが
「ケン、打越で一番高いところはどこか?」
と言う。
うちの団地の奥は高台になっている、そして公民館や打越菅原神社があるところなのかな、などと考えているとグッチのヤツが
「稲荷山だろう?」
などと言っている。
「あそこには古墳があったよね」
などと言っていると
「おい!見に行くぞ」
となった。
ここ打越町は東側には坪井川が流れていて、遊水公園もある。
その昔はそのたりは海だったようで津の浦や船場などその当時の地名が今でも残っている。
小高い丘が続く打越町は、その海の水が打ち越すというところからの地名らしい。
グッチの運転で県立清水が丘の駐車場をお借りした。
男3人と、クーの友達のクッキーとで出かけた。

清水が丘学園のグラウンド(町内体育祭をしたところ)の脇を歩いていると
「どこに行かれるんですか?」
と学園の方から声をかけられた。
「稲荷山の古墳を見に来ました」
と言うと
「どちら様ですか?」
と聞いてくる。
「地元打越町の住民です」
と言うとそれ以上は何も聞かれなかった。

久しぶりの稲荷山古墳なのだ。
しかし、鉄柵で囲まれていて鍵までかかっていた。
直径30m、高さ6mの円墳で、昭和22年に発掘されたものだそうだ。
出土品は豊富で、鏡・直刀・矛・鉄鏃・杏葉・雲珠・金環・轡・勾玉などがあり、6世紀後半の古墳と考えられる。
と熊本市のHPでは紹介されている。

古墳の周りには椿なのだろうかきれいな花が咲いていた。

帰り道グラウンドを歩いていると、左側の片岡演劇劇場から賑やかな音楽が聞こえてくる。

クルマに乗り込むと、クーには目いっぱいのバカがついていた。

クッキーもすごいことになっていたのだ。
植物の生命力、古墳時代もこんなんだったのか考えた。
熊本市稲荷山古墳
「ケン、打越で一番高いところはどこか?」
と言う。
うちの団地の奥は高台になっている、そして公民館や打越菅原神社があるところなのかな、などと考えているとグッチのヤツが
「稲荷山だろう?」
などと言っている。
「あそこには古墳があったよね」
などと言っていると
「おい!見に行くぞ」
となった。
ここ打越町は東側には坪井川が流れていて、遊水公園もある。
その昔はそのたりは海だったようで津の浦や船場などその当時の地名が今でも残っている。
小高い丘が続く打越町は、その海の水が打ち越すというところからの地名らしい。
グッチの運転で県立清水が丘の駐車場をお借りした。
男3人と、クーの友達のクッキーとで出かけた。

清水が丘学園のグラウンド(町内体育祭をしたところ)の脇を歩いていると
「どこに行かれるんですか?」
と学園の方から声をかけられた。
「稲荷山の古墳を見に来ました」
と言うと
「どちら様ですか?」
と聞いてくる。
「地元打越町の住民です」
と言うとそれ以上は何も聞かれなかった。

久しぶりの稲荷山古墳なのだ。
しかし、鉄柵で囲まれていて鍵までかかっていた。
直径30m、高さ6mの円墳で、昭和22年に発掘されたものだそうだ。
出土品は豊富で、鏡・直刀・矛・鉄鏃・杏葉・雲珠・金環・轡・勾玉などがあり、6世紀後半の古墳と考えられる。
と熊本市のHPでは紹介されている。

古墳の周りには椿なのだろうかきれいな花が咲いていた。

帰り道グラウンドを歩いていると、左側の片岡演劇劇場から賑やかな音楽が聞こえてくる。

クルマに乗り込むと、クーには目いっぱいのバカがついていた。

クッキーもすごいことになっていたのだ。
植物の生命力、古墳時代もこんなんだったのか考えた。
熊本市稲荷山古墳