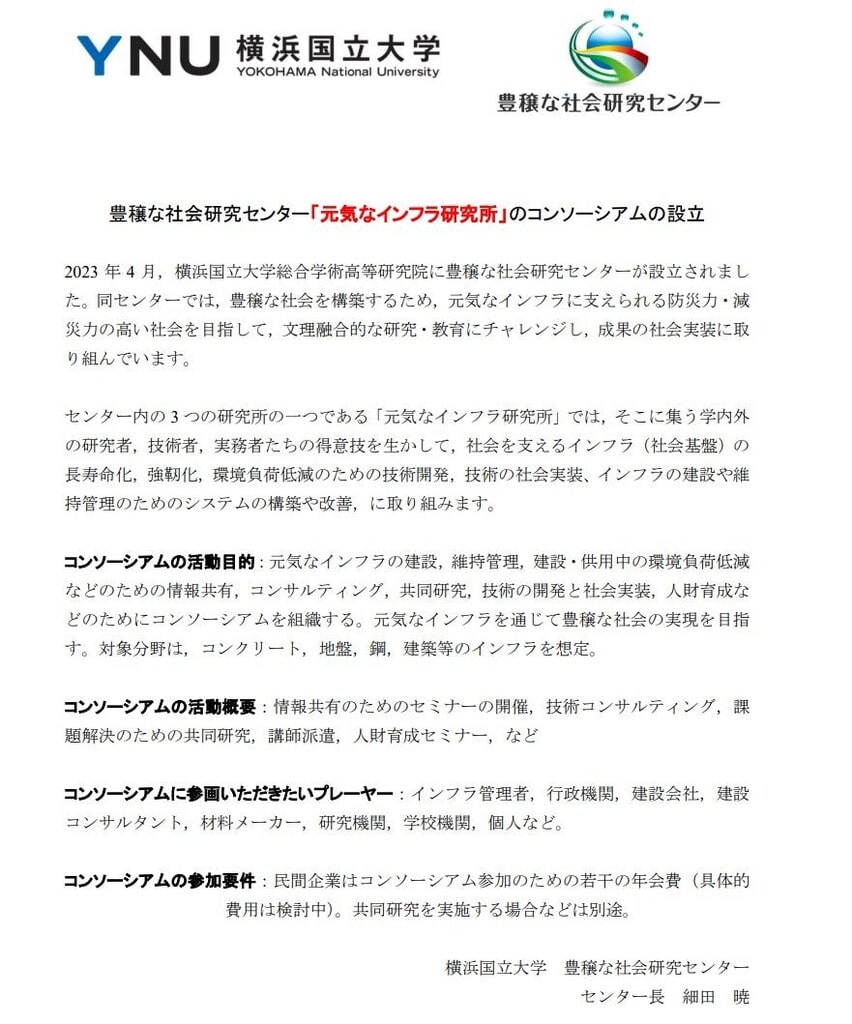2023年の大晦日となりました。このエッセーは浦和の実家で書いております。
まさに世界が激動となり、馬渕睦夫さんによると「2023年に世界の大転換がすでに生じた」とのこと。人類史で少なく見積もっても100年に一度くらいのパラダイムシフトがすでに生じた、ということですから、とんでもない激動になっていくことは確実でしょう。まだ何が起きたか気づいていない方は、ぜひ馬渕さんの著書や動画でフォローしてみてください。
さて、私個人も2023年にはいろいろな出来事があり、まさに全力で駆け抜けてきた感が強いです。ほとんど休日もなく、明らかな休日は数日くらいでした(ある一日は9月19日に大雄山最乗寺に登山・お参り。ある一日は11月4日に友人と筑波山に登山。ある一日は12月29日に昭和記念公園でハーフマラソン)。結局、休日もダイナミックに活動しており、寝転がって過ごす休日はほとんど無かったように思います。
2023年は2月に、田坂広志さんの「死は存在しない」という著書を紹介されて読み、「ゼロ・ポイント・フィールド」という概念を初めて知り、今年の自分の転換の一つの大きなきっかけとなりました。その後、田坂さんの著書や動画をフォローし、7月末には東京コーチング協会のコーチング祭りという三島でのイベントにゲストで呼んでもらって、そこでのコーチングの達人たちの講演の中で村松大輔さんのことを知り、2冊ほど著書を読んで、「ゼロ・ポイント・フィールド」や量子力学の世界の概念について、認識を深めることとなりました。ブッダの世界観と量子力学の世界には共通点も多いように思われ、ある意味で、宗教と科学の融和、という壮大なテーマなのかもしれません。
仏教にも多大な興味があり、多くの著書や動画などを勉強していますが、ゼロ・ポイント・フィールドとの出会いは、私の今後の人生にも大きな影響を与える出来事、きっかけでした。
2月には、ドテラのアロマオイルを始めました。友人に勧められ、始めましたが、すっかりはまってしまいました。10ヵ月以上経過しましたが、睡眠前・中の寝室でのディフーザー、風呂上がりや日常の顔・肌のケア、香水もやめてドテラのオイル、洗濯の洗剤、衣類や靴のスプレー、などすべてドテラの製品に切り替えました。自分でオイルをブレンドしたりしており、これも私の人生に大きな転換をもたらしました。
ついでに食生活について。2022年4月6日から断酒し、そのままずっと継続していますが、飲みたいとは全く思わず、すでに1年9ヵ月。主食は白米を大幅に増やすことにし、食事メソッドは、柏原ゆきよさんのメソッドに従っています。白米を相当な量、食べるメソッドですが、非常に健康で、以前は肌荒れもかなりあったのですが、肌の調子も極めてよいです。体重は63kgくらいをほぼずっとキープで、引き締まっています。
そして、2023年4月から、豊穣な社会研究センターが設立され、センター長としての業務が始まりました。普通の大学教授と兼務ですので、忙しくなるのは当たり前なのでしょうが、まあそれにしても忙しいこと。3つの研究所(元気なインフラ研究所、もしも×可視化研究所、つながり方研究所)を抱えるセンターの長として、まともな研究センターとして機能させるためには、ありとあらゆる努力を実践する必要があり、まさに全力でやってきたと思います。センターが今後、どのような展開を見せるかは、乞うご期待、です。
豊穣Cで活動をともにする同志たちとも出会うことができ、私にとっても新しいチャレンジが続きますが、私の50代を捧げるチャレンジとなるでしょうから、やりがいも大きく、使命感に燃えている状況です。
2022年度から職務としている、留学生プログラムのディレクター職も2年目となりましたが、比較的順調に推移しており、文科省の奨学金プログラムの継続審査も無事に合格し、ディレクターの責務を果たしてホッとしています。
4月に50歳になりましたが、まさに体力勝負。膨大な業務を元気にこなし続けるためにも、とにかく心身の健康がすべてといって過言ではありません。幸いに、メンタル面がへたることもなく、身体面では7月に股関節痛が発生しましたが短期で回復し、3回の海外出張(ベトナム+シンガポール、パキスタン、ウズベキスタン)も無事にこなすことができました。半月後の1月には久しぶりのヨーロッパ出張でイタリアに行く予定です。
心身の健康を維持するため、まさにありとあらゆる努力と修業を重ねている状況で、毎朝の体操+柔軟体操、2週間に一度のカイロプラクティク、ほぼ毎週のスーパー銭湯でのサウナとリンパドレナージュ、日々のウォーキング(通勤での上星川駅からの山登り+下り)、毎朝の娘たちのお弁当作りなど、習慣が仕事のパフォーマンスを支えています。
運動も基本は日々のウォーキングとなりました。一番手軽だし、体への負荷も小さいし、とにかく散歩は楽しい。3月から12月の10ヵ月は、すべて月間平均で10000歩以上/月を達成。特に、10月は13,236歩/月、11月は13,933歩/月と頑張りました。また、一日10000歩以上の連続日数記録も77日(9月16日~12月1日)という自己新記録を作りました。歩く、という行為と様々な記録をつなぎ合わせて、趣味にしてしまいました。
年末も基本的には1月8日締め切りのJCI(日本コンクリート工学会)の投稿論文の添削。8本程度の投稿となりそうで、空いている時間はとにかく添削。
そのまま年始に突入しそうですが、突っ走れる間は走り続けようと思っています。
2024年も心身の不調がなければ、同じように走り続けると思いますが、ご一緒いただく方々にはお世話になると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
数年以内くらいに、3ヶ月程度の海外滞在を考えています。居心地の良い国(例えばベトナム)に拠点を置いて、心身のリラックスと、研究・執筆活動などに専念する充電期間です。それを夢見て、走り続けようと思います。。。
私がセンター長を務めております、豊穣な社会研究センターの中にある3つの研究所の一つ、「元気なインフラ研究所」のコンソーシアムが設立されました。
元気なインフラ研究所の目指す方向性は、上記のリンクでもすでに発信しています。
コンソーシアムがどのようなものなのか、4分程度で分かる動画も公開しています。
コンソーシアムの規約はこちら。
2023年度は会費は無しです。会員資格は各年度の年度末までで、新年度になると更新の手続きが必要となります。2024年度以降は、基本は年会費5万円(1法人ごと)。会費を請求しない場合(例えば行政機関など)もあるので、センター長の細田にお問い合わせください。
コンソーシアムへの参加申込書も、ワードで一枚ですので、お気軽にお問い合わせください(ims-hojyo@ynu.ac.jp まで)。申込書の提出先も、同じメールアドレスで大丈夫です(ims-hojyo@ynu.ac.jp)。
2023年度中に少なくとも1つ、できれば2つ、コンソーシアムのイベントを開催する見込みです。
初回は、おそらく2024年2月6日午後に開催予定で、発信は富山県の高岡市から。オンラインで視聴できるようにする予定です。テーマは「地方自治体のインフラの維持管理を元気に!」という感じ。
熊本県玉名市の素晴らしい橋梁維持管理と、これからスタートする富山県高岡市の橋梁維持管理のスマート化(細田がアドバイザー)のコラボとなります。玉名市の木下義昭課長補佐(博士(工学))とそのブレーンの松永昭吾さん(横浜国立大学客員教授、もちろん豊穣Cの重要メンバー)と、細田とで高岡市に応援に駆け付け、その場で元気なインフラ研究所のコンソーシアムの初回イベントをやっちゃいます。
コンソーシアムの会員になれば、公開セミナー以外の情報もどんどん入ってくるようになると思いますし、コンソーシアムの中で立ち上がる共同研究や、コンサルティングなども利用しやすくなりますので、「開かれた大学」のモデルとして、フル活用していただければと思います。
インフラはもちろん橋梁だけに限りません。人々の暮らしを支える様々なインフラが元気になるように、そしてインフラに関わる人々も元気になるように、できることは何でもやろうと思います。
維持管理はもちろん、新設インフラの品質確保・長寿命化や、将来のインフラに活用する建設材料の技術開発、維持管理に活用する材料・技術の開発、インフラに関する制度やシステムの研究、そして人材育成のための活動などなど、ガンガンやっていこうと思いますので、ぜひぜひ仲間になってください!