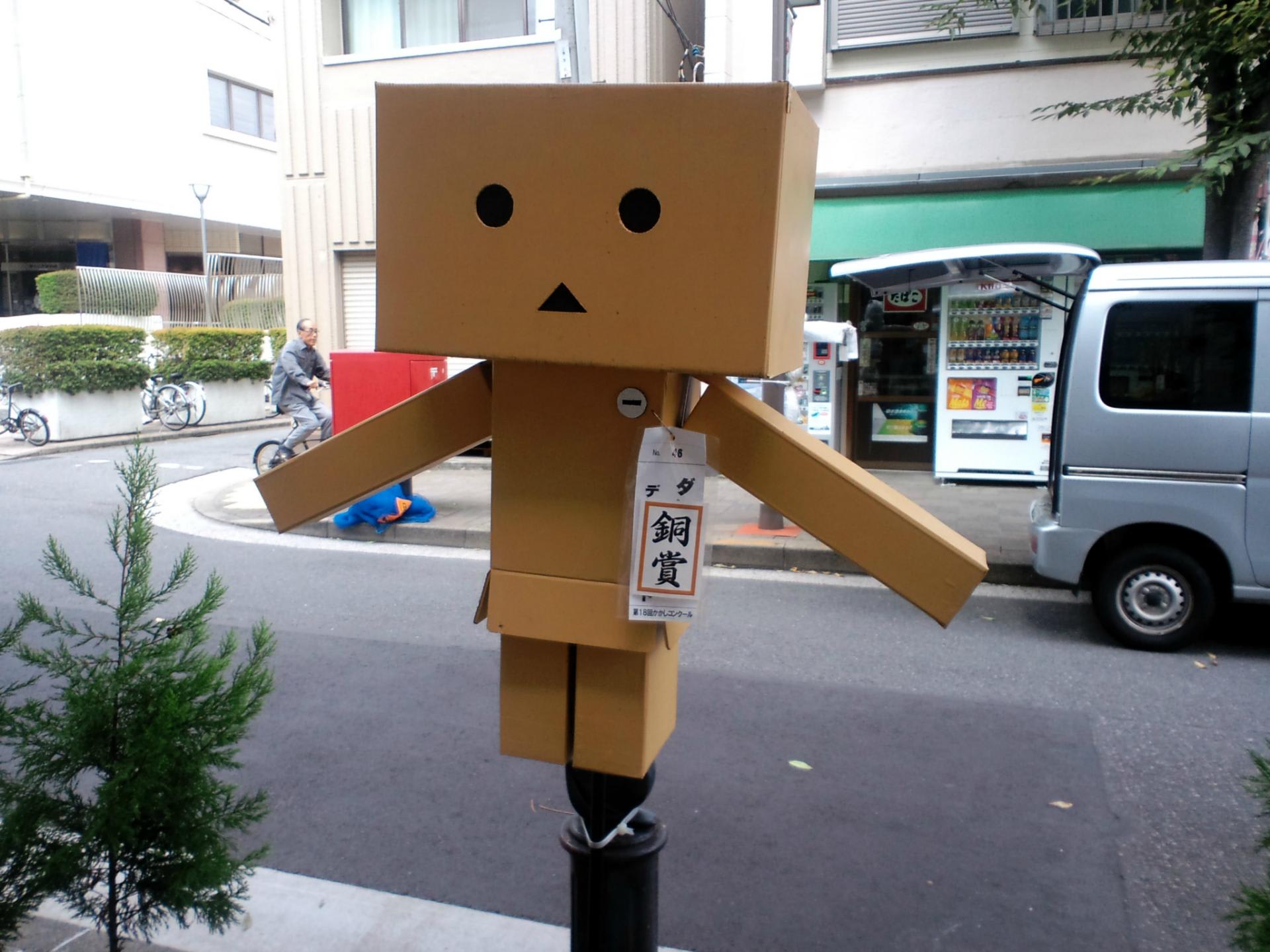根岸から竜泉界隈を走っていたら、鳳神社で工事をしていました。

その形から想像するに、これは酉の市の屋台の骨組みではないでしょうか?
でも、今年の「一の酉」は11月5日です。
いくらなんでも準備は早いような・・・。
酉の市用とは違うのかな?
働いている職人の親方らしい人に訊いてみました。
「酉の市の屋台の骨組みですか?」
「そう」
「もう準備するんですか?」
「我々が骨組みを造って、屋根を造る職人と、屋台の台と間仕切りを造る職人が居るからねえ、もう取り掛からないと」
「今年は三の酉まであるから儲かりますね」
「関係ないよ。我々は骨組みを造って、最後解体するだけだから」

「そうですか。忙しそうですね」
「丁寧にやらないとね。工事屋や熊手販売業者からクレームがあるのよ。去年と違うって直ぐ文句言ってくる。大変なのよ」
「お忙しいところをお邪魔しました」
「最後は愚痴になっちゃったね」
お賽銭は上げないけど、お参りします。
あれっ?いつもと本堂の様子が違います。

お賽銭箱に、大きなお多福の面が鎮座しています。
えっ!こんなのあったっけ?
本堂正面の石段にスロープが付けられています。
お面を搬入する為に付けられたのでしょうか?
左右の酒樽用でしょうか?
酒樽をお供えするのはまだ早くないでしょうか?
ひょっとして、今日のお月見用でしょうか?

さっきの親方に訊いてみようか?
知っているかなあ?
忙しそうだし・・・。
お面は撫でられた手垢で光っているので、新しいものではありませんが、初めて見るものです。
もう、20数年酉の市にお参りしています。
普段も時々覗いています。

毎年酉の市には出ていたのでしょうか。
いつも酉の市の時は手前に賽銭箱を置いていて、そこで手を合わせるので、見えなかったのでしょうか?
でも、普段来ても無かったし・・・。
疑問は尽きることがありません。
酉の市は下町の年末風物詩です。
商売人は熊手を買って来年の商売繁盛を願います。
年末には都下の商店や飲食店に新しい熊手が飾られます。

それにしても、やっと秋口なのに、もう酉の市の準備ですか。
慌ただしいと思う反面、また熊手売りの親子に会える期待が湧いてきます。

その形から想像するに、これは酉の市の屋台の骨組みではないでしょうか?
でも、今年の「一の酉」は11月5日です。
いくらなんでも準備は早いような・・・。
酉の市用とは違うのかな?
働いている職人の親方らしい人に訊いてみました。
「酉の市の屋台の骨組みですか?」
「そう」
「もう準備するんですか?」
「我々が骨組みを造って、屋根を造る職人と、屋台の台と間仕切りを造る職人が居るからねえ、もう取り掛からないと」
「今年は三の酉まであるから儲かりますね」
「関係ないよ。我々は骨組みを造って、最後解体するだけだから」

「そうですか。忙しそうですね」
「丁寧にやらないとね。工事屋や熊手販売業者からクレームがあるのよ。去年と違うって直ぐ文句言ってくる。大変なのよ」
「お忙しいところをお邪魔しました」
「最後は愚痴になっちゃったね」
お賽銭は上げないけど、お参りします。
あれっ?いつもと本堂の様子が違います。

お賽銭箱に、大きなお多福の面が鎮座しています。
えっ!こんなのあったっけ?
本堂正面の石段にスロープが付けられています。
お面を搬入する為に付けられたのでしょうか?
左右の酒樽用でしょうか?
酒樽をお供えするのはまだ早くないでしょうか?
ひょっとして、今日のお月見用でしょうか?

さっきの親方に訊いてみようか?
知っているかなあ?
忙しそうだし・・・。
お面は撫でられた手垢で光っているので、新しいものではありませんが、初めて見るものです。
もう、20数年酉の市にお参りしています。
普段も時々覗いています。

毎年酉の市には出ていたのでしょうか。
いつも酉の市の時は手前に賽銭箱を置いていて、そこで手を合わせるので、見えなかったのでしょうか?
でも、普段来ても無かったし・・・。
疑問は尽きることがありません。
酉の市は下町の年末風物詩です。
商売人は熊手を買って来年の商売繁盛を願います。
年末には都下の商店や飲食店に新しい熊手が飾られます。

それにしても、やっと秋口なのに、もう酉の市の準備ですか。
慌ただしいと思う反面、また熊手売りの親子に会える期待が湧いてきます。