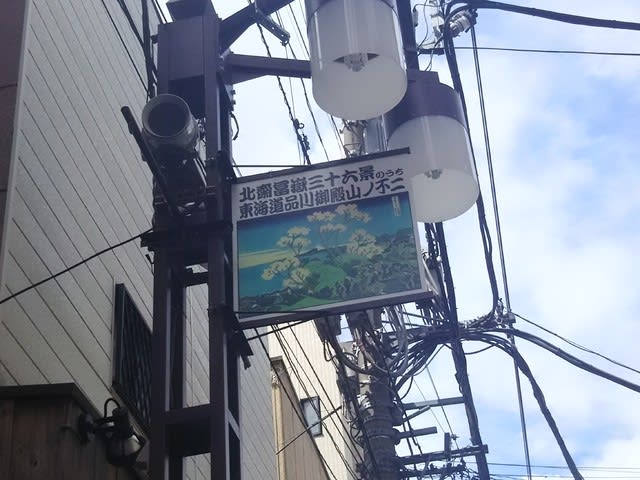坂の下近くにこんな石がありました。

道路脇の休憩所にもなっています。

説明板を読みます。「この坂下にもと千川(小石川とも)が流れていた。(今は暗きょの路地です)

むかし、木の根っ子の股で橋をかけていたので、根子股橋と呼ばれていた。江戸の古い橋で、伝説的に有名であった。ある夕暮れ時、大塚辺の道心者(少年僧)がこの橋の近くに来ると、草の茂みの中を白い獣が追ってくるので、すわ狸かとあわてて逃げて千川にはまった。それから、この橋は、猫又橋といわれるようになった。猫又は妖怪の一種である。

昭和のはじめまでは、この川でどじょうを取り、ホタルを追って稲田(千川たんぼ)に落ちたなど、古老がのどかな田園風景を語っている。
大正7年3月、この橋は立派な石を用いたコンクリート造りとなった。ところが千川はたびたび増水して大きな水害をおこした。それで昭和9年千川は暗きょになり道路の下を通るようになった。 石造りの猫又橋は撤去されたが、地元の故市川虎之助氏(改修工事相談役)はその親柱と袖石を東京市と交渉して自宅に移した。ここにあるのは、袖石の内2基で、千川名残りの猫又橋を伝える記念すべきものである。なお、袖石に刻まれた歌は市川虎之助氏の作で、同氏が刻んだものである。『騒がしき蛙は土に埋もれぬ 人にしあれば如何に恨まん』」

さて、すぐ近くにも説明板があります。同じ場所に説明板が二つあるのは珍しいです。

違った謂われがあるのでしょうか?読みます。「猫又坂 不忍通りが千川谷に下る(氷川下交差点)長く広い坂である。現在の通りは大正11年(1922)頃開通したが、昔の坂は、東側の崖のふちを通り、千川にかかる猫又橋につながっていた。この今はない猫又橋にちなむ坂名である。

また、『続江戸砂子』には次のような話がのっている。 むかし、この辺に狸がいて、夜な夜な赤手ぬぐいをかぶって踊るという話があった。ある時、若い僧が、食事に招かれての帰り、夕暮れどき、すすきの茂る中を、白い獣が追ってくるので、すわっ、狸かと、あわてて逃げて千川にはまった。そこから、狸橋、猫又橋と呼ばれるようになった。猫又とは妖怪の一種である。」

前の説明板とよく似た話なので坂の説明だけで良いと思うのですが、そうもいかない事情があるのでしょうね。