こんにちは! 中之島教室です
だんだんと涼しく 秋らしくなってきた今日この頃。
秋らしくなってきた今日この頃。
日暮れが早くなって虫の声もどことなくもの寂しい……
とセンチメンタルな気分になっている講座担当の Nです。
Nです。
ここで歌の一つでも詠めればいいのですが、残念ながらそんな数寄の素養がないのが悲しいところ
しかし、移りゆく季節に心が動いてしまうのは今も昔も変わらないはずです。
そんな日本人の心の動きを表現した歌を、初めて歌集にしたものが『万葉集』。
ということで、今回は書家の石川九楊さんによる講座 「万葉仮名で楽しむ万葉集」 をご紹介します

石川九楊さんといえば、その独特の前衛的な書だけではなく、
「書く」という視点から展開される書論も高く評価されています。
今回、 担当Nが講座をお願いした時、
担当Nが講座をお願いした時、
今年の1月にご本を出されたこともあってか、テーマに選ばれたのが『万葉集』でした。
この万葉集の歌を原形に近い万葉仮名の姿で読むことで、
新しい解釈 と魅力
と魅力 が見えてくるそうです。
が見えてくるそうです。

例えば、この有名な山上憶良の歌「銀も金も玉も何せむに 勝る宝子に及かめやも」は、
万葉仮名で書くとこうなります。
「銀母金母玉母奈尓世武尓麻佐礼留多可良古尓斯迦米夜母」
…難解ですね。さっぱりです。
どうしてこの漢字でかくの? 歌の意味はちがってくるの? これのどこから仮名文字が出てくるの?
といった疑問を、本講座で解き明かします。
書と歌と文字、それぞれが密接に関係し合う『万葉集』。
石川さんの、冗談を交えた語り口調の講義は、一度も万葉集を読んだことのない方でも、
楽しんでいただけるとお勧めします!
さて、今回の講座をお願いするにあたって、是非ともサイン会を!とお願いしました。
と、いうのも6月の伊丹市立美術館での展覧会での講演会「書と酒と男と女」
(いいタイトルですね。もちろん講演内容も面白かったです。)
で頂いたサインがとても丁寧で素敵で感激した からなのでした。
からなのでした。
サインをする方を必ず見てからサインを書かれるのですが、硯で墨を丁寧にすって小筆を使います。
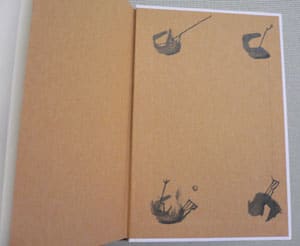
私が石川九楊さんを初めて知ったのは、とある雑誌の連載から。
文字どおり“いろは”から書道を丁寧に教えるという企画で、
白い半紙に鮮やかに黒々と墨でしたためられた「いろは」の文字をみて、
かっこいい! と思ったことを覚えています。
それから何年か経って今回のサインを頂いたわけですが、その時の気持ちをありありと思いだしました。
今回のサイン会は、書籍購入していただいた方を対象に行う予定です。
担当N も当日は頑張って墨をすります!
も当日は頑張って墨をすります!
芸術文化の秋、皆様の沢山のご参加をお待ちしています(^o^)
 お申し込みはコチラ
お申し込みはコチラ
お電話・FAXでも受付しております。
中之島教室:
大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞ビル 5階
TEL 06-6222-5222
FAX 06-6222-5221
窓口営業時間:
午前9時30分~午後6時30分
(第2・4日曜日は午後2時まで)
※休館日=第1・3・5日曜と祝日(振替休日を含む)

だんだんと涼しく
 秋らしくなってきた今日この頃。
秋らしくなってきた今日この頃。日暮れが早くなって虫の声もどことなくもの寂しい……

とセンチメンタルな気分になっている講座担当の
 Nです。
Nです。ここで歌の一つでも詠めればいいのですが、残念ながらそんな数寄の素養がないのが悲しいところ

しかし、移りゆく季節に心が動いてしまうのは今も昔も変わらないはずです。
そんな日本人の心の動きを表現した歌を、初めて歌集にしたものが『万葉集』。
ということで、今回は書家の石川九楊さんによる講座 「万葉仮名で楽しむ万葉集」 をご紹介します


石川九楊さんといえば、その独特の前衛的な書だけではなく、
「書く」という視点から展開される書論も高く評価されています。
今回、
 担当Nが講座をお願いした時、
担当Nが講座をお願いした時、今年の1月にご本を出されたこともあってか、テーマに選ばれたのが『万葉集』でした。
この万葉集の歌を原形に近い万葉仮名の姿で読むことで、
新しい解釈
 と魅力
と魅力 が見えてくるそうです。
が見えてくるそうです。
例えば、この有名な山上憶良の歌「銀も金も玉も何せむに 勝る宝子に及かめやも」は、
万葉仮名で書くとこうなります。
「銀母金母玉母奈尓世武尓麻佐礼留多可良古尓斯迦米夜母」
…難解ですね。さっぱりです。
どうしてこの漢字でかくの? 歌の意味はちがってくるの? これのどこから仮名文字が出てくるの?
といった疑問を、本講座で解き明かします。
書と歌と文字、それぞれが密接に関係し合う『万葉集』。
石川さんの、冗談を交えた語り口調の講義は、一度も万葉集を読んだことのない方でも、
楽しんでいただけるとお勧めします!
さて、今回の講座をお願いするにあたって、是非ともサイン会を!とお願いしました。
と、いうのも6月の伊丹市立美術館での展覧会での講演会「書と酒と男と女」
(いいタイトルですね。もちろん講演内容も面白かったです。)
で頂いたサインがとても丁寧で素敵で感激した
 からなのでした。
からなのでした。サインをする方を必ず見てからサインを書かれるのですが、硯で墨を丁寧にすって小筆を使います。
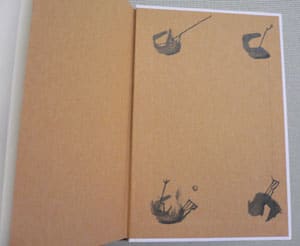
私が石川九楊さんを初めて知ったのは、とある雑誌の連載から。
文字どおり“いろは”から書道を丁寧に教えるという企画で、
白い半紙に鮮やかに黒々と墨でしたためられた「いろは」の文字をみて、
かっこいい! と思ったことを覚えています。
それから何年か経って今回のサインを頂いたわけですが、その時の気持ちをありありと思いだしました。
今回のサイン会は、書籍購入していただいた方を対象に行う予定です。
担当N
 も当日は頑張って墨をすります!
も当日は頑張って墨をすります!芸術文化の秋、皆様の沢山のご参加をお待ちしています(^o^)
 お申し込みはコチラ
お申し込みはコチラお電話・FAXでも受付しております。
中之島教室:
大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞ビル 5階
TEL 06-6222-5222
FAX 06-6222-5221
窓口営業時間:
午前9時30分~午後6時30分
(第2・4日曜日は午後2時まで)
※休館日=第1・3・5日曜と祝日(振替休日を含む)


































 ファッションやメイクに関して、新たな発見もあるかもしれません。
ファッションやメイクに関して、新たな発見もあるかもしれません。


 有名タレントが古地図片手に街歩き。言わずと知れた某番組に熱をあげている
有名タレントが古地図片手に街歩き。言わずと知れた某番組に熱をあげている 講座部員ぴよ子が、
講座部員ぴよ子が、
 」とぴよ子がほれ込んだお方です
」とぴよ子がほれ込んだお方です









 「福島」「浦江」「鷺洲」「海老江」「田蓑島」「佃島」など周辺の地名に島、浦、江、洲といった水辺を意味する
「福島」「浦江」「鷺洲」「海老江」「田蓑島」「佃島」など周辺の地名に島、浦、江、洲といった水辺を意味する 芭蕉の句「かきつばた語るも旅のひとつ哉」とこの地との関連とは……?
芭蕉の句「かきつばた語るも旅のひとつ哉」とこの地との関連とは……?  皆さまのご受講をお待ちしております(^o^)
皆さまのご受講をお待ちしております(^o^) お電話・FAXでも受付しております。
お電話・FAXでも受付しております。

















 こんにちは!
こんにちは!

 林芳辰講師の講座情報はこちら↓
林芳辰講師の講座情報はこちら↓


 井上 治彦さん タイトル<静寂>
井上 治彦さん タイトル<静寂>






















 」、
」、 」など、
」など、




 ~2011年9月
~2011年9月




