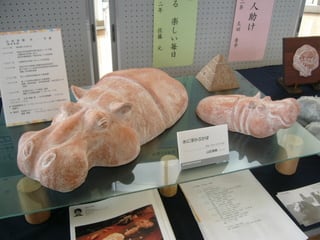野焼きをやったことがあります。
軽トラック2台分のマキを使い切ったのですが、
素焼き程度にしか焼けていませんでした。
工房のマキストーブの中に
ぐい飲みをいれて焼いたことがあります。
これもまた、素焼きよりもうすこし焼けたかなと言う程度。
灰が釉薬になるまで焼くと言う事は、すごいことなんです。
火の色でおおよその温度がわかりますが、
タバコの火の吸い込んだ時の色で800度くらいでしょうか。
1200度を超えると、白熱電球を直視するくらいの輝きになってきます。
鉄も溶ける温度ですから。
温度を上げるための条件
1・熱源
2・熱を逃がさない容器
が必要です。
それが窯ですね。
以前はレンガの窯が一般的でした。
最近は断熱材が進化してレンガを使わない窯も増えてきました。
蒸気機関車が電車になったように
窯も進化したのです。
昔のものは大掛かりだったですね。
大きなのぼり窯なんかは、下のほうで火を燃し始めても上の方はまだ窯詰めしてた、なんて話を聞いたことがあります。
鍋島藩の御用窯跡をみたことがありますが、
一部屋が10畳間くらいあって、そんな部屋が山の斜面の下から上へ続いているのでした。
トラック一杯分の粘土を焼くのに、トラック十杯分のマキがいると言ったようです。
原油も高騰してますし、太陽光で焼ける窯なんか出来るとうれしいな。
益子陶器市コミュもよろしく。

ポチッとお願いします。



軽トラック2台分のマキを使い切ったのですが、
素焼き程度にしか焼けていませんでした。
工房のマキストーブの中に
ぐい飲みをいれて焼いたことがあります。
これもまた、素焼きよりもうすこし焼けたかなと言う程度。
灰が釉薬になるまで焼くと言う事は、すごいことなんです。
火の色でおおよその温度がわかりますが、
タバコの火の吸い込んだ時の色で800度くらいでしょうか。
1200度を超えると、白熱電球を直視するくらいの輝きになってきます。
鉄も溶ける温度ですから。
温度を上げるための条件
1・熱源
2・熱を逃がさない容器
が必要です。
それが窯ですね。
以前はレンガの窯が一般的でした。
最近は断熱材が進化してレンガを使わない窯も増えてきました。
蒸気機関車が電車になったように
窯も進化したのです。
昔のものは大掛かりだったですね。
大きなのぼり窯なんかは、下のほうで火を燃し始めても上の方はまだ窯詰めしてた、なんて話を聞いたことがあります。
鍋島藩の御用窯跡をみたことがありますが、
一部屋が10畳間くらいあって、そんな部屋が山の斜面の下から上へ続いているのでした。
トラック一杯分の粘土を焼くのに、トラック十杯分のマキがいると言ったようです。
原油も高騰してますし、太陽光で焼ける窯なんか出来るとうれしいな。
益子陶器市コミュもよろしく。

ポチッとお願いします。