田並劇場で見た『おはなし絵地図』。
恥ずかしながら、小栗判官と言う言葉は聞き慣れていたけれど、小栗伝説をちゃんと読んだのは、つい最近だったのだ

そして『小栗街道』が、私が住んでいる鮎川市街地~釜場周辺~富里へと続く道が細かく描かれていたのだから、驚きだった。
それを見て「そんな裏道(?)があるの
当時の道中、旅の大変さが忍ばれる。


登り口は、釜場から2kmほど下の所を車道から外れて、川を渡るのだそうだ。

田並劇場で見た『おはなし絵地図』。




はずれ?!
今日の天気は、晴れじゃぁなかったっけこの厚い雲の向こうでは、今まさに天体ショウが始まっているはず…心なしか、暗くなっているのは、雲の厚さか、日食のせいか見られると期待してたのに......
先日の皆既月食もあいにくの曇り空で、見られず


次回は、11月19日の部分月食。
それから、8月お盆前のペルセウス座流星群


見られると良いなぁ


確か先々週頃…梅仕事の真っ最中でバタバタ、ヘトヘトの時に、『蜂の防除に木酢液の希釈を教えて下さい』というメッセージが来た。
受取手は主人で、回答枠を開けて「書いて 」と。
」と。
そう、炭焼きを始めてかれこれ25年。
炭本来の燃やすこと、火付けに関しては主人がメインで答えているが、それ以外のことは、ほぼ私に回される。
例えば・・・
・ 炭を水の浄化に使用する場合の適用量や準備について
・ 炭をインテリアに使ったり、調湿・除湿に使う
・ 木酢液を使用する場合の希釈 など
夕飯を作るタイミングであり、質問がただ単純に”防除”とだけあって、しかも蜂に対しては初めてのこと。
求められているシチュエーションがわかりにくくて、即座に答えられるとは思えなかった。
とりあえず、主人に「『どういうところで使われるのですか?』って聞いておいて 」と頼んで、その場は過ぎた。
」と頼んで、その場は過ぎた。
結局、その後何も来ていないとのことで、この場を借りて書こうと思う。
調べてみたところ…
玄関先や軒下などに侵入や巣を作る防除として空間や地面に散布するなら、原液でなくとも水と1:1の割合で薄めても効果はあるそうだ。
ただし、周辺に植物があったり、壁などは茶色く着色してしまう可能性があるので、散布場所には気を付けること
植物は枯れてしまうので、特に注意が必要だ。
散布後の残留効果は雨など天候で変わる。
その点で言うと、ビンやボトルに入れて、口を開けておいた物を吊したり置いておくのもアリだ。
さて、シチュエーションで困ったのは、山など散策するときの防除だったら…?
私は梅仕事中は、木酢:水=1:3くらいに薄めた物を霧吹きのビンに入れて車にスタンバイさせてある。
余裕ある朝は、帽子と作業服の袖口と襟元に木酢を吹き付けてから着ている。
梅仕事用のシャツ。
衣服に吹き付けるときは、気を付けなければこんな風にシミが出来る場合がある。
作業服だから気にしていないが、この点が要注意なのだ
山仕事用の線香も腰に巻き付けてから梅畑に入る。
線香はブトに効果大
せんこうが切れた瞬間、ブトが顔や手を襲ってくる

 これは何度も体感している
これは何度も体感している
蜂に対しては、畑近くを蜂がブンブン飛んでいる日もあるが、刺された事は無いものの、果たして木酢の効果だとは言い切れないし
不確かな内容になりそうで、タイミングだけでなく、確かな返答は難しいかも(^_^;)




 )
) 」
」 」とだけ答えた。
」とだけ答えた。

 くらいに受け止めている(^_^;)
くらいに受け止めている(^_^;)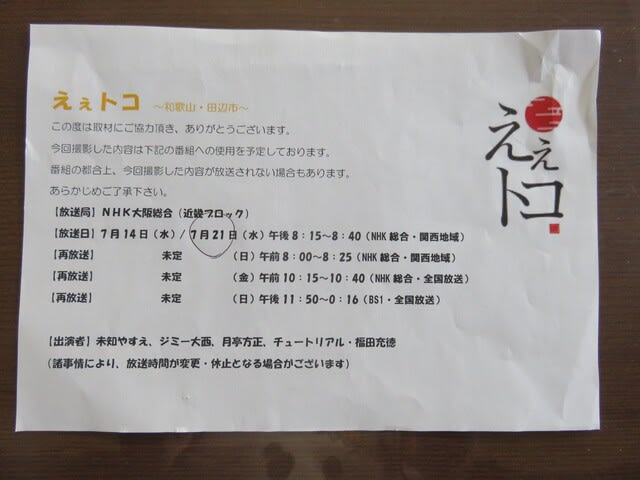

 楽しみにしておこう
楽しみにしておこう
小梅で梅干しに ♪
今年の梅干しは、小梅 小梅を漬けるなら、カリカリ梅がオーソドックス。だが、青いときには収穫の手がまわらず熟して落ち始めた頃にもったいなくて 仕事が一段落した合間に、全採りしたら、1......
昨日、無事終了


今年は、ホントどこも豊作で、「まだ小さいねん 」と言って、なかなか全部が採りきれずに長期戦のようだ
」と言って、なかなか全部が採りきれずに長期戦のようだ
今年はお酒3種類を浸けるだけの梅は頂いたが、梅干しは休憩の年にした。
梅干しは、ちゃんと漬けて土用に干せば、長期保存が可能な食品だ。
その証拠に、去年の小梅はほぼ食べきっているが、一昨年の大きな梅干しはまだ残っているし、息子がもらってきた梅干しもあるので、この1年はそれで間に合いそうだ。
梅干しだけでなく、台所の周辺には梅で漬けた梅サワーに梅味噌、梅干しを作るときにできる梅酢…etc まだ在庫がある。
梅は確かに疲労回復や、何かしら体に良い影響があるので、出来るだけこまめに食していこうと思う。