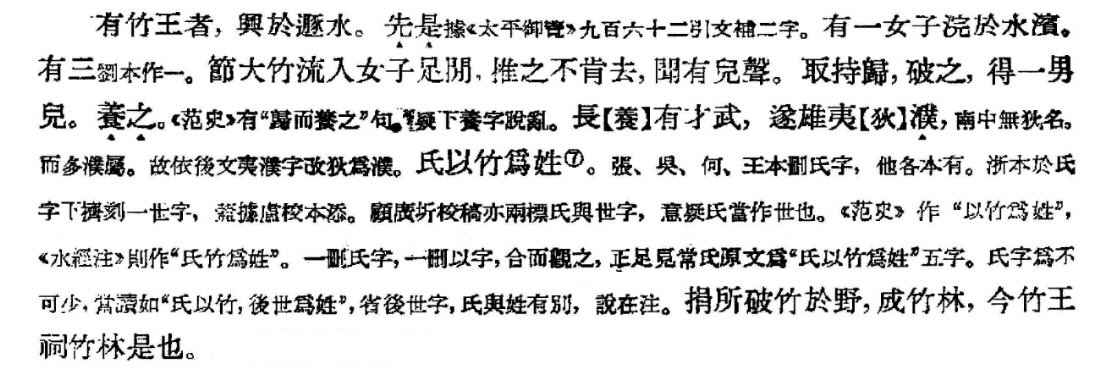以前に書いたことがあったような気がしていたのですが、ちょうど1年前に《「竹取物語」「もも太郎伝説」のルーツ?》と題してやはり書いていました。
テキストを書き写す作業をしていたところ、記憶にある文章に出会ったのです。
先生が引用されているのは、『太平御覧』に引用されている『華陽国志』です。
有竹王者、興於遁水。有一女、浣於水浜、有三節大竹、流入女足間。推之不去,聞有児声。持帰、破竹得男。長養有武才、遂雄夷狄、氏竹爲姓。所破竹、於野成林。今王祠竹林、是也。
以下のものは、『華陽国志校補図注』のものです。
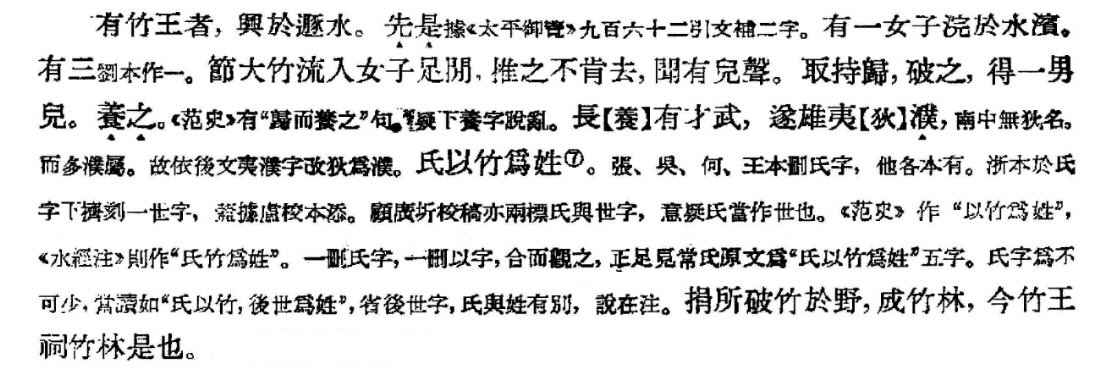
竹の中から出てきたのは男の子で、その竹は竹やぶの中に生えていたのではなく流れてきたという設定の違いは有りますが、『竹取物語』や「もも太郎伝説」を思い起こすのに充分なものと思われます。
契仲は随筆『河社』で、仏典『廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經』の序品が『竹取物語』の種本ではないか、と指摘しているそうです。
以下は『廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經』の序品の一部分です。
「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース」のデータを利用させていただいています。
長すぎて読みづらいので、途中で改行しています。
一切諸佛當來現前安慰其人。
睡眠覺悟行住坐臥常得安樂或於夢中見百千萬世界刹土諸佛如來并諸菩薩前後圍繞。
此陀羅尼有如是等無量無邊不可思議力。時彼仙人得法歡喜欣慶踊躍。
於其住處如新醍醐消沒於地即於沒處而生三竹。
七寶爲根金莖葉竿。梢枝之上皆有眞珠。香潔殊勝常有光明。
往來見者靡不欣悦。生滿十月便自裂破。一一竹内各生一童子。
顏貌端正色相成就。時三童子亦既生已。各於竹下結加趺坐。
3本の竹からそれぞれ3人の男の子が生まれた、と書かれているようですね。
『華陽国志校補図注』によると、『華陽国志』の成立は348年のようですが、該当部分が書かれている「南中志」はそれよりも早く333年ころには書かれていたようです。
仏典『廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經』は唐の菩提流志が漢訳したもの。
『竹取物語』が書かれたとされるのは、866~909年の間のようですから、種本としてはどちらも充分に可能性はありますね。
となると、どのような論が展開されているのか是非とも契仲の随筆『河社』を読んでみなくては!

こんな事に興味を持つなんて・・・
我ながら???

明日は孫の運動会だった!
もう寝なくては!