●ジョリス=カルル・ユイスマンス「ノートル=ダム・ド・パリにおける象徴表現」①
これから取り上げるユイスマンスのエッセイは、彼の死後発刊された『三つの教会と三人のプリミティフ画家』の中の一編であり、大変短いものである。短いがそこにはユイスマンスのゴシック大聖堂に対する、基本的な考え方が確固として示されていて、今日でも読むに値する一編である。
ユイスマンスはまず、フランス19世紀ロマン主義によるゴシック・リヴァイヴァルによって、ノートル=ダム・ド・パリへの評価が復活し、「称賛の声が澎湃として起るまでになった」ことを歓迎している。それに貢献した人物としてユイスマンスが名を挙げているのは、ヴィクトル・ユゴー、モンタランベール、ヴィオレ=ル=デュック、ディドロンの四人である(ユゴーとデュック以外の二人は未詳)。
ユイスマンスはユゴーが言ったことと同じようなことを言っているが、それはユゴーの直接的な影響なしには考えられない。
「あの時代の芸術にあっては、ガラスや石といった物質の形において、もろもろの感情や思考を表現しようとする目的を自己に課したのである。いわば、自分たち用の文字体系を創造したのだった。一基の彫像、一枚の絵画が、単語に相当するものとなり、その集まりが、パラグラフ、文章に当たるものとされたのだった。」
このエッセイの最後にもユイスマンスはユゴーに対して賛辞を送っている。
「ヴクトル・ユゴーのような小説家は、この構造をもとにして、多少とも真実めいた飾りつけを創造し、全部が全部まったく想像に成る人物をそこに住まわせた。それにしても、当時、中世の象徴表現についてなにがしかの感受力を持っていた詩人は、かれひとりだった。」
ユゴーはしかし、そうした象徴表現について深く探究しようとする姿勢は見せていないが、ユイスマンスは象徴表現の解読を試みる。それはユゴーの努力にも拘わらず、当時の建築家、考古学者が陥っていた「歴史的建造物の物質的研究」に対して飽き足りないものを感じ、そのような研究に対して批判の眼を向けていたからである。
象徴表現とは「一つの彫像や図像を、何か他のものを示すしるしとして用いる技術であって、中世の偉大な着想の一つであった」と、ユイスマンスは言っている。そうした中世の表現手法を研究することなしに、物質としての大聖堂を研究するだけでは、何も理解できないということを言いたいのだ。
しかもそれは単なる技術や手法に止まるものではない。ユイスマンスによればそれは「紙という源泉から出てきた事実、神ご自身の語られた言語であるという事実」でもあるのだ。ユゴーが思想表現としての石の建築ということを言ったのからさらに進んで、ユイスマンスはそこに神自身の言語を読み取ろうとしているのである。
さらにユイスマンスは「象徴表現は、聖書という大地に生えた鬱蒼とした大樹」であり、それは聖書ばかりでなく伝説集や聖書外典をも、文章の替わりに彫刻や絵画を用いて表現し、「堂内にキリスト教教義の諸真理」とともに封じ込めたのだという。ユイスマンスはそのような基本的認識を以下のように書き付けている。
「要するに、カテドラルは、一つの全体、総合なのであった。いっさいを含むものであった。聖書であり、教理問答であり、道徳の教室であり、歴史の講義であった。知識の乏しい人たちのため、目に見える像を文章の代用にしたのだった。」
これがユイスマンスの象徴表現解読の基本的考え方であり、このエッセイより10年前に書かれた、シャルトル大聖堂への賛美に貫かれた『大伽藍』を書く基本的スタンスでもあった。
ここでユイスマンスが「知識の乏しい人たちのため」と書いているのは必ずしも正確ではない。本来は〝文字の読めない人たちのため〟としなければならない。あれほどに彫像や図像にこだわり、文字なしでいっさいを語り尽くそうとした理由は、その対象が文盲の人々であったからだし、それほどに当時の識字率は低かったのである。
J=K・ユイスマンス『三つの教会と三人のプリミティフ派画家』(2005、国書刊行会)田辺保訳










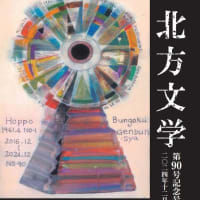
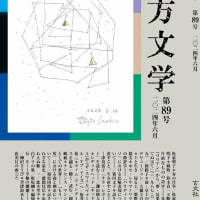
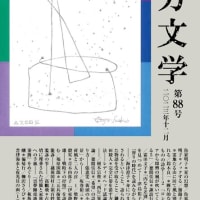

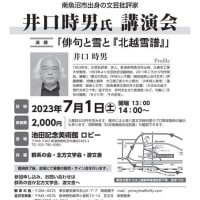

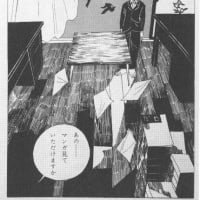
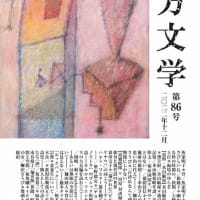
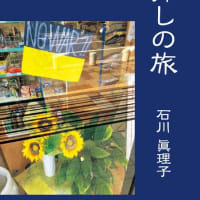
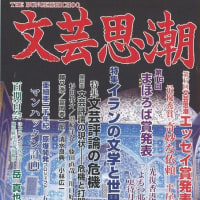

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます