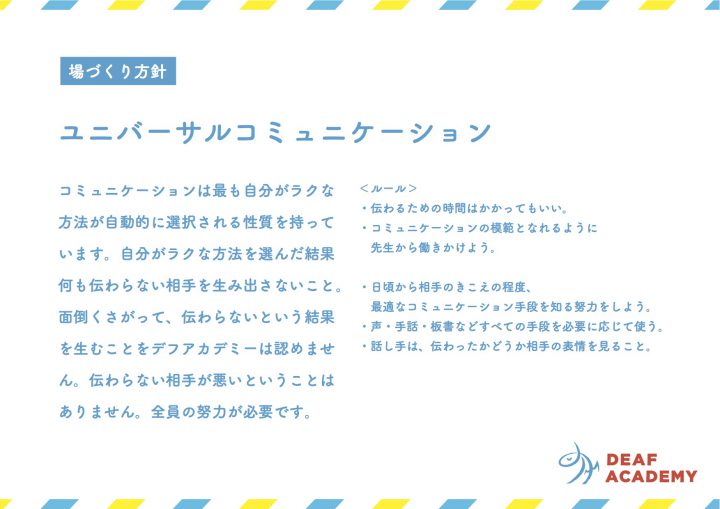尾中友哉さんが夢見る社会とは
同じ空間にいるのに、居合わせた人が別々のスマートフォンを見つめる光景。電車の中やカフェで、あるいは家庭内で目にしたことありませんか? 現代はかつてないほど個人が言葉を綴り、世に発信しています。もしも、それが人々の孤独の反動だとしたら、現代人はかつてないほど孤独を感じているとも言えます。
「聴覚障害者は聞こえない分、最も孤独を感じやすい存在です。でも、だからこそ孤独を乗り越える方法も知っている。彼らの世界が持つ可能性が社会に出たら面白いなと思うんです」。
NPO法人および株式会社「サイレントボイス」の尾中友哉さんはそう言います。なぜそう言い切れるかというと、ご両親が聴覚障害者であるために乳幼児の頃から手を使った言葉で、この世界の色と形を知ってきた人だから。
前回greenz.jpで尾中さんの取り組みを紹介した際には、大反響をいただきました。あれから約半年。「サイレントボイス」の“現在地”を再びみなさんにお届けします。

「デフアカデミー」は、折れない心を育む場
「サイレントボイス」 はNPO法人と株式会社の2つの形態をとっています。NPO法人としては、聴覚障害・難聴のある子どもたちに特化した総合学習塾「デフアカデミー」を運営。一方、株式会社「サイレントボイス」は企業などに向けてコミュニケーションのマインド向上の研修を提案しています。
まず、「NPO法人サイレントボイス」の活動を見てみましょう。「デフアカデミー」には、両耳の聴力レベルが40デシベル以上の聴覚障害・難聴のある小学生から高校生までの子どもたちが通っています。現在は京都と大阪で開校しており、生徒の数は合計40名ほどになりました。
大阪にある谷町六丁目校は、放課後等デイサービスの事業所として大阪市から指定を受けているため、一般的な収入の家庭であれば費用も月々4600円が上限と良心的。生徒たちは週に2回を目安に通っていますが、中には毎日やってくる子もいるとか。
「デフアカデミー」は聴覚障害・難聴児に特化した総合学習塾なので、カリキュラムも特別です。聴覚障害者は情報を目でキャッチするため洞察力が鋭く、視覚能力も高いと尾中さんは話します。カリキュラムはこうしたいい点を伸ばすよう、オリジナルで開発しました。
同じ空間にいるのに、居合わせた人が別々のスマートフォンを見つめる光景。電車の中やカフェで、あるいは家庭内で目にしたことありませんか? 現代はかつてないほど個人が言葉を綴り、世に発信しています。もしも、それが人々の孤独の反動だとしたら、現代人はかつてないほど孤独を感じているとも言えます。
「聴覚障害者は聞こえない分、最も孤独を感じやすい存在です。でも、だからこそ孤独を乗り越える方法も知っている。彼らの世界が持つ可能性が社会に出たら面白いなと思うんです」。
NPO法人および株式会社「サイレントボイス」の尾中友哉さんはそう言います。なぜそう言い切れるかというと、ご両親が聴覚障害者であるために乳幼児の頃から手を使った言葉で、この世界の色と形を知ってきた人だから。
前回greenz.jpで尾中さんの取り組みを紹介した際には、大反響をいただきました。あれから約半年。「サイレントボイス」の“現在地”を再びみなさんにお届けします。
尾中友哉(おなか・ともや)
株式会社およびNPO法人「Silent Voice」代表。1989年、滋賀県出身。聴覚障害者の両親を持つ耳の聞こえる子ども「通称:CODA(コーダ)」として、手話を第一言語に育つ。大学卒業後、東京の大手広告代理店に勤務。激務の日々の中、「自分にしかできない仕事とは?」について考える。退社後はフリーの広告ディレクターとして活動しながら、2014年2月に任意団体「Silent Voice」を立ち上げる。企業などへのセミナープログラム「DENSHIN」は株式会社「Silent Voice」として、また聴覚障害・難聴のある就学児向けの「デフアカデミー」はNPO法人「サイレントボイス」として運営し、聴覚障害者の強みを生かす社会に向けて活動している。
「デフアカデミー」は、折れない心を育む場
「サイレントボイス」 はNPO法人と株式会社の2つの形態をとっています。NPO法人としては、聴覚障害・難聴のある子どもたちに特化した総合学習塾「デフアカデミー」を運営。一方、株式会社「サイレントボイス」は企業などに向けてコミュニケーションのマインド向上の研修を提案しています。
まず、「NPO法人サイレントボイス」の活動を見てみましょう。「デフアカデミー」には、両耳の聴力レベルが40デシベル以上の聴覚障害・難聴のある小学生から高校生までの子どもたちが通っています。現在は京都と大阪で開校しており、生徒の数は合計40名ほどになりました。
大阪にある谷町六丁目校は、放課後等デイサービスの事業所として大阪市から指定を受けているため、一般的な収入の家庭であれば費用も月々4600円が上限と良心的。生徒たちは週に2回を目安に通っていますが、中には毎日やってくる子もいるとか。
「デフアカデミー」は聴覚障害・難聴児に特化した総合学習塾なので、カリキュラムも特別です。聴覚障害者は情報を目でキャッチするため洞察力が鋭く、視覚能力も高いと尾中さんは話します。カリキュラムはこうしたいい点を伸ばすよう、オリジナルで開発しました。
子どもたちは、みんなすごい集中力です。尾中さんには、聴覚障害者の持つ特性を生かしながら、社会で活躍する人材を育成しようという目標があります。しかし、学習面で成功するには何といっても土台となる“心の成長”が必要です。

「デフアカデミー」の子どもたち。手話を使う環境に定期的に通うことで、手話も上達します。
聴覚障害のある子どもたちの多くは、一般の小・中学校に通っています。聞こえる側のペースで進んでしまう授業では、どうしても孤立してしまう場面もあります。特に思春期になり、自分を客観視するようになると「なぜ自分は周りと違うのだろう?」と悩み、日常生活の中の失敗を聞こえないことのせいにしてしまうこともあるのだそう。そんな時どうすれば諦めずに前向きに努力できるのか? 尾中さんが一番大切にしているのは、折れない心を育むことです。
ここでは、視覚能力(画像記憶力や速読力など)を高めるワークもやりますが、一番大事にしているのは子どもを褒めること。子どもを褒めて存在を認めてあげて、安心して成長できる場所をつくっているんです。
それを続けると、最初は自己肯定感が低くて褒められてもきょろきょろしていた子が、笑うようになったり。子どもがこちらを信頼してくれる瞬間って、わかるんですよ。
2018年1月には、京都を中心に海外にまで学習塾を展開する「株式会社京進」の講師たちによる「夢を描くドリームツリー」授業が開催されました。
内容は、脳科学の考えを取り入れた京進オリジナルの学習法「リーチングメソッド」を用いて、自分の夢を言語化し、夢を叶えるために行動を喚起するというもの。子どもたちは、自分の得意なこと、褒められて嬉しかった言葉などを振り返り、自分の夢を書き出していきました。
言葉や音声を用いないユニークな研修
「株式会社サイレントボイス」の活動も見てみましょう。尾中さんらは、2014年からコミュニケーションのマインド向上をはかる企業研修を行ってきました。
研修では数人のグループをつくり、言葉や音声を用いずに表情やジェスチャーでお題を伝えます。参加者は伝えられないもどかしさを含めて、言葉を超えたところにあるコミュニケーションの根幹に触れます。最近は大阪のみならず、東京でも研修依頼が増えたとか。

研修は音声による言葉や音声を用いないので、外国人の方も参加できます。
僕らが広げている世界は、言語に依存することとは逆の考え方。つまり、“無言語”という発想です。要は言葉が介在しないコミュニケーションです。そこはある意味、言葉の壁がなかったり、誰にでも伝わるというユニバーサル性がすごく高い。
また、企業のみならずこの“無言語”コミュニケーションの研修は、少しバリエーションを変えて「話さない英会話」として関西の某大学にも提案している最中。内容は様々な国籍の学生たちがチームをつくり、言葉による言語を使わないで与えられたミッションをゲーム形式で解決するというもの。時にはジェスチャーですら異なる海外の人々と一緒に問題をクリアするなんて、考えただけでスリリング。そして学びや気づきも多そうです。
本当のコミュニケーションって何だ?
生まれた時から、耳が聞こえない両親に自然と身振り手振りで自分の欲求を伝えてきた尾中さんは、もはや伝えることのプロ。「コミュニケーションって自分がどうこうではなく、相手が理解することなんですよね」と自然に口をついてでてくる言葉が実に深いのです。「デフアカデミー」の企業理念には、伝えることの姿勢についてこう書かれています。
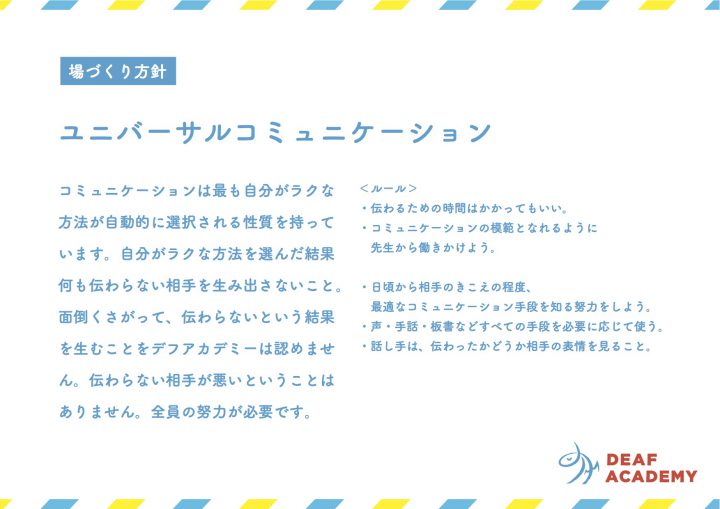
「デフアカデミー」の企業理念。「コミュニケーションは自分がラクな方法が自動的に選択される性質を持って」いると書かれています。まさに、その通り。
「あれだけ言ったのに、わかってない」。「ここに書いてるのに、読んでないのかな?」こんなやりとり、したことありませんか? これって、自分本位な一方的な発信なだけで、相手に伝わっていないならコミュニケーションとしては意味がないもの。
僕は本当のコミュニケーションって何だ? と聞かれたら、相手に本気で伝えることや、相手を本気で理解することを通じて相手に向き合うことだと思うんです。
聴覚障害者は、問題を掘り下げていくとコミュニケーションの壁に行き着きます。だからこそ、聴覚障害者の中に「ながら会話」をする人はいない。相手の目を見る。そして、相手に伝わったか確認する。かすかな表情の変化ですら、今の自分の気持ちを表す「声なき声」なんです。僕らも聴覚障害の人と働いているからこそ、コミュニケーションを深めていける。
だから「DENSHIN」という企業研修で本気で伝える、本気で理解するっていう姿勢を伝えています。この基準を組織が持つと、相手を理解した上で話そうと思えるように変わるんです。
障害者が健常者を救う社会へ
尾中さんのお母さんは、聞こえないながらも喫茶店をきりもりしています。
そんなお母さんのモットーは「ひとつ助けてもらったら、2つ恩返しする」というもの。いつも一生懸命に生きる両親の姿から、尾中さんは聴覚障害者が社会で活躍することを目指して「デフアカデミー」を立ち上げました。
その思いはさらに大きく膨らみ、今は聴覚障害者が人々の孤独を救う社会を夢見ています。

2017年12月にはTED×Kobeにも登壇しました。
イギリスでは6000万人の人口のうち、900万人が孤独を感じていると国がレポートをあげました。また彼らが病院に通ったり働けなくなった場合の経済損失は4.9兆円といわれます。日本だって同じように成熟国で、きっと似たような問題を抱えていると思うんです。
そんな時、孤独の辛さや対処法を知っている聴覚障害者がコミュニケーションの側面からこの問題を考えて解決していけないかな、と考えているんです。日本には550万人の難聴者がいる。世界では4.5億人いるんです。4.5億人の人が、これから80億人に増える人口の孤独を解決できたらおもろいなと思うんですよ。

「みんなの夢AWARD」でグランプリを獲得した瞬間。
尾中さんは去る2月、日本一の夢の祭典「みんなの夢AWARD」にファイナリストとして出場しました。先の壮大な夢を2000人の前でプレゼンテーションしたところ、全国から400名のエントリーがあった中、見ごと栄光のグランプリに輝いたのです。
両親が子どもをつくるとき、親戚には心配の声もあったそうです。でも今僕は毎日が楽しくて。両親が子どもをつくることをあきらめなくて良かったなって思うんです。だって両親があきらめてたら、こんなこと、全部なかったんです。観客席にいた両親の「おめでとう」という手話が見えたとき、自分を産んでくれてありがとうって心底思いました。
だから、聴覚障害のある今の子どもにも「あきらめない」心を持つ大切さを伝えたいんです。それがあれば、ちょっと人と違う場所でだって輝けるんです。
尾中さんいわく、近年は補聴器や医学の発達で聴覚障害者でも聴力を回復しつつあり、将来的には聴覚障害者はいなくなるのでは? ともいいます。
今は聴覚障害者を講師として雇用するなど、具体的に仕事をつくり出すことも行っていますが、本当に目指しているのは聴覚障害者がいなくなったとしても、今と同じようにサービスを続けていける仕組みです。

グランプリを勝ち獲った夜、尾中さんのお父さん、お母さんとともに。
たとえば「デフアカデミー」は、折れない心を育てるプログラムを開発・実践しているので耳の聞こえる聞こえないに関わらず、あらゆる悩みごとを抱えた子どもにも適用できる。
いずれは「DENSHIN」も、元聴覚障害者がコミュニケーションの一番大事なところを伝える研修という形もあるかもしれない。
いつも、聴覚障害者が助かるという視点から、もうひと段階掘り下げて、いかにすべての人にとっての価値に変えていけるかを考えています。同じ人間ですから必ずつながっているはずです。
ものごとには、いつも裏と表があります。尾中さんは、自分に与えられた環境をマイナスと捉えることもできたかもしれません。けれどそうはしなかった。むしろそれを糧に、逆転の発想で新しい価値観を世に問うている。少し先の未来、この新しい価値観が少しずつ世の中の当たり前になっていくことを私は信じます。